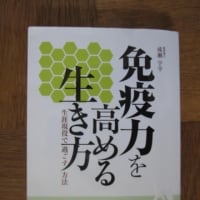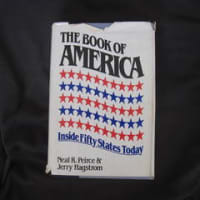大学に入って2年目くらい(昭和31年1956年)のときだったろうか、出淵が能楽を見に行かないかと誘ってくれた。彼の東京にいた叔母さんが切符を送ってきてくれたからではなかったかと思う。
出淵は大学に入学して学内のサークルは「喜多会」に入会していた。父君が謡いをたしなんでおられ、腹から声を出す謡は健康にもよいからというのが理由だと話していたが、もっとほかに理由があったのかも知れない。彼らしい心配りで、私達にはあまり興味のない話題は自分からは持ち出さなかったので、能楽や謡曲に関する話をかれからあまり聞く機会はなかった。
私たちは学生寮のあった三鷹を出て喜多能楽堂に行った。目黒だったのだろうか。彼は何度も行っているのだろう、物慣れたものだった。私は能楽といえば、高校生のころ地方都市で観世流の「土蜘蛛」の特別公演を見に行っただけだったのでこのときは能楽を見たのは2回目だった。
曲目は「松風」だった。
私は内容もわからずに静かに見ていた。
終わって会場を出るときに出淵は私に「どうだった?」とたずねた。
私が答えができずにいると、彼は「松風」は観客が居眠りをするくらいが一番よい演技ということになっているんだ、と話してくれた。
あるいは私は見ている途中に居眠りをしてしまったかもしれない。彼はそれに気づきながら、なじったり、からかったりするのではなく、私が居眠りをするのは私がいけないのではなく、演技が上手なので観客としては当然なのだと心やさしく言ってくれたのだろう。
彼はそのようにいつも周囲の友人たちに暖かい配慮をしてくれる人だった。
今「松風」の謡本を読んで見ると、シテ松風の中納言行平への恋慕の情を幽霊となって物語る激しいものなので、何で居眠りしてしまったのだろうとおかしい気持ちだ。謡曲といえばわけのわからぬ退屈なものだという先入観念が私にはあったのかもしれない。
「恋草の。露も思いも乱れるつつ。露も思いも乱れつつ。心狂気に馴れ衣の。巳の日の。祓いや木綿四手の。神の助けも波の上。あわれに消えし憂き身なり」
松風の気持ちを表わしている松風の中の上歌の一つである。 (つづく)
画像は謡曲「松風」謡本(観世流)