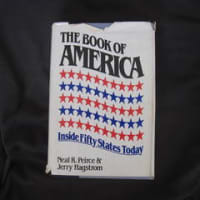文士劇というのは最近聞かないが、今はもうなくなっているのだろうか。
私が大学の教養課程のころだった。大学の早野先生、西村秀夫先生のアイデアで始まり、私達学生が家庭教師の一種としてやっていた、小学生を対象にした「理科クラブ」のために自宅を提供して下さっていた杉並区荻窪のI夫人が、文芸春秋社主催の文士劇の切符を私に下さった。
I夫人は、私のこのブログにも出て来るI氏の母君である。
「理科クラブ」の催しの後に、指導役の大学生の私たちがお茶を頂き雑談しているときに私が文学好きであり、また文学部への進学を希望しているということを聞いておられたのであろう。
その切符は、「リハーサルの切符」であった。
リハーサルが行われていたのはどこの劇場であったろう。50年も前のことで正確には覚えていない。
受付で入場券を見せて席に座っていると、やがてリハーサルが始まった。
観客はまばらである。
リハーサルというより、まだ練習のような段階であった。
題目は歌舞伎からのものであった。
舞台では、客席の前の方に座っている演出のおじいさんの厳しい指示をうけながら動いている背のすらりとした若い女性がいいた。
それが、私たちのあこがれていた、曽野綾子女史であった。
演出を担当しているのは、歌舞伎界の大物であったのだろう。超一流の人気作家連中に厳しい演技修正の指示をとばしていた。怒声である。
いつも周囲にちやほやされているであろう舞台の上の作家連中は、ふくれながらもその演技のふりつけの指示に従っていた。
時代物の大衆文学の大物作家のK氏も舞台の上での配役の一人であったが、が、固くこわばったその場の雰囲気を、
「へいへい、かしこまりました。こうするんですね。わかりやした。」と多少おどけたような口調でとみんなの代表のような形で、演出担当の「おじいさん」に返事しながら、その場の雰囲気をやわらげていた。
この大衆作家は実に大物で私は中学生のころからその作品を読んでおり、雑誌などでその写真もみており見覚えがあった。
なるほど、この人にはこういうところがある人だったのだと好意を持ってていた。
ところで、本題のわれらの曽野綾子女史のことである。同女史はまだ20歳代の後半だったであろう。
演技の指導を受けながら、「おいおい、座るのはそこではない。もっと左、左!」と演出のこわい「おじいさん」に怒鳴られたた。
そうすると、われらが曽野綾子女史は黙ってすっと立ち、その上に自分が座っていた座布団を、自分の足の親指と足の人差し指?とでつまんで持ち上げて手に持ち、演出が指示する場所に座布団をおいて座ったのである。
足の指で座布団を持ち上げるなどということは子供のころの私たちは得意であったが、それをやってよく母親に、行儀が悪いと言って叱られたものである。
わららのあこがれの的の女流作家の曽野綾子氏が、それをさりげなくされているのを見て、私は内心驚きながら、今まで以上に親密さが増したような気ががして、心の中で拍手を送ったのであった。
頭のよい東京の良家の子女はなかなかスマートだなというのが私の印象であった。
ある時、このことを義兄の船山幸哉に話したところ、彼は顔をほころばせ、「やんぬるかな」というような様子で喜んでいた。彼の曽野綾子女史に対するフアンとしての気持ちはますます高まったのではないかという気がする
1955年か56年のころの話である。
余談であるが、義兄船山幸哉は昨年10月に、敬虔なカトリック信者としての一生を終えた。
中途で文学部志望を変えて法学部へ行き、そして製造メーカーでサラリーマン生活を送った私とはちがい、義兄船山は大学で学生にドイツ語を教え、ドイツ文学はじめ、各国の文学を読み、語りながら私が学生時代に接したと同じような生活をしてその一生を終えた。
彼の息子の一人すなわち私の甥の一人は、この文士劇を主催していた文芸春秋社に入社し、今では私達が若いころ、同人雑誌を作ると選評を期待しては送った「文学界」の編集長をしているようである。(「文学」というものでメシを食えて、何と幸せな甥だろうと思うのだが・・・)
私が船山に、文士劇での曽野綾子女史の話を報告したときには、まだ、この甥は生まれていなかった。
私に、この文士劇のリハーサルの切符を下さった、杉並区荻窪のI夫人は残念ながら数年前に亡くなった。今はそのご子息夫妻が、私のよいお付き合い相手である。
前述の私の甥の母親、船山幸哉の妻はであり私の姉はもう二十年以上前に老いる前に亡くなった。
弟思いのよい姉であった。
曽野綾子女史の随筆集「あすは野となれ」を手にしながら、私は遠い昔のことを思い出しているのである。
(曽野綾子女史が、座布団を足のの指で持ち上げることなどするはずはない。それは年老いて夢も誠も判別できなくなったお前の妄想だろうとおっしゃる曽野フアンの方も多いと思う。
そうです。私の記憶違いか、思いちがいだったのかもしれません。
もしく曽野先生はは演出のおじいさんの怒声に憤激して、おやりになったことかもしれません。
曽野先生には、今後ともますますお元気で健筆をふるって頂きたいものだと思います。)
(おわり)
画像:筆者撮影
関連記事:「I家の人々」1
同 2
同 3 曽野綾子著「あとは野となれ」1
私が大学の教養課程のころだった。大学の早野先生、西村秀夫先生のアイデアで始まり、私達学生が家庭教師の一種としてやっていた、小学生を対象にした「理科クラブ」のために自宅を提供して下さっていた杉並区荻窪のI夫人が、文芸春秋社主催の文士劇の切符を私に下さった。
I夫人は、私のこのブログにも出て来るI氏の母君である。
「理科クラブ」の催しの後に、指導役の大学生の私たちがお茶を頂き雑談しているときに私が文学好きであり、また文学部への進学を希望しているということを聞いておられたのであろう。
その切符は、「リハーサルの切符」であった。
リハーサルが行われていたのはどこの劇場であったろう。50年も前のことで正確には覚えていない。
受付で入場券を見せて席に座っていると、やがてリハーサルが始まった。
観客はまばらである。
リハーサルというより、まだ練習のような段階であった。
題目は歌舞伎からのものであった。
舞台では、客席の前の方に座っている演出のおじいさんの厳しい指示をうけながら動いている背のすらりとした若い女性がいいた。
それが、私たちのあこがれていた、曽野綾子女史であった。
演出を担当しているのは、歌舞伎界の大物であったのだろう。超一流の人気作家連中に厳しい演技修正の指示をとばしていた。怒声である。
いつも周囲にちやほやされているであろう舞台の上の作家連中は、ふくれながらもその演技のふりつけの指示に従っていた。
時代物の大衆文学の大物作家のK氏も舞台の上での配役の一人であったが、が、固くこわばったその場の雰囲気を、
「へいへい、かしこまりました。こうするんですね。わかりやした。」と多少おどけたような口調でとみんなの代表のような形で、演出担当の「おじいさん」に返事しながら、その場の雰囲気をやわらげていた。
この大衆作家は実に大物で私は中学生のころからその作品を読んでおり、雑誌などでその写真もみており見覚えがあった。
なるほど、この人にはこういうところがある人だったのだと好意を持ってていた。
ところで、本題のわれらの曽野綾子女史のことである。同女史はまだ20歳代の後半だったであろう。
演技の指導を受けながら、「おいおい、座るのはそこではない。もっと左、左!」と演出のこわい「おじいさん」に怒鳴られたた。
そうすると、われらが曽野綾子女史は黙ってすっと立ち、その上に自分が座っていた座布団を、自分の足の親指と足の人差し指?とでつまんで持ち上げて手に持ち、演出が指示する場所に座布団をおいて座ったのである。
足の指で座布団を持ち上げるなどということは子供のころの私たちは得意であったが、それをやってよく母親に、行儀が悪いと言って叱られたものである。
わららのあこがれの的の女流作家の曽野綾子氏が、それをさりげなくされているのを見て、私は内心驚きながら、今まで以上に親密さが増したような気ががして、心の中で拍手を送ったのであった。
頭のよい東京の良家の子女はなかなかスマートだなというのが私の印象であった。
ある時、このことを義兄の船山幸哉に話したところ、彼は顔をほころばせ、「やんぬるかな」というような様子で喜んでいた。彼の曽野綾子女史に対するフアンとしての気持ちはますます高まったのではないかという気がする
1955年か56年のころの話である。
余談であるが、義兄船山幸哉は昨年10月に、敬虔なカトリック信者としての一生を終えた。
中途で文学部志望を変えて法学部へ行き、そして製造メーカーでサラリーマン生活を送った私とはちがい、義兄船山は大学で学生にドイツ語を教え、ドイツ文学はじめ、各国の文学を読み、語りながら私が学生時代に接したと同じような生活をしてその一生を終えた。
彼の息子の一人すなわち私の甥の一人は、この文士劇を主催していた文芸春秋社に入社し、今では私達が若いころ、同人雑誌を作ると選評を期待しては送った「文学界」の編集長をしているようである。(「文学」というものでメシを食えて、何と幸せな甥だろうと思うのだが・・・)
私が船山に、文士劇での曽野綾子女史の話を報告したときには、まだ、この甥は生まれていなかった。
私に、この文士劇のリハーサルの切符を下さった、杉並区荻窪のI夫人は残念ながら数年前に亡くなった。今はそのご子息夫妻が、私のよいお付き合い相手である。
前述の私の甥の母親、船山幸哉の妻はであり私の姉はもう二十年以上前に老いる前に亡くなった。
弟思いのよい姉であった。
曽野綾子女史の随筆集「あすは野となれ」を手にしながら、私は遠い昔のことを思い出しているのである。
(曽野綾子女史が、座布団を足のの指で持ち上げることなどするはずはない。それは年老いて夢も誠も判別できなくなったお前の妄想だろうとおっしゃる曽野フアンの方も多いと思う。
そうです。私の記憶違いか、思いちがいだったのかもしれません。
もしく曽野先生はは演出のおじいさんの怒声に憤激して、おやりになったことかもしれません。
曽野先生には、今後ともますますお元気で健筆をふるって頂きたいものだと思います。)
(おわり)
画像:筆者撮影
関連記事:「I家の人々」1
同 2
同 3 曽野綾子著「あとは野となれ」1