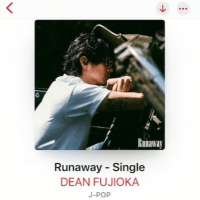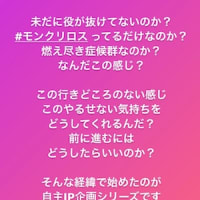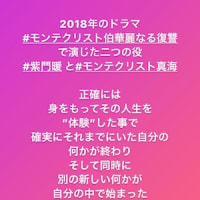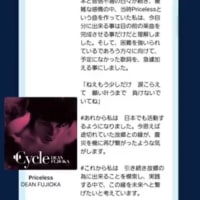上方の伝統芸能についてコメントを投稿いただき、その
お返事を書きながら、自分が全然わかっていないことに
気づいた。Ah、ビギナー脱出はまだまだムリだ~。
以下、上方歌舞伎と上方式・江戸式 について一部引用・
転載をさせていただき自分用メモとする。

<自分用整理メモ>
●上方歌舞伎
主として大阪・京都を中心に発展してきた歌舞伎の型、
技法、演出、演技法、演目、劇壇などを総称して言う。
江戸歌舞伎とともに歌舞伎の両輪をなす。
(ウィキペディアより)
●上方歌舞伎の祖は、元禄期の名優坂田藤十郎とされて
いる。もっとも、上方歌舞伎の歴史は江戸歌舞伎ほどは
判然とはしていない。型や伝統を重んじる江戸歌舞伎に
対して、上方の気質というものは、個人の工夫というも
のを大切にしたために、型や芸脈の系譜というものがた
どりにくいのである。
(写真 岩田アキラ『扇雀 上方芸と近松』より)
●江戸歌舞伎と上方歌舞伎のもっとも大きな差は、前者
が伝統を重んじ、型を尊重するのに対し、後者は父祖や
師匠から受け継いだ演出よりも自分自身のくふうに重点
をおいているともいえる。(中略)
和事は根本的な段取りはあっても、いかに表現すべきか
は各人の技量にかかり、荒事よりはるかに写実性がある。
(監修 河竹登志夫『歌舞伎』より)
●丸本物には上方式と江戸式の演出がある。
(ウィキペディアより)
●人形浄瑠璃との密接な交流の期間に、歌舞伎の様式に
は大きな変化が現れてきた。(中略)
「糸にのる」せりふをいう手法など、さらに進んでは
「人形ぶり」の演出までも創りだしていた。とりわけ
上方歌舞伎にあってはこの傾向が強くなり、義太夫の素養
があり、丸本物の様式的演技をしこなすことが役者の基本
条件になったほどである。音楽劇的傾向は、東西の役者の
交流を通じて江戸歌舞伎にももたされた。
(監修 河竹登志夫『歌舞伎』より)
●江戸時代の中期から末期にさしかかるころ、一般に歌
舞伎の演技に写実的傾向が表面化した。江戸の初代中村
仲蔵や上方の四代目市川団蔵や三代目中村歌右衛門の模
索した新しい丸本物の創造法がそれであった。
(監修 河竹登志夫『歌舞伎』より)
●近代に入って、九代目市川団十郎はからだを大仰に様式
的に動かすことを抑えて、人物の性格・心理の表現を重ん
ずる「腹芸」という演技術をはじめた。(中略)
創造の姿勢や態度・演技術としては九代目団十郎の方法が
正統のものとされて、現代に影響を与えている。
(監修 河竹登志夫『歌舞伎』より)
●熊谷は古風な「芝翫型」から七代目団十郎を経て、九代目
が武士魂あふれる近代的な「団十郎型」を完成させた。
「首実検の後、敦盛と偽った息子の首を素知らぬ顔で妻に渡
す。胸中に万感あろうと、さあ我が子だよ、なんて芝居はし
ない。九代目が作り上げた腹芸が、武士の世界を見せる上で
非常に重要になっている。言わぬは言うに言い勝る。熊谷の
真骨頂です。世の無常、理不尽に向き合う姿を、演じつつ感
じていたいと思います。」(団十郎)
(朝日新聞デジタル 2012年3月3日 「団十郎、世の無常と
向き合う 13年ぶり「熊谷陣屋」」より)
●実事
立役の役柄の一つを指すとともに演技の一系統を意味します。
誇張された力を表現する荒事、優美で時には滑稽な表現の伴う
和事に対して、実事では誠実な人物が悲劇的な状況の中で苦悩
しながらも事件に立ち向かう姿を描きます。代表的な役には
『仮名手本忠臣蔵』の大星由良之助、『一谷嫩軍記』の熊谷
(次郎)直実などがあげられ、いずれも内面的な演技が要求
されます。
(『歌舞伎事典』より)
●現在でもよく出る芝居ですが、大阪の狂言でありながら東京
の人がやることが多くなって、大阪の泥絵具で描いたような、
脂っこいというか、灰汁が強いというか、そういった感じがな
くなりつつあるのですね。この『夏祭』がすっきりしては困る
のです。
(片岡仁左衛門 著『夏祭と伊勢音頭』より)
●河内屋のおじさん(二代目延若)、靍砂屋さん(三代目中村
梅玉)、魁車さん(初代中村魁車)と、上方の座組の中にわた
くし一人が東京から飛びこんだんだけど、やっぱり全然違うん
ですよ。顔世とおかると、人数が少いんで討ち入りの佐藤与茂
七にも出ましたけどね、六、七段目なんか全然違うんですよ。
下座(黒御簾)一つにしてもね。それでまあまあそちらのほう
へも付き、また東京式にもしたり致しましたけどね。
(六世中村歌右衛門)
(関容子『芸づくし忠臣蔵』より)
●江戸式が盛んになって、そちらが本来の演り方やと思ってお
られる方も多い。それがとっても淋しいと思っていましたけれ
ど、最近は上方の演り方も分かってもらえるようになってきた
のが嬉しいことですね。
(片岡秀太郎『上方のをんな』「仮名手本忠臣蔵」より)
●いがみの権太は、実家のすし屋で母親を騙して、お金を貰う。
上方のあかんたれが母に甘えて媚びている匂いと、江戸っ子の
小粋な悪党が母親にねだっている雰囲気とでは、やっぱり全然
違いますね。父は愛嬌のある上方の権太でしたし、(三代目實川)
延若にいさんのこてっとした上方の権太も、とても印象に残っ
ています。
(片岡秀太郎『上方のをんな』「義経千本桜」より)
●上方歌舞伎・想い出の俳優バックナンバー
(『歌舞伎美人』歌舞伎コラムより)
●京・大阪で生まれた「上方舞」。江戸の歌舞伎から舞踊部分
を取り出した「踊り」に対して、上方の「舞」は能や文楽の
影響を色濃く受けて発展しました。身体の動きを極限まで抑え
て、心の内面を表現することが特徴です。
(堀口初音『上方伝統芸能あんない』より)