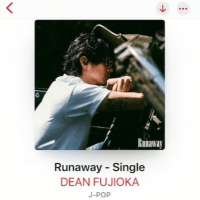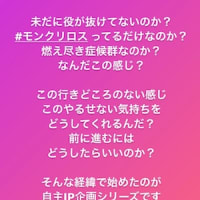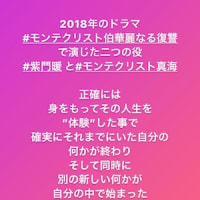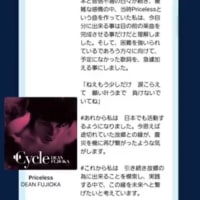重複回避また記録として、訪問したら記録するページ(10)。
記録優先!随時追記あり。
京都は★、奈良は●、その他は■
2015年
<7月>
5日
■勝尾寺(西国二十三番札所)
紫陽花がまだ見られると聞きお参りした。
赤い仁王門の向こうにお浄め橋があり橋の下からミストが出ていた。
勝ちダルマ納め所があるのが独特。このダルマはただ一つのお願い
ごとに対して直接目を入れるお守りであるとのこと。「次のお願い
ごとをしてはいけない」と書かれていた。
参道や屋根や燈籠などいたるとことに飾られている小さなダルマは
おみくじのダルマさん。
歴史を感じる建物、お堂がたくさん。ボリュームはないけれど、
紫陽花もきれいだった。
11日
祇園祭。鉾建てを見て回る。(※ブログに)
19日
●奈良散策
日本聖公会 奈良基督教会礼拝堂を見学。(※ブログに)
白鳳展(奈良国立博物館)
薬師寺の薬師三尊の月光菩薩、法隆寺の夢違観音から、たくさんの
金銅仏、押出仏、出土品にいたるまで。
ポスターにもある伝橘夫人の念持仏である阿弥陀三尊像は背後の
屏風と底部の蓮池が一体に考えられたデザインが見事だった。
薬師寺の月光菩薩は光背なしの状態で近づいて360度から見られる。
キュッ絞って捻った腰や逆三に盛り上がった背中、法衣のディテール
などまでじっくり拝見できた。これは展覧会じゃないとムリ。
国宝・重要文化財がぎっしりで、今までに現地のお寺で拝観したこと
のある仏さまもけっこうあった。私が白鳳仏を意識し始めたのは奈良の
般若寺だったと思う。
鶴林寺のあいたたの観音にも再会。横から見ると笑顔が倍増!
仏頭(国宝)は8月後半にお目見え。興福寺の国宝館で二度ほど拝見
しているので今回はよしとする。
まだ拝観できていなかった奈良・正暦寺のご本尊、薬師如来倚像を
初めて見ることができた。博物館では白い仮の台に坐られているがお寺
では何の上に越し掛けておられるのだろう。
野中寺の秘仏、弥勒菩薩半跏像は金銅仏の中でもめずらしい坐像で
頭部の飾りや法衣の模様などが緻密で細かいつくりだった。
26日
■大龍寺(神戸)
急きょ出かけられることになり、近場である地元神戸のお寺へ。
再度山にあり、以前にも来たはずだがゆっくり拝観したのは初めて。
和気清麻呂の開基になる。弘法大師が入唐の前に求法を祈り、帰朝の
のちに再び登山したことから「再度山」の名がついた。大師道という
名の参道(登山道)もある。
ご本尊は秘仏である如意輪観音立像。7月の土用の入りに法要があり
御開帳になるらしい。ちょうど1週間前だったとのこと。
如意輪観音で立像はめずらしい。ご朱印をいただく際にカラー写真
を見せていただいたが、ちょっと室生寺の阿弥陀さまを思い出した。
境内から再度山山頂に向かう途中、岩の上に弘法大師作とされる亀石
があった。
帰りは大師道を下り、猩々池に出て諏訪山方面へ。青もみじがきれいな
登山道で、途中で出会った人にも秋の紅葉が素晴しいと聞いた。
季節を変えてまた登ってみよう。
<8月>
2日
■高月の観音さま(滋賀県)
「第31回観音の里たかつきふるさとまつり」で湖北にある高月へ。
1年にこの日だけ開くお堂や、ふだん見られない仏さまを見せていただ
ける。私たちが拝観できるのは暑い中お世話してくださる地元の皆さん
のおかげ。いっぱい見て、歩いて、地元の人たちとお話して癒されました。
冷えたお茶、お菓子、西瓜をごちそうになり、ありがとうございました。
拝観したお寺9社。
磯野寺(小さな十一面観音立像、三光の松)
赤分寺(金色の十一面観音立像)
尾山釈迦堂(重文の釈迦如来座像、大日如来坐像)
雨森観音寺(千手観音立像。袋かけ観音:頭上で手を重ねる清水寺式)
保延寺観音堂(小さな千手観音立像)
円満寺(阿弥陀如来立像は整ったお顔。拝観料300円)
理学院(聖観音菩薩立像、百体観音像、浅井長政の母親の住まい)
浄光寺(白いお顔の十一面観音立像)
柏原阿弥陀堂(阿弥陀如来像、薬師如来・日光・月光・十二神将、
長浜市指定自然記念物のケヤキの大木)
北近江リゾートでランチ。
9日
★京都国立博物館
特別展観「第100回大蔵会記念 仏法東漸―仏教の 典籍と美術─」
小金銅仏
★京の七夕(鴨川)、迎え鐘(六波羅蜜寺、六道珍皇寺)
14日
■粉河寺(和歌山県)



粉河寺前から南の山を望む

根来寺(和歌山県)
見上げる三尊に圧倒された「大傳法堂」。ご本尊は大日如来、脇仏は
金剛薩埵(こんごうさった)と尊勝仏頂。
境内のどの角度、どの場所から見ても、塔内に入って中を拝観しても
素晴しい「大塔」。この形で高野山を思い出したが、今ではこちらの
ほうが古い。日本最大の木造多宝塔で、明治32年に国宝に指定。
弘法大師の像をお祀りする「大師堂」の須弥壇。大傳法堂、大塔ととも
に、豊臣秀吉の紀州攻めの焼打ちを免れたもの。
奥の院の御廟所に眠る覚鑁(かくばん)上人。ここでも高野山を感じる。
ご朱印をお願いしている合間に、覚鑁上人のお像を安置する光明殿を
見せていただいた。修行僧が授かる守護札らしきものも見つけた。
外に出て夕陽を受けた大門を見たとき、やっぱりここは高野山、プチ
高野山だという思いがした。
現在は「新義真言宗」のお寺だけれど、弘法大師入定から300年後に
真言密教の教学修行を復興した覚鑁上人の思いが隅々にまで行き渡って
いるように感じられ、余韻に浸りながら帰途についた。



16日
★福勝寺、清和院(洛陽第三十三番)
★千本釈迦堂(送り鐘、行快作の釈迦如来坐像1年に一度のご開帳、
霊宝館再訪。快慶作の木造十大弟子立像、定慶作の六観音像ほか)
★五山の送り火
<9月>
13日
★神光院(京都三弘法のひとつ、明治の女流歌人蓮月尼ゆかりの茶室ほか)
大将軍神社、西方寺(蓮月尼供養碑)、霊源皇寺(岩倉具視ゆかりの寺、
外だけ)、上賀茂神社(式年遷宮)、二葉姫稲荷神社(上賀茂さんの奥)





賀茂川をさかのぼって神光院ほか西賀茂を散策。上賀茂神社に
お参りした後、再び賀茂川・鴨川をゆっくりあるいた。
ランニングする人、楽器を演奏する者、ベンチで女子会、犬の散歩、
寝そべったり、キャッチボールしたり・・・思い思いに過ごす夕暮れ時
の鴨川の気持ちいいこと。川の上を滑空するとんび、鴨川に最もふさわ
しいマガモ軍団、カモを牽制しながら段差の下で魚を狙う白サギ。
川を往復している間にヌートリアを3頭見つけた。ヌートリアに餌をやら
ないようにと注意を促す看板がまだ新しかった。


2~3週間ほど休めずまったく歩いていなかったため、足のコンディション
が最悪だったが、5時間ぐらい歩いたおかげで足の痛みがスッと消えた。
20日
■室生寺
※ブログ「室生寺の「灌頂堂」特別開帳。」に。
23日
■無動寺
箕谷~衝原
<10月>
4日
★直指庵
嵯峨野・嵐山界隈
※ブログ「嵯峨野から嵐山へ。」に。
12日
■大津市歴史博物館
★毘沙門堂
※ブログ「大津市歴史博物館と毘沙門堂(1)」に。
※ブログ「大津市歴史博物館と毘沙門堂(2)」に。
18日
■安楽寺(若狭)
■高成寺・栖雲寺・常高寺(小浜)
※ブログ「みほとけの里・若狭(1)安楽寺」に。
※ブログ「みほとけの里・若狭(2)高成寺と栖雲寺」に。
※ブログ「みほとけの里・若狭(3)常高寺」に。
25日
■東山寺(淡路島)
勤王の志士と廃仏毀釈~歴史秘話にいろどられた淡路島の古刹。



31日
★東寺(灌頂院、講堂、金堂、五重塔初層)
★京都国立博物館
※ブログ「京都国立博物館」で「琳派誕生400年記念 琳派 京を彩る」に。
<11月>
7日
★西方寺(阿弥陀如来坐像)
★金戒光明寺 秋の特別公開:山門(天井画「蟠龍図」、市内一望の絶景)
御影堂・大方丈・庭園(伝運慶作・文殊菩薩像、吉備観音像、
伊藤若冲筆「群鶏図」屏風、虎の襖絵、紫雲の庭と回遊式庭園)
★西雲院(紫雲石)
★真如堂
※ブログ「京都・西方寺~金戒光明寺~真如堂」に。
15日
★醍醐寺(2015年醍醐寺霊宝館秋冬期特別展「宗達とその時代」)
俵屋宗達筆の「舞楽図屏風」「扇面散図屏風」「芦鴨図衝立」
(舞楽図屏風、扇面散図屏風は京都国立博物館の琳派展に陳列されて
いたもので、こちらは人も少なくゆっくり観られた。)
薬師三尊像の薬師如来坐像・日光菩薩像・月光菩薩像(国宝)ほか
★坂上田村麻呂の墓
新感線の「阿弖流為」を見て思い出した。死後もずっと都を守護し続けて
いる将軍の姿を想像し切なくなったので、再びこのお墓にお参りした。
プレートの説明書きによれば、「この墓には、平安前期の武将坂上田村麻呂
を葬っている」とある。さらに「嵯峨天皇の勅により甲冑・剣や弓矢を
具した姿で棺に納められ、平安京に向かって立ったまま葬られた」とのこと。
明治28年の平安遷都千百年祭にさいし整備されたこの墓地は現在、住宅地の
真ん中にあり、隣りには児童公園もある場所。
小野篁の少年期の話を書いた『鬼の橋』(伊藤遊著、福音館文庫)には、
死後も甲冑姿で都を守り続ける将軍の話が出てくる。冥界の入り口に立ち続け、
鬼と戦っている様子を、偶然冥界に迷い込んだ小野篁は見てしまう。
奥のほうにはあの世へ渡る橋があり、皆は渡ってゆくのに、坂上田村麻呂だけ
は渡れないのだという。やがて小野篁が父親の転勤で都を離れるという時、
冥界からやってきた鬼で、今は人間の心を取り戻した非天丸にある願いを託す。
お前は力持ちだから、立ったままでいる将軍の棺を横にしてあげてくれと。
スバラシイ!子供向きの本だしファンタジーだというのにすっかり共感大拍手。
おかげで切ない気持ちがやわらいだ。
この本をお墓に連れて行き、ツーショットで記念撮影。はたして棺は今も立って
いるのか?非天丸は来たのか? などという思いが頭をかすめつつ。
第3回児童文学ファンタジー大賞受賞作品。大人の私にも面白い本だった!
22日
■神戸 布引~トゥエンティクロス~森林植物園
大師道の紅葉が目的だったのに、どうせならと登りコースに森林植物園を追加。
子供からお年寄りまで歩いている初心者コース。整備され、あまりに安全でつい
公園を歩いている気持ちになったのがいけなかった。平坦な道にあった倒木の
小さな枝に足を引っかけて前のめりに転倒。ムム、慢心につけいる倒木妖怪
トーボックのしわざか。軽傷と思いきや、その後も右膝から血がポタポタ流れ
続け、止まらず。やむなく森林植物園から途中リタイア。その日は自宅でランチ。
目的の大師道の紅葉が見られず残念!植物園の紅葉はタイミングがわるかった
ようで、もみじ坂のあたりはイマイチだったなぁ。
(翌朝も血が止まらず、出勤前に救急で受診。化膿の危険性があったため縫わず
に処置。当日なら縫えたので、そんな時はすぐに来るようにと言われた。)
29日
■當麻寺
※ブログ「當麻寺西南院と、ちょこっと葛城の道。(1)」に。
■九品寺、綏靖天皇葛城高丘宮趾、葛城一言主神社
※ブログ「當麻寺西南院と、ちょこっと葛城の道。(2)」に。
<12月>
6日
■諏訪神社~大師道~大龍寺~布引の滝
※ブログ「ふたたびのみち、大師道。」に。
12日

京都の嵐山を散策。嵐山花灯路にも少しだけ。
★大悲閣、櫟谷神社・宗像神社、車折神社





20日
京都国立博物館と寺町界隈散策
・特集陳列「さるづくしー干支を愛でるー」
(重文 巌樹遊猿図屏風 式部輝忠筆、曾我蕭白、長澤蘆雪、
森狙仙、伊藤若冲 ほか)
・特集陳列「獅子と狛犬」
(丹生都比売神社の大きな獅子・狛犬がよかった。)
あいにく「刀剣を楽しむ」のコーナーは行列ができており、
待ち時間も長くて鑑賞をあきらめた。
名品ギャラリーの1階仏像の部屋に長岡京市、光明寺の千手観音立像
が展示されていた。どっしりと量感のある木造の観音さま。お顔が
なんとも素敵で、こういう表情のことを「晦渋」というのだそうだ。
国の重文に指定されてからは京博に寄託中。
(ちなみに、現在光明寺の観音堂に安置されているのは粟生観音寺の
十一面千手観音とのこと。)
★本能寺
記録優先!随時追記あり。
京都は★、奈良は●、その他は■
2015年
<7月>
5日
■勝尾寺(西国二十三番札所)
紫陽花がまだ見られると聞きお参りした。
赤い仁王門の向こうにお浄め橋があり橋の下からミストが出ていた。
勝ちダルマ納め所があるのが独特。このダルマはただ一つのお願い
ごとに対して直接目を入れるお守りであるとのこと。「次のお願い
ごとをしてはいけない」と書かれていた。
参道や屋根や燈籠などいたるとことに飾られている小さなダルマは
おみくじのダルマさん。
歴史を感じる建物、お堂がたくさん。ボリュームはないけれど、
紫陽花もきれいだった。
11日
祇園祭。鉾建てを見て回る。(※ブログに)
19日
●奈良散策
日本聖公会 奈良基督教会礼拝堂を見学。(※ブログに)
白鳳展(奈良国立博物館)
薬師寺の薬師三尊の月光菩薩、法隆寺の夢違観音から、たくさんの
金銅仏、押出仏、出土品にいたるまで。
ポスターにもある伝橘夫人の念持仏である阿弥陀三尊像は背後の
屏風と底部の蓮池が一体に考えられたデザインが見事だった。
薬師寺の月光菩薩は光背なしの状態で近づいて360度から見られる。
キュッ絞って捻った腰や逆三に盛り上がった背中、法衣のディテール
などまでじっくり拝見できた。これは展覧会じゃないとムリ。
国宝・重要文化財がぎっしりで、今までに現地のお寺で拝観したこと
のある仏さまもけっこうあった。私が白鳳仏を意識し始めたのは奈良の
般若寺だったと思う。
鶴林寺のあいたたの観音にも再会。横から見ると笑顔が倍増!
仏頭(国宝)は8月後半にお目見え。興福寺の国宝館で二度ほど拝見
しているので今回はよしとする。
まだ拝観できていなかった奈良・正暦寺のご本尊、薬師如来倚像を
初めて見ることができた。博物館では白い仮の台に坐られているがお寺
では何の上に越し掛けておられるのだろう。
野中寺の秘仏、弥勒菩薩半跏像は金銅仏の中でもめずらしい坐像で
頭部の飾りや法衣の模様などが緻密で細かいつくりだった。
26日
■大龍寺(神戸)
急きょ出かけられることになり、近場である地元神戸のお寺へ。
再度山にあり、以前にも来たはずだがゆっくり拝観したのは初めて。
和気清麻呂の開基になる。弘法大師が入唐の前に求法を祈り、帰朝の
のちに再び登山したことから「再度山」の名がついた。大師道という
名の参道(登山道)もある。
ご本尊は秘仏である如意輪観音立像。7月の土用の入りに法要があり
御開帳になるらしい。ちょうど1週間前だったとのこと。
如意輪観音で立像はめずらしい。ご朱印をいただく際にカラー写真
を見せていただいたが、ちょっと室生寺の阿弥陀さまを思い出した。
境内から再度山山頂に向かう途中、岩の上に弘法大師作とされる亀石
があった。
帰りは大師道を下り、猩々池に出て諏訪山方面へ。青もみじがきれいな
登山道で、途中で出会った人にも秋の紅葉が素晴しいと聞いた。
季節を変えてまた登ってみよう。
<8月>
2日
■高月の観音さま(滋賀県)
「第31回観音の里たかつきふるさとまつり」で湖北にある高月へ。
1年にこの日だけ開くお堂や、ふだん見られない仏さまを見せていただ
ける。私たちが拝観できるのは暑い中お世話してくださる地元の皆さん
のおかげ。いっぱい見て、歩いて、地元の人たちとお話して癒されました。
冷えたお茶、お菓子、西瓜をごちそうになり、ありがとうございました。
拝観したお寺9社。
磯野寺(小さな十一面観音立像、三光の松)
赤分寺(金色の十一面観音立像)
尾山釈迦堂(重文の釈迦如来座像、大日如来坐像)
雨森観音寺(千手観音立像。袋かけ観音:頭上で手を重ねる清水寺式)
保延寺観音堂(小さな千手観音立像)
円満寺(阿弥陀如来立像は整ったお顔。拝観料300円)
理学院(聖観音菩薩立像、百体観音像、浅井長政の母親の住まい)
浄光寺(白いお顔の十一面観音立像)
柏原阿弥陀堂(阿弥陀如来像、薬師如来・日光・月光・十二神将、
長浜市指定自然記念物のケヤキの大木)
北近江リゾートでランチ。
9日
★京都国立博物館
特別展観「第100回大蔵会記念 仏法東漸―仏教の 典籍と美術─」
小金銅仏
★京の七夕(鴨川)、迎え鐘(六波羅蜜寺、六道珍皇寺)
14日
■粉河寺(和歌山県)



粉河寺前から南の山を望む

根来寺(和歌山県)
見上げる三尊に圧倒された「大傳法堂」。ご本尊は大日如来、脇仏は
金剛薩埵(こんごうさった)と尊勝仏頂。
境内のどの角度、どの場所から見ても、塔内に入って中を拝観しても
素晴しい「大塔」。この形で高野山を思い出したが、今ではこちらの
ほうが古い。日本最大の木造多宝塔で、明治32年に国宝に指定。
弘法大師の像をお祀りする「大師堂」の須弥壇。大傳法堂、大塔ととも
に、豊臣秀吉の紀州攻めの焼打ちを免れたもの。
奥の院の御廟所に眠る覚鑁(かくばん)上人。ここでも高野山を感じる。
ご朱印をお願いしている合間に、覚鑁上人のお像を安置する光明殿を
見せていただいた。修行僧が授かる守護札らしきものも見つけた。
外に出て夕陽を受けた大門を見たとき、やっぱりここは高野山、プチ
高野山だという思いがした。
現在は「新義真言宗」のお寺だけれど、弘法大師入定から300年後に
真言密教の教学修行を復興した覚鑁上人の思いが隅々にまで行き渡って
いるように感じられ、余韻に浸りながら帰途についた。



16日
★福勝寺、清和院(洛陽第三十三番)
★千本釈迦堂(送り鐘、行快作の釈迦如来坐像1年に一度のご開帳、
霊宝館再訪。快慶作の木造十大弟子立像、定慶作の六観音像ほか)
★五山の送り火
<9月>
13日
★神光院(京都三弘法のひとつ、明治の女流歌人蓮月尼ゆかりの茶室ほか)
大将軍神社、西方寺(蓮月尼供養碑)、霊源皇寺(岩倉具視ゆかりの寺、
外だけ)、上賀茂神社(式年遷宮)、二葉姫稲荷神社(上賀茂さんの奥)





賀茂川をさかのぼって神光院ほか西賀茂を散策。上賀茂神社に
お参りした後、再び賀茂川・鴨川をゆっくりあるいた。
ランニングする人、楽器を演奏する者、ベンチで女子会、犬の散歩、
寝そべったり、キャッチボールしたり・・・思い思いに過ごす夕暮れ時
の鴨川の気持ちいいこと。川の上を滑空するとんび、鴨川に最もふさわ
しいマガモ軍団、カモを牽制しながら段差の下で魚を狙う白サギ。
川を往復している間にヌートリアを3頭見つけた。ヌートリアに餌をやら
ないようにと注意を促す看板がまだ新しかった。


2~3週間ほど休めずまったく歩いていなかったため、足のコンディション
が最悪だったが、5時間ぐらい歩いたおかげで足の痛みがスッと消えた。
20日
■室生寺
※ブログ「室生寺の「灌頂堂」特別開帳。」に。
23日
■無動寺
箕谷~衝原
<10月>
4日
★直指庵
嵯峨野・嵐山界隈
※ブログ「嵯峨野から嵐山へ。」に。
12日
■大津市歴史博物館
★毘沙門堂
※ブログ「大津市歴史博物館と毘沙門堂(1)」に。
※ブログ「大津市歴史博物館と毘沙門堂(2)」に。
18日
■安楽寺(若狭)
■高成寺・栖雲寺・常高寺(小浜)
※ブログ「みほとけの里・若狭(1)安楽寺」に。
※ブログ「みほとけの里・若狭(2)高成寺と栖雲寺」に。
※ブログ「みほとけの里・若狭(3)常高寺」に。
25日
■東山寺(淡路島)
勤王の志士と廃仏毀釈~歴史秘話にいろどられた淡路島の古刹。



31日
★東寺(灌頂院、講堂、金堂、五重塔初層)
★京都国立博物館
※ブログ「京都国立博物館」で「琳派誕生400年記念 琳派 京を彩る」に。
<11月>
7日
★西方寺(阿弥陀如来坐像)
★金戒光明寺 秋の特別公開:山門(天井画「蟠龍図」、市内一望の絶景)
御影堂・大方丈・庭園(伝運慶作・文殊菩薩像、吉備観音像、
伊藤若冲筆「群鶏図」屏風、虎の襖絵、紫雲の庭と回遊式庭園)
★西雲院(紫雲石)
★真如堂
※ブログ「京都・西方寺~金戒光明寺~真如堂」に。
15日
★醍醐寺(2015年醍醐寺霊宝館秋冬期特別展「宗達とその時代」)
俵屋宗達筆の「舞楽図屏風」「扇面散図屏風」「芦鴨図衝立」
(舞楽図屏風、扇面散図屏風は京都国立博物館の琳派展に陳列されて
いたもので、こちらは人も少なくゆっくり観られた。)
薬師三尊像の薬師如来坐像・日光菩薩像・月光菩薩像(国宝)ほか
★坂上田村麻呂の墓
新感線の「阿弖流為」を見て思い出した。死後もずっと都を守護し続けて
いる将軍の姿を想像し切なくなったので、再びこのお墓にお参りした。
プレートの説明書きによれば、「この墓には、平安前期の武将坂上田村麻呂
を葬っている」とある。さらに「嵯峨天皇の勅により甲冑・剣や弓矢を
具した姿で棺に納められ、平安京に向かって立ったまま葬られた」とのこと。
明治28年の平安遷都千百年祭にさいし整備されたこの墓地は現在、住宅地の
真ん中にあり、隣りには児童公園もある場所。
小野篁の少年期の話を書いた『鬼の橋』(伊藤遊著、福音館文庫)には、
死後も甲冑姿で都を守り続ける将軍の話が出てくる。冥界の入り口に立ち続け、
鬼と戦っている様子を、偶然冥界に迷い込んだ小野篁は見てしまう。
奥のほうにはあの世へ渡る橋があり、皆は渡ってゆくのに、坂上田村麻呂だけ
は渡れないのだという。やがて小野篁が父親の転勤で都を離れるという時、
冥界からやってきた鬼で、今は人間の心を取り戻した非天丸にある願いを託す。
お前は力持ちだから、立ったままでいる将軍の棺を横にしてあげてくれと。
スバラシイ!子供向きの本だしファンタジーだというのにすっかり共感大拍手。
おかげで切ない気持ちがやわらいだ。
この本をお墓に連れて行き、ツーショットで記念撮影。はたして棺は今も立って
いるのか?非天丸は来たのか? などという思いが頭をかすめつつ。
第3回児童文学ファンタジー大賞受賞作品。大人の私にも面白い本だった!
22日
■神戸 布引~トゥエンティクロス~森林植物園
大師道の紅葉が目的だったのに、どうせならと登りコースに森林植物園を追加。
子供からお年寄りまで歩いている初心者コース。整備され、あまりに安全でつい
公園を歩いている気持ちになったのがいけなかった。平坦な道にあった倒木の
小さな枝に足を引っかけて前のめりに転倒。ムム、慢心につけいる倒木妖怪
トーボックのしわざか。軽傷と思いきや、その後も右膝から血がポタポタ流れ
続け、止まらず。やむなく森林植物園から途中リタイア。その日は自宅でランチ。
目的の大師道の紅葉が見られず残念!植物園の紅葉はタイミングがわるかった
ようで、もみじ坂のあたりはイマイチだったなぁ。
(翌朝も血が止まらず、出勤前に救急で受診。化膿の危険性があったため縫わず
に処置。当日なら縫えたので、そんな時はすぐに来るようにと言われた。)
29日
■當麻寺
※ブログ「當麻寺西南院と、ちょこっと葛城の道。(1)」に。
■九品寺、綏靖天皇葛城高丘宮趾、葛城一言主神社
※ブログ「當麻寺西南院と、ちょこっと葛城の道。(2)」に。
<12月>
6日
■諏訪神社~大師道~大龍寺~布引の滝
※ブログ「ふたたびのみち、大師道。」に。
12日

京都の嵐山を散策。嵐山花灯路にも少しだけ。
★大悲閣、櫟谷神社・宗像神社、車折神社





20日
京都国立博物館と寺町界隈散策
・特集陳列「さるづくしー干支を愛でるー」
(重文 巌樹遊猿図屏風 式部輝忠筆、曾我蕭白、長澤蘆雪、
森狙仙、伊藤若冲 ほか)
・特集陳列「獅子と狛犬」
(丹生都比売神社の大きな獅子・狛犬がよかった。)
あいにく「刀剣を楽しむ」のコーナーは行列ができており、
待ち時間も長くて鑑賞をあきらめた。
名品ギャラリーの1階仏像の部屋に長岡京市、光明寺の千手観音立像
が展示されていた。どっしりと量感のある木造の観音さま。お顔が
なんとも素敵で、こういう表情のことを「晦渋」というのだそうだ。
国の重文に指定されてからは京博に寄託中。
(ちなみに、現在光明寺の観音堂に安置されているのは粟生観音寺の
十一面千手観音とのこと。)
★本能寺