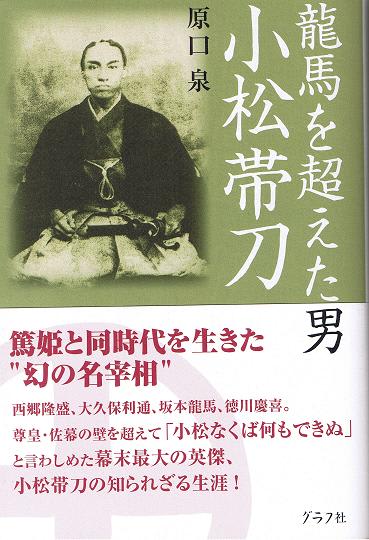本:鈴木亜久里の挫折
著者:赤井邦彦
出版社:文春文庫
感想:
スーパーアグリの立ち上げから終わりまでの内情が書かれた本ですが
知らなかった事がわかって面白かった反面、やっぱり金と権力がある
方が強くて何でもできる世の中なんだなと、実感させられた本でも
ありました。
オリンピックもWBCもそうだったけど、欧米のテレビの時間に合わせて
試合の時間が決まるんですよね。F1に関していえば、シンガポールで
初めてのナイトレースがありましたが、これもヨーロッパのテレビの
時間に合わせるためで、開催国は照明のために余計な出費が必要になる
んです。
これに味をしめて、次は日本とかのアジアは全部ナイトレースにしろ
と言い出すでしょう。まるで植民地支配そのものです。戦争を繰り返
しても、そういう発想は変わらないって事でしょうか?
著者:赤井邦彦
出版社:文春文庫
感想:
スーパーアグリの立ち上げから終わりまでの内情が書かれた本ですが
知らなかった事がわかって面白かった反面、やっぱり金と権力がある
方が強くて何でもできる世の中なんだなと、実感させられた本でも
ありました。
オリンピックもWBCもそうだったけど、欧米のテレビの時間に合わせて
試合の時間が決まるんですよね。F1に関していえば、シンガポールで
初めてのナイトレースがありましたが、これもヨーロッパのテレビの
時間に合わせるためで、開催国は照明のために余計な出費が必要になる
んです。
これに味をしめて、次は日本とかのアジアは全部ナイトレースにしろ
と言い出すでしょう。まるで植民地支配そのものです。戦争を繰り返
しても、そういう発想は変わらないって事でしょうか?