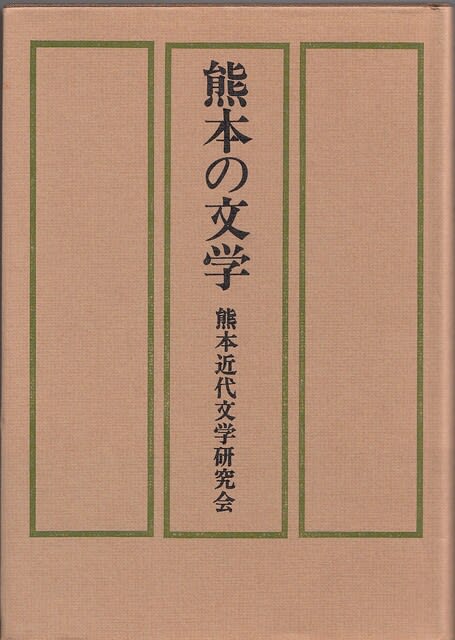三島由紀夫と〈熊本〉 ―「奔馬」をもとにして―
初出 『熊本の文学 第三』熊本近代文学研究会編 審美社 1996年03月
一 三島由紀夫と「奔馬」
「奔馬」は、昭和四十二年二月号から翌年八月号にかけて分載された後、昭和四十二年二月に新潮社から刊行された小説である。連作長編小説『豊饒の海』四部作のうちの第二巻にあたる。寺田透氏が『豊饒の海』論(『文芸』昭47・8) のなかで、この「奔馬」を〈優作〉と認め、主人公勲は作者が作者の外界に胚種をとらえ成長させてもう一人の自己となしえたという理由で「気持ちがわるい位感染力に富んだ、強い表現力ゆえに、嫌悪を覚えつつも傑作と言う他ない作品」と評したのはつとに有名である。
「奔馬」を一口で言えば、〈神風連史話〉に傾倒する主人公飯沼勲が昭和の神風連を標榜しながら昭和維新を企て、その挫折ののちに海に臨んで割腹自殺をする物語である。第四十章からなる「奔馬」には第9章がそっくりそのまま山尾綱紀著「神風連史話」という小冊子の掲載に使われている。この「奔馬」の基本的モチーフとも言うべき「神風連史話」については、寺田氏はまた、「奔馬」という作品の不可解な点を三つ挙げていて、その第一に〈神風連史話〉が三島たちの昭和四十五年十一月二十五日の行動の完全な予告であることの意味は何かと述べている。そして、松本鶴雄氏は、それを踏まえた考えのもとでの「三島由紀夫作品論事典](「三島由紀夫とは何であったか」『国文学』学燈社・昭56年7月号) の「奔馬」の項で、「特に〈神風連史話〉は第二巻の十分の一の量を占め、単なる小説効果にとどまらない。この史話が、死と結びついた時のみ純粋は存在し、目的の成就か否かにかかわらず、あるのは〈死〉のみという勲の行動原理を生み、ひいては三島の精神構造とも相似形をなすことを考え合わせると、無視できない点であろう」と記している。寺田氏にしろ、松本氏にしろ、「奔馬」における〈神風連史話〉なるものに注目し、「奔馬」という作品そのものと三島由紀夫の自決との関連に言及していることで共通している。
二 三島由紀夫と神風連
三島由紀夫と神風連との関係についての論考では、大久保典夫氏が『編年体・評伝三島由紀夫』(『三島由紀夫必携』NO・19・学燈社) のなかで「三島由紀夫の諫死としての決起の主旨は、『檄』に端的に現れているが、三島が、近代的サラリーマンたる自衛隊員に向かって、ハンド・マイク一つ持たずに決起を呼びかけたのは、電線の下を通るとき頭上に扇子をかざしたというあの神風連の故事にならったのかも知れない。この無垢の純潔を嗤えようか」と書き、三島の生涯にわたる知己である村松剛氏が『三島由紀夫の世界』(新潮社・平2・9)のあとがきのなかでさえ「日本人としての魂をとりもどせと、市ヶ谷台上で三島は死を賭して訴えました。当面の問題としたのはアメリカ製の憲法であり敗戦後の社会でしたが、神風連的な心情がその根底に息づいていたことは、疑いを容れません」と述べていることに最も注目している。この指摘にうべなう気持ちがあるのは、三島自身が自決直前、古林尚氏との対談で「どろ臭い、暗い精神主義ぼくは、それが好きでしょうがない。うんとファナティックな、蒙昧主義的な、そういうものがとても好きなんです。それがぼくの中のディオニソスは、神風連につながり、西南の役につながり、萩の乱その他、あのへんの暗い蒙昧ともいうべき破滅衝動につながっているんです」(「いまにわかります」『図書新聞』・昭45・11・18)と告白して、神風連的な〈破滅衝動〉への志向を表明していること、また溯っては、昭和四十二年一月一日元旦の「年頭の迷い」と題する『読売新聞』の文章のなかで「西郷隆盛は五十歳で英雄として死んだし、この間熊本へ行って神風連を調べて感動したことは、一見青年の暴挙と見られがちなあの乱の指導者の一人で、壮烈な最期を遂げた加屋霄堅(かやはるかた)が、私と同年で死んだという発見であった。私も今なら、英雄たる最終年齢に間に合うのだ」と書いて、加屋に同化しつつ〈英雄〉としての死への決意を確認していることと深く関連しているからである。つまり、これら本人自身の発言によっても、晩年の三島の自死に至る過程に神風連と関わりのあることが容易に予想できる。
ところで、三島由紀夫の神風連への接近をより具体的に知ることのできるのは何よりも神風連の取材のために来熊した際の資料が有力な手掛かりとなるであろう。熊本滞在期間中の動静は荒木精之氏の著書や福島次郎氏の証言によってほぼ明らかである。特に、荒木氏の「三島由紀夫氏の神風連調査の旅」という文章(『初霜の記 三島由紀夫と神風連』日本談義社・昭46・11所収。以下、荒木氏に関わる文章はこの本からの引用である) が詳しく、神風連研究家ならではの指摘に富んでいる。おおむねその記述に譲るとするが、論述上特に触れて置かなければならない点を挙げてみる。荒木氏は三島が来熊前、神風連に関する著書をほとんど目にし、さらには神風連が信条としていた古神道を知るために三日間も大和の大三輪神社に参籠してやってきた事実はまだしも、「奔馬」の装幀には神風連の加屋霄堅の漢詩が真筆そのまま複写されているを知って、それが極めて入手困難な神風連関係の遺墨であっただけに三島の熱の入れように驚いている。実際の対話のなかでも、現代の神風連を書きたいという三島の熱い息吹きが感じられたというし、「奔馬」の作品に出てくる<神風連史話>の新開皇大神宮の拝殿の様子や金峯山の山頂にある蔵王権現、そこから眺められる熊本の情景などの描写にしても、直接見聞して感銘したものでなければ書けない瑞々しい文章であるというのである。このようなことからもわかるように、三島の神風連への傾倒ぶりは荒木氏のような専門家の目で見ても尋常でないものであったようである。
それはそれとして、神風連取材の旅が確かに三島由紀夫にとって感銘深いものであったことはまちがいない。それを物語っているのは、三島由紀夫の荒木精之氏宛の熊本取材に対する感謝の書簡であって、「短い滞在のあひだに、神風連の核心に触れ、神風連の事跡を肌に感じるやうに感じることができたのは全く荒木様のお蔭であると存じ、もし荒木様の御指導を受ける機会に恵まれなければ、永久に堂々めぐりをしてゐたにちがひあるまいと思ふと、しみじみ身の幸運を感じます。」と述べていることである。神風連の<核心>に触れた<身の幸運>を語っていさかかオーバーな身振りが感じられるこの手紙が端なる社交辞令を越えて本心を述べているのだとわかるのは、先程の『読売新聞』の「この間熊本へ行って感動したことは」云々の本人の弁や清水文雄氏の「故三島由紀夫が四十一年夏、小説『奔馬』の取材のため熊本に赴き、荒木さんの指導によって、神風連に開眼した喜びを、彼から直接聞いたことも、今思い出します」という随筆『続・河の音』(「王朝文学の会」昭57・4 )の文章からも確認できる。このように、熊本での取材が三島にとって神風連への〈開眼〉をもたらしたものであったことは注目されていい。
従って、ここで確認したいのは、神風連の<核心>に触れた幸運にしても、〈開眼〉した喜びにしても、その幸運やその喜びの延長線上において、「奔馬」という作品が生み出され、三島自身の自死に繋がって行ったということである。
三 三島由紀夫と蓮田善明
一八七六年の明治政府に対する熊本の復古的攘夷主義的な士族反乱をふつう『神風連の乱』と呼称している。神風連の乱そのものについては、「奔馬」において〈神風連史話〉を読んだ本田の感想のなかの「今まで神がかりの不平士族の叛乱としか考えていなかったあの事件」という記述のような見方が一般的である。神風連の郷土史家でもある荒木精之氏が「神風連は長い間殆んど誤解の中にあった。この純烈な国学者たちが死を以て明らかにしようとした悲懐はかへりみられれること少なく、久しくうづもれてゐた」と慨嘆していることも、或いは神風連を初めて総合的に捉えたと橋川文三氏に讃えられた『神風連とその時代』(葦書房・昭52・30)の著者渡辺京二氏にしても、「神風連という呼称が一種の滑稽感をともないながら世俗的に流布されているわりに、学者と呼ばれるような人びとの間で研究らしい研究がほとんど行なわれていない」と述べていることからもその一端が理解できると思うのだが、神風連の存在が反時代的で、しかも熊本という一地方で起こった事件であるがゆえにかえって無視されてきたといってよい。従って、東京という中心都市出身者である三島由紀夫がほとんどと言っていいほど知られていない神風連の存在をどうして知ったのかということこそ、むしろ問題にすべきなのかも知れない。
今ここに、昭和一七年十一月一日発行の『文芸文化』(第三巻第十一号) という雑誌を手にしている。その中には蓮田善明の「神風連のこころ」と題する森本忠氏の同題の書評が掲載されている。そこで驚くべきなのは、その文章の直前部分に、平岡公威こと、三島由紀夫の「伊勢物語のこと」と題した文章があることである。このときの『文芸文化』が若い日の三島にとって〈神風連〉の存在に初めて接する機会を与えてくれることになった雑誌であろうことは充分想像される。例えば、蓮田善明が「『電線の下ば通る時や、かう扇ばぱつと頭の上に広げて 。』と話されたのも石原先生ではなかつたらうか」と書いている神風連の故事は、極めて神風連の特色を示しているだけに初めて知るものの記憶に残るだろうし、しかも「私にはこの話がずつと、非常に清らかな、そして絶対動かせない或るものを、今日まで私に指し示すものになつてゐる」と述べているからには、ましてや私淑している蓮田の文章であるならば、若き日の三島の脳裏に印象鮮やかに映ったにちがいない。むろん、その当時から確実に記憶の底に残していたといえないまでも、記憶の片隅に留め置かれていたであろう。そう考えるのは、三島が決起の折にハンド・マイクという文明の利器を使わなかったのは神風連の故事にならったものだという既出の大久保氏の指摘は言うに及ばず、三島が神風連を理解する際の基本線は蓮田の文章から取り入れているように思われるからである。羅列的に示すと、蓮田善明の、
〈神風連は唯だたましひの事だけを純粋に、非常に熱心に思いつゞけたのである。日本人が信じ、大事にし守り伝へなければならないものだけを、この上なく考へ詰めたのである〉 〈かういふ精純な「攘夷」とは、日本の無比の歴史を受け、守り、伝へる心なのだ〉
〈神風連は実際は敵らしい敵を与へられてゐないともいえる。にも拘らず彼等は何が敵であるかをはつきり知つてゐた〉
〈彼等は自ら討つべきものを討つたことに殉じて死ななければならないことも、彼等は知つてゐた〉
という神風連の捉え方は、三島が熊本での神風連取材を前にして林房雄との対談『対話 日本人論』(番町書房・昭41・10) で語った
「僕はこの熊本敬神党、世間では神風連と言っていますが、(中略)彼らがやろうとしたことはいったいなにかと言えば、結局やせても枯れても、純日本以外のものはなんにもやらないということ」
「食うものから着物からなにからかにまでいっさい西洋のものはうけつけない。それが失敗したら死ぬだけなんです。失敗するのにきまっているのですがね。僕はある一定数の人間が、そういうことを考えて行動したということに、非常に感動するのです」
「神風連というものは、目的のために手段を選ばないのではなくて、手段イコール目的、目的イコール手段、みんな神意のまにまにだから、あらゆる政治運動における目的、手段のあいだの乖離というのはあり得ない。それは芸術における内容と形式と同じですね。僕は、日本精神というもののいちばん原質的な、ある意味でいちばんファナティックな純粋実験はここだったと思うのです」
という言葉の端々から理解される神風連の捉え方とは、その純潔日本主義的な観念といい、行動の直截的な把握の仕方といい、或いは特に注目すべき死への潔い覚悟、つまり「目的の成就か否かにかかわらず、あるのは〈死〉のみという行動原理」(松本鶴雄)といい、あまり径庭を感じさせることなく、むしろ蓮田の考えを敷衍させているかのように思われるからである。これはもちろん、昭和の神風連たらんとする「奔馬」の飯沼勲の思考と行動とに通じていることはいうまでもない。
それにしても、なぜ<戦前に日本浪曼派周辺にいた三島が、戦後二十近くたってから神風連に興味を示しはじめたのか>(松本健一)という疑問を待つまでもなく、晩年の三島にとって神風連の事跡がクローズアップしてくる不思議さは隠せない。その問いに答えることのできる鍵はまたしても蓮田善明の存在であり、彼を抜きにしては考えられないと言わなければならない。だが、正確に言えば小高根二郎氏の労作『蓮田善明とその死』(筑摩書房・昭45・3。のちに改刊、島津書房・54・8)という書物である。
雷が遠いとき、窓を射る稲妻の光と、雷鳴との間には、思はぬ永い時間がある。私の場合には二十年があつた。そして在世の蓮田氏は、私には何やら目をつぶす紫の閃光として現はれて消え、二十数年後に、本著のみちびきによつて、はじめて手ごたへのある、腹に響くなつかしい雷鳴が、野の豊饒を約束しつつ、轟いて来たのであつた。
これは、その『蓮田善明とその死』の序文に記した三島由紀夫の文章からの抜粋である。この巧みな比喩によって、蓮田善明に対して抱いている晩年の気持ちが浮き彫りにされている点で見るべきものがある。三島が自決一年前、『蓮田善明とその死』の完結にあたり小高根二郎氏に宛てた手紙(『蓮田善明とその死』跋) で「この御作品のおかげで、戦後二十数年を隔てて、蓮田氏と小生との結縁が確かめられ固められた気がいたしました」と直截的に書いていることからも、学習院在学中の恩師清水文雄氏の推挽によって「花ざかりの森」を発表したのをきっかけにして生まれた蓮田善明との黙契(小高根氏)とも呼ばれる<結縁>の深さを改めて確認していることが窺える。これもまた、三島はその自決一年前、昭和四十四年十一月の下旬、東京荻窪の普茶料理屋で催された<蓮田善明二十五回忌>の会に参加している。しかも、そこに居合わせた神谷忠孝氏から「日本浪漫派を保田与重郎中心だけで考察するのは片手落ちで、死の美学を説きながら生き延びた保田与重郎と死んだ蓮田善明の両方を視野に入れるべきだ」と話しかけられたとき、「三島由紀夫がきらりと光る眼で私を招き、盃に酒をついでくれながら、私の意見に賛成してくれた」という逸話(島津書房刊『蓮田善明全集』発刊に際しての宣伝用パンフレット) や、自決の八ヶ月前、三月に会った村松剛氏に「蓮田善明は、おれに日本のあとをたのむといって出征したんだよ」としんみりとした口調で言ったという事実(前掲)に至っては、晩年の三島が蓮田の存在を重く意識していたことを示すものである。が、ここでは、やはり三島由紀夫にとって蓮田の存在が立ち現れてくるのはこの晩年に近い頃だということを指摘するだけで事足りる。そのきっかけを与えたものが小高根二郎氏著『蓮田善明とその死』であり、そして蓮田の存在とともに記憶の底に眠らされていた神風連の存在を思い起こしたのである。とすれば、このことは、「奔馬」の「創作ノート」(昭三十九~) における北一輝の息子(大輝)から「奔馬」における神風連に心酔する飯沼勲へと主人公が変更された謎をも解き明かしてくれるものである。なぜなら、それは晩年の三島において蓮田の存在が大きく立ちはだかってきたことによって、神風連の存在が俄かに浮かび上がり、突然「奔馬」のモチーフに取って変わったことを意味するからである。
さらに言えば、先程の小高根二郎氏宛の手紙には「御文章を通じて蓮田氏の声が小生に語りかけて来ました。蓮田氏と同年にいたり、なほべんべんと生きてゐるのが恥かしくなりました。……今では小生は、嘘もかくしもなく、蓮田氏の立派な最期を羨むほかに、なす術を知りません」という文章があるが、これなどは敗戦の三日後、上官を射殺して〈日本の捨て石になる〉決意でなされた蓮田善明の自決と三島由紀夫のそれとの関連を類推したい誘惑に駆られる。蓮田の三島の自死への影響については、三島本人の叙述以外では端的に触れているものが多く、例えば、清水文雄氏は〈三島由紀夫の追悼の集い〉(詳しくは荒木精之氏の著書参照)で蓮田が三島の「晩年の思想と行動に深い影響を与えた」と指摘していることもさることながら、松本徹氏は「蓮田は、少年期と晩年の三島にとって、優しい父親の役割を果した」と述べ、ここでも「三島は、蓮田に従い、死によって『文化を創る人間』になる覚悟を決めていた」という結論に達しているのは、三島の<少年期>と<晩年期>における蓮田善明の存在や三島の自決と蓮田のそれとの関連という点で触れて置かなければならない文献(「日本浪曼派と戦後」『解釈と鑑賞』昭54・1)である。しかし、特に強調して置きたいのは、小高根著『蓮田善明とその死』という本によって「蓮田の自死を知り、その後、戦後社会を人気作家として生きてしまった自分を、再び蓮田によって悟らされたとき、三島は死への道を急いだのであろう」(「三島由紀夫と日本浪曼派」『国文学』平4・4月号)と述べる越次倶子氏を代表として、「あの事件の日まで、彼が、肌身はなさず愛読していた『蓮田善明とその死』がしめす意味や、『コギト』や『日本浪曼派』の同人で、三島由紀夫を遠くから見つめていた伊藤佐喜雄の言葉、『三島由紀夫は、蓮田善明に倣いたいと希った。その事実の闡明が『南方ジョホールバルでの蓮田さんのはげしい行動と死コギト』の小高根二郎によってなされたとき、三島君は自分自身の行動と死を決定したにちがいない』」に三島の死の謎を解く鍵がある(『資料三島由紀夫』朝文社・一九八九・六) とする福島鑄郎氏などの記述が増えてきているのは、三島の自死にとって『蓮田善明とその死』という本、直接的にはそこに描かれた自決に至る蓮田善明の姿がいかに重要な関わりをもつものであるかに気付いているものの言であるということである。
以上のことから、三島由紀夫が蓮田を意識し始めるのは蓮田の自決を描いた『蓮田善明とその死』の連載を目にしてからであって、その過程で蓮田善明によって知らされた神風連の自決の群像が甦ってきて、「奔馬」の素材を提供したのみならず、蓮田と神風連の自死の姿が三島の理想とする自裁の雛型の役目を担ったといえる。
四 三島由紀夫と熊本
これまで縷々と説明してきたのは、多くとは言えないまでもすでに触れられてきているが、それとて、三島と「奔馬」・三島と神風連・三島と蓮田善明といったぐあいに個別的であったり、三島とこの三者との関係などは論じられていなかったりで、また、個別的にせよ、論じられたもののほとんどが具体的例証に乏しく、思い付きの範囲を出ないものが多かったためである。
それではここで煩をいとわず、三島と「奔馬」・三島と神風連・三島と蓮田、或いは三島とこの三者の関係を整理して述べてみたい。三島由紀夫と神風連との間に介在したという点では蓮田善明の存在は大きく、三島はその蓮田を偲びながら神風連をモチーフとした「奔馬」を書き上げた。そして、特に三島の自死に焦点を当てれば、神風連・蓮田・「奔馬]そのものが関係し合いながら取り囲み、三島由紀夫はそれらの自死の系譜に添うかたちで自刃して果てたということになろう。
このように、三島において極めて重要な意味を持つ神風連・蓮田善明が育まれたということによって、熊本の地が特別な価値を持つようになってくるのは当然であろう。この間の事情を物語るものに荒木精之氏宛の礼状であって、この手紙では「しかし熊本を訪れ、神風連を調べる、といふこと以上に、小生にとつて予期せぬ効果は、日本人としての小生の故郷を発見したといふ思ひでした」と書き、神風連取材の旅が単に素材を得たにとどまらず、三島由紀夫という作家自身の心の故郷=思想の核を確認したといわんばかりの筆致である。そして、「一族に熊本出身の人間がゐないにも不拘 今度、ひたすら、神風連の遺風を慕つて訪れた熊本の地は、小生の心の故郷になりました。日本及び日本人が、まだ生きてゐる土地として感じられました」とより直接的に<熊本の地>が<心の故郷>であることを強調し、「神風連は小生の精神史に一つの変革を齎らしたやうであります」とまで言い切っている。これが礼儀上の言葉でなく、偽らない心情の告白と受け取ってよいことは、すでに明らかである。あえて言えば、現在流布している最も近親者である瑶子夫人が夫を自殺に導いた理由で熊本県人を嫌っているという話は、ことの真意を別にすると、晩年の三島と熊本の関係を暗示しているといえまいか。
さて、<熊本の地>が「心の故郷」「日本人としての故郷」であることを発見したことの意味は重い。それは、三島文学において<故郷回帰>という重要な問題を投げかけている。故郷喪失者とも言うべき都市出身者三島由紀夫が日本人として自分の故郷を確認したのは、保田与重郎が自分の生国大和奈良井の里を<日本の故郷>或いは<故郷としての風景>だとして回想し保持することに<日本への回帰>の一表現を見る思想と軌を一にするものである。従って、神谷忠孝氏が『日本浪曼派の本質』(「日本浪曼派の本質」『近代文学6』有斐閣双書昭52・10)の中で「日本浪曼派を形成する文学者のほとんどが地方農村の裕福な子弟であるということで共通している事は重視すべきであろう。(中略)<故郷>概念を個々の文学者において考察することで日本浪曼派の本質が見えてくる」という指摘は、今や三島における〈熊本〉の概念を考察することで三島文学の本質が見えてくるのではないかという示唆を与えてくれる。
五 《剣の思想》
昭和四十一年八月三十一日付の熊本日日新聞には「応接間」という欄に離熊直前の三島由紀夫の顔写真とともにインタビュー記事が掲載されている。すぐに気付くことは中央上段に「“日本人の神髄”を考えたい」と大文字で書いてあることである。この記事は興味深い内容を多く含んでいるが、ここでは本論に関係ある部分のみ抜粋してみたい。〈いま「新潮」に「春の雪」を書いているが、その第二巻「奔馬」に昭和の神風連ともいうべき青年が登場する。そこで荒木精之さんをたよって調べにきたのです〉〈「春の雪」の背景に神風連を出そうと考えたのは一年ぐらい前からです。ここで日本人の神髄は何かを考えてみたいのです。/いま日本に帰れとか、明治の日本人に帰れとかよく言われている。しかしどこに帰るか非常にあいまいだと思う。日本にはインドのガンジーの糸車に象徴される抵抗の精神はなぜなかったのか、いろいろ考えているうち、神風連がガンジーの糸車にあたることに思い至ったわけです。「英霊の声」や「二・二六事件」の精神の純粋なものは神風連のそれに通じているとみてもらってよいでしょう〉〈「春の雪」の第一巻は僕の以前の傾向と同じ作品だ。貴族のみやびやかな恋愛 そういうものが主題だが、第二巻では昭和七年の神風連ともいうべき青年が登場し、話は昭和七年と明治を行ったり戻ったりする。筋はつぶれてもこれだけは入れたいと思う。とにかくこの作品でいままでのものを集大成したいと考えています〉〈ますらおぶりの文学に志すようになったようだ。「剣」などもその一つと思う。それが広がってきたものだ〉と語っている。このインタビューで記者の質問の意図は予想できないが、「奔馬」の執筆動機が簡素ながらも明らかにされている点で貴重な資料である。
この頃の三島由紀夫は熊日新聞の記事のなかでも「ここで“日本人の神髄は何かを考えてみたい」と語っているようにいわゆる『日本人』論を唱えようとしていたといえる。そのことは、来熊の数ヶ月前に行った林房雄との対談(前掲)のなかで、「僕はいまの、日本だ、日本人だと云い、ウイスキーを飲みながら、おれは日本人だ、自動車に乗りながら、おれは日本人だ、と云っている連中の観念のあいまいさ、それは林さんのおっしゃるように、総括的には立派な日本人ですよ。しかし一度、あいまいな日本精神とかなんとかを、ここでもってもう一度よくこれを振り返って欲しいのです。そういう意味で、僕は神風連を云うのですよ」と語っていることからも理解できる。もちろんこれには、明治百年祭がまぢかに迫ってきていた昭和四十一年頃の〈日本に帰れ、明治の日本人に帰れ〉と叫ばれた社会的な背景が影響していたことはまちがいない。それは一種の復古運動であったが、三島はその雰囲気のなかで〈インドのガンジーの糸車に象徴される抵抗の精神はなぜなかったのか〉という問題を日本人のアイデンティティとからめて真剣に考えようとしていたふしが窺える。その結果、〈神風連がガンジーの糸車にあたること〉を知るに及んで、ついに〈「英霊の声」や「二・二六事件」の精神の純粋なものは神風連のそれに日本通じている〉ことを悟ったというのである。つまり、いささか簡略的になるが、三島の「日本人」論とは、ガンジーの糸車+「英霊の声」・「二・二六事件」・神風連の精神的純粋性=日本人の抵抗の精神とはいかなるものかということである。ここで日本人の抵抗精神の問題が浮かび上がってくることになるのは意外なことのように思われる。しかし、思えば「英霊の声」や「二・二六事件」・「奔馬」はいずれも右翼的で復古的であるものの、体制批判的な人物たちの声や行動であることで類似している。従って、神風連調査の目的は日本人の純粋な抵抗精神とは何かを神風連の思想や行動を通して探ってみることにあったと言わなければならない。
神風連が決起した原因が欧化主義の一環として発布された明治政府による廃刀令であったことは歴史的な事実である。が、その精神的な背景となると曖昧模糊としている。先程の渡辺京二氏の『神風連とその時代』によれば、神風連の志士たちにとって容認できなかったのは、〈帯刀被髪〉という風儀の問題であり、その風儀は政治的制度とは違って日本民族の精神に関わる問題を孕んでいるものだという特異な認識を持っていたということである。その認識を端的に言えば、「神風連が固執したのは、たとえば廃刀令ひとつとってもあきらかなように外形の問題であった。つまり彼らにとって外形とは精神とひき離せぬものであって、外形すなわち風儀を否定すれば精神はそのときただちに死ぬのであった」というものである。このような神風連の思想は〈日本刀〉を迫り来る欧化主義に対する抵抗の精神の拠り所にしたという点で、便宜上《剣の思想》と名付けて置きたい。
「奔馬」においても、重要な場面で神風連の《剣の思想》との類縁を感じさせる箇所がある。例えば、剣道部の「合宿に参加しなかったのは、ただ竹刀に飽いたからである。竹刀の勝利があまり容易であることに飽き、竹刀が剣の単なる象徴にすぎぬことに飽き、又、竹刀が何ら『本物の危険』を伴わぬことに飽いたのである」という文章は、剣道においては自他とも認める主人公飯沼勲の関心が〈竹刀〉から本物の〈刀〉へと移行していく契機を表しているところであって、勲が本物の行動家・実践家へと突き進み、〈日本刀〉で自刃する最終場面に繋がっていく非常に重要なところである。或いはまた、飯沼勲が決起の成否の最大の決手である武器として「それよりも日本刀だ。どうしても二十本は揃えなくちゃ」と言っていることは、勲たちがいくら〈神風連の純粋〉に学ぼうとしたといっても、近代兵器で武装した軍隊に対して〈日本刀〉で戦うのは無謀極まりなく、時代錯誤もはなはだしい。しかし、「昭和の神風連」たらんとした飯沼勲は神風連と同じように〈日本刀〉を自らの純粋精神と引き離せないものと考えていたとしたらどうだろうか。つまり、三島が主人公に〈日本刀〉を掛け替えのないものとして扱わせているところに「奔馬」の中心思想もまた《剣の思想》であったことを明示している。従って、批評家としても一流であった三島由紀夫は、みずからの洞察力によって神風連の思想的根幹をなす《剣の思想》をを充分に把握し、「奔馬」という作品において具体的に展開してみせたといえる。そして、三島の自衛隊突入後みずから死んだのも、まさにその《剣の思想》に共鳴したことのはての出来事なのであろう。
ところで、神風連取材のため来熊した三島由紀夫の《剣》にまつわる面白く、しかも注目すべきエピソードが数多い。荒木精之氏によれば、熊本にきた記念として古道具屋で日本刀を購入したと言ってそれを非常に喜んでいたというし、三島とほぼ三日間同行した福島次郎氏からも、やはり熊本の土産として刀の鍔とか剣道具の類するものばかりを買い、果てはホテル内で刀を盛んに振り回してみせたという証言を得ている。さらに興味深いのは、来熊三日目のこと、三島がふと思い出したように「せつかく熊本にきたので、町道場を紹介してくださいませんか」と言ったために、荒木氏が水前寺の龍驤館に案内していることである。正味三日間というわずかな日程のなかで貴重な時間をさこうとしていることや「せつかく」という言葉からも、三島が〈熊本〉と《剣》とを結び付けていたと考えるのはうがちすぎであろうか。なお、その道場の範士紫垣正治氏がのちに「こゝにはいく人となく剣道者がやつてきますが稽古も試合も形式だけ、それも二、三番とるともう終わりです。今日のやうに最後まで竹刀をにぎつて徹底的に相手になつてくれたのは三島氏がはじめてですよ」としきりに感嘆していたということも荒木氏の著書からであるが、この三島の龍驤館訪問は、《剣の思想》が今もなお熊本で息づいているかどうかを探る意図があったものと思われる。そうであったからこそ、三島がそのことを荒木氏宛の神風連調査に対する謝礼文に「龍驤館の清爽なる印象も、永く心を去らぬことと思ひます」と記しているのは端なる礼状にとどまらない極めて深い意味を持っていたといえる。三島由紀夫が神風連取材の旅を通して確認したのは、熊本がまさしく《剣の思想》をまっとうしている土地だということである。たとえそれが三島自身の認識の範囲内のことであろうとも、そう認識した上で〈熊本〉を「心の故郷」「日本人としての故郷」と規定していることは明らかである。
このように、神谷氏の指摘に触発されて三島における「故郷」としての〈熊本〉の概念を考察してきた中で浮かび上がってきたのは、故郷回帰、或いは日本(浪曼)回帰とも言うべき晩年の三島由紀夫の脳裏には、日本人の純粋な抵抗精神の発露である《剣の思想》の重要性への認識があり、《剣の思想》を実践して果てる過程で、その思想の体現者としての神風連、その思想のまったき理解者としての蓮田善明の存在、そしてそれにもましてその両者の由縁の地としての〈熊本〉が大写しになっていたということである。
三島由紀夫文学が海外で殊の外高い評価を得ていることは、この国際社会では日本が三島の作品を通して見られることである。もしそうであるならば、それは三島が精神の拠り所にした〈熊本〉とその《剣の思想》が注目されることでもあることを忘れてはならない。
註1 昭和四十五年十一月二十五日の三島由紀夫の衝撃的な割腹事件が確かに『奔馬』に注目させる要素はある。例えば、松本健一氏は三島の自決が『奔馬』の主人公飯沼勲と同じく「恋闕の論理」の結果だ(「恋闕者の論理」ユリイカ・昭51・10) とし、徳岡孝夫氏は三島の自刃が『奔馬』の勲の切腹して果てる場面との類似(「太陽と鉄」『国文学』昭61・7)を指摘しているのもその代表である。
註2 これまでにも、三島由紀夫の自裁事件以来、三島の処女作品とも言 うべき「花ざかりの森」が発表連載された雑誌『文芸文化』の文学運動、特にその中心的存在であった蓮田善明との関係が取り沙汰されては きていた。例えば、日本浪曼派の研究家で知られる大久保典夫氏は「三島由紀夫を日本浪曼派の影響下に文学的出発をしたと考えるのはかならずしも間違いではないが、日本浪曼派を保田与重郎の美学に代表させて考えれば、そこにはかなりの逕庭があるのであって、やはり三島 は『文芸文化』(昭一三・七創刊) の蓮田善明の直系と考えたほうがいい」( 日本文学研究叢書「日本浪曼派」有精堂・昭52) 述べ、これまで保田与重郎の影響が指摘されることが多かったなかで蓮田の存在を高く持ち上げた点では先 蹤となるものである。同じく日本浪曼派の研究家神谷忠孝氏は「蓮田善明の『鴎外の方法』(昭14・11、子文書房) における<戦死 にわれわれは芸術を見なければなばならない。戦死が詩であることを、はつきり知らなければならない>という文章も、その根底には死を賭けての変革の意志があることはたしかであり、三島由紀夫の自決の意味も蓮田善明の思想と関連されると説明可能である」(「日本浪曼派の本質」『近代文学6』有斐閣双書・昭52)と述べていることも、三島の自決の原因を解明するのに蓮田の思想を抜きにしては考えられないことを指摘している。しかし、そのことを端的に要約しているのは、三島由紀夫研究家の野口武彦氏の「どちらかといえば三島は、保田与重郎からよりも、(中略)蓮田善明 から、多くのものを受け取っている」とし、「三島の自死に至る行程に蓮 田が影を投げかけていることは、『氏の享年に近づくにつれ、氏の死が、その死の形が何を意味していたかが、突然啓示のやうに私の久しい迷蒙を照らし出した』(「序」小高根二郎『蓮田善明とその死』)という一節からも明らかである」と述べている文章(〈日本浪曼派〉「三島由紀夫事典」『三島由紀夫必携』NO19・学燈社) である。これらの論文からも、蓮田善明と晩年の三島との関係がかなり密接であったことが三島の自決を通して説明されている。このように論じられる傾向はこれからも増えこそすれ、減りはしないだろう。
註3 この話を松本健一氏は「蓮田善明 日本伝説」(『群像』昭12 ) の中で「 それがなあ、三島さんが亡くなられたあと、熊本のさる知り合いが三島さんの家にいったとですよ。すると、瑤子さんといわれましたか、三島さんの未亡人に、熊本の人は嫌いです、といわれたらしかですよ。/敏子さんはそう語って、哀しそうに目をしばたいた」と紹介して、「三島夫人は三島が蓮田善明の激烈なる自決の伝説をなぞるかたちで死ん だ、と明らかに思ったのである。(そして、蓮田敏子もそれを追認している。)」と述べている。「熊本のさる知り合い」とは熊本在住の作家福 島次郎氏のことである。この話は実は『熊本の文学 第二 』(審美社・一九八八・十一) の「蓮田善明」を執筆するのをきっかけに何度となく敏子さんを訪れたなかで紹介し、福島氏自身を伴った際にも本人自身からも話をしてもらった。それはその時私自身が蓮田と三島との関係を何とか確 かめたい気持ちが強かったためである。
註4 三島の《剣》との関係は、すでに劉建輝氏が「三島由紀夫語彙辞典」(「いま三島由紀夫を読む」」『国文学』昭61・7月号) の中で「剣」の部を要約して、「『武』の原理を代表するもので、『花』の対極に位置づけられ、常 に作中人物の行動を象徴する存在」であり、剣 行動 死という構図は 『憂国』から『剣』、さらに『奔馬』の主人公達それぞれに受け継がれていると述べている。この文章は特に『奔馬』の主人公飯沼勲の一連の行動哲学の見取図として参考になる。