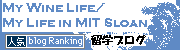エズラ・ボーゲル(Ezra Vogel) と言えば、1979年に「Japan as No.1」を書いた著名な日本学研究者。
そんな有名人のボストンの私邸で月一度行われる勉強会がある。その名も「Vogel塾/松下村塾」。
Vogel氏は70年代という、まだ世界の日本への関心が薄い時期、華々しい戦後経済成長を遂げた日本に着目。90年代に日本が凋落(?)してからも親日家として知られ、日本の研究を続けている。そんな彼が、ボストンに学ぶ日本人を集め、幕末に日本を変えた志士を生んだ松蔭の松下村塾のように、将来の日本を背負うリーダーを育てたいという目的で開いている私塾がこれ。
木曜は今年度初めての集まり。
来ているのは全員日本人だが、そのバックグラウンドは多様。ハーバードのケネディスクールの学生が中心だが、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)、ハーバード・メディカル・スクールやロー・スクール、タフツ大学やボストン大学で国際関係論や社会学を研究する研究者も来ている。MITスローンからも数名。
人数が多いので自己紹介に時間がかかったが、その後20分ほどの議論がなかなか盛り上がった。
議論はすべて英語。
まずは自己紹介で何人かが興味を持っていた、日本の少子化問題をとっかかりに議論が始まる。
その解決方法のひとつとして移民政策へ。
日本人が「当然あるもの」と考えているHomogeneity、それをベースとする「平和観」が移民受け入れの際の壁になること。じゃあ「平和観」とは何物なのか、という社会学的な議論へ突入してしまう。
私としては、「平和観」とは何か、という議論をしても神学論争になるだけ、という思いがあったので、違う方向に議論を振らせることにした。
日本人の強み・Identityを維持しながら、いかに文化的多様性を生かすか、というジレンマは移民政策に限った話でない。企業経営の切り口からも大きな問題になっている、ということでGlobalizationを進める日本企業のジレンマについて発言してみた。
近年、自動車・電機などの日本企業は、生産工場だけでなく、R&Dや商品開発などの上流部分も海外に移行する必要に迫られている。少子化で十分な技術者が日本だけで採用できない、という事情もあるが、海外で売れる商品を作るため、現地での商品開発が必須であったり、IT・電機関連だと、海外のほうが優秀な研究者がいる、という事情もある。いわゆる「R&D Globalization」と呼ばれる。
ところが、実際に移行しようとすると、高品質・効率性といった日本ならではの強みが、実は日本人のBasic educationの高さや文化、High-contextな言語に起因しているため、一筋縄ではいかない。それで、外人技術者をうまくイノベーションのプロセスに組み込めないし、組み込むと日本の強みが生かせない、というジレンマに陥っているのが現状。
そんな話を提供すると、他のビジネススクールの学生などからも議論が巻き起こった。
そもそもMulticultureをどこまで入れる必要があるのか、分野によっては無理に多様化させず日本人だけでやっていく方法もあるのではないか、など。
議論時間が20分しかなかったので、そのあたりで議論は終了。
来週木曜に再度集まって、複数の分科会に分かれ、今後1年間で勉強したいトピックを決めるという。
集まっている日本人学生は多様で、政治、経営だけでなく、医療・健康や、国際貢献といった幅広い分野から来ている。出来るだけ多くの学生の興味を満たすようなテーマを選ぶ必要がある。
ちょっと考えて、松下村塾のメーリングリストに次のトピックをポストしてみた。
Japan as a melting pot or Sakoku - How to manage multi-culture and diversity while maintaining Japan's strength and identity (日本・日本企業が、日本のIdentityと強みを維持しつつ、今後迎えうる、文化・人材の多様性をどう組み込んでいくか)
こういうテーマなら、移民問題や私が言った企業のGlobalizationの課題だけでなく、医療や国際貢献などの分野にもアナロジーのきく問題があるのではないか、と思ったのだ。