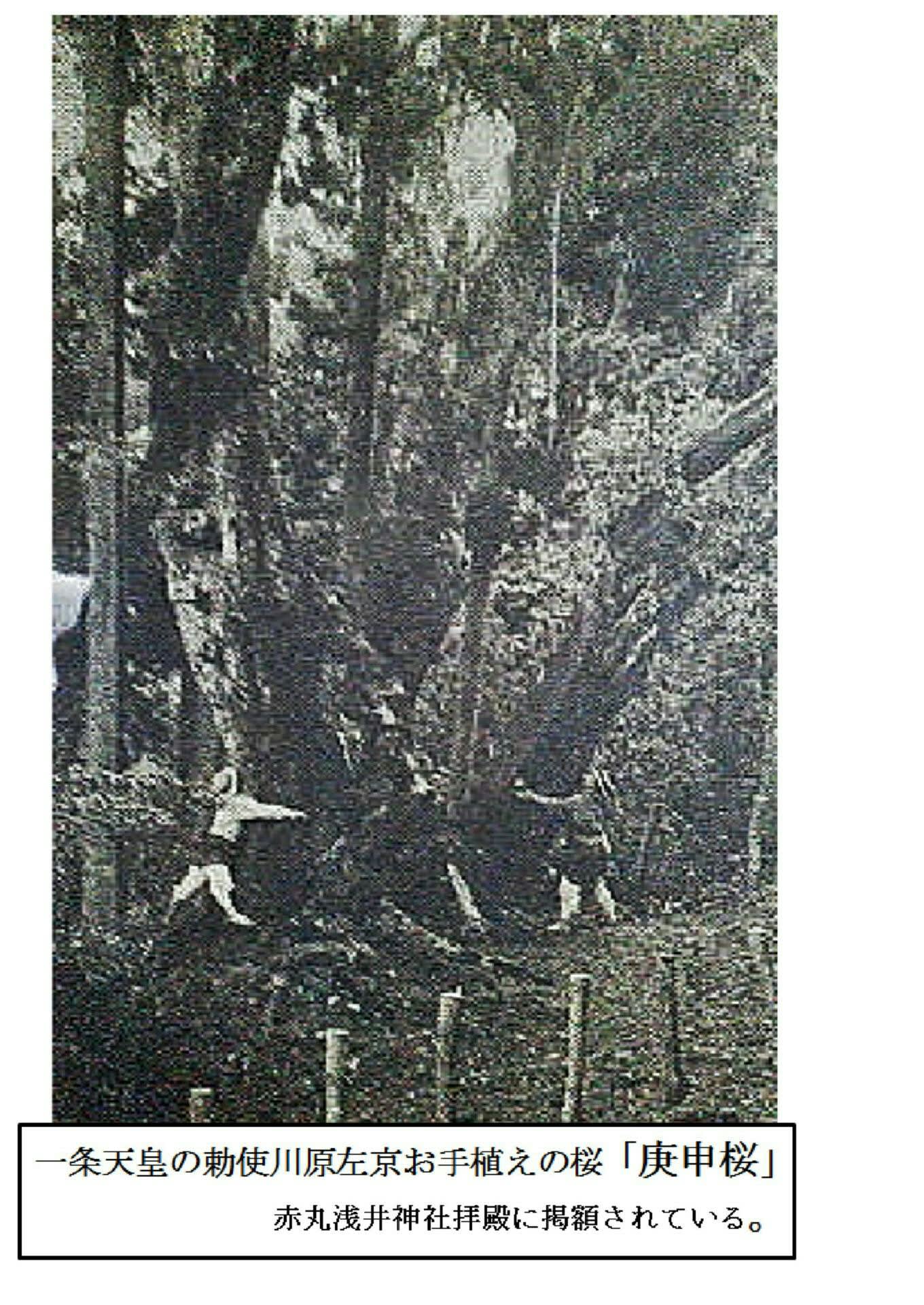■「足利義満」は「越中五位庄」を室の「業子」の追善料として【相国寺(※塔頭寺院「鹿苑寺金閣」)】に寄進した。





■「越中五位庄」の前身の「越中吉岡庄」は元々、藤原氏と密接な庄園で在り、「吉岡庄」の「延喜式内社郷社赤丸浅井神社」には「一条天皇が勅使川原左京を勅使で派遣された」と伝わり、この時期の左京職は「藤原道長」で在った。この勅使がお手植えの二本の桜木は「勅使桜」と呼ばれて昭和初期迄存続した。その後、藤原道長の末裔の藤原摂関家長者「藤原頼長」は「越中吉岡庄」を自らの庄園としていたが、「保元の乱」で敗れてこの庄園は「後白河上皇」の「後院領」に成り、その後、「後鳥羽上皇」から「後醍醐天皇」迄皇室庄園として続いた。「後醍醐天皇」が開いた南朝と、足利氏が支援した北朝は「足利義満」の時に合一した。
■鎌倉時代に浄土宗から分派して浄土真宗を開いた「親鸞」は藤原氏の系譜「日野家」から出て、本家日野家は幕府に圧迫されていた親鸞を密かに庇護していたと云う。親鸞の弟子の蓮如は越前河口に「吉崎御坊」を開き、福光の奥に「土山御坊」を開いた。この「土山御坊」はその後小矢部市を経て高岡市の古国府跡に移転した。越中はその影響で浄土真宗が広く布教されて、越中砺波郡の古代氏族で藤原氏の福光石黒氏やその一族の加賀富樫氏は一向一揆に滅ぼされた。一方、加賀で起こった一向一揆は越前、越中でも猛威を奮い、一揆衆は「五位庄」の石堤長光寺を中心に終結し、一時期は「赤丸浅井城」を一揆の坊官「下間和泉」が居城とした。
(※「肯泉達録」)
■南朝の牙城の赤丸村を抑えた足利幕府は「五位庄」を室町幕府第三代将軍足利義満の室の「日野業子」の追善料として臨済宗相国寺に糧所として寄進した。(※「五位庄」は足利幕府政所代を勤めた越中蜷川氏が統治して、その後も引き続き足利家菩提寺の「等持院」、「等持寺」の庄園として存続した。)(※「万山編年精要」)