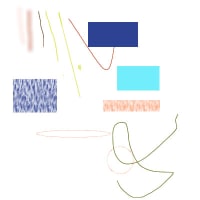学生時代の友人から北朝鮮鎮南浦の地図の写しと日本鉱業の鎮南浦製錬所の巨大煙突の写真コピーを貰った。

大東亜戦争前に鎮南浦で生活した人々の親睦会で入手したのだという。
父が日本鉱業の鎮南浦製錬所

で分析技師をしていた筆者は鎮南浦で出生し、敗戦の8月15日には小学1年生であったが大煙突のことは
よく知っていたのでとても懐かしく思った。また地図には筆者が産声を上げた道立病院の位置

も記されており、感慨一入であった。
と同時に思い出すのは38度線を突破して父祖の国日本へ引き上げるための逃避行の苦しい旅のことである。
父は出征していた。銃後には7才の筆者を頭に4才と1才の二人の幼女が残され食料難の中を母は悪戦苦闘していた。
内地への引き揚げは子供3人を引き連れて母子4人が38度線を突破しての難儀な逃避行であった。
敗戦の日から引き揚げ決行の日までの一年強の期間は敗戦国民として祖国へ帰還することのみを待ち続ける忍従の竹の子生活であった。
経路は鎮南浦港から船で大同江を渡り対岸の村へ。船を降りてからは南北国境の38度線まで山野を野宿しながらの徒歩。
38度線越境、米軍のジープで開城のテント村へ収容、仁川のテント村へ米軍のジープで移動し収容。仁川港から貨物船で佐世保港へ、
佐世保港より国鉄線を乗り継いで郷里へ。
昭和21年10月20日に父母の故郷である岡山県の早島町へ母子4人が生還することによって引き揚げの旅は終了した。
この時の様子は自分史の一節に以下のように記録している。
自分史の骨格5・・・38度線で聞いた銃声 早島 潮
国境近くに来た時は警戒も厳しくなり、夜陰に乗じてこれを突破することになった。
昼間山中で仮眠し、暗くなってから腰までつかる浅瀬の川をじゃぶじゃぶ歩いて渡った。
このとき私は母親と妹からはぐれてしまったが、隊列から離れないでついて行けば、家族にはまた会えると必死で衰弱した体で足を滑らせながら浅瀬を渡った。このあと、続けて三十八度線の国境を渡った。この時も私一人で母達の所在は不明であった。
国境警備兵が威嚇射撃をしたため、その銃声は国境突破の一行に悲壮感を与えるのに効果充分であった。
私が母や妹とはぐれたのは、突然聞こえた銃声が原因となった。
「川を渡ったり、国境を越えるときには、遅れないように、大人の男の人の後について歩くんですよ。和子は母さんが、手を引いていきますからね」
と母が言っていたので、私は知り合いの後藤さんの小父さんの後ろについて、一生懸命歩いた。
そこへ威嚇射撃ではあったが、銃声が聞こえて隊列が乱れ蜘蛛の子を散らすように、岩陰へ隠れるグループや構わずにどんどん行進を続ける
グループとに分かれたのである。私がついて行った後藤さんは行進派だったので私も後藤さんの後ろについてどんどん歩いた。ところが、一時岩陰に身を寄せた母は私達のグループから遅れをとったという次第である。
国境を無事突破して、小休止したとき母と妹に再会した。私はあまり心配していなかったが、母の方は私の体がマラリヤのために衰弱しているので、私が、皆から落伍してしまったのではないかと、私の顔をみるまでは心配で心配でたまらなかったそうである。
母はこのとき私を日本へ連れて帰れないかもしれないと覚悟したと後に述懐している。
後年今は亡き母の法事でその時の様子を妹の和子が語って聞かせてくれたが、髪を振り乱して「たかしはおらんか。たかし返事をしなさい」
と発狂したようにあちこち人混みの中を駆けずり廻っていたという。年配の人になだめられて漸く、隊列に戻ったらしい。
国境を越えてからの旅は恵まれていた。米軍のジープやトラックが国境線近くに待ちうけていて、次々に開城のテント村まで運んでくれた。
テント村に入る前に頭からDDTをふりかけられて体中真っ白になった。このテント村には一週間抑留された。
テント村は北朝鮮から脱出してくる日本人引き揚げ者を船便の手配が出来るまで収容しておく米軍経営の難民キャンプであった。
アルマイト製の食器を与えられ、朝、昼、晩と決まった時間に給食があったが、とうもろこしのスープに大根の切れ端や葉っぱが申し訳程度に浮いている粗末なものであった。ほかにも食べ物が支給されたのかもしれないが、私の記憶に残っているのはとうもろこしのスープだけであった。
私達一家は女子供だけの家族であったから、荷物が少なく鎮南浦を出るとき用意した干し飯や煎り豆などの食料は食べ尽くしていたので、給食を有り難く食べるしか術がなかった。しかし、男手のある家族は米や豆をまだ持っており、携帯した飯盒で炊いて美味しそうに食べていた。
それを遠くから羨ましそうに眺めているだけであった。 いじましい話だが、米を持っているグループが座っていた場所の筵の目の中にこぼれて入り込んでいる米粒を叩き出して、二粒、三粒の生米をかじったこともある。
七日間のテント生活は、殆ど雨に降られたため、テントに閉じ込められて生活したように思う。鎮南浦出発以来、入浴していないうえ、野宿したり、川を渡ったりしたので、着衣は垢と汗で臭くなっており、DDTで入村時に消毒されたにもかかわらず、腰のバンドの下に虱がわいたのを覚えている。
テント生活の中では夜になると、退屈凌ぎに歌合戦をしようと提案する人があり、順番に一家族ずつ得意の歌を披露することになった。
お国自慢の民謡や小学唱歌が多かったが軍歌を勇ましく歌う人もいた。我が家の番が廻ってきたときには、私が小学唱歌の子馬の歌を音程を外して歌い、背筋に冷汗をかいた。何才になっても歌を歌うことだけは苦手である。戦時中に音楽は「ドレミファ」ではなく「ハニホヘト」で教えられ、感受性の強い時期に音楽的な環境に縁遠い生活を余儀なくされていたせいであると自らを慰めている。それにしても、歌が人前で物怖じせずに歌える人が羨ましく思える今日この頃である。
藤原ていさんの著作「流れる星は生きていた」に比べると私達の国境までの逃避行はまだ、恵まれていた方である。日本鉱業の従業員とその家族を主体としたグループであったから、比較的統制のとれた行動ができたせいか、道中、無法者に略奪暴行されたり、婦女子が凌辱を受けるという悲劇もなく落伍した一家族を除いては、全員無事に国境を越えることができた。朝鮮人の中にも親切な人はいるもので、田舎道で空き馬車を引いていた
「アボジ」が、子供達や荷物を荷台へ乗せて二里程の道のりを無報酬で運んで呉れるということもあった。
我々引き揚げ者のグループが何人いたのか正確には覚えていないが、現在薄れかけた記憶を辿って当時の隊列を思い出してみると四~五百人の人数だったのではないかという気がする。
国境線で落伍した児玉さん一家は丁度我が家と同じような家族構成で、若い母親が三人の幼小児をひきつれていた。
逃避行という異常な状況の中では誰しも自分のことだけで精一杯になり、落伍しそうな家族があっても、せいぜい声をかけて励ます程度のことしか出来ず、悲しく情けない思いをしたのは、私だけではなかったであろう。児玉さん一家もこのときは落伍したが、何か月か後には無事内地までたどりついたという噂を聞いた。
「児玉さんが、落伍したときには、どんなことがあっても、子供達だけは無事内地へ送り届けなくてはならない」と内心決意を新たにしたと後日、母は述懐しているし、内地へ先に復員していた父は、「多分一番下の信子は生還しないであろうと思っていた」と漏らしたことがある。
また、母は私の家内にも晩年、何も財産らしいものは残せなかったが、3人の幼子を誰一人欠けることなく日本へ連れて帰って来たことが母の誇りであるし母の無形の財産であると語ったということである。
開城のテント村から仁川のテント村への移動も米軍のジープとトラックで行われた。
威嚇射撃をしたり、賄賂を要求する「ロ助」と比較すれば、さらに七日間の徒歩による逃避行のことを思えば、乗り物に乗せて内地へ確実に一歩ずつ近付けて呉れる米軍はまさに地獄に仏の存在であった。
開城から仁川へ向かうトラックを運転していた兵士は黒人で、チューインガムをむしゃむしゃ噛んでいる唇の合間に見える白い歯が、非常に印象的であった。また仁川のキャンプ村へ近付いたとき、通り抜けた茶色い切り通しの崖のうえに仰いだ、雲一つない青空は私の人生の中で感じた最も美しい色の一つであった。
港の海面も太陽に眩しいばかりに輝いており、紺碧の色は苦難を乗り越えて、父祖の国へ確実に近付いている引き揚げ者の明るい気持ちを象徴しているようであった。
後日、機会があって韓国旅行のとき自由時間に仁川の港を訪問したことがあるが、生憎くの雨で海の色はどす黒く沈んでおり、切り通しの崖も見出すことが出来なかった。
仁川でもまずDDTの洗礼を受けてからテント村へ入った。ここでは三日間の短い日数であったから、記憶に残る思い出はない。
停泊中の貨物船に乗り込んで佐世保の港まで玄界灘の荒波に悩まされながらも、一行の気持ちだけは寛いでいた。
しかし、引き揚げ船の中で片桐さんの生後三、四か月の嬰児が栄養失調が原因で死亡するという悲しい出来事があった。
苦しい逃避行の中でもそれまで死者はなかったのに、祖国を目前にしてついに犠牲者が出てしまった。
貨物船の薄暗い船底でお経をあげ、水葬にするという侘しくも悲しい弔いであった。
佐世保港へついてからも直ちに上陸が許された訳ではない。検疫のため、肛門に注射器ようのものを挿入されて便を採られた。
さらにDDTで消毒されたので、下船までには随分時間がかかった。やっと踏みしめた祖国の大地であった。
このあと港の倉庫で引き揚げ列車の順番を待ったり、帰国手続きのために一晩をあかすことになった。貨物船も狭い場所へ大勢の人がごろ寝をしたが、体を横にして手足を伸ばすだけの場所はあった。ところが、上陸したとはいえ、一晩を過ごした倉庫の中は手狭で、横になるだけのスペースがないため、床に腰を降ろして立て膝をしたまま仮眠するのがやっとの状態であった。積み重ねたリュックサックに背中をもたせかけて、立て膝を両手で抱えこんだ姿で鼾をかきながら一行は、安堵の夢を結んだのである。
港から倉庫へ移動するとき、妹の和子が風邪をひいて咳込み、苦しがっているので、私が背中を叩いてやったが、なかなか直らず、ぜーぜー咳をしながら泣きじゃくっていた姿が強く頭に焼き付いていて忘れられない。
厚生省の援護局から内地の紙幣を支給されて、佐世保駅から上り列車にやっと乗り込むことが出来た。博多の駅や下関の駅につくごとに、土地の婦人会の人達が湯茶の接待をして下さっり、「長い道中、御苦労様でした」とねぎらいの言葉をかけて下さったので、やはり祖国はいいなとしみじみ思ったものである。
引き揚げ列車であったから、佐世保の駅を発車したときには乗客は引き揚げ者ばかりであったが、着く駅ごとに引き揚げ者は少なくなり、一般の乗客が乗りこんできた。一目で引き揚げ者と分かるので、いろいろ話かけてくる人もあり、話を聞いて涙ぐむ老婆もあった。
途中の駅で駅弁を売っているところがあり、早速母が支給されたばかりの内地の紙幣でこれを求めた。中身は稲荷寿司なので、久し振りに御馳走が食べられると喜んで、かぶりついたところが、油揚げの下からでてきたのはお酢のよくきかせてある「おから」であった。
内地だから、稲荷寿司には当然米の飯が使われているものと早合点した私達のほうに内地の経済事情についての認識不足があった。
爆撃を受けて、生産施設に壊滅的な打撃を受けた日本の経済はまだ復興の緒についたばかりの段階で、米の配給制度は厳然として行われており、駅で売られる弁当に米が使われるような状態ではなかったのである。そのときやはり内地も敗戦国の苦しみを味わっているんだなということを認識した。
宇野線の早島駅に昭和二十一年十月二十一日未明に到着し駅前で畳表や茣座の卸問屋を営んでいる母方の伯母(母の実姉)宅へ辿りつき、苦しかった北朝鮮鎮南浦からの引き揚げは終わったのである。この日は早島の秋祭りの日であった。母子四人が無事生還できたのは、ひとえに母の頑張りのおかげである。このあと栄養失調に陥っていた母子四人は一か月程の静養の後、健康を取り戻したのである。


大東亜戦争前に鎮南浦で生活した人々の親睦会で入手したのだという。
父が日本鉱業の鎮南浦製錬所

で分析技師をしていた筆者は鎮南浦で出生し、敗戦の8月15日には小学1年生であったが大煙突のことは
よく知っていたのでとても懐かしく思った。また地図には筆者が産声を上げた道立病院の位置

も記されており、感慨一入であった。
と同時に思い出すのは38度線を突破して父祖の国日本へ引き上げるための逃避行の苦しい旅のことである。
父は出征していた。銃後には7才の筆者を頭に4才と1才の二人の幼女が残され食料難の中を母は悪戦苦闘していた。
内地への引き揚げは子供3人を引き連れて母子4人が38度線を突破しての難儀な逃避行であった。
敗戦の日から引き揚げ決行の日までの一年強の期間は敗戦国民として祖国へ帰還することのみを待ち続ける忍従の竹の子生活であった。
経路は鎮南浦港から船で大同江を渡り対岸の村へ。船を降りてからは南北国境の38度線まで山野を野宿しながらの徒歩。
38度線越境、米軍のジープで開城のテント村へ収容、仁川のテント村へ米軍のジープで移動し収容。仁川港から貨物船で佐世保港へ、
佐世保港より国鉄線を乗り継いで郷里へ。
昭和21年10月20日に父母の故郷である岡山県の早島町へ母子4人が生還することによって引き揚げの旅は終了した。
この時の様子は自分史の一節に以下のように記録している。
自分史の骨格5・・・38度線で聞いた銃声 早島 潮
国境近くに来た時は警戒も厳しくなり、夜陰に乗じてこれを突破することになった。
昼間山中で仮眠し、暗くなってから腰までつかる浅瀬の川をじゃぶじゃぶ歩いて渡った。
このとき私は母親と妹からはぐれてしまったが、隊列から離れないでついて行けば、家族にはまた会えると必死で衰弱した体で足を滑らせながら浅瀬を渡った。このあと、続けて三十八度線の国境を渡った。この時も私一人で母達の所在は不明であった。
国境警備兵が威嚇射撃をしたため、その銃声は国境突破の一行に悲壮感を与えるのに効果充分であった。
私が母や妹とはぐれたのは、突然聞こえた銃声が原因となった。
「川を渡ったり、国境を越えるときには、遅れないように、大人の男の人の後について歩くんですよ。和子は母さんが、手を引いていきますからね」
と母が言っていたので、私は知り合いの後藤さんの小父さんの後ろについて、一生懸命歩いた。
そこへ威嚇射撃ではあったが、銃声が聞こえて隊列が乱れ蜘蛛の子を散らすように、岩陰へ隠れるグループや構わずにどんどん行進を続ける
グループとに分かれたのである。私がついて行った後藤さんは行進派だったので私も後藤さんの後ろについてどんどん歩いた。ところが、一時岩陰に身を寄せた母は私達のグループから遅れをとったという次第である。
国境を無事突破して、小休止したとき母と妹に再会した。私はあまり心配していなかったが、母の方は私の体がマラリヤのために衰弱しているので、私が、皆から落伍してしまったのではないかと、私の顔をみるまでは心配で心配でたまらなかったそうである。
母はこのとき私を日本へ連れて帰れないかもしれないと覚悟したと後に述懐している。
後年今は亡き母の法事でその時の様子を妹の和子が語って聞かせてくれたが、髪を振り乱して「たかしはおらんか。たかし返事をしなさい」
と発狂したようにあちこち人混みの中を駆けずり廻っていたという。年配の人になだめられて漸く、隊列に戻ったらしい。
国境を越えてからの旅は恵まれていた。米軍のジープやトラックが国境線近くに待ちうけていて、次々に開城のテント村まで運んでくれた。
テント村に入る前に頭からDDTをふりかけられて体中真っ白になった。このテント村には一週間抑留された。
テント村は北朝鮮から脱出してくる日本人引き揚げ者を船便の手配が出来るまで収容しておく米軍経営の難民キャンプであった。
アルマイト製の食器を与えられ、朝、昼、晩と決まった時間に給食があったが、とうもろこしのスープに大根の切れ端や葉っぱが申し訳程度に浮いている粗末なものであった。ほかにも食べ物が支給されたのかもしれないが、私の記憶に残っているのはとうもろこしのスープだけであった。
私達一家は女子供だけの家族であったから、荷物が少なく鎮南浦を出るとき用意した干し飯や煎り豆などの食料は食べ尽くしていたので、給食を有り難く食べるしか術がなかった。しかし、男手のある家族は米や豆をまだ持っており、携帯した飯盒で炊いて美味しそうに食べていた。
それを遠くから羨ましそうに眺めているだけであった。 いじましい話だが、米を持っているグループが座っていた場所の筵の目の中にこぼれて入り込んでいる米粒を叩き出して、二粒、三粒の生米をかじったこともある。
七日間のテント生活は、殆ど雨に降られたため、テントに閉じ込められて生活したように思う。鎮南浦出発以来、入浴していないうえ、野宿したり、川を渡ったりしたので、着衣は垢と汗で臭くなっており、DDTで入村時に消毒されたにもかかわらず、腰のバンドの下に虱がわいたのを覚えている。
テント生活の中では夜になると、退屈凌ぎに歌合戦をしようと提案する人があり、順番に一家族ずつ得意の歌を披露することになった。
お国自慢の民謡や小学唱歌が多かったが軍歌を勇ましく歌う人もいた。我が家の番が廻ってきたときには、私が小学唱歌の子馬の歌を音程を外して歌い、背筋に冷汗をかいた。何才になっても歌を歌うことだけは苦手である。戦時中に音楽は「ドレミファ」ではなく「ハニホヘト」で教えられ、感受性の強い時期に音楽的な環境に縁遠い生活を余儀なくされていたせいであると自らを慰めている。それにしても、歌が人前で物怖じせずに歌える人が羨ましく思える今日この頃である。
藤原ていさんの著作「流れる星は生きていた」に比べると私達の国境までの逃避行はまだ、恵まれていた方である。日本鉱業の従業員とその家族を主体としたグループであったから、比較的統制のとれた行動ができたせいか、道中、無法者に略奪暴行されたり、婦女子が凌辱を受けるという悲劇もなく落伍した一家族を除いては、全員無事に国境を越えることができた。朝鮮人の中にも親切な人はいるもので、田舎道で空き馬車を引いていた
「アボジ」が、子供達や荷物を荷台へ乗せて二里程の道のりを無報酬で運んで呉れるということもあった。
我々引き揚げ者のグループが何人いたのか正確には覚えていないが、現在薄れかけた記憶を辿って当時の隊列を思い出してみると四~五百人の人数だったのではないかという気がする。
国境線で落伍した児玉さん一家は丁度我が家と同じような家族構成で、若い母親が三人の幼小児をひきつれていた。
逃避行という異常な状況の中では誰しも自分のことだけで精一杯になり、落伍しそうな家族があっても、せいぜい声をかけて励ます程度のことしか出来ず、悲しく情けない思いをしたのは、私だけではなかったであろう。児玉さん一家もこのときは落伍したが、何か月か後には無事内地までたどりついたという噂を聞いた。
「児玉さんが、落伍したときには、どんなことがあっても、子供達だけは無事内地へ送り届けなくてはならない」と内心決意を新たにしたと後日、母は述懐しているし、内地へ先に復員していた父は、「多分一番下の信子は生還しないであろうと思っていた」と漏らしたことがある。
また、母は私の家内にも晩年、何も財産らしいものは残せなかったが、3人の幼子を誰一人欠けることなく日本へ連れて帰って来たことが母の誇りであるし母の無形の財産であると語ったということである。
開城のテント村から仁川のテント村への移動も米軍のジープとトラックで行われた。
威嚇射撃をしたり、賄賂を要求する「ロ助」と比較すれば、さらに七日間の徒歩による逃避行のことを思えば、乗り物に乗せて内地へ確実に一歩ずつ近付けて呉れる米軍はまさに地獄に仏の存在であった。
開城から仁川へ向かうトラックを運転していた兵士は黒人で、チューインガムをむしゃむしゃ噛んでいる唇の合間に見える白い歯が、非常に印象的であった。また仁川のキャンプ村へ近付いたとき、通り抜けた茶色い切り通しの崖のうえに仰いだ、雲一つない青空は私の人生の中で感じた最も美しい色の一つであった。
港の海面も太陽に眩しいばかりに輝いており、紺碧の色は苦難を乗り越えて、父祖の国へ確実に近付いている引き揚げ者の明るい気持ちを象徴しているようであった。
後日、機会があって韓国旅行のとき自由時間に仁川の港を訪問したことがあるが、生憎くの雨で海の色はどす黒く沈んでおり、切り通しの崖も見出すことが出来なかった。
仁川でもまずDDTの洗礼を受けてからテント村へ入った。ここでは三日間の短い日数であったから、記憶に残る思い出はない。
停泊中の貨物船に乗り込んで佐世保の港まで玄界灘の荒波に悩まされながらも、一行の気持ちだけは寛いでいた。
しかし、引き揚げ船の中で片桐さんの生後三、四か月の嬰児が栄養失調が原因で死亡するという悲しい出来事があった。
苦しい逃避行の中でもそれまで死者はなかったのに、祖国を目前にしてついに犠牲者が出てしまった。
貨物船の薄暗い船底でお経をあげ、水葬にするという侘しくも悲しい弔いであった。
佐世保港へついてからも直ちに上陸が許された訳ではない。検疫のため、肛門に注射器ようのものを挿入されて便を採られた。
さらにDDTで消毒されたので、下船までには随分時間がかかった。やっと踏みしめた祖国の大地であった。
このあと港の倉庫で引き揚げ列車の順番を待ったり、帰国手続きのために一晩をあかすことになった。貨物船も狭い場所へ大勢の人がごろ寝をしたが、体を横にして手足を伸ばすだけの場所はあった。ところが、上陸したとはいえ、一晩を過ごした倉庫の中は手狭で、横になるだけのスペースがないため、床に腰を降ろして立て膝をしたまま仮眠するのがやっとの状態であった。積み重ねたリュックサックに背中をもたせかけて、立て膝を両手で抱えこんだ姿で鼾をかきながら一行は、安堵の夢を結んだのである。
港から倉庫へ移動するとき、妹の和子が風邪をひいて咳込み、苦しがっているので、私が背中を叩いてやったが、なかなか直らず、ぜーぜー咳をしながら泣きじゃくっていた姿が強く頭に焼き付いていて忘れられない。
厚生省の援護局から内地の紙幣を支給されて、佐世保駅から上り列車にやっと乗り込むことが出来た。博多の駅や下関の駅につくごとに、土地の婦人会の人達が湯茶の接待をして下さっり、「長い道中、御苦労様でした」とねぎらいの言葉をかけて下さったので、やはり祖国はいいなとしみじみ思ったものである。
引き揚げ列車であったから、佐世保の駅を発車したときには乗客は引き揚げ者ばかりであったが、着く駅ごとに引き揚げ者は少なくなり、一般の乗客が乗りこんできた。一目で引き揚げ者と分かるので、いろいろ話かけてくる人もあり、話を聞いて涙ぐむ老婆もあった。
途中の駅で駅弁を売っているところがあり、早速母が支給されたばかりの内地の紙幣でこれを求めた。中身は稲荷寿司なので、久し振りに御馳走が食べられると喜んで、かぶりついたところが、油揚げの下からでてきたのはお酢のよくきかせてある「おから」であった。
内地だから、稲荷寿司には当然米の飯が使われているものと早合点した私達のほうに内地の経済事情についての認識不足があった。
爆撃を受けて、生産施設に壊滅的な打撃を受けた日本の経済はまだ復興の緒についたばかりの段階で、米の配給制度は厳然として行われており、駅で売られる弁当に米が使われるような状態ではなかったのである。そのときやはり内地も敗戦国の苦しみを味わっているんだなということを認識した。
宇野線の早島駅に昭和二十一年十月二十一日未明に到着し駅前で畳表や茣座の卸問屋を営んでいる母方の伯母(母の実姉)宅へ辿りつき、苦しかった北朝鮮鎮南浦からの引き揚げは終わったのである。この日は早島の秋祭りの日であった。母子四人が無事生還できたのは、ひとえに母の頑張りのおかげである。このあと栄養失調に陥っていた母子四人は一か月程の静養の後、健康を取り戻したのである。