1854年の1月31日に那覇港に寄港して、10日間滞在した、ロシアの作家、イワン・A・ゴンチャローフは、のちに『日本渡航記』を著し、琉球の印象を「緑のたわむれる島」と評し、樹草の広がりに
「美しさと種類の多様さに呆然として、沈黙していた」(「ゴンチャロフ日本渡航記」高野明・島田陽訳 講談社学術文庫)
とその印象を綴っている。
かれの『日本渡航記』に書いている琉球の風景の記述は、バジル・ホールやペリーの航海記よりも表現が豊かだ。さすが、のちに「オブローモフ」を書いた作家の文章である。上陸した琉球の印象を感動的に書いていた文脈は、最後には「単調な生活よさらば」と書くことになるが、ゴンチャローフがみていた緑の島の自然は、近代化の波に洗われ、以後160年後の今日、ごらんのとおり、となった。その間の事情はいろんな書物があるのでそれにゆずるが、この長期にわたる、歴史変動と島の自然の改変は豊かさとひきかえに島から緑を喪失する。沖縄戦で灰燼となり、大規模な軍事基地建設でむしばまれ、1972年復帰後は沖縄振興名目で土地開発、道路建設で伐採、形状を破壊し、空き地があると建造物や家をつくることしかしない。人口増加に伴う住宅の建設はすさまじい。道ができると家ができる。繁殖旺盛なキノコのような住宅増加は、<緑がたわむれる島>をどんどんとうしなっていく。そこには、自然よりも人間の生活を優先する思考がある。その結果、島が都市化し、人工の空間が増大し、自然から人間が遠ざかる。いや、人間から自然が遠ざかるような生活を強いられる。墓地のすぐそばにも住宅、聖地を囲んでいた樹木を切り倒す。鬱蒼としていた墓地や聖地は尊さがない。広大な基地がどんと居座り続ける。普天間基地の移転も同じ島のなかで模様替えや増改築のように進められようとしている。
「ここでは二千年前と同様に、何の変化もなく人が暮らしているのだという思いがして一驚されるであろう。人も情熱も仕事もーすべてが素朴で単純で原始的である。自然には依然として美と安寧がある。陽は暑く真っ赤に輝き、水は静かに流れ、果実はたわわに実っている。書物も火薬もその他のそれと類似した堕落も存在しない。今後どういうことになるか注目しよう。果たして新しい文明がこの忘れられた古代の片隅にふれることがあるのだろうか。」(〃)
このゴンチャローフの言い方は、琉球の歴史をあまり知らない書き方である。まるで文明と関係ない、なにもない手つかずの自然の島、自然人が住んでいるという印象である。岡本太郎の「何もないことのめまい」につながるような見方だ。だがこの頃の琉球は強固な封建国家の島であり、本屋はないが書物はあったし、また当時ペリーの来航であたふたしている時期である。那覇や首里の邑民は異国人の来訪を恐れ、路で会うと女子供たちは逃げ惑うが、男たちはだいたいお辞儀して礼儀正しいという印象であった。
ゴンチャローフ一行がベッテルハイムにあったときの話が面白い。ベッテルハイムが琉球人の実情を訴え、琉球人が礼儀正しいとみえるのは嘘で「迎えるより送るほうが好き」「警察のスパイ」「大変な酒飲み」「賭博する」「宣教師(自分)を殴った」「バジル・ホールを信用するな。なにもかも真実と反対」などと刑事犯的論告をするのにうさんくささを感じ、ゴンチャローフはバジル・ホールも信用しないが彼も信用しないと断じる。幕府の鎖国制度が薩摩を通して、琉球にも示達されていて日本人が後ろにいてキリスト教を迫害していることは、ゴンチャローフも知っていたから、「あまり功を急ぐな」と彼に忠告したりする。
そして那覇を離れるとき、「自然と、いくら独特でも動物的な生活だけでは人間は満足できない」という感想をもらすのである。
ドストエフスキーが書いたものには、宗教への懐疑心と自問自答と内部の人間と他者への接近と乖離に引き裂かれた人間があるが、ゴンチャロフの「オブローモフ」には他者との関係を回避した臆病な煮え切らない、しかし無為無欲なおっとりした人間がいる。ドストエフスキーはロマン主義者にたいして「破滅するのがお似合いだよ」とけなしたが、絶望しても光を求める精神だけはうしなっていなかった。それにくらべたら、いわば富裕層のおぼっちゃまあがりのゴンチャロフは社会のシステムにどこか鈍感な人間のように思える。このプチャーチン提督の日本渡航の秘書役として志願したのも、スランプ生活の気晴らしのような軽いノリで決めている。どこでもいい、なんでもいい、計画性のない、旅の生活を楽しもうといい具合だったろうか。関わりを避け、ものごとを面倒くさいというのは、もはや女性の心理をつかめない。おかげで生涯独身だったのは自ら選択した生き方だったかもしれない。
オブローモフ的人間は現代にも存在する。
「君は、このお伽噺めいた風景や森の中に隠れている茅屋や美しい小川を一笑に付すであろう。すべてこうしたものは苔生す木々が生え、透き通った水が流れ、判で捺したような人間が登場する風景画に似ているように思われる。しかし原物を見たら、現実に似たようなものを何かつくろうとする絵画の無力をもっぱら笑うであろう。」(〃)
最新の画像[もっと見る]
-
 リトアニアの作曲家 チュルリョーニス の思い出 第27回沖縄市民コンサート 1999年11月
5ヶ月前
リトアニアの作曲家 チュルリョーニス の思い出 第27回沖縄市民コンサート 1999年11月
5ヶ月前
-
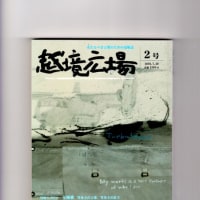 島言葉(しまくとぅば)詩作の現場―疎外言語を詩的言語へ (ユンタク) 松原敏夫 × 東中十三郎
5年前
島言葉(しまくとぅば)詩作の現場―疎外言語を詩的言語へ (ユンタク) 松原敏夫 × 東中十三郎
5年前
-
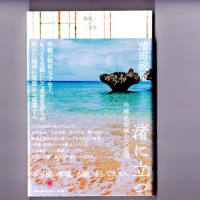 清田政信著『渚に立つ』 共和国 境界の文学 2018年8月15日
6年前
清田政信著『渚に立つ』 共和国 境界の文学 2018年8月15日
6年前
-
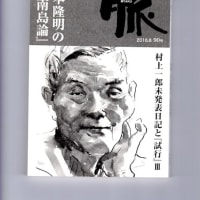 吉本隆明ノート Ⅱ ― 吉本「南島論」の片隅で
6年前
吉本隆明ノート Ⅱ ― 吉本「南島論」の片隅で
6年前
-
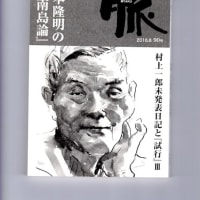 吉本隆明ノート Ⅰ ー 『心的現象論』ランダムノート ①玄関口で
6年前
吉本隆明ノート Ⅰ ー 『心的現象論』ランダムノート ①玄関口で
6年前
-
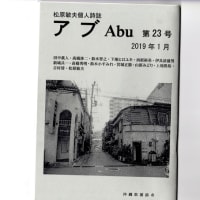 松原敏夫個人詩誌「アブ」第23号ー田中眞人、髙橋渉二、鈴木智之、下地ヒロユキ、西原裕美、伊良波盛男、新城兵一、高橋秀明、鈴木小すみれ、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、平良清志
6年前
松原敏夫個人詩誌「アブ」第23号ー田中眞人、髙橋渉二、鈴木智之、下地ヒロユキ、西原裕美、伊良波盛男、新城兵一、高橋秀明、鈴木小すみれ、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、平良清志
6年前
-
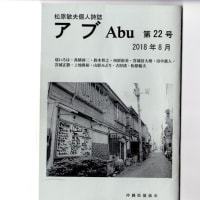 松原敏夫個人詩誌「アブ」第22号―瑶いろは、髙橋渉二、鈴木智之、西原裕美、田中眞人、宮城信大朗、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、吉村清
6年前
松原敏夫個人詩誌「アブ」第22号―瑶いろは、髙橋渉二、鈴木智之、西原裕美、田中眞人、宮城信大朗、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、吉村清
6年前
-
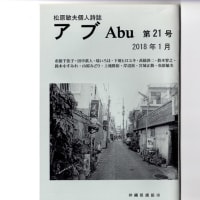 松原敏夫個人詩誌「アブ」21号―市原千佳子、田中眞人、瑶いろは、下地ヒロユキ、髙橋渉二、鈴木智之、鈴木小すみれ、山原みどり、上地隆裕、岸辺 裕、宮城正勝
6年前
松原敏夫個人詩誌「アブ」21号―市原千佳子、田中眞人、瑶いろは、下地ヒロユキ、髙橋渉二、鈴木智之、鈴木小すみれ、山原みどり、上地隆裕、岸辺 裕、宮城正勝
6年前
-
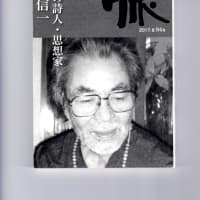 詩は手套のような女―川満信一の詩と思想 対談:松原敏夫×東中十三郎 (脈94号 特集:沖縄の詩人・思想家 川満信一)
6年前
詩は手套のような女―川満信一の詩と思想 対談:松原敏夫×東中十三郎 (脈94号 特集:沖縄の詩人・思想家 川満信一)
6年前
-
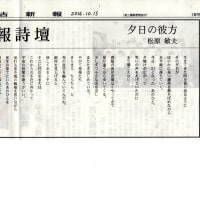 近作詩 夕日の彼方
6年前
近作詩 夕日の彼方
6年前











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます