八重洋一郎詩集『沖縄料理考』(出版舎Mugen、2012年7月) 料理と詩、不似合いを化合する諧謔
沖縄料理考、と聞いたとき、へえー、八重さんて、もしかしたら、酒が好きでグルメで、食べ物に相当関心のあるひとで、だからとうとう沖縄・八重山の料理の本をだすようになったか、と勘違い、詩集とあるから、おやや、こんなタイトルでいいのかな、詩集名にはちょっとなあ、と遠慮なき感想をもった。
近代のある時期、詩人という種族は言葉の芸術と自我生の自由を至上して<食べ物>という世俗的なもの、動物的胃袋とつながるものなんかにはまったく興味のない存在、というか生活に関心をもたないという偏見がアル中ランボー病、チュウヤ逆転病を患っていた私の中で構築されていた。やせて青白い青年……。酒や反秩序で生活破綻して世俗から追い出され、運良く母性的女性に救われ生きながらえる、というのは、古い時代のカッコいい伝説的な詩人像。いまやちゃんとした定職をもち家庭をもち世俗に合わせ、スマートフォンのように機能的で何でも器用にこなすワザを確保しているのが21世紀的イッパン詩人のようだ。(とこれまた独断・偏向病で書いている)
明治、大正、昭和の近代期、前世代の詩人達が世俗を離れた詩人の生き方はこんなものよ、と食えない詩で生きようと迫真演技まがいの生き様を晒し、こんな、近代詩の先祖、爺ちゃん、父ちゃん詩人たちのブザマな姿を見ている後世代の子孫、理由なき世代はそんな歴史をマネすまいと真摯な紳士を装うモダニズムで無意識を押し殺しているか。そんなプチ世代は彼ら前世代の汚辱の後始末と後遺症を引きずっているように思えるが。
これぞ現代の詩人像―というちゃんとした定型像はない。あるわけがない。ないが、言語を芸術革命と運と資質と精神と棘を包括してばらまきすれば、そこは戦後詩の思想で抑圧されない残余のよりどころとして、まだ見ぬ言語の滴りが形を顕わすかもしれない、と期待したりするのだが、詩の個人としての頭の良さと知識の豊富さと育ちのよさや骨格のよさと弛緩したエロスや生のエネルギーが共存並立して対立や葛藤のない、かっこいい言語哲学思想の用語をまとった言説からむなしい言葉が勢いづいて並び出す。または瀟洒なレトリックを巧みに使いわけ「まさに詩人」と人にいわせ注目を浴びれば勝ち組。資本主義の不断な商品生産と物や知的なメタ的生産に言葉は加担してさらにさらに分解して言語商品とメディアの欲望と開発と軽薄な囲い込みに芯を抜かれ脱色される。とそこから何がうまれるのか。詩人名簿などに数千の詩人が登録されているが、ほんとうの<詩人>はどこにいるのか。
とまあ、詩と料理に思いを馳せれば勝手な妄想、妄念が走り出してしまったので書きとめた次第。ということは、この『沖縄料理考』という詩集が私の散漫な脳を刺激したということだ。感謝とご勘弁を記しておきたい。
さて八重洋一郎さんは詩歴の長いひとである。八重さんは、なにしろ「沙漠」を「ひろがり」、「空間」を「つらなり」、「眩暈」を 「くるめ」、「存在」を「かなしみ」とルビで読ませる語彙の意味解体と置換を爆ぜた『素描』(1972)の詩人というのが私のなかにある詩人像なのだ。言葉への思念の叩きこみ、読みの転換、意味をイメージに変え、既存の言葉を手繰り寄せ、巧みにおのれの言語にしてしまう詩的化学をあやつる言語の演奏者でもあるのだ。
詩の素材はどこにもある、と思えばいい。言葉のもつ物のみかたやイメージの、新鮮な像形を突きだすような面白い詩のほうがいい。誰かの後追い、模倣、使い古された言葉、韜晦、影響下はもういい。詩壇は書くのも読むのも詩人同士でわたりあう、境界内言語の社会だから誰が異と先をいっているかに敏感だ。おそらく現代詩は微に細に書いたものが出回っているから<私性を撃つもの>が詩として固有性を主張するなら、その隙間を、つまり誰のものでもない、誰も書いていない、未踏の詩の言語を狙っていくのが戦略として必要であろう。
そこに<食>そのものの詩を集めた詩集だ。虚を突かれた。一見、食い物と詩は似合わないというイメージがあるが裏切られた。
あいつらは僕らの糞を食べ 僕らは
あいつらの足の尖までことごとく
なんというおいしさよ
やめられないよ クセになる アワモリ飲んで
豚足 食べて そして
しまいに
(足の指先)
灼けつく通風
尿酸たっぷり 赤々と関節は腫れ 豚のうらみは
激烈
激烈」
(アシティビチ)
ねこの肉は夜ひかる
ねこの肉は夜ひかる
うすあおく その青い目のように
うすあおく その青い目のように
さあ お前たちもためしにお食べ
(猫)
肉食や酒飲の、人への警告と逆襲といい猫肉のリアルな描写といい不気味なハーモニーを奏でている。グルメから遠い私でも「およよ」と感応してしまった。いってみればこの沖縄料理詩は諧謔味、味の落とし穴のある詩集である。耳ガー、チラガー、ヒージャー汁、アシティビチ、ラフテー……。沖縄という地に生まれた特有な料理の陰翳や自身の記憶をちりばめている。沖縄に住む私には親しい聞き慣れたメニューだ。でも食ったことのない、猫、蛙、イラブー、枝サンゴはどんな味がするのだろう。私もゴーヤー、ナーベーラー、フーチーバーを詩にしたことがあるが、さすがに肉料理は書いていない。ただ生々しい肉の解体のプロセスを省略しているところが、幼年期に山羊やニワトリを殺処分し解体する実体験をもつ私にはちょっと不満なところか。
耳ガーにスタブローギンが登場するとは実に楽しい。沖縄料理を文学にしたところに拍手だ。食う事へ捉え直し、異化、愛、想像がうまく味を出している。食は輪廻舌の最たるものだ。しかも単なる料理詩かと思いきや世の批判や思念を組み込むところはいい作戦だ。生活の自然にポエジーを構築する方法は地上の生き物に、リアリズムとは違う愛とまなざしと発見をすること、この地を支配する自然と風土の歴史に馴染んだ食の異形を表出すること―と、この詩集を読みながら雑駁たる詩想に思いめぐらした。
わが生涯 最高のあこがれ
かすみを食って生きること そして
神秘をうたうこと
(霞)
さりげなく書いたこの言葉は不可能と至高を合体した八重さん独特の出し方だ。もっとも気に入った。
イリプスⅡnd 10号(2012年10月)
最新の画像[もっと見る]
-
 リトアニアの作曲家 チュルリョーニス の思い出 第27回沖縄市民コンサート 1999年11月
8ヶ月前
リトアニアの作曲家 チュルリョーニス の思い出 第27回沖縄市民コンサート 1999年11月
8ヶ月前
-
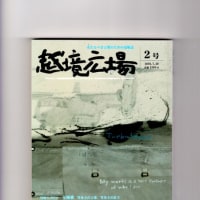 島言葉(しまくとぅば)詩作の現場―疎外言語を詩的言語へ (ユンタク) 松原敏夫 × 東中十三郎
6年前
島言葉(しまくとぅば)詩作の現場―疎外言語を詩的言語へ (ユンタク) 松原敏夫 × 東中十三郎
6年前
-
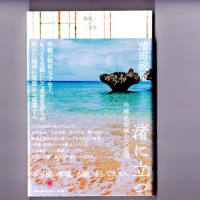 清田政信著『渚に立つ』 共和国 境界の文学 2018年8月15日
6年前
清田政信著『渚に立つ』 共和国 境界の文学 2018年8月15日
6年前
-
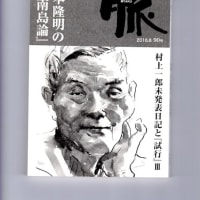 吉本隆明ノート Ⅱ ― 吉本「南島論」の片隅で
6年前
吉本隆明ノート Ⅱ ― 吉本「南島論」の片隅で
6年前
-
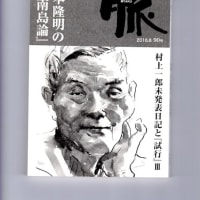 吉本隆明ノート Ⅰ ー 『心的現象論』ランダムノート ①玄関口で
6年前
吉本隆明ノート Ⅰ ー 『心的現象論』ランダムノート ①玄関口で
6年前
-
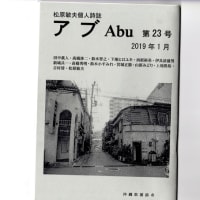 松原敏夫個人詩誌「アブ」第23号ー田中眞人、髙橋渉二、鈴木智之、下地ヒロユキ、西原裕美、伊良波盛男、新城兵一、高橋秀明、鈴木小すみれ、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、平良清志
6年前
松原敏夫個人詩誌「アブ」第23号ー田中眞人、髙橋渉二、鈴木智之、下地ヒロユキ、西原裕美、伊良波盛男、新城兵一、高橋秀明、鈴木小すみれ、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、平良清志
6年前
-
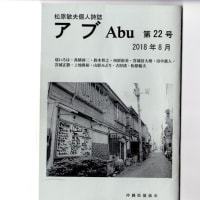 松原敏夫個人詩誌「アブ」第22号―瑶いろは、髙橋渉二、鈴木智之、西原裕美、田中眞人、宮城信大朗、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、吉村清
6年前
松原敏夫個人詩誌「アブ」第22号―瑶いろは、髙橋渉二、鈴木智之、西原裕美、田中眞人、宮城信大朗、宮城正勝、山原みどり、上地隆裕、吉村清
6年前
-
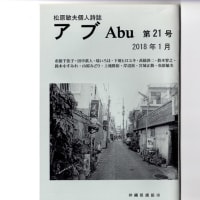 松原敏夫個人詩誌「アブ」21号―市原千佳子、田中眞人、瑶いろは、下地ヒロユキ、髙橋渉二、鈴木智之、鈴木小すみれ、山原みどり、上地隆裕、岸辺 裕、宮城正勝
6年前
松原敏夫個人詩誌「アブ」21号―市原千佳子、田中眞人、瑶いろは、下地ヒロユキ、髙橋渉二、鈴木智之、鈴木小すみれ、山原みどり、上地隆裕、岸辺 裕、宮城正勝
6年前
-
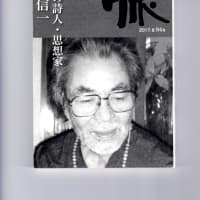 詩は手套のような女―川満信一の詩と思想 対談:松原敏夫×東中十三郎 (脈94号 特集:沖縄の詩人・思想家 川満信一)
6年前
詩は手套のような女―川満信一の詩と思想 対談:松原敏夫×東中十三郎 (脈94号 特集:沖縄の詩人・思想家 川満信一)
6年前
-
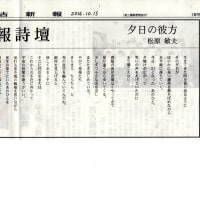 近作詩 夕日の彼方
6年前
近作詩 夕日の彼方
6年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます