 西銘郁和詩集『時の岸辺に』(非世界出版会、2008年6月)
西銘郁和詩集『時の岸辺に』(非世界出版会、2008年6月)
自然、社会から位置をずらして言語のための詩という領域を疾走し<戦後詩はもはや、なつメロのようなものです。>というパラダイム的雰囲気がただよっているのが現代詩の状況であろう。しかし詩は時代を突き抜けていく感受性を表現する言葉が求められるはずだし、当世詩のパラダイムから故意に距離をおいて個人的生存を素材にして書く方法は傍流ではなく、むしろ本流に近いはずだ。そこには個人的でありながら出自を基層にして自然を内在化した言葉が立ちあらわれ、存在を表現へと転移する等身大バースを読むことができる。
耳を澄ませば いまでも
海鳴りが聴こえてくる
(跨越す少年)
「神」の怒号にも聴こえる
この海鳴りは
とおく とおく
胎児の頃にも聴こえていた
(ホノホシ紀行)
西銘の出自が沖縄中部の宮城島であることを知って、<海鳴り>は特別の意味を持っていると思った。幼年期のパナリ島での生活風景は裏の島、静寂、光、闇、海風、サトウキビ、瓦屋根、海の青、そして絶えず繰り返す海鳴りではなかったか。記憶と心性にはおそらくこのパナリの海鳴りが脈うっているのだろう。そしてそれはさかのぼって母の子宮で胎児であったときにも聴いていたとする。それほど<海鳴りの音>というのは身体にしみこんだ音であった。海の音、風の音、雨の音は近くに奏でる島の音楽のようなものであった。それは包み込むような静かなときもあれば、たしかに怒り狂ったような<神の怒号>のような時もあった。そして、島を離れて観念の過剰と暴走を内包した青春から遠く歳月をへだてて<いま>を生きる<時の岸辺>に書かれた詩編が詩集となった。
この詩集には日常や家族、係累、友人、他者あるいは記憶の風景や旅の事象への関わり事に触発された後に発生する言語が織り込まれている。西銘にとっては、詩はつくるものではなく、起こるものだという認識があるように思う。作者が現実に生起する出来事に触発されて、これを詩にしたいと思わなければ詩にならない。 たとえば「詩を書くために/県立・中部病院に通ったことがある」で始まる「詩を書くために」という作品には二人の叔母の、リアルな死の場面があるが、その場面に起こった出来事に触発されたものを語り調で書いている。
表現を歌的な技法か語り的な技法を択ぶのは、作者が決めることだ。手法は私的な出来事から詩的モチーフを紡ぎ出して喩法を使わず語り調で言語を展開する特徴とみた。西銘は出来事の詩人である、と乱暴にいっていいかもしれない。











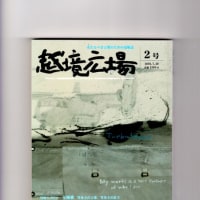
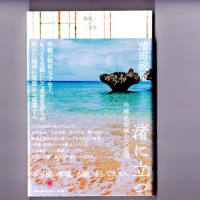
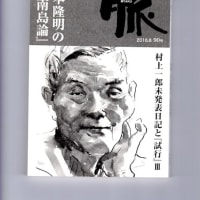
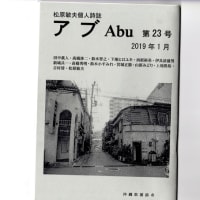
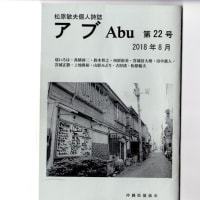
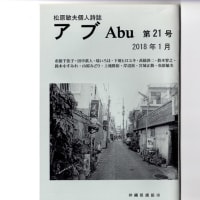
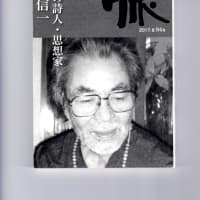
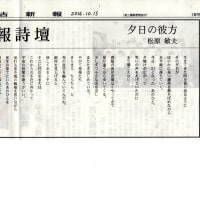
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます