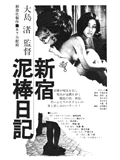★★★★ 2008年/日本 監督/筧昌也
「原作の映画化としては大成功」
原作を読んでいるのですが、正直この作品の映画化は難しいだろうと思っていました。なぜなら、6話程度のショートストーリィから成り、2時間という尺でうねりを出すような風合いの物語ではないからです。言わば、間を楽しむといった手合いの小説。しかし、観てみると期待以上の出来映え。ふんわりとしたムードを押さえつつ、3話のエピソードが死神を軸にしっかりと1つにまとめあげられています。これは、脚本がうまいですね。上手に削り、上手に付け加えました。原作に相棒の黒犬は出てきませんが、犬と死神が無言で会話するという現実離れしたシチュエーションも作品が醸し出す浮遊感をうまく盛り上げています。
何と言っても本作の面白味は、「何事も達観している死神」と「目の前の出来事に一喜一憂しているちっぽけな人間」の対比が実に良く効いていること。その一番の貢献者は、やはり死神を演じている金城武です。近年の彼の作品の中ではベストアクトではないでしょうか。浮世離れした風貌、飄々としたセリフ回し、どんな設定の人間になっても何色にも染まらない透明感。立場は人間より上ですが、全く嫌味がありません。しかも、その存在がでしゃばり過ぎていない。だから、3つのエピソードの人間たちの悩みや苦しみがきちんと際だっているのです。焦点の合わない目でヘッドフォンを付け、リズムに合わせて肩を揺らす様子も実におかしい。
また、3話のエピソードは時を超えて繋がってくるわけですが、ラストにかけてどうだと言わんばかりの仰々しさが全くないのも非常に好感が持てます。作り手としては、どうしても観客をあっと言わせたいがために、種明かし的な演出に走りがちですけれども、実にさらっとしています。そして、そのことによって、最終的には金城武演ずる死神の人生がクローズアップされてくるんですね。それまで語り部としての役割しか持たなかった死神に、初めてこの世の美しさ、人間世界の温かみといったものを体感させる。なかなかじんわりできるエンディングです。不安が多くて足が向かなかったのですが、こんなことなら、映画館で観れば良かったです。
「原作の映画化としては大成功」
原作を読んでいるのですが、正直この作品の映画化は難しいだろうと思っていました。なぜなら、6話程度のショートストーリィから成り、2時間という尺でうねりを出すような風合いの物語ではないからです。言わば、間を楽しむといった手合いの小説。しかし、観てみると期待以上の出来映え。ふんわりとしたムードを押さえつつ、3話のエピソードが死神を軸にしっかりと1つにまとめあげられています。これは、脚本がうまいですね。上手に削り、上手に付け加えました。原作に相棒の黒犬は出てきませんが、犬と死神が無言で会話するという現実離れしたシチュエーションも作品が醸し出す浮遊感をうまく盛り上げています。
何と言っても本作の面白味は、「何事も達観している死神」と「目の前の出来事に一喜一憂しているちっぽけな人間」の対比が実に良く効いていること。その一番の貢献者は、やはり死神を演じている金城武です。近年の彼の作品の中ではベストアクトではないでしょうか。浮世離れした風貌、飄々としたセリフ回し、どんな設定の人間になっても何色にも染まらない透明感。立場は人間より上ですが、全く嫌味がありません。しかも、その存在がでしゃばり過ぎていない。だから、3つのエピソードの人間たちの悩みや苦しみがきちんと際だっているのです。焦点の合わない目でヘッドフォンを付け、リズムに合わせて肩を揺らす様子も実におかしい。
また、3話のエピソードは時を超えて繋がってくるわけですが、ラストにかけてどうだと言わんばかりの仰々しさが全くないのも非常に好感が持てます。作り手としては、どうしても観客をあっと言わせたいがために、種明かし的な演出に走りがちですけれども、実にさらっとしています。そして、そのことによって、最終的には金城武演ずる死神の人生がクローズアップされてくるんですね。それまで語り部としての役割しか持たなかった死神に、初めてこの世の美しさ、人間世界の温かみといったものを体感させる。なかなかじんわりできるエンディングです。不安が多くて足が向かなかったのですが、こんなことなら、映画館で観れば良かったです。