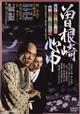★★★★ 1978年/日本 監督/東陽一
「帰るべきホームがない」
野球部で活躍するサードというあだ名の少年。クラスで仲のいい友人はなかなかの秀才。ある日、クラスメイトの女子と街を出て東京に住みたいがそのためのお金がないという話になり、資金稼ぎに売春と斡旋に手を染めるようになる…。
すいぶん昔に見たんですけど、改めて再観賞。脚本が寺山修司なんですね。スポーツマンと秀才のふたりの高校生が「何となく」始めた売春斡旋で人生の坂を転がり落ちてしまう。彼らの行いを分別のつかない若さゆえ、と判断するのは難しい。だって、売春だもんね。昔見たときは少年院で行き場のないモヤモヤを心に溜めるサードに心奪われていたけど、今回見て感じるのは、売春を始めるふたりの少女の空虚感。
「あたしたちの体を売ればいいじゃん」喫茶店でコーヒーを飲みながら、あどけない顔の森下愛子が言う。それをサードはこう述懐する。「まるで大根を売るみたいだった」と。実に印象的なセリフです。そして、少年院にいるサードは知る。事件後、彼女たちは東京には出ずに田舎で普通に結婚したと。
何となく体を売り、それが駄目になったら、何となく誰かと結婚する。きっと、彼女たちは何となく子供を産み、何となく年を経ていくのだろう。彼女みたいな子たちは現代にもいっぱいいる。最近の映画「蛇とピアス」や「M」にも同じような女が出てくる。
しかしそうして、女たちは何となく自分の居場所に着地するのに対し、サードたち少年たちは帰るべき場所を持たない。ただひたすらに黙々と少年院のグラウンドをランニングする。一塁ベースを踏み、二塁、三塁と回るけれども、なぜかホームベースが置かれていないグラウンドがそれを物語っている。
さて、永島敏行と森下愛子の若手俳優陣が光る中、異彩を放つ脇役がいる。島倉千代子だ。「溺愛する母」と「反抗する息子」の組み合わせは、この時代の日本映画によく登場してくるモチーフだけれども、本作でもこのテーマは重要な位置を占めている。風呂上がりに上半身裸で出てくる息子に対して、「あら、いやだよ。母さんだって女なんだから」と猫なで声で言う。何だか気味悪くて背筋がぞぞっとしてしまうのだった。
「帰るべきホームがない」
野球部で活躍するサードというあだ名の少年。クラスで仲のいい友人はなかなかの秀才。ある日、クラスメイトの女子と街を出て東京に住みたいがそのためのお金がないという話になり、資金稼ぎに売春と斡旋に手を染めるようになる…。
すいぶん昔に見たんですけど、改めて再観賞。脚本が寺山修司なんですね。スポーツマンと秀才のふたりの高校生が「何となく」始めた売春斡旋で人生の坂を転がり落ちてしまう。彼らの行いを分別のつかない若さゆえ、と判断するのは難しい。だって、売春だもんね。昔見たときは少年院で行き場のないモヤモヤを心に溜めるサードに心奪われていたけど、今回見て感じるのは、売春を始めるふたりの少女の空虚感。
「あたしたちの体を売ればいいじゃん」喫茶店でコーヒーを飲みながら、あどけない顔の森下愛子が言う。それをサードはこう述懐する。「まるで大根を売るみたいだった」と。実に印象的なセリフです。そして、少年院にいるサードは知る。事件後、彼女たちは東京には出ずに田舎で普通に結婚したと。
何となく体を売り、それが駄目になったら、何となく誰かと結婚する。きっと、彼女たちは何となく子供を産み、何となく年を経ていくのだろう。彼女みたいな子たちは現代にもいっぱいいる。最近の映画「蛇とピアス」や「M」にも同じような女が出てくる。
しかしそうして、女たちは何となく自分の居場所に着地するのに対し、サードたち少年たちは帰るべき場所を持たない。ただひたすらに黙々と少年院のグラウンドをランニングする。一塁ベースを踏み、二塁、三塁と回るけれども、なぜかホームベースが置かれていないグラウンドがそれを物語っている。
さて、永島敏行と森下愛子の若手俳優陣が光る中、異彩を放つ脇役がいる。島倉千代子だ。「溺愛する母」と「反抗する息子」の組み合わせは、この時代の日本映画によく登場してくるモチーフだけれども、本作でもこのテーマは重要な位置を占めている。風呂上がりに上半身裸で出てくる息子に対して、「あら、いやだよ。母さんだって女なんだから」と猫なで声で言う。何だか気味悪くて背筋がぞぞっとしてしまうのだった。