★★★ 2005年/日本 監督/三谷幸喜
「ドタバタ劇にも群像劇にもなってない」
大晦日にホテルで起きた奇跡がコンセプトなんだろうが、豪華なおもちゃ箱をひっくり返して、適当に遊んでまた箱に戻しました、みたいな印象。で、一体どこが有頂天なんだろうか?タイトルからしてわからない。
まずこの作品は非常に登場人物が多い。ここまで多くさせるなら、とことん「あの人とあの人が!」という仕掛けやハプニングをもっともっと出してハチャメチャにしないと。この程度の繋がり具合なら、この手の作品の批評によくある「あの話はいらなかった」という意見が出ても当然だろう。「このネタはいる」「このネタはいらん」という意見そのものがまかり通ること自体、ひとつの作品としては大きな欠陥と言わざるを得ない。
大晦日の奇跡に絞ったドタバタ劇ならそれに徹すればいいものを、群像劇として心温まる物語にしようという無理矢理感も全体の統一感のなさの一因。ラストシーンはお客様を出迎える役所広司なわけで「ホテルはあなたの家、ホテルマンはあなたの家族」というコンセプトもこの作品には見受けられるが、これに関しては描き方が甘すぎる。これをメインコンセプトにして、「ホテルマンとゲスト」の衝突や対話、信頼などにスポットを当てれば、物語としてはもっと面白くなったと思う。伊東四朗、生瀬勝久、戸田恵子。この3名のホテルスタッフが全然お客様と絡んでこない。これはもったいない。
「好きなことをあきらめないで」というセリフや、鹿のかぶりもので笑いを取るなど、驚くほどベタな演出も多い。ボタンの掛け違いから次々と笑いを生みだすいつもの手法も、引っ張りすぎでつまらない。そうつまらないのだ。三谷幸喜ならもっとウィットに富んだ会話や笑いが作れるはずなのに、どうして?という悲しい声がぐるぐると頭を駆け回る。
結局ハチャメチャにできなかったのは、ハートウォーミングで上品な作品に仕上げたかったからだろう。(元ネタの『グランドホテル』ってそういう感じなんでしょうか?未見なのでわかりません)でも群像劇としてしっかり作り込むのには、登場人物が多すぎる。このジレンマに苦しんで生まれた作品と感じた。豪華役者陣勢ぞろいで舞台はホテルです!みたいな企画がまず最初にあったのかなあ。三谷幸喜は好きな作家だけにこの作品は非常にがっかり。見所は昔のワルに戻る瞬間の役所広司の演技。さすが、ドッペルゲンガー。
「ドタバタ劇にも群像劇にもなってない」
大晦日にホテルで起きた奇跡がコンセプトなんだろうが、豪華なおもちゃ箱をひっくり返して、適当に遊んでまた箱に戻しました、みたいな印象。で、一体どこが有頂天なんだろうか?タイトルからしてわからない。
まずこの作品は非常に登場人物が多い。ここまで多くさせるなら、とことん「あの人とあの人が!」という仕掛けやハプニングをもっともっと出してハチャメチャにしないと。この程度の繋がり具合なら、この手の作品の批評によくある「あの話はいらなかった」という意見が出ても当然だろう。「このネタはいる」「このネタはいらん」という意見そのものがまかり通ること自体、ひとつの作品としては大きな欠陥と言わざるを得ない。
大晦日の奇跡に絞ったドタバタ劇ならそれに徹すればいいものを、群像劇として心温まる物語にしようという無理矢理感も全体の統一感のなさの一因。ラストシーンはお客様を出迎える役所広司なわけで「ホテルはあなたの家、ホテルマンはあなたの家族」というコンセプトもこの作品には見受けられるが、これに関しては描き方が甘すぎる。これをメインコンセプトにして、「ホテルマンとゲスト」の衝突や対話、信頼などにスポットを当てれば、物語としてはもっと面白くなったと思う。伊東四朗、生瀬勝久、戸田恵子。この3名のホテルスタッフが全然お客様と絡んでこない。これはもったいない。
「好きなことをあきらめないで」というセリフや、鹿のかぶりもので笑いを取るなど、驚くほどベタな演出も多い。ボタンの掛け違いから次々と笑いを生みだすいつもの手法も、引っ張りすぎでつまらない。そうつまらないのだ。三谷幸喜ならもっとウィットに富んだ会話や笑いが作れるはずなのに、どうして?という悲しい声がぐるぐると頭を駆け回る。
結局ハチャメチャにできなかったのは、ハートウォーミングで上品な作品に仕上げたかったからだろう。(元ネタの『グランドホテル』ってそういう感じなんでしょうか?未見なのでわかりません)でも群像劇としてしっかり作り込むのには、登場人物が多すぎる。このジレンマに苦しんで生まれた作品と感じた。豪華役者陣勢ぞろいで舞台はホテルです!みたいな企画がまず最初にあったのかなあ。三谷幸喜は好きな作家だけにこの作品は非常にがっかり。見所は昔のワルに戻る瞬間の役所広司の演技。さすが、ドッペルゲンガー。
























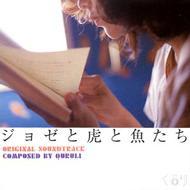
 映画ランキングに参加しています。面白かったらポチッと押してね。
映画ランキングに参加しています。面白かったらポチッと押してね。
