
雀蜂
大きな羽音がした。それを蜂だと察知し、私は素早く頭を下げた。
案の定、雀蜂が頭上を飛んで行く。
こんな時期に山登りなどしなければよかった。うっかり蜂の巣に近づいたらえらい目に合う。
頭を上げた矢先、またもや雀蜂が通り過ぎ、「ひゃっ」と声を上げて再びしゃがみ込んだ。やはり巣が近いのかもしれない。
蜂は私に見向きもせず一方向へまっしぐらに飛んでいく。丸めた餌を持っていたので巣に帰るのだとわかった。
雀蜂はテリトリーに入った人間を威嚇し、攻撃する。巣のある方向に歩を進めるわけにはいかない。残念だが来た道を戻ることにした。
その後も団子を持った何匹もの蜂に出くわし、ひやひやする。
どれだけの数の蜂がいるんだろう。よく働くもんだ。帰ったら習性でも調べてみるか。
そう思いながら歩を進めていたが、雀蜂の団子を持ってくる方向が無性に気になった。
いったい何を運んでいるのか。
少しぐらい登山道から外れても迷うことはないだろうと、飛んでくるほうに見当をつけ、蜂を避けながら繁茂する木々の枝をかき分けた。
臭覚がおぞましい腐臭をとらえる。
「あっ」
雀蜂が飛びまわる草むらに人間の腐乱死体が横たわっていた。
無数の雀蜂がその上で一生懸命肉団子を作っていた。
*
「雀蜂の巣ぅ探すにゃあ、これを用意するがぁ」
色褪せた麦わら帽をかぶった老人がひゃひゃひゃと笑った。
指にひとかけの白っぽい肉片がつままれている。
「それは何ですか? キムラさん」
「鳥のささみだで。これを仕掛けるが」
「へええ」
「仕掛けたささみを取りに来たらこん印を脚につけるがぁ」
こよりの付いた糸をキムラ翁が差し出す。
「へええ」
さっきから自分が間抜けな返事しかしていないことに気付いて心の中で笑った。
心機一転、田舎暮らしを実行した私は、不満を漏らしながらもついてきてくれた妻のご機嫌を取りつつ、のんびりしたその生活を満喫していた。
幸運なことにご近所さんはみんな親切でなんでも教えてくれる。
私は隣人のキムラ翁に蜂の子の取り方を教わっていた。
この辺りの蜂の子で作った佃煮がうまいと聞き、作ってみたくなったのだ。
一度でも試食できたらわざわざ作りたいと思わなかったかもしれない。
だが、あまりの美味さに食べ尽くしてしまうので、村のどこにも作り置きがないのだそうだ。土産物屋にも出回らない地元民だけのご馳走だとキムラ翁がいう。
これは食べてみなくては。
妻から「そんなもの作れんの?」と馬鹿にされ、意地でもやってやろうと決心した。
収穫の時期に近いということもあり、私の頼みをキムラ翁が快諾してくれたというわけだ。
だが。
「ほら、来たで」
どこにいるのか見えないのに大きな羽音がする。嫌な音だ。
怖くなり思わず木の陰に隠れてキムラ翁に視線を送る。
「怖くないんですか?」
「こんなん怖がっとったら蜂の子取れんで」と、ひゃひゃひゃと笑う。「おっ、止まったで、よう見とくがぁ」
木の陰からそっと覗くと枝に刺したささみの肉に食らいつく大きな雀蜂の後ろ姿が見えた。
キムラ翁は恐れもせず蜂に近づき、その後脚にこよりの糸を引っかけた。
しばらくして飛び立ったので、私は再び木の陰に引っ込んだ。こんなところを見たら妻が笑うだろうが、手も足も出ない。
「早よっ、追うで」
ふわりと飛んでいくこよりをキムラ翁は追った。
私も恐る恐る木陰から出てその後を追う。
当たり前のことだが、雀蜂は追ってくる人間のことなど考えていない。道から外れた藪の上を飛んでいくのでしっかり視野に捉えるのは大変だった。
だが、キムラ翁は迷いなく追いかけていく。
「ここやな」
いったん足を止めた翁は、今度は藪の中に入り込んだ。
しばらくして藪から出てくると、離れた場所で隠れ待つ私に両手で大きな丸を作ってみせた。
近隣の男たちが集まった。
煙幕とシャベルを持って目印を付けた場所へ蜂の子確保に向かう。
ぶんぶんという羽音すら怖くて、結局私はそばに行くことができなかった。
役立たずだ。まだまだ村の男として認めてもらえないだろう。巣を取り出す場面すら見ることができず、自己嫌悪に陥る。
だが、そんなことを気にしている人たちはいない。みないい人たちばかりだ。
キムラ家の庭先が祭りのような騒ぎになる。ここにはちゃっかり私も混ざった。
蜂の巣は結構な大きさでみな大喜びだ。
ゴミ用袋いっぱいに入った蜂の巣が取り出される。
小さな六角形の一つ一つの部屋に蜂の子が入っていた。白い芋虫状の体に茶色い頭が付いて、もぞもぞと蠢いている。
私は目を凝らして何度も見直した。目を擦り、何度も何度も見直した。
見間違いでも錯覚でもない。
蜂の子の顔は人のそれだった。その目や口を歪め、甲高い声で泣き叫んでいる。
巣を守ろうとしがみついて死んでいる親蜂も人の顔をしていた。
呆然と見つめる私にキムラ翁が耳打ちする。
「ここの蜂ぁ山で自殺したもんの死体を喰うでぇ、みなこんなだ。ひゃひゃひゃ」
私は田舎暮らしをこのまま続けていけるかどうか自信がなくなった。
*
「ほれ楽しみにしてた蜂の子だで、食いな。うまいでぇ」
キムラ翁は蜂の子の佃煮が入った小皿を差し出し、「おまん、あんとき蜂の子持って帰らんかったで、おすそ分けや」と笑った。
「蜂の子取りでは役に立たなかったんで、いただくのは申し訳ないかなと思いまして――」
「そんな遠慮せんでええのにぃ、水くさいのぉ」
ひゃひゃひゃとまた笑う。
好意は嬉しいが、あの蜂の子を調理する気にはどうしてもなれなかった。
偽りの言い訳をキムラ翁が気づいていないことを願う。
あの時、甲高い声で『泣いて』いる蜂の子を村のみんなは嬉々として持ち帰った。
キムラ翁に至っては生きた親蜂もそのまま焼酎に付け込んでいた。
「遠慮せんと早よ食え。
嫁はんに持って帰る分はちゃんと用意してるで心配いらんよ」
私は躊躇していたが、せっかくの好意を無にするのは今後の付き合いに支障が出る。
目を閉じれば何とか食べられるだろう。
そう決断した。
震える手を皿に伸ばし、一つだけ翁に確認する。
「人がこれ食べたら『どう』なるんですかね?」
「滋養強壮や。『元気』になる決まっとるがぁ。
嫁さん泣いて喜ぶでぇ。ひゃひゃひゃ」
質問の意図はくみ取ってもらえなかった。
翁の顔が、いや村人たちの顔が何となく蜂に似ているのはただの偶然か――それを知りたかったのだが。
目を閉じて蜂の子を口に放り込む。
むちっとした歯触りがして、甘辛さと何とも言えぬ濃厚でクリーミーな味が口に広がった。
確かに、確かに美味い。
もらった瓶詰の佃煮を帰って妻に見せた。茶色に煮詰まった小さな小さな人面の集まりを見て悲鳴を上げるだろうと思っていたが、何もためらうことなく大喜びし、ふたを開けるや否やがつがつと全部食べてしまった。
*
散歩の途中、蟻の隊列に出くわした。
例の雀蜂の死骸を運んでいる。
まさか蟻まで――
しゃがんでよく見てみた。普通の蟻だった。
なんとなくほっとする。
小さな蟻に混じって頭の大きな兵隊蟻が数匹、応援に駆け付けてきた。
そいつらはこちらに人面を向けるとにやりと笑った。










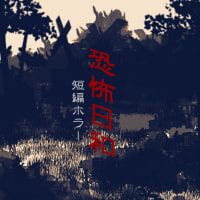
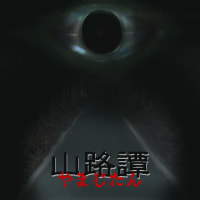

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます