残念だが、一元論が大事なので、今回の記事はその補足のようなものである
学校が始まるので、次回の記事がいつになるかは分からないが、その時はきっと
新しく興味深い価値観(陰陽五行説とか)を紹介できると信じたい(できなかったら心の哲学に入る)
この記事で私のブログの一元論に一旦区切りをつけて、しばらくは封印したいと思う
まず「=」の意味についてだ
これはA=Aのようなトートロジー(無意味な繰り返し)ではなく
A=Bのように、表面上(表記)は違うが、本質が同じ(同質)である場合に用いる
例えば「明けの明星」=「宵の明星」=「金星」といった感じである
数学においてこの一元論は、表す数が同じである場合の「=」のみに適応されるようで
1=2=3=・・・=自然数、と表記したら、数学者に怒られてしまうのである(苦笑)
しかし、数ではなく概念に対して適応するなら、数学者は我々哲学者の意見を蔑ろにはできまい
「直線」=「円」であり、その本質は【円】である、というのは「一元論者」には当たり前の話であろう
直線は半径無限大の円である
円であるが故にその両端を定義することはできない
「両端()は繋がっているに違いないが、それを我々が想像しうるかどうかは全くの別問題である」と述べておく
私はゼミの発表で殻模型と呼ばれるものについても述べることがあった
「原子において原子核の周りを電子がまわっているのと同様に、原子核において陽子核や中性子核の周りを中性子や陽子がまわっているのである」と述べたのだが、これこそがミクロな世界の面白さであるなどと言ってうまく誤魔化しておいた
この話をきちんと理解するには、フラクタル的な考えと一元論的な考えの両方が必要であり、視聴者にそれを強いるのは酷であった
人智を超えているのは明らかであり、想像することは原理的に不可能かもしれないが、頑張って理解してもらえるとうれしいです
次は三段論法についてだ
A=BかつB=CならA=Cであるだとか
A<BかつB<CならA<Cであるといった論である
例えば、「明けの明星」は「金星」であり、「宵の明星」も「金星」であるから、「明けの明星」は「宵の明星」であるという風になる
もちろん正しいに決まっているのだが、「=」の意味を理解していない人間にとっては間違いに見えるのかもしれない
え、僕が間違ってるって?
誰か「リンゴは赤いというのはリンゴならば赤いという一方通行の矢印であり、その逆は成り立たない。リンゴ→赤いであってリンゴ←赤いではないのだ!」
俺「いやあ、【=】と【は】を同じものとして扱いたいという前提を共有した上で言わせてもらおう。子供の頃の遊びを思い出して欲しい。りんごはあかい。あかいはいちご。いちごは小さい。小さいはすな。......【=】が特定の性質の等しさを示す記号だとすればうまく説明できるよね。少なくとも国語における【=】はこれでいいだろう」
あくまでも私が否定するのは国語における三段論法であって、数学の世界に限って言えば三段論法は正しいのだ。まあ、現実の説明には全く役に立たないという意味であるが。
もう一つ例を挙げると、「ぐー」は「ちょき」より強く、「ちょき」は「ぱー」より強いので、「ぐー」は「ぱー」より強いという風になる
もちろん正しいに決まっているのだが......いいや、間違ってるよ!
今回の場合は「相性」が全く考慮されていないね
ポケモンとかが有名だし、【相性】を理解するのに役立つかな
とにかく三段論法を現実問題で使うのはやめておいた方が良いということだけを確認したつもりだ
最後に、逆説(パラドックス)についてだ
例えば「アキレスと亀」
亀の方が先にスタートして後から足の速いアキレスが追いかける
アキレスがスタートした時の亀の位置にアキレスが追いついたとき、亀はそれよりも少し先(位置1)に進んでいる
位置1までアキレスが来たときに、亀はさらにその先(位置2)に進んでいる
位置2まで....(以下略)
アキレスは亀に永遠に追いつけないというパラドックスだ
普通に計算すると、当然アキレスが亀に追いつく時間が出てくる
実はこの話、アキレスが亀に追いつくまでの時間しか見ていないのだ
つまり、今と未来を見ずに、過去だけを見ているような話である
このように物事の一側面だけを見ると、その本質を見誤ってしまうかもしれない
他の例:「全ては無意味である、だから自殺します。」というのは、世界の虚無的側面だけを見た場合に得られる結論である
それは確かに正しいが、同時に間違っているのだ
物事の本質だけを見せることはできない
表面と本質は具体例においてセットでしか認識され得ない
だから複数のセットを見せることで本質を浮き彫りにするのが一般的である
分類における一元論:君も私も人間。人間も犬も動物。動物も植物も生物。と言う風に一つにまとめていく
絶対と相対と虚無における一元論:有が無い=無が有る()
考える意味:裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏を読んだ僕の負けでした(*≧∀≦*)
過度の一般化:一元論は過度の一般化である。独我論を過度に一般化して、「全ての人間に心がある」などというふざけた考えを持っている人間に対してのみ有効である。
一元論はそれ自体に自己批判を含んでおり、他理論からの批判を一切受け付けないということも知っておいて欲しい。
一元論に則って考えると、半分正しくて半分間違っているという状態はなく、全ては100%間違っていると同時に100%正しいのである(正しい=間違っている)
一元論は、全てが一つであり唯一無二であるという考え方であり、無個性的なもの(全部同じだもの)はすべて個性的(全てであり一つしかないから)なのである
また、一元論は本質についてのみの話であり、人を見かけで判断している人々にはあまり説得力の無い話であるが、逆に中身で判断している人を批判するのに適している
一元化するのもしないのも同じこと、信じるのも信じないのも同じこと。自由に束縛できないことを自由と呼ぶのだ。
。一元論については語り尽くせないので、自分で暇なときに考えておくとよい
おわり←
関連:(三段論法)妻より1円の方が良い? (論理と意味)
学校が始まるので、次回の記事がいつになるかは分からないが、その時はきっと
新しく興味深い価値観(陰陽五行説とか)を紹介できると信じたい(できなかったら心の哲学に入る)
この記事で私のブログの一元論に一旦区切りをつけて、しばらくは封印したいと思う
まず「=」の意味についてだ
これはA=Aのようなトートロジー(無意味な繰り返し)ではなく
A=Bのように、表面上(表記)は違うが、本質が同じ(同質)である場合に用いる
例えば「明けの明星」=「宵の明星」=「金星」といった感じである
数学においてこの一元論は、表す数が同じである場合の「=」のみに適応されるようで
1=2=3=・・・=自然数、と表記したら、数学者に怒られてしまうのである(苦笑)
しかし、数ではなく概念に対して適応するなら、数学者は我々哲学者の意見を蔑ろにはできまい
「直線」=「円」であり、その本質は【円】である、というのは「一元論者」には当たり前の話であろう
直線は半径無限大の円である
円であるが故にその両端を定義することはできない
「両端()は繋がっているに違いないが、それを我々が想像しうるかどうかは全くの別問題である」と述べておく
私はゼミの発表で殻模型と呼ばれるものについても述べることがあった
「原子において原子核の周りを電子がまわっているのと同様に、原子核において陽子核や中性子核の周りを中性子や陽子がまわっているのである」と述べたのだが、これこそがミクロな世界の面白さであるなどと言ってうまく誤魔化しておいた
この話をきちんと理解するには、フラクタル的な考えと一元論的な考えの両方が必要であり、視聴者にそれを強いるのは酷であった
人智を超えているのは明らかであり、想像することは原理的に不可能かもしれないが、頑張って理解してもらえるとうれしいです
次は三段論法についてだ
A=BかつB=CならA=Cであるだとか
A<BかつB<CならA<Cであるといった論である
例えば、「明けの明星」は「金星」であり、「宵の明星」も「金星」であるから、「明けの明星」は「宵の明星」であるという風になる
もちろん正しいに決まっているのだが、「=」の意味を理解していない人間にとっては間違いに見えるのかもしれない
え、僕が間違ってるって?
誰か「リンゴは赤いというのはリンゴならば赤いという一方通行の矢印であり、その逆は成り立たない。リンゴ→赤いであってリンゴ←赤いではないのだ!」
俺「いやあ、【=】と【は】を同じものとして扱いたいという前提を共有した上で言わせてもらおう。子供の頃の遊びを思い出して欲しい。りんごはあかい。あかいはいちご。いちごは小さい。小さいはすな。......【=】が特定の性質の等しさを示す記号だとすればうまく説明できるよね。少なくとも国語における【=】はこれでいいだろう」
あくまでも私が否定するのは国語における三段論法であって、数学の世界に限って言えば三段論法は正しいのだ。まあ、現実の説明には全く役に立たないという意味であるが。
もう一つ例を挙げると、「ぐー」は「ちょき」より強く、「ちょき」は「ぱー」より強いので、「ぐー」は「ぱー」より強いという風になる
もちろん正しいに決まっているのだが......いいや、間違ってるよ!
今回の場合は「相性」が全く考慮されていないね
ポケモンとかが有名だし、【相性】を理解するのに役立つかな
とにかく三段論法を現実問題で使うのはやめておいた方が良いということだけを確認したつもりだ
最後に、逆説(パラドックス)についてだ
例えば「アキレスと亀」
亀の方が先にスタートして後から足の速いアキレスが追いかける
アキレスがスタートした時の亀の位置にアキレスが追いついたとき、亀はそれよりも少し先(位置1)に進んでいる
位置1までアキレスが来たときに、亀はさらにその先(位置2)に進んでいる
位置2まで....(以下略)
アキレスは亀に永遠に追いつけないというパラドックスだ
普通に計算すると、当然アキレスが亀に追いつく時間が出てくる
実はこの話、アキレスが亀に追いつくまでの時間しか見ていないのだ
つまり、今と未来を見ずに、過去だけを見ているような話である
このように物事の一側面だけを見ると、その本質を見誤ってしまうかもしれない
他の例:「全ては無意味である、だから自殺します。」というのは、世界の虚無的側面だけを見た場合に得られる結論である
それは確かに正しいが、同時に間違っているのだ
物事の本質だけを見せることはできない
表面と本質は具体例においてセットでしか認識され得ない
だから複数のセットを見せることで本質を浮き彫りにするのが一般的である
分類における一元論:君も私も人間。人間も犬も動物。動物も植物も生物。と言う風に一つにまとめていく
絶対と相対と虚無における一元論:有が無い=無が有る()
考える意味:裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏を読んだ僕の負けでした(*≧∀≦*)
過度の一般化:一元論は過度の一般化である。独我論を過度に一般化して、「全ての人間に心がある」などというふざけた考えを持っている人間に対してのみ有効である。
一元論はそれ自体に自己批判を含んでおり、他理論からの批判を一切受け付けないということも知っておいて欲しい。
一元論に則って考えると、半分正しくて半分間違っているという状態はなく、全ては100%間違っていると同時に100%正しいのである(正しい=間違っている)
一元論は、全てが一つであり唯一無二であるという考え方であり、無個性的なもの(全部同じだもの)はすべて個性的(全てであり一つしかないから)なのである
また、一元論は本質についてのみの話であり、人を見かけで判断している人々にはあまり説得力の無い話であるが、逆に中身で判断している人を批判するのに適している
一元化するのもしないのも同じこと、信じるのも信じないのも同じこと。自由に束縛できないことを自由と呼ぶのだ。
。一元論については語り尽くせないので、自分で暇なときに考えておくとよい
おわり←
関連:(三段論法)妻より1円の方が良い? (論理と意味)










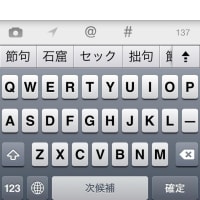

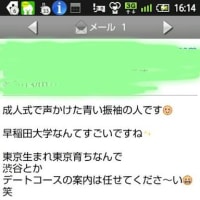

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます