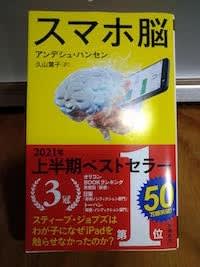まずはいつものように近況報告から入りたいと思います。
先月はほどんどアニメ見ませんでした。
実は鬼滅の刃の劇場版をまだ見ていないので(汗)、今放映されている無限列車編は見ておこうとは思っているのですが、まだ見ていません。
代わりに何をやっていたかというと、ゲームのモンハンライズやってることが多かったです。
今年の3月に発売されてから、特に他にやりたいゲームがなかったこともあり、ここ半年ずっとボチボチやっていたものの、モンハン初心者の私にとっては難易度が高く一向に上手くならなかったのですが、ここ最近ようやくモンハンというゲームのシステムが少し分かってきたのか、結構楽しくなってきました。

まぁもっとお金になることに時間を使った方がいいのかもしれませんが、ここしばらくはゲームをやっててもあまり楽しくなかったので、またゲームが楽しいと思えるようになっただけでも個人的には嬉しいですね。
〜〜〜
というわけで、今回は先月観た唯一のアニメ、「メイド・イン・アビス」について感想などを書いてみようと思います。
2017年に放映されていたアニメということで、ようやく見てみた感じです。
評判は結構良いと思うのですが、Googleで検索してみると「メイドインアビス 鬱」とか「メイドインアビス グロ」とかが予測で出てくることからも想像できるように、面白かったものの、なかなか一筋縄ではいかないアニメでした。
今回のブログは、前半はネタバレ少なめでざっと紹介する感じ、後半はガッツリネタバレしながら感想を書いていきたいと思っています。
簡単にあらすじを書いておくと、巨大な底知れぬ大穴「アビス」の淵の町で過去の「遺物」を発掘しながら孤児院で生活している少女リコは、ある日アビスの底から来たと思われる記憶を無くした少年の姿をしたロボット・レグと出会い、探窟家で死亡扱いとなっている行方不明の母親を探すためにアビスの底を目指す…という話です。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
最初見ていて思ったのは、「天空の城ラピュタ」の真逆、というか、鏡像、っていう感じだなぁ、と思いました。
主人公:少年パズー ↔︎ 少女リコ
ヒロイン:少女シータ ↔︎ 少年(ロボ)レグ
目指すもの:天空の城 ↔︎ 大穴の底
ただ、世界観は似ているものを感じます。
どこかヨーロッパの田舎町を彷彿とさせるような街並みや、主人公がどちらも両親がいないもののたくましく生活しているところなど、です。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
読んではいないのですが原作はマンガということで、この原作者さん、多分ジブリで育った我々と同世代なんじゃないか?と思ってWikiで調べたら、同い年でした(笑)
なんとなくワクワクしてくるような世界設定ですが…今回は、普段アニメを見ない人に向けて素直におすすめできるかというと、ちょっと難しいでしょうか。
先にもちょっと述べましたが、ストーリー展開に結構しんどいものがあると思います。
第6話ぐらいからちょっとざわっとしたものを感じ始め、第10話ぐらいから、え、ちょっと待って…という感じになり、第1期最終話の第13話は、嘘だろ…嘘だと言ってくれ…という感じになりました。

個人的にどれぐらいキツかったかというと、第10話から第13話が一気に見られなかったので、ちょこちょこコメディ映画「ポリス・アカデミー」を見ていたのですが、シリーズ全7作品を結局見てしまっていたくらいです。
結局第10話以降を見終わるまでに2週間以上かかりましたかねぇ(遠い目)
まぁポリスアカデミーを見ていたのはメイドインアビスのせいだけではないので、半分冗談なのですが、久々にキツいものを見たような気がします。
系統的には、ドラマ「ウォーキング・デッド」のどぎつさを少し思い出しました。
「ウォーキング・デッド」って、ゾンビのグロさもあるのですがそれよりも、人間のおぞましさ、みたいなのを際立たせている感じがあると思います。
(まぁウォーキングデッドに関しては、逆に、人間というか人類ってここまで酷くないだろ、とやり過ぎな感じも受けるので、最近は見ていません。)
と言っても、「メイド・イン・アビス」は名作と言える作品だと思います。
まだ原作も完結していないようなので、現段階では、となりますが。
自己判断でトラウマ耐性があると思われる方は、見てみるのはいかがでしょうか。
ストーリーとしては面白いと思います。
お時間の無い方には、再構成された総集編もあるみたいですね。13話まるまる見るよりは短いかと。
私はそっちの方は見ていないのですけど、新規カットもあるらしいので見た方がいいのかな。
ちなみに、前編・後編に分かれていて、後編はPG12ということです(笑)
さらに、その続編の劇場版「深き魂の黎明」はR15+となっております。
まぁ一つだけ不満な点というと大げさなのですが、挙げておきます。
第1話のオープニングが、起承転結の「起」が終わった後にスッと入ってくるのですが、これがめちゃめちゃカッコよかったんですよね。
曲もいわゆる「アニソン」ではなく英詞のアンビエントな感じで、アニメというよりは映画のオープニングみたいな感じでした。
それが、第2話からはオープニング・エンディングの両方とも、キャラソンというか、声優さんを歌い手に起用した曲になっていて、あれ?となってしまいました。
別に私は、洋楽至上主義でもキャラソン否定派でもないのですが、第1話のオープニングがカッコ良すぎたので、少し残念に思いました。

権利とかの関係で使えなかったのか、監督さんの何かしらの思惑があるのか、何か事情があるのかは分かりませんが。
まぁでも後半に差しかかると、なじんで違和感はなくなりました。
もともと悪い曲というわけではないので。特にエンディングの曲は結構好きですね。
「底の知れない大穴」というのは、ユング心理学的に言うと、人間の「自己」において、「無意識」の部分をあらわしていると言えると思います。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
大穴の底に向けて旅をしていく、ということは、「無意識」の中の光の当たらない、自分の中のおぞましい部分にも対峙せざるを得ない、ということで、「メイド・イン・アビス」が鬱展開になるのも、必然だったのかも知れないと思います。
(が、個人的には「無意識」の中にも、美しいものは存在しているのではないかと思いますし、また、おぞましいものが自分の中に存在しているとしても、それはあくまでも自分の「一部」なので、あまりそればかりに目を向けてしまうとかえって取り込まれてしまうこともあるのではないかと思います。)
この後のブログの後半はネタバレ有りで、もう少しユング心理学的なことを書いてみたいと思います。
一気に書こうかとも思いましたが、後半は改めて次回にしようと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
先月はほどんどアニメ見ませんでした。
実は鬼滅の刃の劇場版をまだ見ていないので(汗)、今放映されている無限列車編は見ておこうとは思っているのですが、まだ見ていません。
代わりに何をやっていたかというと、ゲームのモンハンライズやってることが多かったです。
今年の3月に発売されてから、特に他にやりたいゲームがなかったこともあり、ここ半年ずっとボチボチやっていたものの、モンハン初心者の私にとっては難易度が高く一向に上手くならなかったのですが、ここ最近ようやくモンハンというゲームのシステムが少し分かってきたのか、結構楽しくなってきました。

まぁもっとお金になることに時間を使った方がいいのかもしれませんが、ここしばらくはゲームをやっててもあまり楽しくなかったので、またゲームが楽しいと思えるようになっただけでも個人的には嬉しいですね。
〜〜〜
というわけで、今回は先月観た唯一のアニメ、「メイド・イン・アビス」について感想などを書いてみようと思います。
2017年に放映されていたアニメということで、ようやく見てみた感じです。
評判は結構良いと思うのですが、Googleで検索してみると「メイドインアビス 鬱」とか「メイドインアビス グロ」とかが予測で出てくることからも想像できるように、面白かったものの、なかなか一筋縄ではいかないアニメでした。
今回のブログは、前半はネタバレ少なめでざっと紹介する感じ、後半はガッツリネタバレしながら感想を書いていきたいと思っています。
簡単にあらすじを書いておくと、巨大な底知れぬ大穴「アビス」の淵の町で過去の「遺物」を発掘しながら孤児院で生活している少女リコは、ある日アビスの底から来たと思われる記憶を無くした少年の姿をしたロボット・レグと出会い、探窟家で死亡扱いとなっている行方不明の母親を探すためにアビスの底を目指す…という話です。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
最初見ていて思ったのは、「天空の城ラピュタ」の真逆、というか、鏡像、っていう感じだなぁ、と思いました。
主人公:少年パズー ↔︎ 少女リコ
ヒロイン:少女シータ ↔︎ 少年(ロボ)レグ
目指すもの:天空の城 ↔︎ 大穴の底
ただ、世界観は似ているものを感じます。
どこかヨーロッパの田舎町を彷彿とさせるような街並みや、主人公がどちらも両親がいないもののたくましく生活しているところなど、です。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
読んではいないのですが原作はマンガということで、この原作者さん、多分ジブリで育った我々と同世代なんじゃないか?と思ってWikiで調べたら、同い年でした(笑)
なんとなくワクワクしてくるような世界設定ですが…今回は、普段アニメを見ない人に向けて素直におすすめできるかというと、ちょっと難しいでしょうか。
先にもちょっと述べましたが、ストーリー展開に結構しんどいものがあると思います。
第6話ぐらいからちょっとざわっとしたものを感じ始め、第10話ぐらいから、え、ちょっと待って…という感じになり、第1期最終話の第13話は、嘘だろ…嘘だと言ってくれ…という感じになりました。

個人的にどれぐらいキツかったかというと、第10話から第13話が一気に見られなかったので、ちょこちょこコメディ映画「ポリス・アカデミー」を見ていたのですが、シリーズ全7作品を結局見てしまっていたくらいです。
結局第10話以降を見終わるまでに2週間以上かかりましたかねぇ(遠い目)
まぁポリスアカデミーを見ていたのはメイドインアビスのせいだけではないので、半分冗談なのですが、久々にキツいものを見たような気がします。
系統的には、ドラマ「ウォーキング・デッド」のどぎつさを少し思い出しました。
「ウォーキング・デッド」って、ゾンビのグロさもあるのですがそれよりも、人間のおぞましさ、みたいなのを際立たせている感じがあると思います。
(まぁウォーキングデッドに関しては、逆に、人間というか人類ってここまで酷くないだろ、とやり過ぎな感じも受けるので、最近は見ていません。)
と言っても、「メイド・イン・アビス」は名作と言える作品だと思います。
まだ原作も完結していないようなので、現段階では、となりますが。
自己判断でトラウマ耐性があると思われる方は、見てみるのはいかがでしょうか。
ストーリーとしては面白いと思います。
お時間の無い方には、再構成された総集編もあるみたいですね。13話まるまる見るよりは短いかと。
私はそっちの方は見ていないのですけど、新規カットもあるらしいので見た方がいいのかな。
ちなみに、前編・後編に分かれていて、後編はPG12ということです(笑)
さらに、その続編の劇場版「深き魂の黎明」はR15+となっております。
まぁ一つだけ不満な点というと大げさなのですが、挙げておきます。
第1話のオープニングが、起承転結の「起」が終わった後にスッと入ってくるのですが、これがめちゃめちゃカッコよかったんですよね。
曲もいわゆる「アニソン」ではなく英詞のアンビエントな感じで、アニメというよりは映画のオープニングみたいな感じでした。
それが、第2話からはオープニング・エンディングの両方とも、キャラソンというか、声優さんを歌い手に起用した曲になっていて、あれ?となってしまいました。
別に私は、洋楽至上主義でもキャラソン否定派でもないのですが、第1話のオープニングがカッコ良すぎたので、少し残念に思いました。

権利とかの関係で使えなかったのか、監督さんの何かしらの思惑があるのか、何か事情があるのかは分かりませんが。
まぁでも後半に差しかかると、なじんで違和感はなくなりました。
もともと悪い曲というわけではないので。特にエンディングの曲は結構好きですね。
「底の知れない大穴」というのは、ユング心理学的に言うと、人間の「自己」において、「無意識」の部分をあらわしていると言えると思います。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
大穴の底に向けて旅をしていく、ということは、「無意識」の中の光の当たらない、自分の中のおぞましい部分にも対峙せざるを得ない、ということで、「メイド・イン・アビス」が鬱展開になるのも、必然だったのかも知れないと思います。
(が、個人的には「無意識」の中にも、美しいものは存在しているのではないかと思いますし、また、おぞましいものが自分の中に存在しているとしても、それはあくまでも自分の「一部」なので、あまりそればかりに目を向けてしまうとかえって取り込まれてしまうこともあるのではないかと思います。)
この後のブログの後半はネタバレ有りで、もう少しユング心理学的なことを書いてみたいと思います。
一気に書こうかとも思いましたが、後半は改めて次回にしようと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました!