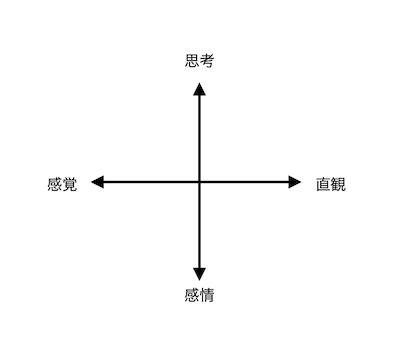今回は
前回のブログの続きとなります。
結局あの後、おさらいの意味で総集編は見てみて、続編劇場版ももう一度見てみました。
今回は、感想に交えて、ユング心理学的な解釈を手前ミソな感じで書いていきたいと思っております。
私はユング心理学を正式に学んでいるわけではなく、趣味として好き勝手書いていきますので、一個人の解釈ということでご理解ください。
そして今回は「メイド・イン・アビス」のTVアニメ版第1期(劇場版総集編・前編「旅立ちの夜明け」後編「放浪する黄昏」)、劇場版「深き魂の黎明」のネタバレを含みますので、まだ見ていないのでネタバレは嫌だという方は、ここでこのブログを閉じていただけますようにお願いいたします。
またネタバレ気にしないという方にも、詳細なストーリー説明は省いていくつもりですので、ご了承をお願いいたします。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
①大穴の意味
前回のブログの最後の方で少し触れましたが、「底知れぬ大穴」というのは、人間の「無意識」をあらわしていると考えられます。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
ユング心理学の考え方は、「自己」の中において「意識」は海面に浮かぶ氷山の一角のようなもので、もっと大きな「無意識」が存在していると考えています。
そしてその「無意識」はさらに「個人的無意識」と「普遍的無意識」に分けられる、という考えです。

(河合隼雄「ユング心理学入門」岩波書店 を参考に作成)
「個人的無意識」については後で取り上げたいと思うので一旦置いておいて、「普遍的無意識」について考えてみたいと思います。
「普遍的無意識」とは、人類は無意識のある部分を共有しているのではないか、という考えです。
世界の昔話にどこか似たようなものが多く存在していること、「虫の知らせ」という現象を体験する人もいることなどから、ユングはそのような考えに至ったようです。
それに対してリコも、いざ大穴に向けて旅立とうと孤児院の仲間に別れを告げる時に、「もしかしたら2度と会えないかも知れないけど、私たちはアビスでつながっている」という発言をしていて、興味深いなぁと思いました。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
(まぁ私個人としては、「普遍的無意識」を完全に信じているわけではなくて、まぁ本当にそうだったら楽しそうだよなぁ、くらいな感じです。)
また不動卿オーゼンも、アビスから地上に戻ってくる時の上昇負荷、すなわち「呪い」について、「心がやられると体にも出てくる」と述べていて、アビスと心に深いつながりがあることがうかがえます。
時折現実の人間も、人間の闇の部分に触れてしまうと心が壊れてしまい、現代の医療技術では元に戻らないことも残念ながらありますが、それと似たものを感じます。
②息を吹き返すアニマ
最初見た時は、オーゼンのシーンでは特に思うところがなく、更なる鬱展開への助走なのかな、みたいな感想しかありませんでした。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
ですが、2回目に総集編で見たところ、不動卿オーゼンと黎明卿ボンドルドはもしかしたら”対”として描かれているのかなぁ、という感じがしました。
不動卿オーゼンのところで、リコは死産だった、という事実が発覚します。
河合先生の「ユング心理学入門」のアニマの章のところで、アニマは夢の中で少女の形を取ることが多く、死にかけの少女が息を吹き返してホッとしたという夢を見た男性の話が出てきたのをふと思い出しました。
オーゼンはリコの母ライザの師匠だったわけですが、ライザがある日、結婚相手を連れてきたときに、めっちゃショックを受けています。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
恋愛感情、というよりは、娘を嫁にやる父親の喪失感に近いんじゃないのかな、と個人的には思っています。
もしくは両方入り混じってるのか分かりませんが。まぁオーゼンの性別は女性のように見えますけどね。
リコが死産で取り出されたということは、オーゼンの中でのアニマ(優しさ、柔らかさ)喪失の危機があったことをあらわしているのではないかと思います。
しかし、「呪いよけのかご」に入れられたリコは息を吹き返します。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
地上に戻るまでに何度も捨てそうになった、とのことですが、オーゼンは地上まで運び上げます。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
結果オーゼンは、リコすなわち自分のアニマを守り切った、と想像することができます。
もし、途中で捨ててしまっていたとしたら、おそらくライザとも絶交となってしまっていたでしょうし、そうなればもしかするとオーゼンも黎明卿のように、血も涙もない感じになってしまっていたかも知れません。
しかし、めっさ怖いおばさんではあるものの、チラッと見え隠れする優しさが、オーゼンの魅力になっていると思います。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
オーゼンは自分の仲間の探窟隊「地臥せり」のことを「地上に帰る場所のないろくでなしども」と呼んでいますが、同じく「筋金入りのろくでなし」と呼んでいる黎明卿やアンブラハンズと比べると、かなり地臥せりさんたちは人間らしさが残っているので、彼らを通してオーゼンの人間性も透けて見えるような気がします。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
話が逸れますが、わりと騒がしいキャラの多い印象の豊崎愛生さんがマルルク役ではいつもと違う雰囲気だったので、へぇ豊崎さん、こういう声も出るんですか、すご!って思いました(笑)
③成れ果て
第4層までたどり着いたリコとレグは、タマウガチに襲われ、リコは瀕死の重傷を負ってしまいます。
そこでナナチに助けられ、アジトでミーティと遭遇します。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
ナナチは自分のこともミーティのことも「成れ果て」と言っていますが、ミーティは人間性が失われてしまっています。
第6層から第5層への上昇負荷で人間は人間性を失ってしまう、ということですが、ナナチとミーティは黎明卿の実験体として使用されたために、そのような姿になってしまったことが後々わかります。
第6層には多くの「成れ果て」の子供たちが残されているようです。
この「成れ果て」とは何なのだろうなぁと思っていたところ、河合先生の個人的無意識について説明したところに、面白いことが書いてありました。
「個人的無意識 これは第一に、意識内容が強度を失って忘れられたか、あるいは意識がそれを回避した(抑圧した)内容、および、第二に意識に達するほどの強さをもっていないが、何らかの方法で心のうちに残された感覚的な痕跡の内容から成り立っている。」
(河合隼雄 「ユング心理学入門」 岩波書店)
これって…「成れ果て」そのものじゃないですか…?
少し噛み砕いて、例えば私自身のことで言い換えてみますか。
私は、普段は忘れている子どもの頃の記憶がふとした時によみがえることが時折あります。
そんな時は、何であんなことしてしまったのだろう、と、恥ずかしさや後悔などから、叫び声を上げたくなったりします。
が、そんな記憶でも今の私を作ってきた一部ではあります。

叫び声を上げたくなるほどグロいけど、よく見るとかわいらしく見えなくもない「成れ果て」と似ているところがあるなぁと思いました。
もしかしたら私の無意識の中には、そうした記憶の痕跡が、無数にうごめいているかもしれない、と考えると、ちょっとゾッとしますが、まぁそんなものかもしれないとも思います。
④ニュートンの法則と異世界への案内役
ナナチは、レグに火葬砲でミーティを葬ってもらうことに決めます。
そしてそれと入れ替わるように、リコは目を覚まします。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
この、何かを得るためには何かを代償にしなければならない、というのは昔話などでよく見られるようで、河合先生も時折言及することがあります。
例えば、厳密には昔話ではありませんが「泣いた赤鬼」で、赤鬼が人間の友達を得た代償として、青鬼は去らなければならなかった、というような感じです。

物理法則と通じるものもあり、興味深いところです。

© Warner Bros. Entertainment Inc.
そしてナナチは、リコとレグの旅についていくことに決めます。
人間も、先に進むためには時折、子供の時の大事なものを、心を裂かれるような思いで決別しなければならない時がある、ということでしょうか。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
また、ナナチは第5層の黎明卿の実験場にいたのでこの先のことにも詳しく、案内役ともなります。
河合先生によると、「言葉を話す動物」というのは、無意識世界への橋渡しとして昔話などに登場することがあるようです。
これも昔話ではありませんが、「不思議の国のアリス」に出てくる白ウサギなどは分かりやすい感じですね。

ナナチは動物というよりは、動物の姿になってしまった人間ですが、ウサギっぽいところなどはその辺りのモチーフから来ていることもあるのかもしれません。

©︎つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
⑤愛情と探究心
最初見ていた時は、黎明卿ボンドルドは、なんてひどいやつなんだ!と思っていましたが、2回目見てみると、それほどでもなくなってきました。
もちろん、彼のしでかしたことを肯定するつもりはありませんが…

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
彼の目的は「第6層の上昇負荷による”呪い”をなんとかしたい」というもので、私利私欲のためではない、というか、自分が金持ちになりたい!とか、名声を得たい!とか、性欲を満たしたい!とか、そういうわけではなさそうです。
確かにアンブラハンズはレグの腕をもいじゃったりしてひどいんですが、割とリコも最初レグに酷いことしてました(笑)
リコも技術と機材があったらもしや…と思ってしまいます。
ボンドルドもリコに「君は私が思っているよりずっとこちら側なのかも知れませんね」と言っています(笑)

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
ボンドルドに感情がないかというと決してそんなことはなく、むしろ彼は愛情にあふれた人間であるようです。
実際、”娘”のプルシュカは、普通に”良い子”に育っています。
別に取り繕っているようなようでもなく、リコたちに陰湿な嫌がらせをするわけでもありません。

©︎つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
惨烈な実験が行われている場所で、見せないように気をつけてはいるだろうとはいえ、まっすぐな子に育てたボンドルドは、結構すごいと思うのです。
私に子育ての経験はないので、あまり分かったようなことは言えないのですが。
また彼は、実験に使用した「成れ果て」の子ども達も全て誰が誰だか見分けがついていて、名前も覚えているようです。

©︎つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
(まぁ普通の人が目を背けたくなるようなものを、全て完璧に覚えている、というのも、ちょっと異常な気はしますが…)
ただ、ボンドルドの何が異常かというと、そのように愛情を持ち合わせた人間でありながら、自身の行動の決定に、感情がいっさい介入しない、ということだと思います。
それは、自分の身体に対する愛情に関しても同じで、彼は白笛を得るために自分の身体を犠牲にしたようです。
ユング心理学では「タイプ論」いうのがあって、人の心理的行動基準を、思考型、感覚型、直観型、感情型の4つのタイプに分けるものがあります。
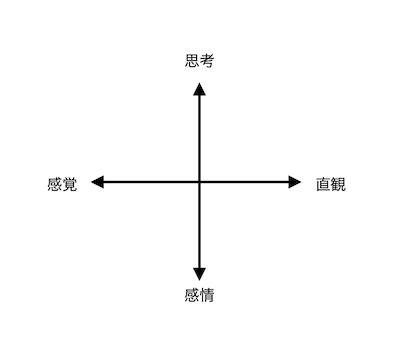
(河合隼雄「ユング心理学入門」岩波書店 を参考に作成)
あまり詳しい説明を今回は省きますが、簡単に私なりの考えも交えて説明すると、
①思考型:理論・ルールを重視する人
②感覚型:自分の感覚情報や、計測データなどを重視する人。例えば、私は自分が見たものしか信じない、とか。
③直観型:ひらめきを重視する人。もしくはロマンチスト。
④感情型:感情を重視する人。例えば、可哀想だから許してあげよう、とか。
どの型が重要視されるか、ということで100%この型だという人はいないと思います。
また、どの型が良い悪いというのではなく、4つともバランスが取れているのが最善と言えると思いますが、ボンドルドの場合は、④の感情型がすっぽり抜け落ちてるような感じがします。
「第6層の呪いを解決しよう!」というロマン、そして数多くの実験を経て、ナナチとミーティの例から呪いを「祝福」に変える方法の糸口をつかみ、それを自分とプルシュカで実践してみた、という感じなのでしょうか。
ただそこに、可哀想だからこの実験はやめておこう、とかの感情による判断が存在していない、というところに異常性を感じます。
激しい戦いののち、ボンドルドは倒されてしまいます。
(最初はやったぜ!と思っていたのですが、2回目の視聴では、長年の実験の結果ようやく「祝福」を獲得した黎明卿の体を破壊されてしまったので、申し訳ないけど、ちょっともったいない…と思ってしまいました。)
これは「バルス」展開来るか!!と思ったものの、リコは黎明卿の生き残りを見逃します。
「探究心」というのも人間にはもちろん重要で、それを完全に滅ぼすことはできない、ということなのでしょうか。
こうしてリコはプルシュカにより白笛を手に入れるわけですが、「呪い」を「祝福」に変えるカギというのが、極限状態で他人を思いやる心、というのがなんとも泣けました。

©︎つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
⑥第2期への期待
来年2022年には第2期「烈日の黄金郷」が放映されるとのことです。
PV第一弾が公開されているようですが、これ以上ブログが長くならないように、ブログをアップしてから見ようと思います(笑)
最後にまとめますが、リコの当初の目的は、アビスの底で待つという母親を探す、というものですから、ユング心理学的に言えば「普遍的無意識」の底にあるグレートマザー(人類共通の”母”のイメージ)を探究する、というのが物語の目的、と言えそうです。
奈落の底で見出すのは、聖女か魔女か。

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会
とは言いながらも、アビスの底に向かう旅を描く、ということは、作り手さんたちが自分自身の無意識部分と向き合う、ということとも言えると思うので、相当キツい作業にはなるのではないかと思います。
と思っていたら、原作者さんは体調があまりよろしくないようで…
もし私なら「オレたちの冒険はこれからだ!」でとっくに投げ出してると思うので、余計なお世話ですがご自愛いただきたいものです…
〜〜〜
というわけで、長いブログを最後まで読んでくださりありがとうございました。
感想後編も二つに分けようかとも思いましたが、分けるとまた書こうという気にならない恐れがあったので、一気に書いてしまいました。
わりとひらめき重視でダーっと書いてしまったので、おかしなところがあったら、後日こっそり修正しているかもしれません(笑)
次回は、「マトリックス レザレクションズ」がもうじき公開ということで、マトリックス3部作について最近妄想していることなどを書こうかなと思っています。
重ねて、読んでくださりありがとうございました!