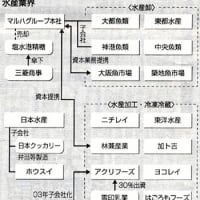「朝日記者による田中康夫氏コメント情報捏造事件」については、すでに「JANJAN」でも、「マスコミ料理教室(10) ホントにあきれた『朝日』の捏造事件」、「朝日はいくつ委員会をつくるつもりか~社会の公器として落伍メディアだ」といった記事が掲載されているので、詳細は省略する。
この事件を受け、朝日新聞自身が8月31日、「虚偽報道 朝日新聞が問われている」と題した社説を掲載した。そこでは今回の事件のみならず、「サンゴ事件」「中国新聞の記事を盗用事件」「武富士からの5千万円の資金提供」「NHK幹部らを取材した社内資料の流出問題」などにも言及し、「こうしたことにきちんと目を向けて、病弊を根本から取り除く。日々の取材や紙面づくりで地道に努力する。それしか読者の信頼を取り戻す道はない。あらためて、そう誓いたい」と決意を語った。
ただ、そこで朝日自身が示した、これらの問題の原因についての言及は、「こうも続いて起こると、何か構造的な問題があるのではないかと感じざるをえない。このくらいならという気のゆるみやおごり。社内外での競争がもたらす重圧や焦り。朝日新聞という伝統と看板がかえって組織の病を生んではいないか」という認識だった。この表現では、朝日自身も「構造的な問題」が「何か」が、分かりかねている、と読み取れる。
ただ、朝日のこの問題に対する他の新聞各社の反応は早かった。最初にこの問題を社説で取り上げたのは、同じ日の毎日新聞である。
毎日新聞は社説「情報ねつ造 官僚的な対応は朝日の体質か」で、「残念ながら、誤報は時として起きる。しかし、誤報は意図してするものではない。ねつ造は意図してウソを作り上げるものだ。報道機関が決して犯してはならない犯罪的行為である」と今回の事件を「虚報問題」ではなく「情報ねつ造」と表現、「疑問は何ら解消されていない。朝日新聞が説明しないからである」「朝日新聞は先に記事資料流出を認めた時も、関係者に謝罪文書を送付したと発表するだけで会見していない」と、朝日の姿勢を「官僚的」という言葉で批判した。
「毎日新聞は、絶えず朝日を『目の敵』のように批判し、それを売り物にするかのような一部メディアと一線を画してきた。そして、毎日新聞がいつも正しいというつもりも毛頭ない。ただ、メディアは、もう少し謙虚になって誠実で丁寧な説明を心がけたい」という言葉が重く響く。
翌日9月1日には、読売新聞、産経新聞、中日新聞も一斉にこの問題を社説で取り上げた。ところが、それらが、一方的に朝日を糾弾するのとは、異なる論調だったのが意外だった。
読売新聞は、社説「情報捏造 新聞の報道倫理が問われている」(9月1日付)で、「今回の問題の持つ意味の深刻さを考えると、朝日新聞だけの不祥事として済ませることは、できない」「新聞に対する読者の信頼を失わないためには、事実に基づく正確な報道こそが“命”である。読売新聞もそのことを、改めて肝に銘じたい」と「自戒」を強調した。
中日新聞の社説「虚偽報道 他山の石と自戒したい」(9月1日付)は、「朝日新聞で明るみに出た不祥事は、報道に対する国民の信頼を根底から揺るがす。わがことと受け止め自戒する」「朝日新聞はトカゲのしっぽ切りのような記者解雇で終わらせず、関係者の言動や心理を詳しく調査して率直に公表すべきだ。メディアの信頼回復のため、そこから得た教訓を国民と報道関係者が共有したい」と述べた。
あの朝日に厳しい産経新聞も「ねつ造」とは言わず、「虚報」という表現にとどめ、「主張:朝日の虚偽報道 構造的体質なのかメスを」(9月1日付)では、「同じような虚報は欧米でも起きている。1980年、米国で反響を呼んだワシントン・ポスト紙の『ジミーの世界』というルポルタージュは、架空の少年の物語だった。2003年、イラク戦争に従軍して行方不明になった息子の消息を待つ母親のインタビュー記事がニューヨーク・タイムズ紙に載ったが、書いた記者は母親に会っていなかった」とわざわざ、アメリカの例まで紹介し、「他の報道機関にとっても、今回の朝日の虚報は他山の石である。朝日は、特別チームを社内に立ち上げ、社を挙げて取材・報道の心構えや記者倫理のあり方を抜本的に見直すとしている。今度こそ、実のある再点検を求めたい」と、表現は意外なほど穏やかである。
それを受けた朝日新聞は、異例の2回目の社説を9月2日に掲載した。それは、記者と報道「事実の重みをかみしめて」というもので、その中で朝日は、「事情を知っている人々に何度も足を運び、早朝から深夜まで取材をする。そうした取材の中で、今回のように、1つでも架空の情報が混じり、それをチェックできなければ、事実は遠ざかる」「記者1人ひとりが事実の持つ重みを自覚して、事実を伝えるという記者の原点に戻らねばならないと思う」と改めて、今回の事件の原因として、今の朝日に欠けていたと思われる、報道における「事実の重み」について言及した。
ただ、そこで問題となるのが、毎日新聞が最初に問題にした、「疑問は何ら解消されていない。朝日新聞が説明しないからである」「朝日新聞は先に記事資料流出を認めた時も、関係者に謝罪文書を送付したと発表するだけで会見していない」という視点である。
報道における「事実の重み」を認識するならば、そこで問われるのは「事実」を明らかにしようとする姿勢である。「事実の重み」を本当に認識したのなら、NHK番組改変問題においても、明らかにすべき「事実」、国民の知る権利に答えていない「事実」が数多く残っている。それを行動で示してこそ、失った朝日新聞への信頼回復の一歩だろう。
翻って、この「JANJAN」を眺めてみよう。例え、権力者をチェックするためであろうと、平和主義といった正義を貫徹するためであろうと、「事実」を捻じ曲げないということが、報道の大原則だ。
先に、「黙とう:甲子園で広島代表校が提案、高野連が制止」(05年8月6日付『毎日新聞』)という誤報により、誤った高野連批判が紙面に掲載された。それについて、編集部は記事の下段に訂正記事の存在は告知してあるが、その記事に基づく高野連に対する批判記事は放置したままだった。
もし、「JANJAN」が報道機関を自認するなら、「事実」に基づかない記事をそのままタレ流す姿勢はいかがなものだろう。僕はひと言、編集部としても、「高野連」への謝罪文書を掲載すべきではなかったかと考える。
いずれにしろ、今回の「虚報事件」を、朝日への糾弾だけではなく、「JANJAN」においても、「事実の重み」を心に刻む契機にしたいと考える。
JANJAN 2005年9月5日
Link
この事件を受け、朝日新聞自身が8月31日、「虚偽報道 朝日新聞が問われている」と題した社説を掲載した。そこでは今回の事件のみならず、「サンゴ事件」「中国新聞の記事を盗用事件」「武富士からの5千万円の資金提供」「NHK幹部らを取材した社内資料の流出問題」などにも言及し、「こうしたことにきちんと目を向けて、病弊を根本から取り除く。日々の取材や紙面づくりで地道に努力する。それしか読者の信頼を取り戻す道はない。あらためて、そう誓いたい」と決意を語った。
ただ、そこで朝日自身が示した、これらの問題の原因についての言及は、「こうも続いて起こると、何か構造的な問題があるのではないかと感じざるをえない。このくらいならという気のゆるみやおごり。社内外での競争がもたらす重圧や焦り。朝日新聞という伝統と看板がかえって組織の病を生んではいないか」という認識だった。この表現では、朝日自身も「構造的な問題」が「何か」が、分かりかねている、と読み取れる。
ただ、朝日のこの問題に対する他の新聞各社の反応は早かった。最初にこの問題を社説で取り上げたのは、同じ日の毎日新聞である。
毎日新聞は社説「情報ねつ造 官僚的な対応は朝日の体質か」で、「残念ながら、誤報は時として起きる。しかし、誤報は意図してするものではない。ねつ造は意図してウソを作り上げるものだ。報道機関が決して犯してはならない犯罪的行為である」と今回の事件を「虚報問題」ではなく「情報ねつ造」と表現、「疑問は何ら解消されていない。朝日新聞が説明しないからである」「朝日新聞は先に記事資料流出を認めた時も、関係者に謝罪文書を送付したと発表するだけで会見していない」と、朝日の姿勢を「官僚的」という言葉で批判した。
「毎日新聞は、絶えず朝日を『目の敵』のように批判し、それを売り物にするかのような一部メディアと一線を画してきた。そして、毎日新聞がいつも正しいというつもりも毛頭ない。ただ、メディアは、もう少し謙虚になって誠実で丁寧な説明を心がけたい」という言葉が重く響く。
翌日9月1日には、読売新聞、産経新聞、中日新聞も一斉にこの問題を社説で取り上げた。ところが、それらが、一方的に朝日を糾弾するのとは、異なる論調だったのが意外だった。
読売新聞は、社説「情報捏造 新聞の報道倫理が問われている」(9月1日付)で、「今回の問題の持つ意味の深刻さを考えると、朝日新聞だけの不祥事として済ませることは、できない」「新聞に対する読者の信頼を失わないためには、事実に基づく正確な報道こそが“命”である。読売新聞もそのことを、改めて肝に銘じたい」と「自戒」を強調した。
中日新聞の社説「虚偽報道 他山の石と自戒したい」(9月1日付)は、「朝日新聞で明るみに出た不祥事は、報道に対する国民の信頼を根底から揺るがす。わがことと受け止め自戒する」「朝日新聞はトカゲのしっぽ切りのような記者解雇で終わらせず、関係者の言動や心理を詳しく調査して率直に公表すべきだ。メディアの信頼回復のため、そこから得た教訓を国民と報道関係者が共有したい」と述べた。
あの朝日に厳しい産経新聞も「ねつ造」とは言わず、「虚報」という表現にとどめ、「主張:朝日の虚偽報道 構造的体質なのかメスを」(9月1日付)では、「同じような虚報は欧米でも起きている。1980年、米国で反響を呼んだワシントン・ポスト紙の『ジミーの世界』というルポルタージュは、架空の少年の物語だった。2003年、イラク戦争に従軍して行方不明になった息子の消息を待つ母親のインタビュー記事がニューヨーク・タイムズ紙に載ったが、書いた記者は母親に会っていなかった」とわざわざ、アメリカの例まで紹介し、「他の報道機関にとっても、今回の朝日の虚報は他山の石である。朝日は、特別チームを社内に立ち上げ、社を挙げて取材・報道の心構えや記者倫理のあり方を抜本的に見直すとしている。今度こそ、実のある再点検を求めたい」と、表現は意外なほど穏やかである。
それを受けた朝日新聞は、異例の2回目の社説を9月2日に掲載した。それは、記者と報道「事実の重みをかみしめて」というもので、その中で朝日は、「事情を知っている人々に何度も足を運び、早朝から深夜まで取材をする。そうした取材の中で、今回のように、1つでも架空の情報が混じり、それをチェックできなければ、事実は遠ざかる」「記者1人ひとりが事実の持つ重みを自覚して、事実を伝えるという記者の原点に戻らねばならないと思う」と改めて、今回の事件の原因として、今の朝日に欠けていたと思われる、報道における「事実の重み」について言及した。
ただ、そこで問題となるのが、毎日新聞が最初に問題にした、「疑問は何ら解消されていない。朝日新聞が説明しないからである」「朝日新聞は先に記事資料流出を認めた時も、関係者に謝罪文書を送付したと発表するだけで会見していない」という視点である。
報道における「事実の重み」を認識するならば、そこで問われるのは「事実」を明らかにしようとする姿勢である。「事実の重み」を本当に認識したのなら、NHK番組改変問題においても、明らかにすべき「事実」、国民の知る権利に答えていない「事実」が数多く残っている。それを行動で示してこそ、失った朝日新聞への信頼回復の一歩だろう。
翻って、この「JANJAN」を眺めてみよう。例え、権力者をチェックするためであろうと、平和主義といった正義を貫徹するためであろうと、「事実」を捻じ曲げないということが、報道の大原則だ。
先に、「黙とう:甲子園で広島代表校が提案、高野連が制止」(05年8月6日付『毎日新聞』)という誤報により、誤った高野連批判が紙面に掲載された。それについて、編集部は記事の下段に訂正記事の存在は告知してあるが、その記事に基づく高野連に対する批判記事は放置したままだった。
もし、「JANJAN」が報道機関を自認するなら、「事実」に基づかない記事をそのままタレ流す姿勢はいかがなものだろう。僕はひと言、編集部としても、「高野連」への謝罪文書を掲載すべきではなかったかと考える。
いずれにしろ、今回の「虚報事件」を、朝日への糾弾だけではなく、「JANJAN」においても、「事実の重み」を心に刻む契機にしたいと考える。
JANJAN 2005年9月5日
Link