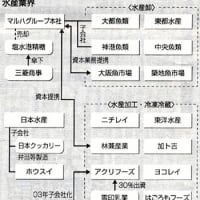100年後に魚の生息域変化
地球温暖化が進むと、百年後には日本近海の魚類の生息域が大きく変わり、九州を中心とする西日本ではアジやタイ、ヒラメなどの漁獲が三-七割近く減るとの調査結果を、独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所(茨城県神栖市)が二十七日、明らかにした。
温暖化が漁業に与える影響を地域や魚種ごとに細かく予測した例は世界的にも初めてという。
漁業対象種の変化は全国に及び、漁業者は新たな対応を迫られそう。食卓になじみの深い魚が変わるなど、食生活への影響も予想される。
調査では、最新の温暖化予測を基に二一〇〇年に日本近海の水温が今より一・四-二・九度高くなると想定。沿岸漁業に特に関係が深い三十四種の魚介類などの生息域の変化や、実際の漁港をモデルにした漁獲量の変化を調べた。
その結果、東シナ海に面した長崎、鹿児島県の漁港では、マアジやマサバ、マダイ、ヒラメ、スルメイカなどの漁獲が三-七割も減少。能登半島周辺の富山、石川県ではマダイやトラフグが、関東沿岸の茨城、千葉県ではマイワシが、北海道の太平洋沿岸でサンマがそれぞれ三割以上減少すると予測された。
一方、三陸沖など本州北部の太平洋でマアジやマダイの漁獲量が増加。関東沿岸や能登半島でもマアジの漁獲が、北海道でカキなどの水揚げが増えるとの結果も出た。
四国や九州では現在の漁獲対象種が軒並み減少するが、新たにフエダイやハタといった亜熱帯種の漁獲が期待できる。
同研究所の桑原久実・環境分析研究室長は「これからは温暖化に伴う漁獲の変化を監視し、状況に応じて漁業戦略を変えていくことが必要になる」と指摘している。
結果は水産庁がまとめた「地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告書」に盛り込まれた。
中日新聞 2005年8月27日
Link
地球温暖化が進むと、百年後には日本近海の魚類の生息域が大きく変わり、九州を中心とする西日本ではアジやタイ、ヒラメなどの漁獲が三-七割近く減るとの調査結果を、独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所(茨城県神栖市)が二十七日、明らかにした。
温暖化が漁業に与える影響を地域や魚種ごとに細かく予測した例は世界的にも初めてという。
漁業対象種の変化は全国に及び、漁業者は新たな対応を迫られそう。食卓になじみの深い魚が変わるなど、食生活への影響も予想される。
調査では、最新の温暖化予測を基に二一〇〇年に日本近海の水温が今より一・四-二・九度高くなると想定。沿岸漁業に特に関係が深い三十四種の魚介類などの生息域の変化や、実際の漁港をモデルにした漁獲量の変化を調べた。
その結果、東シナ海に面した長崎、鹿児島県の漁港では、マアジやマサバ、マダイ、ヒラメ、スルメイカなどの漁獲が三-七割も減少。能登半島周辺の富山、石川県ではマダイやトラフグが、関東沿岸の茨城、千葉県ではマイワシが、北海道の太平洋沿岸でサンマがそれぞれ三割以上減少すると予測された。
一方、三陸沖など本州北部の太平洋でマアジやマダイの漁獲量が増加。関東沿岸や能登半島でもマアジの漁獲が、北海道でカキなどの水揚げが増えるとの結果も出た。
四国や九州では現在の漁獲対象種が軒並み減少するが、新たにフエダイやハタといった亜熱帯種の漁獲が期待できる。
同研究所の桑原久実・環境分析研究室長は「これからは温暖化に伴う漁獲の変化を監視し、状況に応じて漁業戦略を変えていくことが必要になる」と指摘している。
結果は水産庁がまとめた「地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告書」に盛り込まれた。
中日新聞 2005年8月27日
Link