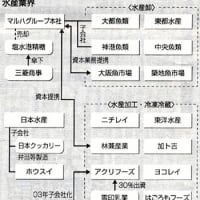信州の味“飛騨ブリ”
飛騨や信州では、正月にブリを食べる風習があるという。「年取り魚」と呼ぶそうだ。
輸送手段がつたない時代。日本海で捕れ、浜塩されたブリは、牛馬で三日かけて高山に運ばれ、さらに峠越えで一週間余かけ、松本や伊那、木曽地方へと届けられた。
この地域の誰もがブリを食べていたのかと思いきや、高山市七日町の民俗学研究家桐谷忠夫さん(73)に「ブリを食べられたのは上流社会の一部の人たち。戦前の飛騨高山の庶民の年取り魚は、『煮イカ』か『イワシの頭付き』だった」とくぎを刺された。
高山市史によると、「旅人逗留(とうりゅう)日限留帳」に、江戸時代末期、一八六六(慶応二)年、信州商人がブリ買い入れのために高山に泊まった記録が残る。旧暦の十二月初旬に来て買い付け、中旬に出発している。
古い町並みに近い同市上二之町に、「町年寄 川上氏宅跡」と記された小さな石柱があった。時の城主金森氏のお墨付きを得て、富山から入ってくる魚のすべてを扱った魚問屋「川上」があった場所だ。この地から先、「越中ブリ」は「飛騨ブリ」と呼び名を変え、信州へと向かった。
大変だったのは、飛騨と信州を隔てる峠越え。旧高根村史によると、同村上ケ洞に荷物問屋があり、松本、伊那、木曽行きと分けられた。積雪一メートルまでは牛で運ばれたが、それ以上雪深くなると、近くの農民による「百姓歩荷(ぼっか)」が荷を運んだ。
野麦集落の人にとって歩荷は、冬場の大切な収入源だった。背負子(しょいこ)に荷を結わえて背負い、四十-五十人が列を成す。「男は三十貫(約百十キロ)、女は十七、八貫(約六十キロ)が普通であった」と同村史は記す。
高山市高根町野麦の下野国蔵さん(86)は「両親とも歩荷をやっとったが、子どものころブリを食べた記憶はない」という。雪の中、命がけで運ばれた飛騨ブリ。「ブリ一本、米一俵」というほど高価な魚だったのだ。
信州の松本平や南信地方には、今もブリにまつわる風習が残る。飛騨ブリに詳しい長野県穂高町柏原の元県立上田高校長細川修さん(65)によると、塩ブリは丸ごと一本買い、大みそかの午後、一家の主人がさばく。切り落とした尾は白木のはしに刺して、神棚の恵比須様に供えるのだ。一年間供え古くなった尾は、暮れのすす払いにお札と一緒に焼くという。
「子ども時分は、大みそかから正月を挟み、小正月のころまでブリざんまい。ゆでたり、焼いたり、雑煮にしたり。骨も皮も食べたものです」。
夫婦二人暮らしの細川さん方では、今は切り身で買うため、尾だけ知り合いの魚屋に分けてもらい、飾っている。なるほど。Y字型の幅十五センチ、長さ二十センチもの立派な尾が神棚に鎮座していた。
「成人の日のころに食べた、発酵が進んだピリッと舌を刺す味が懐かしい」と細川さん。木曽生まれの島崎藤村も著書「をさなものがたり」の中で、「お年取りの膳(ぜん)についた塩ブリの味などは忘れられない」と書いている。
そうと聞くと、なおさら食べてみたい。天然塩ブリよ。年末、お目にかかろう。
■ブリ(鰤) アジ科の魚で、全長1メートル以上になる。日本各地の沿岸や朝鮮半島東岸などを回遊。成長するにつれ呼び名が変わり「出世魚」と呼ばれる。地域ごとに呼び名が異なり、関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ。関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリ。11-12月に日本海側で捕れる「寒ブリ」は、脂が乗って肉も厚く味がよいとされる。
中日新聞2005年6月27日
Link
飛騨や信州では、正月にブリを食べる風習があるという。「年取り魚」と呼ぶそうだ。
輸送手段がつたない時代。日本海で捕れ、浜塩されたブリは、牛馬で三日かけて高山に運ばれ、さらに峠越えで一週間余かけ、松本や伊那、木曽地方へと届けられた。
この地域の誰もがブリを食べていたのかと思いきや、高山市七日町の民俗学研究家桐谷忠夫さん(73)に「ブリを食べられたのは上流社会の一部の人たち。戦前の飛騨高山の庶民の年取り魚は、『煮イカ』か『イワシの頭付き』だった」とくぎを刺された。
高山市史によると、「旅人逗留(とうりゅう)日限留帳」に、江戸時代末期、一八六六(慶応二)年、信州商人がブリ買い入れのために高山に泊まった記録が残る。旧暦の十二月初旬に来て買い付け、中旬に出発している。
古い町並みに近い同市上二之町に、「町年寄 川上氏宅跡」と記された小さな石柱があった。時の城主金森氏のお墨付きを得て、富山から入ってくる魚のすべてを扱った魚問屋「川上」があった場所だ。この地から先、「越中ブリ」は「飛騨ブリ」と呼び名を変え、信州へと向かった。
大変だったのは、飛騨と信州を隔てる峠越え。旧高根村史によると、同村上ケ洞に荷物問屋があり、松本、伊那、木曽行きと分けられた。積雪一メートルまでは牛で運ばれたが、それ以上雪深くなると、近くの農民による「百姓歩荷(ぼっか)」が荷を運んだ。
野麦集落の人にとって歩荷は、冬場の大切な収入源だった。背負子(しょいこ)に荷を結わえて背負い、四十-五十人が列を成す。「男は三十貫(約百十キロ)、女は十七、八貫(約六十キロ)が普通であった」と同村史は記す。
高山市高根町野麦の下野国蔵さん(86)は「両親とも歩荷をやっとったが、子どものころブリを食べた記憶はない」という。雪の中、命がけで運ばれた飛騨ブリ。「ブリ一本、米一俵」というほど高価な魚だったのだ。
信州の松本平や南信地方には、今もブリにまつわる風習が残る。飛騨ブリに詳しい長野県穂高町柏原の元県立上田高校長細川修さん(65)によると、塩ブリは丸ごと一本買い、大みそかの午後、一家の主人がさばく。切り落とした尾は白木のはしに刺して、神棚の恵比須様に供えるのだ。一年間供え古くなった尾は、暮れのすす払いにお札と一緒に焼くという。
「子ども時分は、大みそかから正月を挟み、小正月のころまでブリざんまい。ゆでたり、焼いたり、雑煮にしたり。骨も皮も食べたものです」。
夫婦二人暮らしの細川さん方では、今は切り身で買うため、尾だけ知り合いの魚屋に分けてもらい、飾っている。なるほど。Y字型の幅十五センチ、長さ二十センチもの立派な尾が神棚に鎮座していた。
「成人の日のころに食べた、発酵が進んだピリッと舌を刺す味が懐かしい」と細川さん。木曽生まれの島崎藤村も著書「をさなものがたり」の中で、「お年取りの膳(ぜん)についた塩ブリの味などは忘れられない」と書いている。
そうと聞くと、なおさら食べてみたい。天然塩ブリよ。年末、お目にかかろう。
■ブリ(鰤) アジ科の魚で、全長1メートル以上になる。日本各地の沿岸や朝鮮半島東岸などを回遊。成長するにつれ呼び名が変わり「出世魚」と呼ばれる。地域ごとに呼び名が異なり、関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ。関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリ。11-12月に日本海側で捕れる「寒ブリ」は、脂が乗って肉も厚く味がよいとされる。
中日新聞2005年6月27日
Link