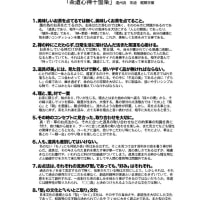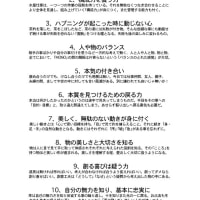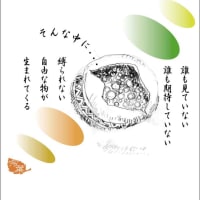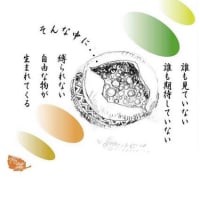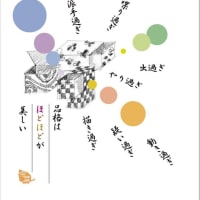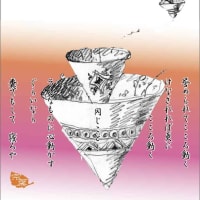●はじめに
興奮や、感動を与える席というのは「なぜ」そうなるのでしょう。亭主の取り合わせの妙もありますが、一方にはそれを受け取る側、即ち「客」の素養によって受け取る感動も違います。
しっかりとした茶への知識、それらを取り巻く要素への関心と造詣の深さがより一層茶の湯を楽しくするものとなります。
茶の湯を「取り巻く要素」の最大で最も関心の深いものは「茶道具」でしょう。まさに「茶道具」が分からなければ本当に茶の湯を楽しむことは出来ません。茶道具は茶の湯の芸術性の一翼を担うものの一つで、美術品としては鑑賞するだけではなく実際に口にしたりして「使用する器」であることは世界的に見ても特異な存在ではないでしょうか。
茶会の取り合わせはまず「茶事」を基本と考えることを第一とします。「茶事」は「茶の湯文化」を捉えるにあたり最も基準となるもので、ここへ立ち返ることにより取り合わせばかりでなく多くの茶の湯に関する疑問が容易に解決できる基となると信じております。
最近では茶の湯の取り合わせを趣向(テーマ)を中心に身近で楽しく一見分かりやすいようにしています。こういったものの多くは趣向を現すことに終始している感があり、趣向のためのみに取り合わせたような無理な取り合わせになっているものもありがちです。
趣向を中心に組み立てると茶道具の品性、歴史性、格式などは無視される場合も少なくありません。また「見立て」を多く用いることによってますますその傾向が助長され品の無い取り合わせがこの頃多く見られるような感もあります。
また、大寄せの茶会が主流になっている現代では薄茶のみの席での取り合わせを多く語られているが故に、なんでも一気に詰め込んでしまっている傾向もあるように思われます。
勿論「茶道具」には歴史的背景による格式や品格があります。いわゆる「名物」や「伝世、伝来の茶道具」を説明する方向で記された、茶道具の解説書の多くは美術館、博物館に所蔵されているような茶道具などの解説を中心にしていますので、一般には手に入り難い茶道具の説明に終始しています。長い歴史の中で培われた茶道具の世界で重要な価値基準となり、取り合わせを考えるときには欠かせない「教養」の根幹をなす物なのですが、あまりに一般の茶道愛好家には手の届かない高価な世界であったり、すでに美術館、博物館に入ってしまっていて実際に手に取り「茶事」「茶会」で使用できる物ではありません。
茶会や茶事などを催す際にも道具の取り合わせというのは、最も重要に捉えられますが、実際に手に入る範疇で、この双方の要素、すなわち、茶道具の格式に基づき、どのように道具を求め、どのように取り合わせたらよいのか、単にお茶道具といっても多岐にわたりますので、一口では解説がつかないのですが、身近なところから基本となり、格式、品格に因った茶事、茶会の取り合わせのポイントを茶道具の種類に分けてまずはお話いたしましょう。
点前においても重要な要素の中に茶道具は関わってきます。たとえば、皆さんは良くご存知と思いますが「点前の真、行、草」があるように「道具の真、行、草」の手分けがあります。個々の点前に相応しい「道具の真行草」の手分けもあれば「扱いとしての真行草」もあります。
またその「真行草」の中にも「真行草」があったりもします。また、茶道具がどのような背景から使われだしたのかによっても「真行草」が決まる場合もあります。
「(茶道具自体の)時代が深い(古い)浅い(新しい)」や「(茶道具の格式が)重い(高い)軽い(低い)」なども加味した表現と考えていただきたいと思います。また茶道具の持ち合わせた「品性」も重要なのですが、これは多くの「本物」と向き合わないとなかなか見いだせません。
格式の高い点前に使われる茶道具は「重い」道具といえますし格式の高い点前は「古い点前」と考えられるので「深い」道具が使われることが妥当でしょう。実際に格式の高い点前というのは、道具も大変貴重かつ古い道具が使われ、軽い点前のものは近世、あるいは現代の茶道具使い「(時代が)浅い」もので「軽い」道具組での取り合わせでも大いに楽しめます。いずれにしても「釣合」が大事ではないでしょうか。
具体的にこのような取り合わせが相応しいのかを道具の種類(格式、時代、手法、作家、繋がり、釣合等)が如何に関わるのかを加味しながら解き明かせたらと考えておりますし、また「趣向」とはどのような物なのかを、決してテーマや物語を語ることだけが趣向ではない考えております。
興奮や、感動を与える席というのは「なぜ」そうなるのでしょう。亭主の取り合わせの妙もありますが、一方にはそれを受け取る側、即ち「客」の素養によって受け取る感動も違います。
しっかりとした茶への知識、それらを取り巻く要素への関心と造詣の深さがより一層茶の湯を楽しくするものとなります。
茶の湯を「取り巻く要素」の最大で最も関心の深いものは「茶道具」でしょう。まさに「茶道具」が分からなければ本当に茶の湯を楽しむことは出来ません。茶道具は茶の湯の芸術性の一翼を担うものの一つで、美術品としては鑑賞するだけではなく実際に口にしたりして「使用する器」であることは世界的に見ても特異な存在ではないでしょうか。
茶会の取り合わせはまず「茶事」を基本と考えることを第一とします。「茶事」は「茶の湯文化」を捉えるにあたり最も基準となるもので、ここへ立ち返ることにより取り合わせばかりでなく多くの茶の湯に関する疑問が容易に解決できる基となると信じております。
最近では茶の湯の取り合わせを趣向(テーマ)を中心に身近で楽しく一見分かりやすいようにしています。こういったものの多くは趣向を現すことに終始している感があり、趣向のためのみに取り合わせたような無理な取り合わせになっているものもありがちです。
趣向を中心に組み立てると茶道具の品性、歴史性、格式などは無視される場合も少なくありません。また「見立て」を多く用いることによってますますその傾向が助長され品の無い取り合わせがこの頃多く見られるような感もあります。
また、大寄せの茶会が主流になっている現代では薄茶のみの席での取り合わせを多く語られているが故に、なんでも一気に詰め込んでしまっている傾向もあるように思われます。
勿論「茶道具」には歴史的背景による格式や品格があります。いわゆる「名物」や「伝世、伝来の茶道具」を説明する方向で記された、茶道具の解説書の多くは美術館、博物館に所蔵されているような茶道具などの解説を中心にしていますので、一般には手に入り難い茶道具の説明に終始しています。長い歴史の中で培われた茶道具の世界で重要な価値基準となり、取り合わせを考えるときには欠かせない「教養」の根幹をなす物なのですが、あまりに一般の茶道愛好家には手の届かない高価な世界であったり、すでに美術館、博物館に入ってしまっていて実際に手に取り「茶事」「茶会」で使用できる物ではありません。
茶会や茶事などを催す際にも道具の取り合わせというのは、最も重要に捉えられますが、実際に手に入る範疇で、この双方の要素、すなわち、茶道具の格式に基づき、どのように道具を求め、どのように取り合わせたらよいのか、単にお茶道具といっても多岐にわたりますので、一口では解説がつかないのですが、身近なところから基本となり、格式、品格に因った茶事、茶会の取り合わせのポイントを茶道具の種類に分けてまずはお話いたしましょう。
点前においても重要な要素の中に茶道具は関わってきます。たとえば、皆さんは良くご存知と思いますが「点前の真、行、草」があるように「道具の真、行、草」の手分けがあります。個々の点前に相応しい「道具の真行草」の手分けもあれば「扱いとしての真行草」もあります。
またその「真行草」の中にも「真行草」があったりもします。また、茶道具がどのような背景から使われだしたのかによっても「真行草」が決まる場合もあります。
「(茶道具自体の)時代が深い(古い)浅い(新しい)」や「(茶道具の格式が)重い(高い)軽い(低い)」なども加味した表現と考えていただきたいと思います。また茶道具の持ち合わせた「品性」も重要なのですが、これは多くの「本物」と向き合わないとなかなか見いだせません。
格式の高い点前に使われる茶道具は「重い」道具といえますし格式の高い点前は「古い点前」と考えられるので「深い」道具が使われることが妥当でしょう。実際に格式の高い点前というのは、道具も大変貴重かつ古い道具が使われ、軽い点前のものは近世、あるいは現代の茶道具使い「(時代が)浅い」もので「軽い」道具組での取り合わせでも大いに楽しめます。いずれにしても「釣合」が大事ではないでしょうか。
具体的にこのような取り合わせが相応しいのかを道具の種類(格式、時代、手法、作家、繋がり、釣合等)が如何に関わるのかを加味しながら解き明かせたらと考えておりますし、また「趣向」とはどのような物なのかを、決してテーマや物語を語ることだけが趣向ではない考えております。