松無古今色(まつにここんのいろなし)
「松無古今色 竹有上下節」春夏秋冬、一年を通じ、また、幾歳月を経
ても、松は常に青々としてその色の変わることはない。百年の風雪に耐え
た松の緑こそは日本の誇りである。現代は緑を保つために現代の科学を動
員しなければならない。不断の工夫と努力で失われゆく緑の世界を守り、
その言葉の裏にひそんだ「竹に上下の節あり」の平等即差別、差別即平等
の対句を忘れてはなるまい。
瀧 直下三千丈(たき ちょっかさんぜんじょう)
水は自ら形無くともどのような形にも順応し、低きについて先を争わず、
時にはすべての生き物のすさまじい力となりて岩石も砕くエネルギーとな
る。全身全霊を叩きつける勇者の姿に筆魂が宿る。「飛流直ちに下る三千
尺、疑うらくは、是れ銀河の九天より落つるかと。」と李白はうたう。
明歴々露堂々(めいれきれきろどうどう)
「山川草木悉皆成仏」大自然、すべては仏法の貴い姿。少しも、うそ、か
くしがなく目の前に堂々と現われている真理を無心に眺めることの大切さ
に気づくことが尊い。
渓声便是広長舌(けいせいすなわちこれこうちょうぜつ)
夜来八万四千の偈・・朝から晩まで絶えることのない如来の無限のご説法
を聞くことが出来るではないか。他日如何が人に挙示せん・・このすばら
しい仏のご説法の感激を誰に、どう伝えようか、言葉でも言い表せない筆
舌しがたいことだ。
“ 野に山に仏の教えはみつるれども仏の教えと聞く人ぞなし”
との歌にも通じよう。実に、谷や川、山や木々は無情であり、何ら人の心
があるわけではない。けれど、その無情の山川草木から偉大なる仏の教え
を見つけ、聞きだし心洗うことが出来る優れた感性、能力を人は頂いてい
るのだ。すべての計らい、捉われから解き放ち、謙虚に大自然に抱かれて
見るとき、自ずから清浄法身仏の雄弁なるご説法にふれることが出来よう。
一行三昧
禅で言う三昧は全身全霊そのことに徹し、なり切りながらも、なんら自性
を失うことなく、日常底においても持続する境地でなければほんものでは
ない。しかも常に純一無雑にして活発自在な働きをもつ三昧である。茶の
湯に於ける利休は、茶の湯の極意として「火をおこし、湯を沸かし、茶を
喫するまでのことなり、他事ある可からず」とのべているごとく、様々な
作法、決りごと多々ある茶の湯の世界で、なおそのことに縛られず、淡々
と三昧になって直心の交わりをもって茶を楽しんだ人である。
百尺竿頭進一歩(無門関)百尺竿灯に一歩を進む
その悟りより、「さらに一歩、歩を進めよ」と言うことは、百尺の竿の先
きから踏み出すほどに不惜身命、命をも投げ出して、衆生救済へ向かって
こそ、悟りの意義があると言う意味。いかに大安心の悟りを得ようとも、
そこに腰をすえておったならば、禅者としての悟りの意味は無くなってし
まう。なぜなら、それは自ら一人の安心、満足であっては、大乗仏教とし
て、多くの人々の救済、済度という禅者の使命を果たすことができないか
らである。
清風萬里秋 (せいふうばんりのあき)
人生の無常を感じつつ、今年も落ち葉を掃く季節が到来した。無心に散っ
た一葉に、自分を燃やし盡くしたものの姿の美しさを感得したい。市中の
息苦しい書窓にも、数竿の長竹は無限の清風を呼ぶ。心の自由を取り戻し
た身心脱落の人にこそ一葉のそよぎに真の清凉の世界を体感する。
独坐大雄峰(どくざだいゆうほう)
「我がくらし楽にならざり、じっと掌を見る」啄木が詠じた歌の中に或る
種の嘆きと未来を真剣に見つめる思いがこめられ、かけがえのない自分の
発見とともに大切に生きようと念ずる人生観を窺い知ることが出来る。今、
ここに「独りの絶対的な自分の存在」を感謝をもって自覚出来ることは
素晴らしい。
遠観山有色(とおくみてやまにいろあり)
「遠観山有色 近聴水無聲」山を離れて遠くから見れば、千紫萬紅の多彩
は消えて青山一色、そこには悟りの鋭さを拭い去った境涯がうかがえる。
山の中にいて山の大きさはわからないが遠く離れて始めて気付く山の大き
さでもある。
白雲抱幽石(はくうんゆうせきをいだく)
深山峡谷に湧く入道雲。さながら眼前に石を抱く夏の妙景は喩えようもな
く悠大である。生けるものの如き夏雲の大自然の閑境に無心でひたるひと
ときにほっとする。
日出乾坤輝(ひいでてけんこんかがやく)
「日出乾坤輝 雲収山岳青」水平線上の初日の出は、旧年の闇を一掃して
大光明は天地にかがやく。新しい世界が生まれた。地上のたたずまいはそ
のままに、無限の光りを浴びて祝福の浄土が出現する。これは大悟の風光
である。心の太陽は、いかなる闇夜、いかなる暗雲の中にも必ず存在する。
人は無知のゆえに、時に迷いと絶望の深底に沈むが、心の太陽の実在を信
ずる者は、やがて豁然と夜明けを見ることができるだろう。
平常心是道(びょうじょうしんこれどう)
日常生活は茶飯事にこだわることなく、伸び伸びと人生を味わい乍ら生き
たいもの。 ところが、その伸び伸びとする心を真に自らのものにするこ
とは至難の行である。道は四六時中、踏まれても怒らないし、踏む人も踏
んでいることを忘れている。平易な言葉の中にもこのように意識が働く教
えの厳しさを味うべきだ。
無事是貴人(ぶじこれきにん)
厳しい修行規格に従い、妙法に修行して転迷開悟の実をあげ、更に悟後の
修行で悟りの臭みをぬき去り、到達した迷悟両忘、酒々楽々の境涯からさ
らに無作無心の高貴な境涯に体達した人物こそ貴人。無造作に自然法爾に
行ずることが「無事」の意味。単に事故の無い安全、有閑徒食と間違えて
はならない。
一華開五葉(いっかごようをひらく)
対句に『結果自然に成る』とは、一つの花に五弁の花びらが開き、やがて
自然に実るように、初祖達磨の教えが末広がりに栄えていくことを予言し
て、二祖に伝えたとされる言葉。
竹有上下節(たけにじょうげのふしあり)
「松無古今色 竹有上下節」人間平等の面だけを主張し、老幼の差別
順序を無視し、貧富、上下の差別のみを認めて人間としての平等を認めな
いのは物事の一面しか見ていない。悪平等の傾向にある社会への警鐘でも
ある。
紅爐一点雪(こうろいってんのゆき)
煩悩妄念を断滅した坐禅三昧の正念のある処、ここにはどんな邪念も寄せ
つけない。迷妄、邪悪は、恰も紅蓮の炎をあげて赤々と燃え盛る炉の上に、
一片の雪花が舞い落ち、一瞬のうちに溶けて跡形もなく消えてしまうかの
ようだ。
松樹千年翠(しょうじゅせんねんのみどり)
春は花、夏は新緑、秋は紅葉と感覚的な美しさに押されて、松の翠が人の
目をひくことは少ないが、寒風吹きすさぶ蕭条の候ともなれば、今まで
目立たなかった松の翠の万古不易の美しさが、改めて見直されることにな
る。うつろいやすい世の中の、うつろうもののみに目を奪われて、常住
不変の真理を見失うようなことがあってはならない。
青山常運歩(せいざんじょううんぽ)
山は動かないものの代名詞だが、仏法の山は山のままで仏法を説き、仏道
を示す。あますところなく私達を包み込むように仏法を説きつつ、我が眼
前にせまって来る清浄身つまり仏様。人間の歩行のようでなくとも常に広
大無辺青山より運歩して来る事なるを疑う事があってはならないと先哲は
説く。
青山元不動(せいざんもとよりふどう)
千変万化の人生の姿に本性不動の喩し。青山は本来、人の持つ仏性に、白
雲は妄想や煩悩によく喩えることがある。雲があってもなくても、青山は
元々不動のものである。どこで何をするにしても、万縁万境に本性をとら
われることなく、自らは変幻極まり無い雲に動じない悠々たる山のように
泰然としていれば、魔性も亦、入り込む隙はなかろう。
春眠不覚暁(しゅんみんあかつきをおぼえず)
童心は道心に通ずとか。人は生まれ乍らに仏心を具備し、教えずとも、
おのずから輝き出る天真爛漫眠りのしぐさがそれを語る。それを妨げるも
のは大人の欲。陽が高く昇ってもなお静かに眠る童子はどんな夢を見てい
るのだろうか。春の眠りは深い。
盛唐の詩人孟浩然(689~740)の「春暁」の一句。
「松無古今色 竹有上下節」春夏秋冬、一年を通じ、また、幾歳月を経
ても、松は常に青々としてその色の変わることはない。百年の風雪に耐え
た松の緑こそは日本の誇りである。現代は緑を保つために現代の科学を動
員しなければならない。不断の工夫と努力で失われゆく緑の世界を守り、
その言葉の裏にひそんだ「竹に上下の節あり」の平等即差別、差別即平等
の対句を忘れてはなるまい。
瀧 直下三千丈(たき ちょっかさんぜんじょう)
水は自ら形無くともどのような形にも順応し、低きについて先を争わず、
時にはすべての生き物のすさまじい力となりて岩石も砕くエネルギーとな
る。全身全霊を叩きつける勇者の姿に筆魂が宿る。「飛流直ちに下る三千
尺、疑うらくは、是れ銀河の九天より落つるかと。」と李白はうたう。
明歴々露堂々(めいれきれきろどうどう)
「山川草木悉皆成仏」大自然、すべては仏法の貴い姿。少しも、うそ、か
くしがなく目の前に堂々と現われている真理を無心に眺めることの大切さ
に気づくことが尊い。
渓声便是広長舌(けいせいすなわちこれこうちょうぜつ)
夜来八万四千の偈・・朝から晩まで絶えることのない如来の無限のご説法
を聞くことが出来るではないか。他日如何が人に挙示せん・・このすばら
しい仏のご説法の感激を誰に、どう伝えようか、言葉でも言い表せない筆
舌しがたいことだ。
“ 野に山に仏の教えはみつるれども仏の教えと聞く人ぞなし”
との歌にも通じよう。実に、谷や川、山や木々は無情であり、何ら人の心
があるわけではない。けれど、その無情の山川草木から偉大なる仏の教え
を見つけ、聞きだし心洗うことが出来る優れた感性、能力を人は頂いてい
るのだ。すべての計らい、捉われから解き放ち、謙虚に大自然に抱かれて
見るとき、自ずから清浄法身仏の雄弁なるご説法にふれることが出来よう。
一行三昧
禅で言う三昧は全身全霊そのことに徹し、なり切りながらも、なんら自性
を失うことなく、日常底においても持続する境地でなければほんものでは
ない。しかも常に純一無雑にして活発自在な働きをもつ三昧である。茶の
湯に於ける利休は、茶の湯の極意として「火をおこし、湯を沸かし、茶を
喫するまでのことなり、他事ある可からず」とのべているごとく、様々な
作法、決りごと多々ある茶の湯の世界で、なおそのことに縛られず、淡々
と三昧になって直心の交わりをもって茶を楽しんだ人である。
百尺竿頭進一歩(無門関)百尺竿灯に一歩を進む
その悟りより、「さらに一歩、歩を進めよ」と言うことは、百尺の竿の先
きから踏み出すほどに不惜身命、命をも投げ出して、衆生救済へ向かって
こそ、悟りの意義があると言う意味。いかに大安心の悟りを得ようとも、
そこに腰をすえておったならば、禅者としての悟りの意味は無くなってし
まう。なぜなら、それは自ら一人の安心、満足であっては、大乗仏教とし
て、多くの人々の救済、済度という禅者の使命を果たすことができないか
らである。
清風萬里秋 (せいふうばんりのあき)
人生の無常を感じつつ、今年も落ち葉を掃く季節が到来した。無心に散っ
た一葉に、自分を燃やし盡くしたものの姿の美しさを感得したい。市中の
息苦しい書窓にも、数竿の長竹は無限の清風を呼ぶ。心の自由を取り戻し
た身心脱落の人にこそ一葉のそよぎに真の清凉の世界を体感する。
独坐大雄峰(どくざだいゆうほう)
「我がくらし楽にならざり、じっと掌を見る」啄木が詠じた歌の中に或る
種の嘆きと未来を真剣に見つめる思いがこめられ、かけがえのない自分の
発見とともに大切に生きようと念ずる人生観を窺い知ることが出来る。今、
ここに「独りの絶対的な自分の存在」を感謝をもって自覚出来ることは
素晴らしい。
遠観山有色(とおくみてやまにいろあり)
「遠観山有色 近聴水無聲」山を離れて遠くから見れば、千紫萬紅の多彩
は消えて青山一色、そこには悟りの鋭さを拭い去った境涯がうかがえる。
山の中にいて山の大きさはわからないが遠く離れて始めて気付く山の大き
さでもある。
白雲抱幽石(はくうんゆうせきをいだく)
深山峡谷に湧く入道雲。さながら眼前に石を抱く夏の妙景は喩えようもな
く悠大である。生けるものの如き夏雲の大自然の閑境に無心でひたるひと
ときにほっとする。
日出乾坤輝(ひいでてけんこんかがやく)
「日出乾坤輝 雲収山岳青」水平線上の初日の出は、旧年の闇を一掃して
大光明は天地にかがやく。新しい世界が生まれた。地上のたたずまいはそ
のままに、無限の光りを浴びて祝福の浄土が出現する。これは大悟の風光
である。心の太陽は、いかなる闇夜、いかなる暗雲の中にも必ず存在する。
人は無知のゆえに、時に迷いと絶望の深底に沈むが、心の太陽の実在を信
ずる者は、やがて豁然と夜明けを見ることができるだろう。
平常心是道(びょうじょうしんこれどう)
日常生活は茶飯事にこだわることなく、伸び伸びと人生を味わい乍ら生き
たいもの。 ところが、その伸び伸びとする心を真に自らのものにするこ
とは至難の行である。道は四六時中、踏まれても怒らないし、踏む人も踏
んでいることを忘れている。平易な言葉の中にもこのように意識が働く教
えの厳しさを味うべきだ。
無事是貴人(ぶじこれきにん)
厳しい修行規格に従い、妙法に修行して転迷開悟の実をあげ、更に悟後の
修行で悟りの臭みをぬき去り、到達した迷悟両忘、酒々楽々の境涯からさ
らに無作無心の高貴な境涯に体達した人物こそ貴人。無造作に自然法爾に
行ずることが「無事」の意味。単に事故の無い安全、有閑徒食と間違えて
はならない。
一華開五葉(いっかごようをひらく)
対句に『結果自然に成る』とは、一つの花に五弁の花びらが開き、やがて
自然に実るように、初祖達磨の教えが末広がりに栄えていくことを予言し
て、二祖に伝えたとされる言葉。
竹有上下節(たけにじょうげのふしあり)
「松無古今色 竹有上下節」人間平等の面だけを主張し、老幼の差別
順序を無視し、貧富、上下の差別のみを認めて人間としての平等を認めな
いのは物事の一面しか見ていない。悪平等の傾向にある社会への警鐘でも
ある。
紅爐一点雪(こうろいってんのゆき)
煩悩妄念を断滅した坐禅三昧の正念のある処、ここにはどんな邪念も寄せ
つけない。迷妄、邪悪は、恰も紅蓮の炎をあげて赤々と燃え盛る炉の上に、
一片の雪花が舞い落ち、一瞬のうちに溶けて跡形もなく消えてしまうかの
ようだ。
松樹千年翠(しょうじゅせんねんのみどり)
春は花、夏は新緑、秋は紅葉と感覚的な美しさに押されて、松の翠が人の
目をひくことは少ないが、寒風吹きすさぶ蕭条の候ともなれば、今まで
目立たなかった松の翠の万古不易の美しさが、改めて見直されることにな
る。うつろいやすい世の中の、うつろうもののみに目を奪われて、常住
不変の真理を見失うようなことがあってはならない。
青山常運歩(せいざんじょううんぽ)
山は動かないものの代名詞だが、仏法の山は山のままで仏法を説き、仏道
を示す。あますところなく私達を包み込むように仏法を説きつつ、我が眼
前にせまって来る清浄身つまり仏様。人間の歩行のようでなくとも常に広
大無辺青山より運歩して来る事なるを疑う事があってはならないと先哲は
説く。
青山元不動(せいざんもとよりふどう)
千変万化の人生の姿に本性不動の喩し。青山は本来、人の持つ仏性に、白
雲は妄想や煩悩によく喩えることがある。雲があってもなくても、青山は
元々不動のものである。どこで何をするにしても、万縁万境に本性をとら
われることなく、自らは変幻極まり無い雲に動じない悠々たる山のように
泰然としていれば、魔性も亦、入り込む隙はなかろう。
春眠不覚暁(しゅんみんあかつきをおぼえず)
童心は道心に通ずとか。人は生まれ乍らに仏心を具備し、教えずとも、
おのずから輝き出る天真爛漫眠りのしぐさがそれを語る。それを妨げるも
のは大人の欲。陽が高く昇ってもなお静かに眠る童子はどんな夢を見てい
るのだろうか。春の眠りは深い。
盛唐の詩人孟浩然(689~740)の「春暁」の一句。













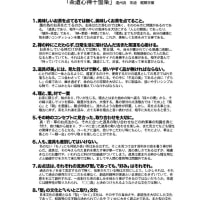
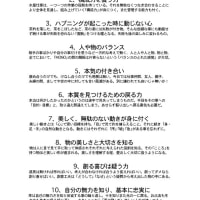
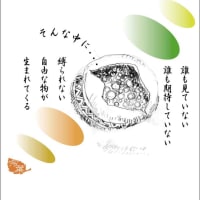

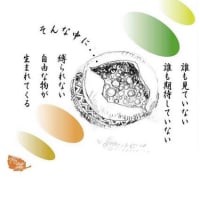
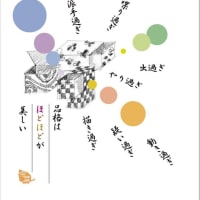
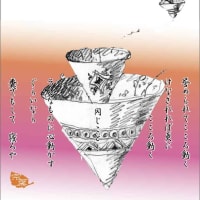
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます