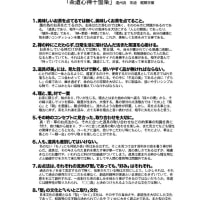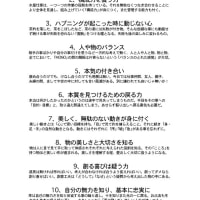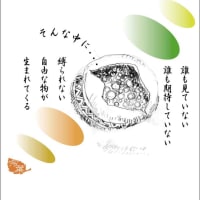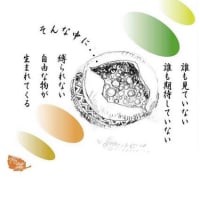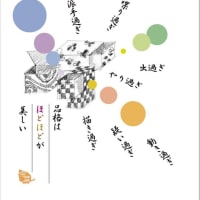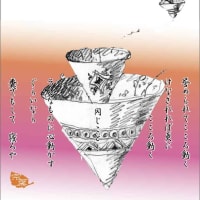体露金風(たいろきんぷう)
体露とは全体の露顕、本体の露出ということで、宇宙大自然の現われであ
り、仏のご慈悲の現われである。金風とは、錦の彩りに染めて豊熟した黄
金の天地を創り出している秋風のこと。自然の風景を眺め、ただ物思いだ
けにふけるのではなく、自己を習わねばならぬ。?
月千古輝(つきせんこにかがやく)
何時の世も変る事なき明日の光が、くまなく燦々と降りそそぐ。悠々たる
秋の夜長の風情は、古来、東洋の詩歌の題材として君臨している。理屈か
ら抜け切り、この幽幻な風光に身心脱落、没入してほしい。
月落碧潭(つきへきたんにおつ)
岸辺の松の枝より天空に悠々と輝く一輪の月の眺めには一点の乱れなく無
限の風趣が溢れている。
淡々と水をたたえ、幽谷に横たわる静かな湖に映える天地万象の脈動にこ
そ無作無心、任運自在の境涯がある。
拈華微笑 (ねんげみしょう)
釈尊は八万の大衆を前にして、無言で一輪の花を示された。大衆沈黙の中
に、ただひとり、迦葉はその意を悟ってにっこりと微笑した。
これで釈尊の後継者は決まった。生きた仏法は、言葉を超え、教義を要せ
ぬ。正に阿吽の呼吸である。これ程単純で真実の道があろうか。ここに到
るにはさまざまの道があり、方法がある。しかし、ここに到れば以心伝心、
無心の心である。
無常迅速(むじょうじんそく)
生死事大、無常迅速。 人の世の移り変りは常にはかなく変転してやまな
い。時は移りゆき、形あるものは必ず滅する。一切が無常であり生滅する
そのことわりを凝視して、ぼやぼやしていたらすぐに死ぬのだから、あた
ら無駄に過ごしてはならない。
流泉為琴(りゅうせんをきんとなす)
岩もあり木の根もあれどさらさらと流れる水の流れは泉声と化し、清凉幽
寂を深める琴の曲となって浮世の塵に汚れがちな人の心を洗ってくれる。
古人は「白雲を蓋と作し流泉を琴と為す」妙趣に至人の境涯を窺えと歌っ
ている。
雨収山岳青 (あめおさまりてさんがくあおし)
降りしきる雨に視界をおおわれてしまうと、われわれの眼には何もはいっ
てこないが、一旦雨があがると、前方に夏の山がいつもの通り青くくっき
りと現れてくる。蒼々たる緑樹は輝かんばかりである。煩悩の雲霧を払っ
てしまえば、人々に円満具足する仏性も、おのずからその輝きを増してく
るであろう。
放下著(ほうげじゃく)
「放下」とは投げ捨てる、ほうり出す等の意味。何ものにも執着をもたず
一切をさっぱりと棄て去ることで「著」は動詞につける助辞。禅匠はこと
さらにおろかな物事へのこだわりを戒めている。捨てきる心こそ、一切が
生きかえる。全くの無一物に徹することは至難の業。
一期一会(いちごいちえ)
茶道から出た人生の名訓。大茶人でもあった井伊直弼が茶道の奥義を書き
残した「茶湯一會集」の巻頭に説かれている。 一期は一生、一会は唯一、
今生の出会い、茶席で幾度同じ主客が会するとしても今日の茶会はただ一
度限りの茶会。なれば主客は全身全霊、誠心を傾けて取り組めと心を示した。
一念忘機(いちねんきをぼうず)
人間は感情の動物と言われる。喜怒哀楽だけにとどまればいいものが、自
我やら執着心が吹き出し、無心になることが極めて難しい。「機を忘ず」
とりもなおさず心を働かせず、無用な一切の計らいを捨て切る処に、何時
も晴れ晴れとした豊かな心の持ち主になれると、先哲は教えられた。
帰家穏坐(きかおんざ)
わが家に帰ってゆっくりとあぐらをかいた時が一番だ。男は外に出ると多
くの敵に出会うという。充実した精一杯の仕事を終えて帰るわが家こそ、
心安らかな自由と安穏の世界がある。心のわが家、魂の憩うふるさとが一
人ひとりの家なのだ。
光陰如箭(こういんやのごとし)
禅堂では時を告げる木板に「生死は大事なり。無常は迅速なり。光陰矢の
如し、時人を待たず」と書して修行者を戒める。時間ほど大きな働きを
するものはあるまい。一日二十四時間に使われず、使ってこそ無限に充実
する。
諸行無常(しょぎょうむじょう)
激動し、変遷が続く現代にあって、釈尊の説かれた真理は、月の光にも似
た光芒を放つ。諸行無常、是生滅法(諸行は無常なり、是れ生滅の法なり)
歓びと悲しみ、そして苦しみ、さまざまな出来事があった中で、限りない
いのちの歓びをたたえて、大晦日には、無常の響きを除夜の鐘が伝えてく
れる。
晴耕雨読(せいこううどく)
晴れた日には山を下り、百姓の牛の尻を追って農耕に従い、雨が降れば草
庵で仏祖の書をひもとき、静かに古教照心のひとときを送る。
晴耕雨読の語は、濃州伊深の里で聖胎長養された頃の関山国師の日常を髣
髴させる。ある日突然勅使が下り、国師は召されて京に上ることになる。
知らぬとはいえ、そんな立派な国師に牛を使わせていた農民のなげきはつ
きないが、国師の面目は、自然に随順して生きた伊深の里の晴耕雨読の生
活にこそあろう。
葉々起清風(ようようせいふうをおこす)
七月炎天下の静寂。「相送って門に到れば修竹あり。君が為に葉々清風を
起す」心と心が触れあい、共に修業で汗を流した交りはさわやかだ。
辛苦の末に悟りを得て、師匠に送られて下山す
洗心(せんしん)
「聖人は此を以って心を洗う」という古語がある。神仏に詣でる時、手を
洗い口を清めるが、同時に自らの心を洗い浄めることが肝要であろう。
手脚の汚れは目についても、心の垢には気がつか
福寿(ふくじゅ)
禍いなく、寿命の長きを願うのは人の常。現実には仲々叶えられない。今
、禍いなければ、それが最大の福、生かされる尊い命あることを寿と受け
とめ、禍いの中に幸福をみる。「生死の中に永遠にほろびぬ生命の歓びを
感得するのが仏法である」と。
慕古(もこ)
『得法を敬重すべし、男女を論ずることなかれ。これ仏道極妙の法則なり』
(礼拝得髄)
吾が身を顧みて、素直に振り返りつつ仏祖の古道をお慕いし、それを現代
生活に反映させる工夫が如何に大切かを道元禅師は説かれた。あらゆる人
間の生き方の根本には大地があり土がある。
共生して生かされている自らであることをゆめゆめ忘れてはなるまい。
帰去来(ききょらい)
「帰りなんいざ、田園将に蕪れなんとす、胡ぞ帰らざる」という陶淵明の
「帰去来の辞」にある有名な語。うかうかと面白おかしく歳月を送るのは
止めにして、人間本分の事に帰ろうよという。
百雑砕(ひゃくざっすい)(ひゃくざっさい)
物体や器物だけではなく、心に宿る煩悩妄想、是非善悪や智識等一切を木
端微塵に打ち砕いてしまえ。地位、名誉の一切合切を捨て切れば、どんな
にか清々した気持になれることか。
平常心(びょうじょうしん)
「禅とは何か」という問いに、「食事がすめばお椀を洗っておきなさい」
と答えた禅匠があった。禅とは、或いは仏道とは何もむずかしい事では
なく、はからいのないあるがままの一瞬一刻を誠実に生きて行くことにほ
かならぬ。理屈ではなく、その積み重ねが一年の歳月、一筋の道につなが
る人生となる事を教えて余りある。
風露香(ふうろかんばし)
自らの修行の正師をそして一真実を真剣に求め、風をくらい野に露宿し、
求道に命をかけ行脚する僧侶の姿にこそ、輝かしい人生行路の象徴を見る
思いだ。
体露とは全体の露顕、本体の露出ということで、宇宙大自然の現われであ
り、仏のご慈悲の現われである。金風とは、錦の彩りに染めて豊熟した黄
金の天地を創り出している秋風のこと。自然の風景を眺め、ただ物思いだ
けにふけるのではなく、自己を習わねばならぬ。?
月千古輝(つきせんこにかがやく)
何時の世も変る事なき明日の光が、くまなく燦々と降りそそぐ。悠々たる
秋の夜長の風情は、古来、東洋の詩歌の題材として君臨している。理屈か
ら抜け切り、この幽幻な風光に身心脱落、没入してほしい。
月落碧潭(つきへきたんにおつ)
岸辺の松の枝より天空に悠々と輝く一輪の月の眺めには一点の乱れなく無
限の風趣が溢れている。
淡々と水をたたえ、幽谷に横たわる静かな湖に映える天地万象の脈動にこ
そ無作無心、任運自在の境涯がある。
拈華微笑 (ねんげみしょう)
釈尊は八万の大衆を前にして、無言で一輪の花を示された。大衆沈黙の中
に、ただひとり、迦葉はその意を悟ってにっこりと微笑した。
これで釈尊の後継者は決まった。生きた仏法は、言葉を超え、教義を要せ
ぬ。正に阿吽の呼吸である。これ程単純で真実の道があろうか。ここに到
るにはさまざまの道があり、方法がある。しかし、ここに到れば以心伝心、
無心の心である。
無常迅速(むじょうじんそく)
生死事大、無常迅速。 人の世の移り変りは常にはかなく変転してやまな
い。時は移りゆき、形あるものは必ず滅する。一切が無常であり生滅する
そのことわりを凝視して、ぼやぼやしていたらすぐに死ぬのだから、あた
ら無駄に過ごしてはならない。
流泉為琴(りゅうせんをきんとなす)
岩もあり木の根もあれどさらさらと流れる水の流れは泉声と化し、清凉幽
寂を深める琴の曲となって浮世の塵に汚れがちな人の心を洗ってくれる。
古人は「白雲を蓋と作し流泉を琴と為す」妙趣に至人の境涯を窺えと歌っ
ている。
雨収山岳青 (あめおさまりてさんがくあおし)
降りしきる雨に視界をおおわれてしまうと、われわれの眼には何もはいっ
てこないが、一旦雨があがると、前方に夏の山がいつもの通り青くくっき
りと現れてくる。蒼々たる緑樹は輝かんばかりである。煩悩の雲霧を払っ
てしまえば、人々に円満具足する仏性も、おのずからその輝きを増してく
るであろう。
放下著(ほうげじゃく)
「放下」とは投げ捨てる、ほうり出す等の意味。何ものにも執着をもたず
一切をさっぱりと棄て去ることで「著」は動詞につける助辞。禅匠はこと
さらにおろかな物事へのこだわりを戒めている。捨てきる心こそ、一切が
生きかえる。全くの無一物に徹することは至難の業。
一期一会(いちごいちえ)
茶道から出た人生の名訓。大茶人でもあった井伊直弼が茶道の奥義を書き
残した「茶湯一會集」の巻頭に説かれている。 一期は一生、一会は唯一、
今生の出会い、茶席で幾度同じ主客が会するとしても今日の茶会はただ一
度限りの茶会。なれば主客は全身全霊、誠心を傾けて取り組めと心を示した。
一念忘機(いちねんきをぼうず)
人間は感情の動物と言われる。喜怒哀楽だけにとどまればいいものが、自
我やら執着心が吹き出し、無心になることが極めて難しい。「機を忘ず」
とりもなおさず心を働かせず、無用な一切の計らいを捨て切る処に、何時
も晴れ晴れとした豊かな心の持ち主になれると、先哲は教えられた。
帰家穏坐(きかおんざ)
わが家に帰ってゆっくりとあぐらをかいた時が一番だ。男は外に出ると多
くの敵に出会うという。充実した精一杯の仕事を終えて帰るわが家こそ、
心安らかな自由と安穏の世界がある。心のわが家、魂の憩うふるさとが一
人ひとりの家なのだ。
光陰如箭(こういんやのごとし)
禅堂では時を告げる木板に「生死は大事なり。無常は迅速なり。光陰矢の
如し、時人を待たず」と書して修行者を戒める。時間ほど大きな働きを
するものはあるまい。一日二十四時間に使われず、使ってこそ無限に充実
する。
諸行無常(しょぎょうむじょう)
激動し、変遷が続く現代にあって、釈尊の説かれた真理は、月の光にも似
た光芒を放つ。諸行無常、是生滅法(諸行は無常なり、是れ生滅の法なり)
歓びと悲しみ、そして苦しみ、さまざまな出来事があった中で、限りない
いのちの歓びをたたえて、大晦日には、無常の響きを除夜の鐘が伝えてく
れる。
晴耕雨読(せいこううどく)
晴れた日には山を下り、百姓の牛の尻を追って農耕に従い、雨が降れば草
庵で仏祖の書をひもとき、静かに古教照心のひとときを送る。
晴耕雨読の語は、濃州伊深の里で聖胎長養された頃の関山国師の日常を髣
髴させる。ある日突然勅使が下り、国師は召されて京に上ることになる。
知らぬとはいえ、そんな立派な国師に牛を使わせていた農民のなげきはつ
きないが、国師の面目は、自然に随順して生きた伊深の里の晴耕雨読の生
活にこそあろう。
葉々起清風(ようようせいふうをおこす)
七月炎天下の静寂。「相送って門に到れば修竹あり。君が為に葉々清風を
起す」心と心が触れあい、共に修業で汗を流した交りはさわやかだ。
辛苦の末に悟りを得て、師匠に送られて下山す
洗心(せんしん)
「聖人は此を以って心を洗う」という古語がある。神仏に詣でる時、手を
洗い口を清めるが、同時に自らの心を洗い浄めることが肝要であろう。
手脚の汚れは目についても、心の垢には気がつか
福寿(ふくじゅ)
禍いなく、寿命の長きを願うのは人の常。現実には仲々叶えられない。今
、禍いなければ、それが最大の福、生かされる尊い命あることを寿と受け
とめ、禍いの中に幸福をみる。「生死の中に永遠にほろびぬ生命の歓びを
感得するのが仏法である」と。
慕古(もこ)
『得法を敬重すべし、男女を論ずることなかれ。これ仏道極妙の法則なり』
(礼拝得髄)
吾が身を顧みて、素直に振り返りつつ仏祖の古道をお慕いし、それを現代
生活に反映させる工夫が如何に大切かを道元禅師は説かれた。あらゆる人
間の生き方の根本には大地があり土がある。
共生して生かされている自らであることをゆめゆめ忘れてはなるまい。
帰去来(ききょらい)
「帰りなんいざ、田園将に蕪れなんとす、胡ぞ帰らざる」という陶淵明の
「帰去来の辞」にある有名な語。うかうかと面白おかしく歳月を送るのは
止めにして、人間本分の事に帰ろうよという。
百雑砕(ひゃくざっすい)(ひゃくざっさい)
物体や器物だけではなく、心に宿る煩悩妄想、是非善悪や智識等一切を木
端微塵に打ち砕いてしまえ。地位、名誉の一切合切を捨て切れば、どんな
にか清々した気持になれることか。
平常心(びょうじょうしん)
「禅とは何か」という問いに、「食事がすめばお椀を洗っておきなさい」
と答えた禅匠があった。禅とは、或いは仏道とは何もむずかしい事では
なく、はからいのないあるがままの一瞬一刻を誠実に生きて行くことにほ
かならぬ。理屈ではなく、その積み重ねが一年の歳月、一筋の道につなが
る人生となる事を教えて余りある。
風露香(ふうろかんばし)
自らの修行の正師をそして一真実を真剣に求め、風をくらい野に露宿し、
求道に命をかけ行脚する僧侶の姿にこそ、輝かしい人生行路の象徴を見る
思いだ。