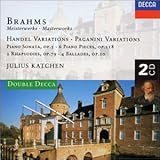Busch Quartet Beethoven "String Quartet No.15" (3. Mov.)
バルトークのピアノ協奏曲第3番は,全体として,穏やかで明るい色調の曲。経済的には幾分好転の兆しがあったとはいえ,アメリカ時代の作曲家の不遇を思うと,なにか不思議な感じがする。因みに,バルトークは,作曲の前年(1944年),ためらう医師から病気が白血病であると告知されている。
この曲でもっとも印象に残るのは,第2楽章「アダージョ・レリジョーソ」。
その第1部では,弦とピアノの対話が5回繰り返されるが,ご存じのとおり,このピアノによるコラール旋律については,ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第15番(作品132)の第3楽章にある「モルト・アダージョ 病気が治った者の神に捧げるリディア調の感謝の歌」との類似性が言われている。
この点,バルトークは,楽聖同様,重い病いから回復しつつあると感じていたから「感謝の歌」を婉曲に引用したとする楽曲解説がある。
確かに,バルトークの体調は件の楽章を作曲していた1945年の夏には一時的に快復していたようだ。実際,ピアノのコラール旋律を聴くと,誰だって「感謝の歌」を想起せずにはいられない。しかし,その類似性はあくまで表面的なものだ。聴きようでは,両者のベクトルは真逆のように思えてくるのだが,どうだろうか。
バルトークの「アダージョ・レリジョーソ」は,最初,発想記号どおり穏やかに始まる。しかし,弦とピアノの対話に入る直前の低弦の一節はたちまち音楽に不吉な陰を与え,その後の展開が単純な健康賛歌ではないことを予告している。
アガサ・ファセット著『バルトーク晩年の悲劇』(みすず書房)等によれば,バルトークの健康は入院と小康を繰り返しながら徐々に悪化していたのは間違いなさそうだ。バルトークの引用が「感謝の歌」にとどまり,あの喜びに満ちた「アンダンテ 新しい力を感じながら」にまで十分届かなかったのには理由があると思う。
やはり,バルトークが件の歌に託したのは,大戦で逝った者へのオーマージュ,そして,やがて逝く自身の告別の辞だとする見方の方が的を射ているのではなかろうか。もちろん,生と死は一枚のコインの表と裏。バルトークにも快復を祈念する気持ちはあったとは思うが。
さて,手元にあるバルトークのピアノ協奏曲第3番のディスクは,シフ/フィッシャー盤,コヴァセヴィチ/デイヴィス盤,アルゲリッチ/デュトワ盤,そして表題のアンダ/フリッチャイ盤,の以上4種。どれも素晴らしい演奏だが,アンダ/フリッチャイ盤の第2楽章はひときわ感銘が深い。
第1部のピアノのコラール旋律が回を重ねる毎にじわじわ熱を帯びていくのは他盤と同じ。しかし,アンダ/フリッチャイ盤の4度目のそれは唐突と思われるほど激烈だ。そして,それに応答する弦の切々としたカンタービレも胸に迫る。
作曲時,ファシズムの崩壊と平和の訪れは決定的であった。しかし,皮肉なことに,同時期,不治の病がとうからずバルトークの生に終止符を打つのも十分予期されていたのだ。ふだんは感情を押し隠していたという冷徹なバルトーク。アンダ/フリッチャイ盤でこの楽章を聴いていると,我知らず,拳をぐっと握りしめる彼の姿を思い浮かべてしまう。用いた素材は喜びに満ちあふれている。しかし,そのことがかえって音楽を清澄なだけでなく悲痛なものにしている。
第3部のピアノの意欲的な表現を含め,アンダ/フリッチャイ盤の第2楽章は,曲の有りように深く踏み込んだ名演だと思う。両端楽章も素晴らしい。
最後になったが,アンダ/フリッチャイ盤については,ピアニスト,指揮者ともにバルトークと同じハンガリー出身であることのほか,この録音が白血病による長期休養からフリッチャイが復帰した直後におこなわれたものであることも付記しておきたい。フリッチャイの同曲には,白血病を発症する前,独奏者にモニク・アースを迎えた録音もある。オケはRIAS響。ご存じのとおり,改称前のベルリン放響で,アンダ盤と同じオケである。フリッチャイの指揮はアンダとの共演盤の方がより陰影の濃いものになっていると思うのだが,どうだろう。気のせいだろうか。
バルトークのピアノ協奏曲第3番は,全体として,穏やかで明るい色調の曲。経済的には幾分好転の兆しがあったとはいえ,アメリカ時代の作曲家の不遇を思うと,なにか不思議な感じがする。因みに,バルトークは,作曲の前年(1944年),ためらう医師から病気が白血病であると告知されている。
この曲でもっとも印象に残るのは,第2楽章「アダージョ・レリジョーソ」。
その第1部では,弦とピアノの対話が5回繰り返されるが,ご存じのとおり,このピアノによるコラール旋律については,ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第15番(作品132)の第3楽章にある「モルト・アダージョ 病気が治った者の神に捧げるリディア調の感謝の歌」との類似性が言われている。
この点,バルトークは,楽聖同様,重い病いから回復しつつあると感じていたから「感謝の歌」を婉曲に引用したとする楽曲解説がある。
確かに,バルトークの体調は件の楽章を作曲していた1945年の夏には一時的に快復していたようだ。実際,ピアノのコラール旋律を聴くと,誰だって「感謝の歌」を想起せずにはいられない。しかし,その類似性はあくまで表面的なものだ。聴きようでは,両者のベクトルは真逆のように思えてくるのだが,どうだろうか。
バルトークの「アダージョ・レリジョーソ」は,最初,発想記号どおり穏やかに始まる。しかし,弦とピアノの対話に入る直前の低弦の一節はたちまち音楽に不吉な陰を与え,その後の展開が単純な健康賛歌ではないことを予告している。
アガサ・ファセット著『バルトーク晩年の悲劇』(みすず書房)等によれば,バルトークの健康は入院と小康を繰り返しながら徐々に悪化していたのは間違いなさそうだ。バルトークの引用が「感謝の歌」にとどまり,あの喜びに満ちた「アンダンテ 新しい力を感じながら」にまで十分届かなかったのには理由があると思う。
やはり,バルトークが件の歌に託したのは,大戦で逝った者へのオーマージュ,そして,やがて逝く自身の告別の辞だとする見方の方が的を射ているのではなかろうか。もちろん,生と死は一枚のコインの表と裏。バルトークにも快復を祈念する気持ちはあったとは思うが。
さて,手元にあるバルトークのピアノ協奏曲第3番のディスクは,シフ/フィッシャー盤,コヴァセヴィチ/デイヴィス盤,アルゲリッチ/デュトワ盤,そして表題のアンダ/フリッチャイ盤,の以上4種。どれも素晴らしい演奏だが,アンダ/フリッチャイ盤の第2楽章はひときわ感銘が深い。
第1部のピアノのコラール旋律が回を重ねる毎にじわじわ熱を帯びていくのは他盤と同じ。しかし,アンダ/フリッチャイ盤の4度目のそれは唐突と思われるほど激烈だ。そして,それに応答する弦の切々としたカンタービレも胸に迫る。
作曲時,ファシズムの崩壊と平和の訪れは決定的であった。しかし,皮肉なことに,同時期,不治の病がとうからずバルトークの生に終止符を打つのも十分予期されていたのだ。ふだんは感情を押し隠していたという冷徹なバルトーク。アンダ/フリッチャイ盤でこの楽章を聴いていると,我知らず,拳をぐっと握りしめる彼の姿を思い浮かべてしまう。用いた素材は喜びに満ちあふれている。しかし,そのことがかえって音楽を清澄なだけでなく悲痛なものにしている。
第3部のピアノの意欲的な表現を含め,アンダ/フリッチャイ盤の第2楽章は,曲の有りように深く踏み込んだ名演だと思う。両端楽章も素晴らしい。
最後になったが,アンダ/フリッチャイ盤については,ピアニスト,指揮者ともにバルトークと同じハンガリー出身であることのほか,この録音が白血病による長期休養からフリッチャイが復帰した直後におこなわれたものであることも付記しておきたい。フリッチャイの同曲には,白血病を発症する前,独奏者にモニク・アースを迎えた録音もある。オケはRIAS響。ご存じのとおり,改称前のベルリン放響で,アンダ盤と同じオケである。フリッチャイの指揮はアンダとの共演盤の方がより陰影の濃いものになっていると思うのだが,どうだろう。気のせいだろうか。
 | バルトーク:ピアノ協奏曲第1~3番アンダ(ゲーザ),バルトーク,フリッチャイ(フェレンツ),ベルリン放送交響楽団ポリドールこのアイテムの詳細を見る |
 | バルトーク 晩年の悲劇アガサ・ファセットみすず書房このアイテムの詳細を見る |