
前回のブログに「七事随身」の掛け軸を掲載しましたが、この意味を調べて見ました。
料理屋の説明: 中国のことわざ。戦に臨む時は事前に七つの武器(
剣、弓、矢等)を身に付けて、十分に準備をしなさい
という意味。転じて、私達もお客さまに接する時は身
だしなみに十分気を付けなさい。と教えられています。
ネットで調べたら: 元は禅の言葉。禅僧が常に身に携えている七つ
道具のこと。即ち、三衣、一鉢、香合、払子、浴
具、尼師壇(座具)、紙被のこと。
転じて、茶道にこの精神を取り入れ、七つの儀式を
つくり出し、これを「七事式」という。即ち、「花月」「且
茶」「茶カブキ」「廻り炭」「廻り花」「花寄せ」「一二三」
のこと。
茶道の事はよくは分かりませんが、料理屋の説明は、教訓になります。













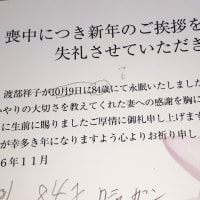





2年前に、妹の3年忌の時にも同じところで会食をしましたが、料理が出てくるのが遅いし、皆さんの評判が良くなかったのですが、最近、板長さんが変わってから料理も美味しくなり、従業員も見違えるように良くなりました。
庭には池があり滝が二筋流れており、鯉も泳いでいました。この動画を撮ってありますので、次回お見せします。
茶事の事は解りませんでしたが心構えと言う事は解りました もしかしてかのと山荘では?
それと妹様が先に行かれてしまわれたのですか?
お若いのに残念な事ですね! その分までとうさん頑張らねば!
有難うございました。
身だしなみは心しておきます。
言葉って多少形を変えながら生きているのが面白いですね。「七つ道具」もこの事からなのかな。
そういえば庭に水琴窟があり、父と聴いてみました。
とても綺麗な音でしたよ。
そのお店に、「料理も美味しく、感じも以前より見違えるようによくなり、皆が褒めていた」旨、電話しましたら、女将は「お褒め頂き、励みになります」と言っていました。
すぐ下の妹は2度目の「くも膜下出血」で平成14年1月に亡くなりました。
七つ道具はここからきた言葉かも知れません。
水琴窟の音を聞いたのですか。良かったですね。私は写真を撮ることばかり気にしていて、すっかり忘れてしまいました。