
1年ぶりの松本市音楽文化ホールでの桒形亜樹子氏のチェンバロコンサートだ。 ★ 👈 HP内ページ
昨年は2種類の音律のチェンバロを用意したソロコンサートだった が、今回はオーボエとジョイントだ。

今年はウィリアム・バード死後400年ということで、まずバードの曲を5曲、「プレリュード」、「ウイリアム・ピーター氏のパヴァーン&ガリアード」、「ウィロビー卿お帰りなさい」、「そんな荒れた森へ行くの?」、「ファンシー」を桒形氏は演奏した。ソロ演奏だ。
古楽の味わいがたまらない。
世俗的な曲の「そんな荒れた森へ行くの?」が牧歌的で楽しかった。
★ 👈 Michael Maxwell Steer の演奏動画。
★ 👈 リュートがメインのアンサンブル Ayreheart の演奏動画。
★ 👈 ニッケルハルパとリコーダーと歌の Wilde Roses の演奏動画。森の中で歌って踊る。軽やかで楽しげで蠱惑的で、なるほどこういうイメージなのか。
William Byrd "Will you walke the woods soe wylde?" とパンフレットにあったのだが、今の英語とスペルが違っていてそこでも時の隔たりを感じる。
「ファンシー」はなにか胸に迫る曲だった。「ファンシー」は「ファンタジー」と同じ意味だそうだ。
5月に行われたチャールズ国王戴冠式でバードは2曲使われた、YouTube で見ることが出来る、という話をされた。
ウイリアム・バード、好きになりました。
その次は現代の ルドルフ・ケルターボーンの「オーボエとチェンバロのためのソナチネ」で、そこで吉村結実氏が登場。
1960年の曲だそうで、不安な感じで始まるのがいかにも現代曲という感じ。
400年の時を一気に跳んで、クラクラする。
そこで休憩に入る。
後半はドイツの作曲家3人。
まずはゲオルク・フィリップ・テレマンで、「フルート(オーボエ)のための12のファンテジーより第8番ホ短調」を吉村氏のソロ、次に「チェンバロのための36のファンテジーより第10番ト長調」を桒形氏のソロ、そしてまた吉村氏で「フルート(オーボエ)のための12のファンテジーより第10番嬰ヘ短調」、と交互にソロで演奏した。
「フルート(オーボエ)のための12のファンテジーより第8番、第10番」 は格調高く美しい旋律で、それを表現できる吉村氏の実力を感じさせられた。
「チェンバロのための36のファンテジーより第10番ト長調」はゆったりとしていて、短調の曲の間にはさまるのにちょうどよかった。
その次はヨハン・セバスツィアン・バッハの「平均律クラヴィーア曲集第2巻より前奏曲とフーガ第19番イ長調 BWV 888 」を桒形氏のソロ。
これもゆったりしていて心地よかった。
そして最後がヨハン・セバスティアン・バッハの次男、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの「オーボエとチェンバロのためのソナタト短調 H.542.5 」で、桒形氏と吉村氏が一緒に演奏した。
チェンバロの音色はきらびやかで オーボエも高い倍音を含んだ音色で、なじむ組み合わせだと思った。
パンフレットの桒形氏の文章によると、この曲は長い間父バッハの作品とされていたが疑いも持たれていたらしい。その2楽章が天国的とさえいえる美しさで何度演奏しても毎回至福のひととき なんだそうだ。
★ 👈 広田智之(オーボエ)曽根麻矢子(チェンバロ)による演奏動画。 7:38から2楽章。
むかし シギスヴァルト・クイケン氏の指揮した父バッハのブランデンブルク協奏曲のCDをよく聴いていたのだが、そういえば合奏にチェンバロが入っているのってそれしか聴いたことなかったんだよな。
このソナタはオーボエとチェンバロの合奏でブランデンブルク協奏曲に比べるとずいぶん小編成だけれど、それでもチェンバロがほかの楽器と合わせるとどうなるのかを生で聴けて、納得した。チェンバロの合奏、楽しそうだな!
👇 開場後開演前、ギリギリまでチェンバロをチューニングしている。
バードとバッハらとケルターボーンを1台のチェンバロで演奏したけれど、いったいどの音律でチューニングしたのだろうか?

そして今回のコンサートには別の目的があった!チェンバロ講習会を申し込むのだ。 ★ 👈 HP内ページ
ドキドキしながら申し込んだが、初回優先ということで無事受けられることになった!
1台のチェンバロを皆で使うようだ。レッスンの日を、グループレッスンに3時間、それ以外の時間を皆で割り振って個人練習なので あまり時間はとれないが。
各々が違う曲をみてもらうのだが、曲も決まった。
そうです、私の課題曲はウイリアム・バード「そんな荒れた森へ行くの?」に決まった。装飾音符はつけずに練習してくるように言われた。
わたしの出番は7月だ。今月のレッスンは見る側だ。とても楽しみだ!




















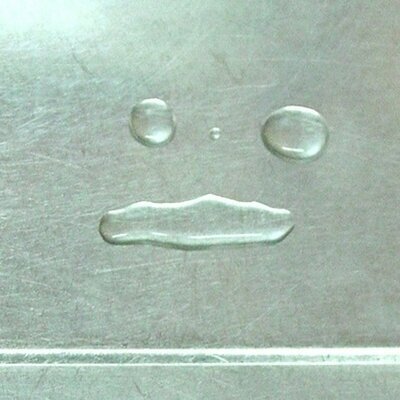




私も一度だけ桒形氏にレッスンしていただいたことがあります。
曲の理解が半端ない方です。
それにしても、そんな講習会があるとは、うらやましいデス!
桒形氏のコンサートの曲の合間のお話が理知的なんです。
パンフレットの文章もひと味ちがう。
レッスンの曲を決めるときに少しだけお話しましたが、期待がうなぎ上りです。
学生時代にオルガンを教わった植田義子氏を思い出しました。
実は先日、9月にもレッスンしていただけることに
なりましてございます。
とっても楽しみです。
他の生徒さんのを見ているんですが、そういえば子供の頃ピアノのレッスンを受けていたときって、待ち時間はまえの順番の生徒さんのレッスンを見ていたなあ、と思い出しました。
生徒さんの脇でちょこっと先生が弾くと、同じ楽器とは思えない音なのにびっくりしました。
バードの装飾音の説明もあったので、家に帰って練習してみましたが、入れると曲が生き生きしてきますね。
ふらっとさんはお忙しいのにどんどん出て行かれていて尊敬します。
9月のレッスンの話をブログで拝見するのを楽しみにしています