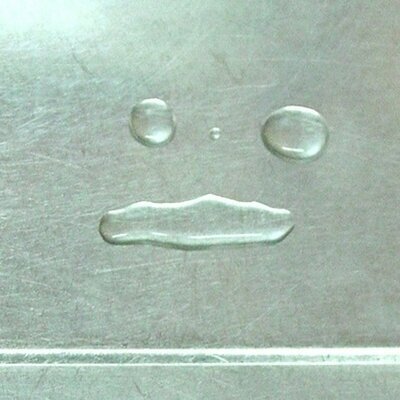記事を溜めないのが目標だったはずなのに、気付けば1ヶ月以上経っている!
5月は色々なところに行ったりしたので記事が渋滞だ。
さる4月25日に、チェンバロではなくヴァージナル、そしてかそけき音のクラヴィコードによるコンサートを聴きに
カルッツかわさき に行ってきた。
演奏するのは
古宮修治 氏である。
会場に入るとクラヴィコードとヴァージナルが並べてある。なぜかその間にフェルメールの絵が飾られている。
左のクラヴィコードには両側からマイクが向けられていて、足元にスピーカーが置いてある。
やはり なま音で会場に音を行き渡らせるのはムリだよね。
プログラム。

古宮氏は当時の衣装で現れた。途中2回変えたので、3種類の格好を見ることが出来た。
ビラビラした襞襟やロン毛のカツラはなかなか暑そうだ。
このコンサートについて古宮氏が自身の
facebook にアップされている。プログラムの内側や裏側も見ることができるし、衣装を纏っての演奏動画を見ることができるので興味のある方はどうぞ見に行ってください。
曲は時代に沿って演奏された。
最初は『ロマネスカによる変奏(作者不詳 16世紀中葉)』のヴァージナル演奏だった。
アルビコルドという、ビリビリ響く特殊な効果を出す装置を稼働させていて、オープニングにふさわしい賑やかな曲だった。

弦のナットレールに沿って装置があって、動かすと弦に金属片を近づける。そうするとギターでいうビビリ音が出る。

ヴァージナルとチェンバロの違いの説明もあった。まあ見た目からしてぜんぜん違うよね。
チェンバロの弦は演奏者の向こうの方へ張られていて、楽器の姿は細長く華奢なグランドピアノのようだ。
ヴァージナルの弦は真横に張られていて、楽器の姿は上の写真のように箱形で 手前の辺の中央部がへこんでいてそこに鍵盤がある。
プログラムの右側、ヴァージナルの楽器解説に
「400年前に大流行したチェンバロの一種。弦の中央部分をはじくことで発するふくよかな音が特徴の今回の楽器は特に「ミュゼラー」と呼ばれます。」
とあったので、家に帰って
日本チェンバロ協会編『チェンバロ大事典』で「ミュゼラー」を調べてみた。
p.18
「弦の中央部分を弾くミュゼラー型は偶数倍音を欠いたきわめて独特の暖かい音がする。」
とある。
弦の撥く場所によって出される音に含まれる倍音の割合が異なる、というのは分かる。でも偶数倍音を欠いた音、というのがどういうものか分からないので調べてみた。
物理学だー。波動だー、音だー。
固有振動(弦など)と気柱振動(管楽器)で違うのね。横波と縦波か。地震のS波とP波みたいか。
倍音はトロンボーンを吹いていたから感覚的に分かる。これは気柱振動の方か。
第2倍音は基音のオクターブ上、第3倍音は1オクターブと完全5度上、第4倍音は2オクターブ上、第5倍音は2オクターブと長3度上、第6倍音は2オクターブと完全5度上、第7倍音は2オクターブと短7度上よりかなり狭いが2オクターブと長6度上よりは2オクターブと短7度上に近い音程 ... 。
第7倍音あたりになってくるとだんだん音階から外れた音になる。
なるほど、偶数倍音の方が基音となじむな。
それで偶数倍音が含まれる音と奇数倍音が含まれる音の違いを検索したら、
スタジオ翁「ミキシングに「倍音」を生かすための3つの方法」 というのがあって、その中に偶数倍音ばかり含む音と奇数倍音ばかり含む音の紹介している動画のリンクが貼ってあった。
聞いてみると、偶数倍音ばかりだとぼんやりする?
しかし、奇数倍音ばかり含む音でも矩形波や三角波がある。
シンセサイザー入門 1:音の正体と性質
波形による音の違い という短い動画では サイン波、矩形波、のこぎり波と三角波を聴くことができる。ちなみに、サイン波は倍音を含まない純粋な音、のこぎり波は偶数倍音も奇数倍音も含む音。
奇数倍音ばかり含む音の矩形波と三角波は、ずいぶん違った音色に聞こえる。うーむ。
そういえば、気柱振動でも閉管だと奇数倍音ばかりになるらしい。
2021年に初めて夫とポルタティーフオルガンを作った ときは開管だったが、実は
今年もポルタティーフオルガンを作った のだ。それは諸事情によりゲダクト(閉管)になったのだが、ゲダクトの音色は いかにも笛という開管とはずいぶん違ってなんだか可愛らしい。
弦の奇数倍音を多く含む音も そういう感じ?
そもそも、弦の中央部を撥くと偶数倍音が欠けるという物理学的根拠を 浅学なわたしは見つけられなかったし。
ここらへんで迷子になってまいりました。
それで奇数倍音から離れて、うちにあるギターで撥く位置を変えて音を鳴らしてみた。
端の方で撥くとはっきりした音色で高音の倍音が多い気がする。なるほど中央付近で撥くとまろやかな音色だ。
【簡単に試せる】クラシックギターで色々な音色を自分で作っていこう!
こういう感じでミュゼラー型はまろやかな音色なのかな。
なんでこんなにくどくどと述べたかというと、コンサートではいまひとつミュゼラー型のヴァージナルの音色とチェンバロとの違いを認識できなかったからだ。
両者ならべて音を鳴らしてくれたら分かっただろうけど、チェンバロは来ていなかったし。
というか、もっと予習して臨めば面白く分かったのかもしれなかったが、予習不足でした。もったいなかった。
会場のヴァージナルに話を戻す。
カルッツかわさきの方のリンクには「使用するヴァージナルは17世紀、フェルメールが描いたものを忠実に復元したものです。」とあった。
なるほどそれでフェルメールの絵を飾っていたのだな。
『ロマネスカによる変奏(作者不詳 16世紀中葉)』に続いて2曲、イギリスの16世紀の曲が続いた。
わたしはフィッツウィリアム・ヴァージナル・ブックが大好きなので、つかみはばっちりです。
ちなみにこの時期のイギリスでは、チェンバロもスピネットもヴァージナルもまとめてヴァージナルと呼んでいたらしい。ヴァージナルブックの曲はヴァージナル専用というわけではない。
3曲弾いたあと一度 古宮氏は会場を去り、衣装を変えて現れた。17世紀前半に流行した垂れ襟にもっさもさのカツラ。
今度はイギリスからフランスに移り、シャンボニエールのクラント「春」をヴァージナルで演奏した。
そして、次はドイツのヴェックマンの「「その愛くるしい眼差し」による変奏曲」をクラヴィコードで演奏した。
そしてまた衣装替え。今度は18世紀、帽子まで被って華々しい。
時代背景や、当時は小氷期とよばれるくらい寒かった話をされた。ルイ14世は寝るときもカツラを被っていたそうだが、防寒のためもあっただろう、とか。
御大ヨハン・セバスティアン・バッハの ピアノでもよく弾かれる「平均律クラヴィア」や「フランス組曲」から古宮氏は演奏した。
その次にフランスのラモーで雰囲気が変わる。
そのあと、クラヴィコードでバッハの「ゴルトベルク変奏曲」のアリアを演奏した。味わい深いメロディの一音一音にビブラートをつけたりダイナミクスをつけたりするのはクラヴィコードならではだ。
古宮氏はリズムカルで早いパッセージの多い曲よりも、こんな風にフレーズを情感をこめてうたう演奏の方が得意なのかもしれないと思った。
最後にまたロンドンに戻ってヘンデルの「パッサカリアト短調」の演奏でプログラムは終了した。
アンコールは2曲演奏された。
演奏会終了後、ちょっと楽器にさわれるコーナーにて写真を撮った。下の写真がクラヴィコード。上の写真もヴァージナルもそのときに撮った。

クラヴィコードを初めて目の当たりにしたのは
2021年12月、浜松市楽器博物館 でのことであった。
チェンバロのように撥くのでもピアノのように打つのでもない音の出し方や シンプルな仕組みに驚いたものだ。

カルッツかわさきの入り口。演奏会の会場は1階だったのでこの階段は上らない。

向かいの川崎市教育文化会館。円錐形に仕立てられた木が並んでいるのが印象的。

川崎駅から歩いている途中の植え込み。白をメインに黒と見紛う紫のコントラストがよい。
チューリップの季節だったんだよなあ。

実はインターネットで知り合いになった古楽仲間のふらっとさんとこのコンサートで初めてリアルにお会いした。もしかしてオフ会ってやつ?
ふらっとさんはたいそうエネルギッシュに活動されている方だ。ぽーっとしているわたしの何倍も動いておられる。
お会いして勇気をもらってわかれました。