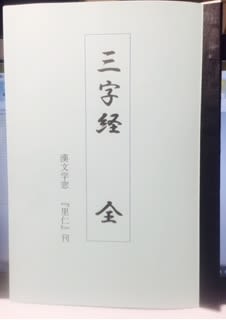告知
太田天籟・須藤明実 展
2015年7月2日(木)~7月7日(火)
11:00~6:00(初日2:00より 最終日4:00まで)
太田天籟 ㈶美術院国宝修理所、錦戸新親氏に師事
野田市金乗院境内守撲庵釈迦如来立像安置
松伏町宝珠院、不動明王立像安置
須藤明実 ギャラリー歩知主宰、
漢文学窓『里仁』主宰
全日本家族論語の会主宰
場所 ギャラリー恵風
〒343?845 再為券越谷市南越谷4≠P5≠P3
Tel・Fax 048-989-1899
JR 武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分
東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩3分

会期中に須藤先生の講話があります。
7月4日『論語』
7月5日『菜根譚』 各回 10:00~11:00 会費1,000円
※ 菜根譚は資料の準備の都合で、事前申し込みをお願いしたいそうです。
太田天籟・須藤明実 展
2015年7月2日(木)~7月7日(火)
11:00~6:00(初日2:00より 最終日4:00まで)
太田天籟 ㈶美術院国宝修理所、錦戸新親氏に師事
野田市金乗院境内守撲庵釈迦如来立像安置
松伏町宝珠院、不動明王立像安置
須藤明実 ギャラリー歩知主宰、
漢文学窓『里仁』主宰
全日本家族論語の会主宰
場所 ギャラリー恵風
〒343?845 再為券越谷市南越谷4≠P5≠P3
Tel・Fax 048-989-1899
JR 武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分
東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩3分

会期中に須藤先生の講話があります。
7月4日『論語』
7月5日『菜根譚』 各回 10:00~11:00 会費1,000円
※ 菜根譚は資料の準備の都合で、事前申し込みをお願いしたいそうです。