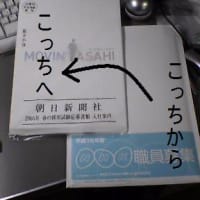【ある企業で】
ある企業の採用試験でグループディスカッションをやったのだけど、そのテーマが「脱ゆとり教育」だった。↓でも「モノを語るときのbackgroud」という話を書いたけど、あまりにも私自身そういう分野についてのbackgroudがなくて、周囲の受験者はだいぶ勉強されてきたようで明らかに準備段階で差があるなと思ったのだが(当然落ちた)、その直後にまたなんか学力テストかなんかの結果が出て、文部科学省的には一喜一憂しているように見える。↓のところで歴史教育について触れたら、なんとなくこの「ゆとり教育」についても触れたくなったのでちょっと書いておこう。
【反意語】
どうして「ゆとり」の反対は「脱・ゆとり」なのだろう、というのが一番の疑問だ。私はどんな問題でもtotalとdetail両方を見ないとモノは見えてこないと思っている。細かく考えたら「ゆとり」の反対は必ずしも「脱・ゆとり」だけではないように思うのだ。ゆとり教育がひとつめざすところに「考える力を養う」というのがあるなら、そのための部品となる「知識」は不可欠だ(これは↓の歴史の話ともリンクするが)。tatalの思想として「考える力」を目指すのなら、どうして知識を入れる量を減らそうという発想になるのだろうか。今回「ゆとり教育」がなんとなくうまく動かない理由には「つめこむ」の反対を「つめこむだけに留めない」と考えるのではなく「つめこむ量を減らす」という発想にしてしまったためだったのではないかと個人的には考えている。しかるべき知識を教える場を設け、その上でそれらの知識を実生活の中でつなげる練習をする場所を総合的学習のコンセプトにすれば、「ゆとり教育」が本来目指した教育のステージができあがるのではないだろうか。つまりは、totalの考える力を構築するためにdetailの知識を軽視することなく教える、ということだ。これまでの「ゆとり」があまり効果をなさなかったからといって、すぐ「脱・ゆとり」にするのではなく、「ちがうかたちのゆとり」という方向性を目指すことはなかったのだろうか。これが一番の疑問なのである。
ある企業の採用試験でグループディスカッションをやったのだけど、そのテーマが「脱ゆとり教育」だった。↓でも「モノを語るときのbackgroud」という話を書いたけど、あまりにも私自身そういう分野についてのbackgroudがなくて、周囲の受験者はだいぶ勉強されてきたようで明らかに準備段階で差があるなと思ったのだが(当然落ちた)、その直後にまたなんか学力テストかなんかの結果が出て、文部科学省的には一喜一憂しているように見える。↓のところで歴史教育について触れたら、なんとなくこの「ゆとり教育」についても触れたくなったのでちょっと書いておこう。
【反意語】
どうして「ゆとり」の反対は「脱・ゆとり」なのだろう、というのが一番の疑問だ。私はどんな問題でもtotalとdetail両方を見ないとモノは見えてこないと思っている。細かく考えたら「ゆとり」の反対は必ずしも「脱・ゆとり」だけではないように思うのだ。ゆとり教育がひとつめざすところに「考える力を養う」というのがあるなら、そのための部品となる「知識」は不可欠だ(これは↓の歴史の話ともリンクするが)。tatalの思想として「考える力」を目指すのなら、どうして知識を入れる量を減らそうという発想になるのだろうか。今回「ゆとり教育」がなんとなくうまく動かない理由には「つめこむ」の反対を「つめこむだけに留めない」と考えるのではなく「つめこむ量を減らす」という発想にしてしまったためだったのではないかと個人的には考えている。しかるべき知識を教える場を設け、その上でそれらの知識を実生活の中でつなげる練習をする場所を総合的学習のコンセプトにすれば、「ゆとり教育」が本来目指した教育のステージができあがるのではないだろうか。つまりは、totalの考える力を構築するためにdetailの知識を軽視することなく教える、ということだ。これまでの「ゆとり」があまり効果をなさなかったからといって、すぐ「脱・ゆとり」にするのではなく、「ちがうかたちのゆとり」という方向性を目指すことはなかったのだろうか。これが一番の疑問なのである。