2016/12/31の記事で紹介した長谷川英祐『働かないアリに意義がある』を読みました[Ref-1a,b]。参考文献に挙げた2つの本は目次からみて同一内容と思われますが、以下、本記事での参照ページ数はRef-1aのものです。
一言で言って非常におもしろい。序章で人間社会との比較も交えてつかみを取り、1章で「働き者のアリ」という固定観念が正確な観察により打ち砕かれ、2-5章では他の生物の実例も交えて、働かないアリの存在する理由(進化論的理由・メカニズム的理由等)を解説しています。各章の最後には章のポイントを箇条書きしてあり非常に親切です。この人は伝え方がうまい。
私の知らなかったことも多々あって勉強になりました。例えば、「こうしたコロニー内の裏切り者は英語の「だます(cheat)者」の意から「チーター」と呼ばれます。」ということ[p116]。いや実は最近はチートの方をよく知っていたもので・・。
他にも、粘菌でのチーターとか[p117]、群れ全体が完全クローンのアリとか[p128-129]、ヤマトシロアリにおける女王の遺伝子と王の遺伝子との生き残り合戦とか[p129-132]、「雌雄は同じ母親から生まれ、交尾もし、ワーカーも両者の遺伝子の混合物としてつくるのに、オスとメス自体は遺伝的に完全な「別種」となっている」アリとか[p137-140]、まさに奇々怪々の世界ですね。ちなみに後の2つの例は、受精卵が産まれるまでのどこかで母由来の遺伝子と父由来の遺伝子を選別するメカニズム、おそらくは生化学的・分子生物学的なメカニズムが働いているわけであり、ドーキンスの定義した"利己的遺伝子"(Selfish Gene)よりも狭い意味での、遺伝子レベルでの進化研究でよく使われる"利己的遺伝子"の実例としてもわかりやすいですね[*1]。
さて「第3章 なんで他人のために働くの?」では真社会性の進化に関する"血縁選択説"と"群選択説"との対立を解説しています。ここで誤解してはならないのは"群選択説"という言葉にはウィキペディアの記事でもわかるように複数の意味があるということです。この本での"群選択説"というのは次のような仮説です。
===========引用開始====下線は私の強調============
利他者と利己者がいれば、メンバー間に相互に利害関係のある「群(ぐん)」が必ずできます。このとき、利他者と利己者のあいだに血縁関係がなかったとしても、群全体の1個体あたりの生産性が、単独のときより大きくなることがあれば、利他者が自らの子どもの数を減らして利己者に尽くしてなお、単独でいるよりも適応度(自分の遺伝子が生き残る率)が高くなるのではないか、という議論です。
この考え方は「群選択」と呼ばれており、1980年頃から議論され始めました。群を形成する効果として、個体の適応度をあげる力が生じていると考えるのが「群選択説」です。この仮説を裏付けるために必要な、協力者数の増加以上に利益があがる効果を「相乗効果(シナジー)」と呼びます。
===========引用終り===============================
そもそも群れること自体に利益があり、その利益を受けるためには利他的形質が必要になる、という話ですね。
"群選択説"を「自然選択される単位は群である」としてドーキンスの"利己的遺伝子説"「自然選択される単位は遺伝子である」の対立仮説と捉えると、現在の定説では間違いとなるでしょう[*2]。とはいえ、群が多数あり、その生成消滅が頻繁で子孫残しに失敗した群(の個体の遺伝子)は消滅する、という状況では、ほぼ「群の淘汰=遺伝子の淘汰」ということにはなるでしょう。極端な話、多細胞生物の個体というのは細胞の群です。そして生殖細胞以外の体細胞は、働きアリと同様に自らは子孫を残すことができません。まあ時には勝手に増えようとする突然変異体が生じたりもしますが、そのような遺伝子はむろん細胞群(個体)と共に消滅し、末永く続くことはできません。すなわち、生殖細胞を差し置いて勝手に増えようとする"遺伝子"はもはや適応度0なのです。
一言いうと、ここで「生産性」という言葉を使ってしまったあたりが混乱を招いたようにも思えます。いやむしろ問題意識を産んだと肯定的に捉えるべきかな。
この議論は理解自体も複雑なのでまたの機会ということにして、著者自身の見解は第3章の「向き合わない両者」という項で示されています。
===========引用開始====下線は私の強調============
私なりの意見を言うと、両者は同じ土俵に立っていないように思えます。
(中略)
同じものを測るのに両者で使っているモノサシが違うようなもので、これが議論が混乱
、する原因と思われます。
(中略)
ともあれ私個人は、群の効果がなくても利他行動が進化し得るという単数倍数性生物の特徴が、このグループにおける真社会性の高頻度な進化をもたらしたのは間違いなく、そのうえで「群の効果があり、その結果として増えた子孫との血縁関係の濃さにより包括適応度が高まる」のであり、群と血縁の両者ともが、利他者の包括適応度を測るために不可分なものと認識しています。現象内に含まれるすべての要因を明示して、その関係性を示すモデルをつくることが、今後は重要になるでしょう。
===========引用終り===============================
こうして両説は止揚されたのでした。当たり前の結論がもっとも真相に近いということですね。
「第5章「群れ」か「個」か、それが問題だ」では上記の「多細胞生物の個体というのは細胞の群とも考えられる」ということも含めて、群というものが生じる、または生じないメカニズムの話が展開されています。
そして「終章その進化はなんのため?」の冒頭「食べ始めたとき、進化した」の項では自然選択説をしっかりと解説しています。しかし次の「自然選択説の限界」から、私にとってはちょっと混乱を招く表現が出てきます。
===========引用開始====下線は私の強調============
この大原則は、「この世代」で「強いもの」が生き残るという思想です。いまこの世代における強弱のみが問題であり、短期的な効率が高いものが最後に残るはずだと言い換えることもできます。ところが、働かない働きアリについては、短期的に高効率なシステムより低効率なものが残るという結論になっています。なぜこんなことになるのでしょうか?「自然選択のもとでは適者生存」という鉄則自体が間違っているのでしょうか?
===========引用終り===============================
私としては「言い換えないでほしかった」と思います。この言い換えはずいぶん誤解を招くと思います。しかし以降をよく読むと、長谷川英祐準教授の考えはまともなものに思えますし、彼の指摘する論点は多くの進化学者の盲点になっていることも確かなのかも知れません。それは一言でいえば自然選択の働くタイムスパンの問題です。
===========引用開始====下線は私の強調============
適応度に基づく進化の考えにはもう一つ大きな問題があります。適応度は未来における値なので、測定する未来をどの時点に置くかで値が違ってくる可能性があるのです。通常は「次世代」または「孫の世代」での適応度を進化の指標にしますが、次世代で適応度が高いある性質も、何百世代もの未来で考えると、次世代で低い適応度しか示せない性質より適応度は低いのかもしれません。言い換えれば「ある生物がどのくらい未来の適応度に反応して進化しているのかはまったくわかっていない」のです。もしかすると、次世代の適応度に反応する遺伝子型と、遠い未来の適応度に反応する遺伝子型がいまこの瞬間も、私たちの体内で競争しているのかもしれません。しかし理論上にせよそんなことが検討されたことはいままでないのです。
===========引用終り===============================
"「次世代」または「孫の世代」での適応度"であれば"働かないアリを生じる遺伝子"の適応度は十分高いでしょう、というのが私のとらえ方だったので、それが自然選択説と矛盾するかのような言い方に違和感を感じていたのでした。テレビでの表現とか"短期的に高効率"とかだと、どうしても「当世代」での個体生存の適応度を指していると誤解しますよ。
それはともかく、長谷川英祐準教授の問題意識を私が理解した限りで、私の表現で書いてみます。
自然淘汰とは現在の環境が生物を淘汰するものです。まだ存在しない未来の環境というものは、現在の生物に働きかけることはできません。また生物も未来環境を予測してそれに適応するという事は、できないはずです。しかしこの"現在"という期間は、どのくらいの長さを持つのでしょうか? 決して現時点という瞬間ではありえません。
自然淘汰が「子孫を残せるか否か」という基準で測られる以上、"現在"が生物の1世代以上の長さを持つことは確かでしょう。しかし100万年もあるとも考えにくいでしょう。では何世代程度までの長さで働きうるのでしょうか? むろんそれは生物の生殖様式でも異なると考えられます。
ヒトやゾウで繁殖期を過ぎてもなお生存できる能力が進化した理由は、そのような高齢個体の経験が孫も含めた群れの個体の生存確率を高めるからだという仮説があります[Ref-2]。この仮説はおそらく正しいと考えられますが、だとするとこのような生物にとっての"現在"は少なくとも3世代程度あるわけです。
昆虫などでは1年の間に数世代を重ねる種も多くいます。それが冬になると様々な方法で冬越しをし、そのために他の季節とは異なる形態となります。すなわち冬越しのための遺伝子は、数世代の間眠っているだけで淘汰されることはなく、冬という危機的環境の到来で発動するのです。この場合の"現在"は1年間数世代以上あるのです。飛蝗(Locust)ともなると危機的環境の到来は不定期で、冬のように定期的に訪れるものでもありません。しかし、このように不定期にしかしある期間の間には必ず訪れる環境変化があれば、そのような環境変化に適応する形質が進化すると考えられます。いや、現に進化しています。しかし、"ある期間"とはどれくらいの長さなのでしょうか?
もしもあるとき冬が訪れなくなったとしましょう。冬のない期間が続けばその間に眠っている冬越し遺伝子はだんだんと中立進化を重ね、そのうちに冬越し遺伝子としては使い物にならない変異を起こすかも知れません。そこで突然また冬が訪れれば、冬越し遺伝子が使えるままだった個体のみが生き残ります。しかし冬のない期間がさらにずーっと続けば、そのうちに冬越し遺伝子は消滅する確率が高くなります。こう考えると"現在"の長さは中立進化の速さ、つまりはそれを決める突然変異頻度にも影響されると言えそうです。もしも冬越し遺伝子が100年くらいでも保存される確率が十分に大きければ、100年後に突然冬が来たとしても、この遺伝子を持つものだけが淘汰されることになります。
うーん、この程度の推論までは進化論の専門家ならすぐに考えると思うのだけど。
===========引用開始====下線は私の強調============
これら自然選択説の盲点を考え合わせると、働かない働きアリの存在も、あながち進化の原則と矛盾していないと思えます。彼らには直近の未来の効率ではなく、遠い未来の存続可能性に反応した進化が起こっている、と私自身は考えています。みながいっせいに働くシステムは直近の効率が高くても、未来の適応度は低いのです。
===========引用終り===============================
矛盾なんかしていません。遠い未来と言っても何十世代も未来とも思えません。本書にも書いてあるように、働く意欲が均一な集団は一斉に働いて一斉に疲れてそれっきり、と割と簡単に消滅しそうです。だとするとこんな形質が存在できるはずもなく、つまりは働かない働きアリのいる集団しか残らない、となりますね。メカニズムから見ても何十世代どころか一世代の期間で差がつくのではないでしょうか? 「みながいっせいに働くシステムは直近の効率が高い」なんて「常に全力で活動する個体は直近の効率が高い」と言うのと同じで、確かに高いかも知れないけれど、生き方はへただね、てことですよね。
===========引用開始====下線は私の強調============
アミメアリのチーターと利他的なワーカーが、個体レベルとコロニーレベルで逆向きの増殖率を示して長期間共存し続けることや、働かない働きアリのいる短期的効率の低いコロニーのほうが長期的な存続可能性が高いことなどは、一見、「適応度の高いものが進化する」という単純な進化の法則に反する事例です。これらの事例は最後に残るものが進化する、という意味では既存の理論に反してはいませんが、時間、空間の広がりのなかで肝心の適応度のカウントをどのレベルまで行うべきなのか、という点でいままでの考え方とは異なる新しい考え方を導入しています。
===========引用終り===============================
同意。まっとうすぎるほどにまっとうな推論です。いや「最後に」とはいつのことなんだ、というまじめな突っ込みはできますが(^_^)。本当に他の進化研究者たちは、これらの事例が「適応度の高いものが進化する」という単純な進化の法則に反するという議論をしたのでしょうか? それほど他の研究者が頭が悪いとは信じられないのですが。だんだんわからなくなってきました。
でも確かに個別事例での適応とか自然淘汰のタイムスパンが実際にどれくらいなのかとか、本書で定義される"群選択"が実際に働いていることを実証するとか、色々と課題はありますね。長谷川英祐準教授にも頑張ってもらって、またおもしろい本を書いてほしいですね。
と、ここまで書いて再度読み直したところ、著者の言う「効率」という言葉の使い方のヒントと思える記載がありました。p100-101の"群選択説"の実証観察事例の話です。まずは鳥や哺乳類の一部で見られる、子が親の子育てを助ける"ヘルパー"と呼ばれる行動の進化についてです。
===========引用開始====下線は私の強調============
特定の血縁を助けることで自分の遺伝子が特に多く残るという効果はないため、子どもが親を手伝う場合、親が残す子どもの数がグループサイズに対して2匹なら2倍以上、3匹なら3倍以上に大きくなる相乗効果がないと、独立して繁殖するよりも有利になりません。つまり、そもそもグループをつくるメリットがないと協力行動は進化してこなかったのではないかという疑問が出されたわけです。
===========引用終り===============================
で、こうした鳥や哺乳類についての実証研究が行われているのですが。
===========引用開始====下線は私の強調============
もちろん、われらが真社会性昆虫でもグループをつくる効果の研究は行われていますが、いまのところ複数の個体が協力しても幼虫の生産数が協力者の数の効果を超えて大きくなることはないようだという、相乗効果を否定する結果が得られています。
===========引用終り===============================
えっ、まさか幼虫の数そのものを適応度の指標にしたのでしょうか? 適応度は次世代をどれだけ残せるかを測る指標でなくてはならないので、少なくとも繁殖年齢まで生き残る幼虫の数でないと意味がないはずです。そもそもこの幼虫ってどの幼虫? 社会性昆虫の幼虫のほとんどは子孫を残さないワーカーです。そんなものがいくら増えても筋肉細胞だけ増えてマッチョになった個体と同じことで、必ずしも子孫を残す能力の向上に直結するわけではありません。鳥や哺乳類とは事情が違います。
遺伝子頻度変化の理論で個体群の大きさを表す有効個体数という概念がありますが[*3]、これは群の実際の個体数ではなく繁殖に関与できる個体数を意味する量で、真社会性昆虫の場合は王と女王しか数には入れないはずです。だから繁殖可能な次代の女王や王の幼虫数ならまだ指標の資格があります。が、それを選別して数えるのはちと苦労しそうな気がします。
===========引用開始====下線は私の強調============
しかし、アメリカ・アリゾナ州立大学のリッシング博士らは、最初に巣をつくるときに血縁関係のない複数の女王が集合して巣を創設するハキリアリの一種を用いて、グループ形成が巣の生存確率を高めることを示しました。このアリではグループサイズが大きいほど、相乗的ではないにしろ、たくさんの働きアリをつくることができました。その結果として、やがて近隣の巣とのあいだで行われる殺し合いに勝ち、生き残ることができるというのです。
このことから、相乗効果はグループの生産性に対してだけ現れるのではなく、生存率や捕食者に対する抵抗力などの生態的なパラメータを大幅に改善する効果にも現れ得るといえます。私たちもコハナバチを材料にして、グループをつくったときのほうが、幼虫の捕食者である地中性のアリに対して防御力が高まり、巣の中にいるメスの数に応じて幼虫の生存率が改善されるという結果を公表しています。
===========引用終り===============================
私から見るとどうも用語の真意が混乱していて読み取りにくいのですが、生産性=幼虫数(ほとんどワーカー)、幼虫の生存率=成虫(ほとんどワーカー)となる幼虫の割合、といったところでしょうか。やっぱりワーカーの生産性なんですね。筋肉が増えてマッチョになれば子供を守れる強い親になり、結果として子孫を残す確率が高くなる、わかりやすい結論ですね。
結論として、群の中のワーカーの数、もしあればワーカー中の種々のカーストの比率、などは適応度に影響する形質ではあっても適応度そのものではない。でもカーストの比率を決める遺伝子なんて誰が持っているのでしょうか? ちょっとおもしろいミステリーかも知れません。
終章の後半以降には著者の哲学みたいなものが現れていておおむね同意なのですが。
===========引用開始====下線は私の強調============
進化は、永遠に終わることのない過程ですが、もしも「完全な適応」が生じれば進化は終わります。私は講義のなかで学生に「すべての環境で万能の生物がいれば、進化は終わるのか?」という問いを必ず投げかけます。全能の生物がもしいれば、どのような環境でも競争に勝てるため、世界にはその生物しかいなくなるからです。進化とはそんな、存在しない「神」を目指す長い道行きだともいえるでしょう。と同時に、なぜそのような生物が存在しないのか、理由を考えることも、生物を理解するうえでは大切な姿勢だといえるでしょう(もちろん理由はありますが、それはみなさんのお楽しみにしておきます)。
===========引用終り===============================
なんだ理由は心得ているんだ、イジワルな先生だなあ(^_^)。まじめな顔して、まるでラマルク以降の定向進化説を基にしているかのような質問で学生を煙に巻くなんて。全能生物と銘打つような生物はSFには色々でてきたように思いますが、実在ではフィエステリア・ピシシーダ(Pfiesteria piscicida)などが随分と全能生物に見えます[*4]。が、決して上記質問で定義されるような真の全能生物ではありません。せいぜい万能生物くらいでしょうか?(^_^)
まあ定向進化理論はホモ・サピエンスの感覚にすっと入るところがあるらしいですから、そこを論理で打ち砕くことを自力でやってみることは科学者の訓練として大切かも知れません。獅子はわが子を千尋の落とし穴に突き落として這い上がるのを待つ・・・厳しいーー。
-------------------------
Ref-1a) 長谷川 英祐『働かないアリに意義がある (メディアファクトリー新書)』メディアファクトリー(2010/12/21), ISBN-13: 978-4840136617
Ref-1b) 長谷川 英祐 『働かないアリに意義がある (中経の文庫)』KADOKAWA (20160/06/14), ISBN-13: 978-4046016287
Ref-2) 「祖父母がもたらした社会の進化」日経サイエンス(2011/11)
-------------------------
*1) 英語版wikipediaには、利己的遺伝子説全般についてのGene-centered view of evolution、ドーキンスの著書と考えについてのThe Selfish Gene、もっとも狭い意味のSelfish DNA、と3つの記事がある。
*2) 見方の問題とも言えるので、必ずしも間違いとは言えないのかも知れない。ややこしいので本記事では省略。
*3) ここでの個体群とは交配可能な集団のことであり、本書の群は多くの場合はひとつの巣の中の集団のことだから意味は違う。しかし進化を論じるなら子孫を残せる個体の数で考えないといけないことは変わらないはず。
*4) 「魚を襲う凶暴な藻類フィエステリア」日経サイエンス(1999/10,p58)、岡田健吉のまとめ記事も参照のこと。
一言で言って非常におもしろい。序章で人間社会との比較も交えてつかみを取り、1章で「働き者のアリ」という固定観念が正確な観察により打ち砕かれ、2-5章では他の生物の実例も交えて、働かないアリの存在する理由(進化論的理由・メカニズム的理由等)を解説しています。各章の最後には章のポイントを箇条書きしてあり非常に親切です。この人は伝え方がうまい。
私の知らなかったことも多々あって勉強になりました。例えば、「こうしたコロニー内の裏切り者は英語の「だます(cheat)者」の意から「チーター」と呼ばれます。」ということ[p116]。いや実は最近はチートの方をよく知っていたもので・・。
他にも、粘菌でのチーターとか[p117]、群れ全体が完全クローンのアリとか[p128-129]、ヤマトシロアリにおける女王の遺伝子と王の遺伝子との生き残り合戦とか[p129-132]、「雌雄は同じ母親から生まれ、交尾もし、ワーカーも両者の遺伝子の混合物としてつくるのに、オスとメス自体は遺伝的に完全な「別種」となっている」アリとか[p137-140]、まさに奇々怪々の世界ですね。ちなみに後の2つの例は、受精卵が産まれるまでのどこかで母由来の遺伝子と父由来の遺伝子を選別するメカニズム、おそらくは生化学的・分子生物学的なメカニズムが働いているわけであり、ドーキンスの定義した"利己的遺伝子"(Selfish Gene)よりも狭い意味での、遺伝子レベルでの進化研究でよく使われる"利己的遺伝子"の実例としてもわかりやすいですね[*1]。
さて「第3章 なんで他人のために働くの?」では真社会性の進化に関する"血縁選択説"と"群選択説"との対立を解説しています。ここで誤解してはならないのは"群選択説"という言葉にはウィキペディアの記事でもわかるように複数の意味があるということです。この本での"群選択説"というのは次のような仮説です。
===========引用開始====下線は私の強調============
利他者と利己者がいれば、メンバー間に相互に利害関係のある「群(ぐん)」が必ずできます。このとき、利他者と利己者のあいだに血縁関係がなかったとしても、群全体の1個体あたりの生産性が、単独のときより大きくなることがあれば、利他者が自らの子どもの数を減らして利己者に尽くしてなお、単独でいるよりも適応度(自分の遺伝子が生き残る率)が高くなるのではないか、という議論です。
この考え方は「群選択」と呼ばれており、1980年頃から議論され始めました。群を形成する効果として、個体の適応度をあげる力が生じていると考えるのが「群選択説」です。この仮説を裏付けるために必要な、協力者数の増加以上に利益があがる効果を「相乗効果(シナジー)」と呼びます。
===========引用終り===============================
そもそも群れること自体に利益があり、その利益を受けるためには利他的形質が必要になる、という話ですね。
"群選択説"を「自然選択される単位は群である」としてドーキンスの"利己的遺伝子説"「自然選択される単位は遺伝子である」の対立仮説と捉えると、現在の定説では間違いとなるでしょう[*2]。とはいえ、群が多数あり、その生成消滅が頻繁で子孫残しに失敗した群(の個体の遺伝子)は消滅する、という状況では、ほぼ「群の淘汰=遺伝子の淘汰」ということにはなるでしょう。極端な話、多細胞生物の個体というのは細胞の群です。そして生殖細胞以外の体細胞は、働きアリと同様に自らは子孫を残すことができません。まあ時には勝手に増えようとする突然変異体が生じたりもしますが、そのような遺伝子はむろん細胞群(個体)と共に消滅し、末永く続くことはできません。すなわち、生殖細胞を差し置いて勝手に増えようとする"遺伝子"はもはや適応度0なのです。
一言いうと、ここで「生産性」という言葉を使ってしまったあたりが混乱を招いたようにも思えます。いやむしろ問題意識を産んだと肯定的に捉えるべきかな。
この議論は理解自体も複雑なのでまたの機会ということにして、著者自身の見解は第3章の「向き合わない両者」という項で示されています。
===========引用開始====下線は私の強調============
私なりの意見を言うと、両者は同じ土俵に立っていないように思えます。
(中略)
同じものを測るのに両者で使っているモノサシが違うようなもので、これが議論が混乱
、する原因と思われます。
(中略)
ともあれ私個人は、群の効果がなくても利他行動が進化し得るという単数倍数性生物の特徴が、このグループにおける真社会性の高頻度な進化をもたらしたのは間違いなく、そのうえで「群の効果があり、その結果として増えた子孫との血縁関係の濃さにより包括適応度が高まる」のであり、群と血縁の両者ともが、利他者の包括適応度を測るために不可分なものと認識しています。現象内に含まれるすべての要因を明示して、その関係性を示すモデルをつくることが、今後は重要になるでしょう。
===========引用終り===============================
こうして両説は止揚されたのでした。当たり前の結論がもっとも真相に近いということですね。
「第5章「群れ」か「個」か、それが問題だ」では上記の「多細胞生物の個体というのは細胞の群とも考えられる」ということも含めて、群というものが生じる、または生じないメカニズムの話が展開されています。
そして「終章その進化はなんのため?」の冒頭「食べ始めたとき、進化した」の項では自然選択説をしっかりと解説しています。しかし次の「自然選択説の限界」から、私にとってはちょっと混乱を招く表現が出てきます。
===========引用開始====下線は私の強調============
この大原則は、「この世代」で「強いもの」が生き残るという思想です。いまこの世代における強弱のみが問題であり、短期的な効率が高いものが最後に残るはずだと言い換えることもできます。ところが、働かない働きアリについては、短期的に高効率なシステムより低効率なものが残るという結論になっています。なぜこんなことになるのでしょうか?「自然選択のもとでは適者生存」という鉄則自体が間違っているのでしょうか?
===========引用終り===============================
私としては「言い換えないでほしかった」と思います。この言い換えはずいぶん誤解を招くと思います。しかし以降をよく読むと、長谷川英祐準教授の考えはまともなものに思えますし、彼の指摘する論点は多くの進化学者の盲点になっていることも確かなのかも知れません。それは一言でいえば自然選択の働くタイムスパンの問題です。
===========引用開始====下線は私の強調============
適応度に基づく進化の考えにはもう一つ大きな問題があります。適応度は未来における値なので、測定する未来をどの時点に置くかで値が違ってくる可能性があるのです。通常は「次世代」または「孫の世代」での適応度を進化の指標にしますが、次世代で適応度が高いある性質も、何百世代もの未来で考えると、次世代で低い適応度しか示せない性質より適応度は低いのかもしれません。言い換えれば「ある生物がどのくらい未来の適応度に反応して進化しているのかはまったくわかっていない」のです。もしかすると、次世代の適応度に反応する遺伝子型と、遠い未来の適応度に反応する遺伝子型がいまこの瞬間も、私たちの体内で競争しているのかもしれません。しかし理論上にせよそんなことが検討されたことはいままでないのです。
===========引用終り===============================
"「次世代」または「孫の世代」での適応度"であれば"働かないアリを生じる遺伝子"の適応度は十分高いでしょう、というのが私のとらえ方だったので、それが自然選択説と矛盾するかのような言い方に違和感を感じていたのでした。テレビでの表現とか"短期的に高効率"とかだと、どうしても「当世代」での個体生存の適応度を指していると誤解しますよ。
それはともかく、長谷川英祐準教授の問題意識を私が理解した限りで、私の表現で書いてみます。
自然淘汰とは現在の環境が生物を淘汰するものです。まだ存在しない未来の環境というものは、現在の生物に働きかけることはできません。また生物も未来環境を予測してそれに適応するという事は、できないはずです。しかしこの"現在"という期間は、どのくらいの長さを持つのでしょうか? 決して現時点という瞬間ではありえません。
自然淘汰が「子孫を残せるか否か」という基準で測られる以上、"現在"が生物の1世代以上の長さを持つことは確かでしょう。しかし100万年もあるとも考えにくいでしょう。では何世代程度までの長さで働きうるのでしょうか? むろんそれは生物の生殖様式でも異なると考えられます。
ヒトやゾウで繁殖期を過ぎてもなお生存できる能力が進化した理由は、そのような高齢個体の経験が孫も含めた群れの個体の生存確率を高めるからだという仮説があります[Ref-2]。この仮説はおそらく正しいと考えられますが、だとするとこのような生物にとっての"現在"は少なくとも3世代程度あるわけです。
昆虫などでは1年の間に数世代を重ねる種も多くいます。それが冬になると様々な方法で冬越しをし、そのために他の季節とは異なる形態となります。すなわち冬越しのための遺伝子は、数世代の間眠っているだけで淘汰されることはなく、冬という危機的環境の到来で発動するのです。この場合の"現在"は1年間数世代以上あるのです。飛蝗(Locust)ともなると危機的環境の到来は不定期で、冬のように定期的に訪れるものでもありません。しかし、このように不定期にしかしある期間の間には必ず訪れる環境変化があれば、そのような環境変化に適応する形質が進化すると考えられます。いや、現に進化しています。しかし、"ある期間"とはどれくらいの長さなのでしょうか?
もしもあるとき冬が訪れなくなったとしましょう。冬のない期間が続けばその間に眠っている冬越し遺伝子はだんだんと中立進化を重ね、そのうちに冬越し遺伝子としては使い物にならない変異を起こすかも知れません。そこで突然また冬が訪れれば、冬越し遺伝子が使えるままだった個体のみが生き残ります。しかし冬のない期間がさらにずーっと続けば、そのうちに冬越し遺伝子は消滅する確率が高くなります。こう考えると"現在"の長さは中立進化の速さ、つまりはそれを決める突然変異頻度にも影響されると言えそうです。もしも冬越し遺伝子が100年くらいでも保存される確率が十分に大きければ、100年後に突然冬が来たとしても、この遺伝子を持つものだけが淘汰されることになります。
うーん、この程度の推論までは進化論の専門家ならすぐに考えると思うのだけど。
===========引用開始====下線は私の強調============
これら自然選択説の盲点を考え合わせると、働かない働きアリの存在も、あながち進化の原則と矛盾していないと思えます。彼らには直近の未来の効率ではなく、遠い未来の存続可能性に反応した進化が起こっている、と私自身は考えています。みながいっせいに働くシステムは直近の効率が高くても、未来の適応度は低いのです。
===========引用終り===============================
矛盾なんかしていません。遠い未来と言っても何十世代も未来とも思えません。本書にも書いてあるように、働く意欲が均一な集団は一斉に働いて一斉に疲れてそれっきり、と割と簡単に消滅しそうです。だとするとこんな形質が存在できるはずもなく、つまりは働かない働きアリのいる集団しか残らない、となりますね。メカニズムから見ても何十世代どころか一世代の期間で差がつくのではないでしょうか? 「みながいっせいに働くシステムは直近の効率が高い」なんて「常に全力で活動する個体は直近の効率が高い」と言うのと同じで、確かに高いかも知れないけれど、生き方はへただね、てことですよね。
===========引用開始====下線は私の強調============
アミメアリのチーターと利他的なワーカーが、個体レベルとコロニーレベルで逆向きの増殖率を示して長期間共存し続けることや、働かない働きアリのいる短期的効率の低いコロニーのほうが長期的な存続可能性が高いことなどは、一見、「適応度の高いものが進化する」という単純な進化の法則に反する事例です。これらの事例は最後に残るものが進化する、という意味では既存の理論に反してはいませんが、時間、空間の広がりのなかで肝心の適応度のカウントをどのレベルまで行うべきなのか、という点でいままでの考え方とは異なる新しい考え方を導入しています。
===========引用終り===============================
同意。まっとうすぎるほどにまっとうな推論です。いや「最後に」とはいつのことなんだ、というまじめな突っ込みはできますが(^_^)。本当に他の進化研究者たちは、これらの事例が「適応度の高いものが進化する」という単純な進化の法則に反するという議論をしたのでしょうか? それほど他の研究者が頭が悪いとは信じられないのですが。だんだんわからなくなってきました。
でも確かに個別事例での適応とか自然淘汰のタイムスパンが実際にどれくらいなのかとか、本書で定義される"群選択"が実際に働いていることを実証するとか、色々と課題はありますね。長谷川英祐準教授にも頑張ってもらって、またおもしろい本を書いてほしいですね。
と、ここまで書いて再度読み直したところ、著者の言う「効率」という言葉の使い方のヒントと思える記載がありました。p100-101の"群選択説"の実証観察事例の話です。まずは鳥や哺乳類の一部で見られる、子が親の子育てを助ける"ヘルパー"と呼ばれる行動の進化についてです。
===========引用開始====下線は私の強調============
特定の血縁を助けることで自分の遺伝子が特に多く残るという効果はないため、子どもが親を手伝う場合、親が残す子どもの数がグループサイズに対して2匹なら2倍以上、3匹なら3倍以上に大きくなる相乗効果がないと、独立して繁殖するよりも有利になりません。つまり、そもそもグループをつくるメリットがないと協力行動は進化してこなかったのではないかという疑問が出されたわけです。
===========引用終り===============================
で、こうした鳥や哺乳類についての実証研究が行われているのですが。
===========引用開始====下線は私の強調============
もちろん、われらが真社会性昆虫でもグループをつくる効果の研究は行われていますが、いまのところ複数の個体が協力しても幼虫の生産数が協力者の数の効果を超えて大きくなることはないようだという、相乗効果を否定する結果が得られています。
===========引用終り===============================
えっ、まさか幼虫の数そのものを適応度の指標にしたのでしょうか? 適応度は次世代をどれだけ残せるかを測る指標でなくてはならないので、少なくとも繁殖年齢まで生き残る幼虫の数でないと意味がないはずです。そもそもこの幼虫ってどの幼虫? 社会性昆虫の幼虫のほとんどは子孫を残さないワーカーです。そんなものがいくら増えても筋肉細胞だけ増えてマッチョになった個体と同じことで、必ずしも子孫を残す能力の向上に直結するわけではありません。鳥や哺乳類とは事情が違います。
遺伝子頻度変化の理論で個体群の大きさを表す有効個体数という概念がありますが[*3]、これは群の実際の個体数ではなく繁殖に関与できる個体数を意味する量で、真社会性昆虫の場合は王と女王しか数には入れないはずです。だから繁殖可能な次代の女王や王の幼虫数ならまだ指標の資格があります。が、それを選別して数えるのはちと苦労しそうな気がします。
===========引用開始====下線は私の強調============
しかし、アメリカ・アリゾナ州立大学のリッシング博士らは、最初に巣をつくるときに血縁関係のない複数の女王が集合して巣を創設するハキリアリの一種を用いて、グループ形成が巣の生存確率を高めることを示しました。このアリではグループサイズが大きいほど、相乗的ではないにしろ、たくさんの働きアリをつくることができました。その結果として、やがて近隣の巣とのあいだで行われる殺し合いに勝ち、生き残ることができるというのです。
このことから、相乗効果はグループの生産性に対してだけ現れるのではなく、生存率や捕食者に対する抵抗力などの生態的なパラメータを大幅に改善する効果にも現れ得るといえます。私たちもコハナバチを材料にして、グループをつくったときのほうが、幼虫の捕食者である地中性のアリに対して防御力が高まり、巣の中にいるメスの数に応じて幼虫の生存率が改善されるという結果を公表しています。
===========引用終り===============================
私から見るとどうも用語の真意が混乱していて読み取りにくいのですが、生産性=幼虫数(ほとんどワーカー)、幼虫の生存率=成虫(ほとんどワーカー)となる幼虫の割合、といったところでしょうか。やっぱりワーカーの生産性なんですね。筋肉が増えてマッチョになれば子供を守れる強い親になり、結果として子孫を残す確率が高くなる、わかりやすい結論ですね。
結論として、群の中のワーカーの数、もしあればワーカー中の種々のカーストの比率、などは適応度に影響する形質ではあっても適応度そのものではない。でもカーストの比率を決める遺伝子なんて誰が持っているのでしょうか? ちょっとおもしろいミステリーかも知れません。
終章の後半以降には著者の哲学みたいなものが現れていておおむね同意なのですが。
===========引用開始====下線は私の強調============
進化は、永遠に終わることのない過程ですが、もしも「完全な適応」が生じれば進化は終わります。私は講義のなかで学生に「すべての環境で万能の生物がいれば、進化は終わるのか?」という問いを必ず投げかけます。全能の生物がもしいれば、どのような環境でも競争に勝てるため、世界にはその生物しかいなくなるからです。進化とはそんな、存在しない「神」を目指す長い道行きだともいえるでしょう。と同時に、なぜそのような生物が存在しないのか、理由を考えることも、生物を理解するうえでは大切な姿勢だといえるでしょう(もちろん理由はありますが、それはみなさんのお楽しみにしておきます)。
===========引用終り===============================
なんだ理由は心得ているんだ、イジワルな先生だなあ(^_^)。まじめな顔して、まるでラマルク以降の定向進化説を基にしているかのような質問で学生を煙に巻くなんて。全能生物と銘打つような生物はSFには色々でてきたように思いますが、実在ではフィエステリア・ピシシーダ(Pfiesteria piscicida)などが随分と全能生物に見えます[*4]。が、決して上記質問で定義されるような真の全能生物ではありません。せいぜい万能生物くらいでしょうか?(^_^)
まあ定向進化理論はホモ・サピエンスの感覚にすっと入るところがあるらしいですから、そこを論理で打ち砕くことを自力でやってみることは科学者の訓練として大切かも知れません。獅子はわが子を千尋の落とし穴に突き落として這い上がるのを待つ・・・厳しいーー。
-------------------------
Ref-1a) 長谷川 英祐『働かないアリに意義がある (メディアファクトリー新書)』メディアファクトリー(2010/12/21), ISBN-13: 978-4840136617
Ref-1b) 長谷川 英祐 『働かないアリに意義がある (中経の文庫)』KADOKAWA (20160/06/14), ISBN-13: 978-4046016287
Ref-2) 「祖父母がもたらした社会の進化」日経サイエンス(2011/11)
-------------------------
*1) 英語版wikipediaには、利己的遺伝子説全般についてのGene-centered view of evolution、ドーキンスの著書と考えについてのThe Selfish Gene、もっとも狭い意味のSelfish DNA、と3つの記事がある。
*2) 見方の問題とも言えるので、必ずしも間違いとは言えないのかも知れない。ややこしいので本記事では省略。
*3) ここでの個体群とは交配可能な集団のことであり、本書の群は多くの場合はひとつの巣の中の集団のことだから意味は違う。しかし進化を論じるなら子孫を残せる個体の数で考えないといけないことは変わらないはず。
*4) 「魚を襲う凶暴な藻類フィエステリア」日経サイエンス(1999/10,p58)、岡田健吉のまとめ記事も参照のこと。










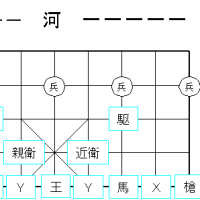
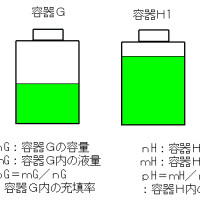
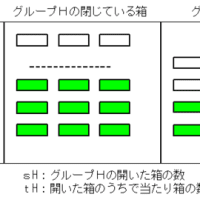
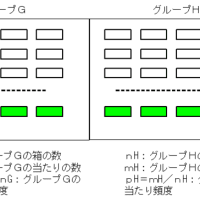
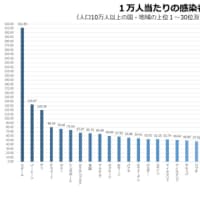
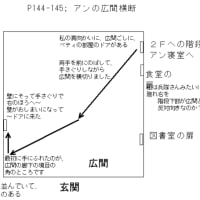
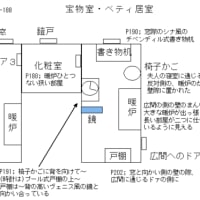

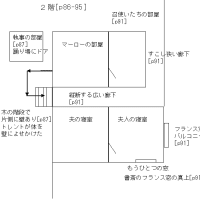
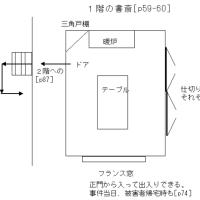







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます