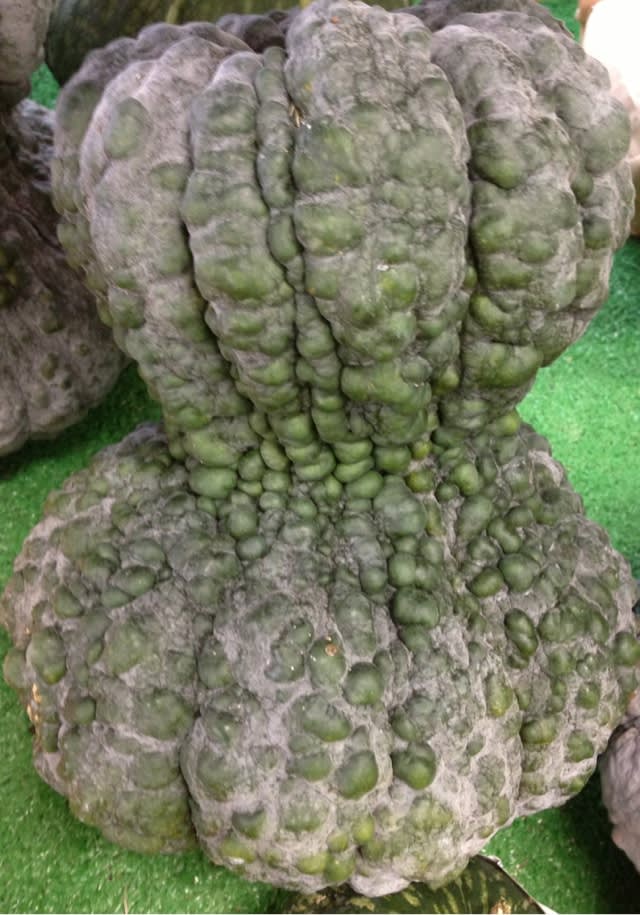昨日、川釣りが趣味の友人からアマゴをいただいた。
奈良県下北山村出身のアマゴ。20匹ほど釣れた中の選りすぐりの5匹だとか。釣り人の想いと自然に深く感謝し、塩焼きにして美味しくいただいた。
山の幸で季節を感じるように私はいつも友人からいただく川魚で季節を感じる。
3月になって一斉にアマゴ釣りが解禁、いよいよ春がやって来たのだ。
鮎をいただくと梅雨近し…ということになる^ ^
ところでアマゴの語源を「雨後」とする説がある。雨が降り出すとよく釣れる魚という意味である。
なるほど!昨夕から降り出した雨が今もまだ降り続いている。
降り出すと長いこの時期の雨に昔の人は「菜種梅雨」という名前をつけた。この「菜種梅雨」、実はこんな風にも呼ばれている。「催花雨(さいかう)」、いろいろな花を催す(咲かせる)という意味である。
この雨が上がると南の方から桜の花便りが届きそうだ。
「雨後」「菜種梅雨」「催花雨」いずれも、昔の人がどれほど自然と向き合って暮らしていたかを感じる名前である。

奈良県下北山村出身のアマゴ。20匹ほど釣れた中の選りすぐりの5匹だとか。釣り人の想いと自然に深く感謝し、塩焼きにして美味しくいただいた。
山の幸で季節を感じるように私はいつも友人からいただく川魚で季節を感じる。
3月になって一斉にアマゴ釣りが解禁、いよいよ春がやって来たのだ。
鮎をいただくと梅雨近し…ということになる^ ^
ところでアマゴの語源を「雨後」とする説がある。雨が降り出すとよく釣れる魚という意味である。
なるほど!昨夕から降り出した雨が今もまだ降り続いている。
降り出すと長いこの時期の雨に昔の人は「菜種梅雨」という名前をつけた。この「菜種梅雨」、実はこんな風にも呼ばれている。「催花雨(さいかう)」、いろいろな花を催す(咲かせる)という意味である。
この雨が上がると南の方から桜の花便りが届きそうだ。
「雨後」「菜種梅雨」「催花雨」いずれも、昔の人がどれほど自然と向き合って暮らしていたかを感じる名前である。