山田映画のユーモアとペーソス 関川宗英

1960年代は、大島渚、篠田正浩、吉田喜重といった気鋭の新人が松竹ヌーヴェルヴァーグとして活躍していた時代であった。日本映画界は巨大な産業システムを維持できず斜陽化していく中、独立プロが次々と生まれていく。ヌーヴェルヴァーグ派も松竹から独立して行き、大島渚がテレビドキュメンタリーに挑戦し、『白昼の通り魔』(1966年)など政治色の強い作品を次々と発表すれば、吉田喜重も独立プロを作り、『エロス+虐殺』などの話題作がアートシアターギルド(ATG)系で公開されるなど傾きかけた映画界の話題をさらっていた。その中で、山田洋次は地味な存在であったといえる。松竹大船調路線を継承し、『下町の太陽』、『馬鹿まるだし』等のコメディを中心とした作品で企業内監督の道を歩むことになる。
市井の人々のささやかな喜びやかなしみを描くこと、これが「松竹大船調」の目指す映画だった。松竹大船調とは、松竹大船撮影所の初代所長城戸四郎によるものとされる。それは次のような映画作りのコンセプトである。
(1)映画は何よりもまず、大衆に喜ばれなければならない
(2)観客は金持ちでなくてよい。平凡な庶民と若者を重視せよ
(3)映画のストーリーに人間の愛情物語を欠かすな
(4)とくに「親子愛」「男女の愛」を無視するな
(5)だれであれ、人生に希望を持たせるストーリーにせよ
(6)映画にシナリオは最重要である
(7)画面に登場の人物のキャラクターをしっかり把握して演出し、演技させよ。
次第に喜劇作家としての評価が高まりつつあった山田洋次は、1969年、『男はつらいよ』を発表する。当初は観客動員も地味であったが高い評判を呼んだ。輪番であった監督が山田単独となる頃から尻上がりに観客も増え、その後27年間に全48作が製作される大ヒットシリーズとなる。「寅さんシリーズ」は毎年お盆と暮れの松竹映画の看板となり、日本人の風物詩、国民的映画とまで言われた。
山田洋次は、松竹大船調の正統的な後継者といえる。フランスのヌーベルバーグは、カメラをスタジオから街に持ち出し、映画を解放したと言われた。スタジオの照明ではなく自然の光による屋外のロケーション撮影を実現することで、ドキュメンタリズム、リアリズムなど新たな映画の地平を切り開いた。ヌーベルバーグが世界を席巻し、その波が日本にも届き、松竹ヌーベルバーグが脚光を浴びていた頃、山田洋次はスタジオの中で映画を撮り続けていた。そして、80本以上の映画を作り、今や映画界の巨匠として君臨している。
山田洋次の映画には、奇想天外なストーリーはない。波瀾万丈の人生もない。ハラハラ、ドキドキの活劇とは正反対の、平凡な人々のありふれた生活が描かれる。
山田洋次は次のように語っている。
悲しい出来事を涙ながらに訴えるのは易しい。また、悲しい事を生真面目な顔で物語るのもそう難しいことではない。しかし、悲しい事を笑いながら語るのはとても困難なことである。だが、この住み辛い世の中にあっては、笑い話の形を借りてしか伝えられない真実というものがある。(「喜劇の意味」松竹映画ホームページより)
山田映画のユーモアとペーソス。フーテンの寅さんの滑稽さは、下町で遠くの高層ビルを見上げながら生きる者達の悲哀の裏返しでもある。誰にでも希望を感じさせる映画を作れ、松竹大船調を受け継いだ山田洋次だが、彼の映画は庶民のささやかな幸せを描きながら登場人物のそれぞれが抱えている悲哀を感じさせるものとなっている。
「フーテンの寅さん」には人生が語られている。いただき物のメロンを食べようとしたところに寅が帰ってきて大騒ぎとなるシーンに笑い、桜がしわくちゃの千円札を寅に渡すシーンに涙する。そんな寅と桜をまた見たくて、観客は映画館に足を運んだのだろう。そして、シリーズは48本までになる。寅のお膝元、浅草の二番館では今も「フーテンの寅さん」が上映される。2000年頃に浅草の二番館に足を運んだことがあるが、寅が例のごとく旅立って映画が終わると、場内から拍手が起きたものだった。笑いながら涙が出てくる、「フーテンの寅さん」。山田映画は、人生の深みを感じさせる一本だから、多くの人々の支持が得られたのだろう。

1960年代は、大島渚、篠田正浩、吉田喜重といった気鋭の新人が松竹ヌーヴェルヴァーグとして活躍していた時代であった。日本映画界は巨大な産業システムを維持できず斜陽化していく中、独立プロが次々と生まれていく。ヌーヴェルヴァーグ派も松竹から独立して行き、大島渚がテレビドキュメンタリーに挑戦し、『白昼の通り魔』(1966年)など政治色の強い作品を次々と発表すれば、吉田喜重も独立プロを作り、『エロス+虐殺』などの話題作がアートシアターギルド(ATG)系で公開されるなど傾きかけた映画界の話題をさらっていた。その中で、山田洋次は地味な存在であったといえる。松竹大船調路線を継承し、『下町の太陽』、『馬鹿まるだし』等のコメディを中心とした作品で企業内監督の道を歩むことになる。
市井の人々のささやかな喜びやかなしみを描くこと、これが「松竹大船調」の目指す映画だった。松竹大船調とは、松竹大船撮影所の初代所長城戸四郎によるものとされる。それは次のような映画作りのコンセプトである。
(1)映画は何よりもまず、大衆に喜ばれなければならない
(2)観客は金持ちでなくてよい。平凡な庶民と若者を重視せよ
(3)映画のストーリーに人間の愛情物語を欠かすな
(4)とくに「親子愛」「男女の愛」を無視するな
(5)だれであれ、人生に希望を持たせるストーリーにせよ
(6)映画にシナリオは最重要である
(7)画面に登場の人物のキャラクターをしっかり把握して演出し、演技させよ。
次第に喜劇作家としての評価が高まりつつあった山田洋次は、1969年、『男はつらいよ』を発表する。当初は観客動員も地味であったが高い評判を呼んだ。輪番であった監督が山田単独となる頃から尻上がりに観客も増え、その後27年間に全48作が製作される大ヒットシリーズとなる。「寅さんシリーズ」は毎年お盆と暮れの松竹映画の看板となり、日本人の風物詩、国民的映画とまで言われた。
山田洋次は、松竹大船調の正統的な後継者といえる。フランスのヌーベルバーグは、カメラをスタジオから街に持ち出し、映画を解放したと言われた。スタジオの照明ではなく自然の光による屋外のロケーション撮影を実現することで、ドキュメンタリズム、リアリズムなど新たな映画の地平を切り開いた。ヌーベルバーグが世界を席巻し、その波が日本にも届き、松竹ヌーベルバーグが脚光を浴びていた頃、山田洋次はスタジオの中で映画を撮り続けていた。そして、80本以上の映画を作り、今や映画界の巨匠として君臨している。
山田洋次の映画には、奇想天外なストーリーはない。波瀾万丈の人生もない。ハラハラ、ドキドキの活劇とは正反対の、平凡な人々のありふれた生活が描かれる。
山田洋次は次のように語っている。
悲しい出来事を涙ながらに訴えるのは易しい。また、悲しい事を生真面目な顔で物語るのもそう難しいことではない。しかし、悲しい事を笑いながら語るのはとても困難なことである。だが、この住み辛い世の中にあっては、笑い話の形を借りてしか伝えられない真実というものがある。(「喜劇の意味」松竹映画ホームページより)
山田映画のユーモアとペーソス。フーテンの寅さんの滑稽さは、下町で遠くの高層ビルを見上げながら生きる者達の悲哀の裏返しでもある。誰にでも希望を感じさせる映画を作れ、松竹大船調を受け継いだ山田洋次だが、彼の映画は庶民のささやかな幸せを描きながら登場人物のそれぞれが抱えている悲哀を感じさせるものとなっている。
「フーテンの寅さん」には人生が語られている。いただき物のメロンを食べようとしたところに寅が帰ってきて大騒ぎとなるシーンに笑い、桜がしわくちゃの千円札を寅に渡すシーンに涙する。そんな寅と桜をまた見たくて、観客は映画館に足を運んだのだろう。そして、シリーズは48本までになる。寅のお膝元、浅草の二番館では今も「フーテンの寅さん」が上映される。2000年頃に浅草の二番館に足を運んだことがあるが、寅が例のごとく旅立って映画が終わると、場内から拍手が起きたものだった。笑いながら涙が出てくる、「フーテンの寅さん」。山田映画は、人生の深みを感じさせる一本だから、多くの人々の支持が得られたのだろう。










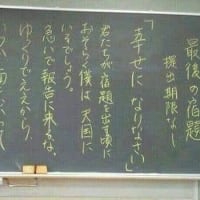

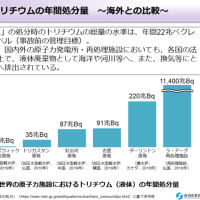
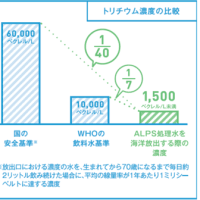
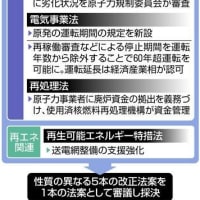


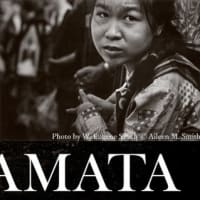








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます