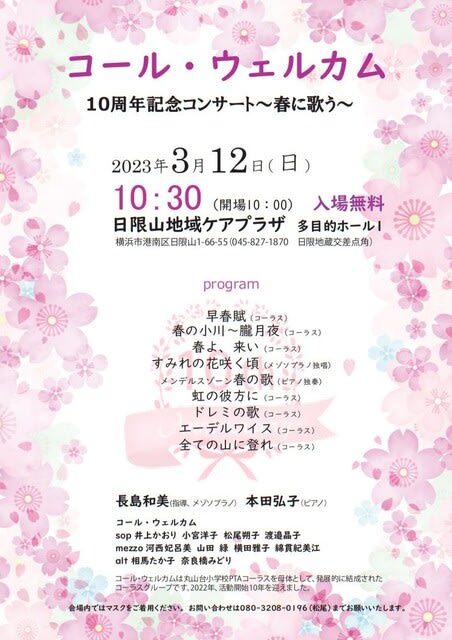日本初の世界的プリマドンナ、三浦環さん。

現在(再)放送中のNHK連続テレビ小説「エール」にも、環さんがモデルと目される双浦環という人物が登場しています。
コメディ調のドラマからは推し量ることができませんが、三浦環さんご自身は、日本の声楽界のパイオニアであり、ロンドンのアルバートホール、ニューヨークのMETなどでオペラのタイトルロールを務められた偉人でもあります。
現在でも刊行がつづく「婦人公論」に、環さんが何号かにわたって自叙伝を寄せていますので、すこしご紹介します。
三浦環さんのご生家は、静岡県朝日奈村で酒造業を営んでいました。お父さんが柴田孟甫さん、お母さんがとわ子さん。
(とわ子さんが嫁いだ時にお姑さん40代だったとか!)
このお姑さんが「朝日奈小町といわれた位、近郷近在に鳴り響いた器量好しで就中(なかんずく)声の美しいことは評判だった。かげでは鶯(うぐいす)小町などというものさえあったそうだ。」とのこと。お姑さんが農作業をしながら歌を歌うと、その声の美しさにみな足を止め、そしてその若々しい美貌も評判だったそうです。
環さんは、男の子ふたりの後に初めての女の子として生まれました。残念なことに兄二人は早世したため、「男の子が育たなかったから、今度は女乍ら(ながら)男のように育てる」と、お父さんは長女に「環」という名前を付けました。
体格がよく、豪胆な性格のお父さんは、酒造業でなした財を東京で生かし、一旗揚げようと静岡から現在の東京・芝のあたりに引っ越しをされます。現在の虎の門あたりに居を構えた柴田家は、のちに公証役場を開くお父さんが明治大学の学生に、お母さんがお針上手の腕前を生かしてお裁縫の先生をします。そして環さんには二人の乳母がつき、文字通り「乳母日傘」で育ったといいます。
芸事が好きなお父さんの教育方針で、環さんは3歳のころには藤間流の日本舞踊を、また同時に山田流のお琴、6歳のころには長唄のお稽古を始めました。このあたりの様子を環さんは「まったく音楽漬けのような生活」と述べていらっしゃいます。

小学校のときに、音楽の植村先生がおっしゃった言葉が紹介されています。
(以下引用)
私が初めて君が代を歌った時、「まあ」といい乍らオルガンを弾く手をやめて、私の顔を見入ったものである。
「まあ、柴田さん、何といういいお声なんでしょう。私はこんな声の美しい生徒は初めてですよ。しっかり御やりなさいね」
と、植村先生は感嘆し乍ら、私に再三再四君が代を歌わせるのだった。
それからは音楽会や、学芸会のある度に、植村先生が、ヴァイオリンで伴奏して、私は君が代を歌わせられた。
(引用終わり)
まさに栴檀は双葉より芳しですね!
そして環さん14歳のみぎり、「虎の門女学院」(現在の東京女学館)に入学します。ここでもまた音楽の先生にその才能を認められ、上野の音楽学校(現在の東京芸大)への入学を勧められます。
ですが、お父さんが大反対。
(以下引用)
父はもとより大反対で、女に女学校以上の教育は不必要であるばかりでなく、ましてや音楽学校へ入れて西洋音楽など修めさせるとはもっての外、そんな西洋の音曲など習わして、西洋の芸者にでもさせるつもりかと、大立腹だった。
(引用終わり)
・・・時代ですね~~。
結局、芝から上野まで自転車で通う、結婚相手と目星をつけていた藤井善一という軍医と結婚する、という2つの条件をつけられて環さんは声楽科の学生になりました。(藤井軍医は中国に赴任し5年間戻らない予定で、いいなずけの帰りを待つあいだ学生をすればいいということだったようです)

このように、環さんの「西洋音楽」学習の旅が始まりました。
波乱万丈のこの続きはまた改めて。