昨晩遅く帰宅して、津波のニュースに目を見張りました。
地震自体の規模もさることながら、津波だけでも被害者が1万4000人とのこと。時間が経つにつれ、報道される死者の数もどんどん増えています。
津波に関しては、現地では警報システムが整っておらず、知らずに巻き込まれた人が大勢いるようです。
突然襲ってくる地震という天災は避けることができません。また、防波堤や防潮堤の不備もあったでしょう。でも、警報さえ出ていれば津波による被害者はもっと少なくて済んだのではないかと思うと、本当に胸が痛みます。
わたしの母は宮城県の塩釜市という港町で育ち、チリ津波を体験しています。こどもの頃から、津波の話は母からも、祖母からも、何度も聞きました。
小さな山の上に建った母の実家からは、港が一望できました。
その日は朝から、港の中を船がくるくると回っていて、母はお祭りのようだと思ったそうです。
お祭りの日、湾内の遊覧船がパレードをする様子にそっくりだったのです。
しかし、ふと水平線をみると、向こうの海が盛り上がって真っ黒な壁のようになっていて、お祭りではないと分かりました。「津波というけれど、あんなものが波だとは思えなかった」と言います。
記録を調べると、波の高さは日本では1mから最大でも5mとのことですから、きっと海面自体が盛り上がっていたことと、その後の被害の様子とを合わせ覚えて、より大きく高い恐ろしいものとして記憶されているのかもしれません。
ともあれ、母の記憶の中では、海の壁は近づくにつれてどんどん大きく高く見えるようになり、あっという間に港町に襲い掛かりました。
波が近づく様子も、その波が全てを押し流した様子も、山の上の家からはすべてが見えていました。やがて、人びとが山の上を目指してどんどん逃げてきました。
祖母はその頃には大慌てで家中の釜いっぱいにご飯を炊き、家族総出でおにぎりを作って登ってきた人たちに分けたそうです。
このチリ津波以降、太平洋では国際的な警報システムが整備されたとのことですが、なによりも、地震があればそれが遠い外国の話であっても津波が来る可能性があるということ、そしてその津波がどれだけ恐ろしいものなのかということを実感し、わたし達日本人も含め被害地域の人間は意識が変わったのだと思います。
同じアジアのこんなに近い国にいながら、そしてこんなに情報が伝わりやすい世の中になっているのにもかかわらず、その教訓を共有することなく新たな津波被害が出てしまったことに、悔しい思いを感じます。
日本政府も支援を惜しまないとの報道がされています。
医療、物資や復旧支援はもちろんのこと、警報システムの普及もぜひ力を入れてもらいたいです。
地震自体の規模もさることながら、津波だけでも被害者が1万4000人とのこと。時間が経つにつれ、報道される死者の数もどんどん増えています。
津波に関しては、現地では警報システムが整っておらず、知らずに巻き込まれた人が大勢いるようです。
突然襲ってくる地震という天災は避けることができません。また、防波堤や防潮堤の不備もあったでしょう。でも、警報さえ出ていれば津波による被害者はもっと少なくて済んだのではないかと思うと、本当に胸が痛みます。
わたしの母は宮城県の塩釜市という港町で育ち、チリ津波を体験しています。こどもの頃から、津波の話は母からも、祖母からも、何度も聞きました。
小さな山の上に建った母の実家からは、港が一望できました。
その日は朝から、港の中を船がくるくると回っていて、母はお祭りのようだと思ったそうです。
お祭りの日、湾内の遊覧船がパレードをする様子にそっくりだったのです。
しかし、ふと水平線をみると、向こうの海が盛り上がって真っ黒な壁のようになっていて、お祭りではないと分かりました。「津波というけれど、あんなものが波だとは思えなかった」と言います。
記録を調べると、波の高さは日本では1mから最大でも5mとのことですから、きっと海面自体が盛り上がっていたことと、その後の被害の様子とを合わせ覚えて、より大きく高い恐ろしいものとして記憶されているのかもしれません。
ともあれ、母の記憶の中では、海の壁は近づくにつれてどんどん大きく高く見えるようになり、あっという間に港町に襲い掛かりました。
波が近づく様子も、その波が全てを押し流した様子も、山の上の家からはすべてが見えていました。やがて、人びとが山の上を目指してどんどん逃げてきました。
祖母はその頃には大慌てで家中の釜いっぱいにご飯を炊き、家族総出でおにぎりを作って登ってきた人たちに分けたそうです。
このチリ津波以降、太平洋では国際的な警報システムが整備されたとのことですが、なによりも、地震があればそれが遠い外国の話であっても津波が来る可能性があるということ、そしてその津波がどれだけ恐ろしいものなのかということを実感し、わたし達日本人も含め被害地域の人間は意識が変わったのだと思います。
同じアジアのこんなに近い国にいながら、そしてこんなに情報が伝わりやすい世の中になっているのにもかかわらず、その教訓を共有することなく新たな津波被害が出てしまったことに、悔しい思いを感じます。
日本政府も支援を惜しまないとの報道がされています。
医療、物資や復旧支援はもちろんのこと、警報システムの普及もぜひ力を入れてもらいたいです。














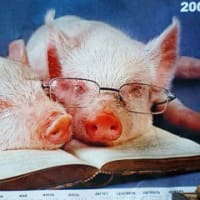





1960年のチリ地震津波ですが、地震発生から丸一日も経って、日本に津波が到達したそうですね。地球の裏側の地震でも、日本では100人以上の死者が出て、3000戸近い家が全壊したとか。
今回の地震でも、プーケットに津波が来たのは地震発生から2時間後だそうですから、いくらでも避難する余裕はあったわけですよね。その辺が、とても悔しいです。
でももし自分がプーケットにいたら、逃げられただろうか?
もしインターネット環境があって、USGSのホームページ(http://earthquake.usgs.gov/eqinthenews/2004/usslav/)を見ていたなら、即座に津波の可能性に気づいただろうと思います。
あるいはテレビのニュースで地震のことを知っていたら、「もしかして?」くらいは考えただろうと思います。
でもリゾート地に遊びに行っていて、果たしてニュースを見ているだろうか?ネットを見ているだろうか?
答はノーだと思います。
だとすると、世界中で気づいた誰かが、積極的に警報を発しなければいけないのだろうと思います。
ちゃんとした警報システムは、お金をかければすぐにでもできるだろうと思いますが、出来上がるまで地震は待ってくれないでしょう。
では今すぐできることって、なんだろう?
今回の地震では地震発生40分後に、気象庁が「この地震による日本への津波の影響はありません」と発表しています。この時点で、おそらくインド洋周辺での津波の危険性について言及できる状態であったと思われます。
「日本への影響」だけでなく、同時に世界の地域について発表できれば良かったんですよね。
おそらく気象庁が正式発表するには、法律の問題とかいろいろあるんだろうと思われますが、この辺なんとかクリアできれば、と思います。
ただ、多くの人が地震の発生自体をしらなかったみたいですね。
本当に、誰かが情報を得ていたら、そして津波の可能性を少しでも疑っていたら、今よりも少しは被害が少なかったのかもしれない・・・と残念です。
実は私、この件に関しては専門家の立場なので(まだ駆け出しですけれど)、こういった時に自分だったら何ができるか、という視点で考えていました。
本当は自分のブログに書くべきなんだろうと思ったんですけど、専門家が軽々しい発言をしたらマズイだろうと思って(それにもっと偉い先生方がいろいろ発言なさっていますし)、こちらに書いてしまいました。本当にすみません。
インド洋で、何分後に何センチの大きさの津波が来るか、といったことまで予測するのは無理かもしれません。でも震源が浅くマグニチュードが大きければ、それなりの津波が起きることは予想がつきます。震源とマグニチュードは、現在の観測網では、世界のどこで地震が起きようともすぐに解析できる状態なので、それを活かせないかなと思って、上記の発言になりました。
先ほど「津波予報、アジア諸国へも…気象庁が監視範囲拡大」というニュースを読みました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041228-00000204-yom-soci
まだ環太平洋のみみたいですが、このまま広がるといいですね。
だんだんと日本政府の対応速度も上がってきて、
近くにいた自衛隊の船を寄せたり、支援策を打ち出したりしてきて、ちょっとホッとしました。
下手してこのまま年末モードでこの災害がスルーされるようだったら、まずいよな、と思って見ていたんですが。
ニュースの第一報を見た瞬間に「!日本が役に立てる!」と思って(災害の規模が規模だけに)自衛隊の動きを期待していたんですが、やっぱり政治的な手続きというか、『お約束』があるみたいですね。先に動いたのは国際救助隊でした。
一人でも多くの人が助かって、一日も早く平穏な生活が取り戻せますように。
(実はasteriaさんのプロフィールに研究職とあったので、こういったご関係かな、と想像したりもしていました)
本当に、地震が起きたというニュースが伝わっていれば、そしてそれを津波の危険性と結び合わせて考えることができていれば、わたしたち一人一人でもなにかできたことがあったのかもしれません。
のれんさんのコメントのように、日本の動き、特に自衛隊の船の動きは、わたしも驚きました。
このような災害が起きてしまった以上、これからは一人でも多くの人を助けられるように協力し合うことが必要ですし、システムの整備も、システムができるまでの間の国を超えた協力も、早く整うといいと思います。
それに、わたしたちにできること、という視点で考えることって大切ですよね。
私たち専門家も、知識や情報をもっとうまく世間に広めていかなければならないと思います。
ただ研究さえ出来ればいい、という考えの人もいますが、私は広報活動をもっと積極的に行う必要があると考えています。
って私が思ってみても、下っ端なので全く役立たずなんですけど・・・
あ。もちろん偉い先生で広報活動の大切さをわかっていらっしゃる方もたくさんいます。
もう自分で自分のこと「ひめ」っていうような歳じゃないんですけど・・・。
父がミャンマーにいて今朝帰国しました。(ちなみにスローフードの辻さんと一緒でした。)イラワジ川の河口でマングローブの植林活動をしています。
朝食の時に震度4ぐらいの地震があってこりゃヤバいかなと思って避難準備をしていたそうです。(ちなみに父も専門家)でも全く津波はなく、海は普通だったそうです。
もともとミャンマー全体は電力事情が悪く,TVも電話もましてやネットもないのが当たり前。船には船舶電話というのがあり,ここから得られる情報がすべてだったようですが,情報が混乱し,「インドと韓国で地震があった」と聞いたと言っていました。
同行の方が20km先の電話がある街まで走り,日本大使館に連絡をしたようですが全く様子がつかめず,次の日,首都ヤンゴンに出てきてからも情報はなく,日本の方が危ないのではないかと思って空港から我が家に電話をして,その時母から事の次第を聞いたみたいです。
とりあえず無事だったので一安心ですが,「警報システム」って言ったって電気ないからできないよ。って父は言っています。
インターネットなどを始めとし,情報網が発達した世の中になってきたような気がしていましたたが,その網の中にいるのはまだまだ世界の一部なのだと感じています。
元々被害の多い日本が一番研究が進んでいるようで
「TSUNAMI」という言葉が
英語として辞書に載るほどです。
(以前は「Tidal Wave」という言葉が用いられていたらしいのですが「Tide」も「Wave」も地震とは無関係なものなので)
その日本にしても、システムによって発せられた情報が地域の住民に行き渡っているか?と言えば、決してそうではないというのは、2004年に各地で起こった地震後の行政の対応を見れた明らかです。
「海面に大きな変化が見られなかったから」避難勧告を行わなかったなどという自治体がありましたが(海面に変化がある時点でもう津波は到達しているのですから確認する余裕はありません)行政担当者に対しても、津波に関する知識の普及を行わなければ、折角の情報も生かせません。
普段地震の少ない地域では、システムにしても行政の対応にしても後手後手になってしまいがちです。実際、地震や津波の発生するサイクルを考えると、東海沖地震がいつ発生するか?といった話と、それへの備えがどのくらい前から行われてきたか考えればどのようなものかわかると思います。
とりあえず今出来る限りのことをやって、少しでも被害を減らすということは大切ですが、物だけで何とかなるという話ではないですね。
今回の津波の被害、「○○が~~だったら・・・」と、たった一つ何かが整っていれば防げたものではないですね。
BROSさんのおっしゃるとおり、物だけで何とかなる話ではないというのはそのとおりだと思います。
ただ今回一番歯がゆいなと思ったのが、やはり津波について知らなすぎたために巻き込まれた方が多い点なのです。
警告を出すべき行政側もそうですし、地元の住民の方々も。
たとえばシステムが整っていても、行政がその危険性を受け止めてすぐに警告を促さなければ被害は防げません。
また、その警報に住民がどんな対応をするかによっても、被害はまったく違ってきます。
インド洋付近での地震の可能性は専門家から指摘されていたのに、災害対策に生かされなかったという報道を見ました。今回の被害地域では今まで津波はなかったのかもしれませんが、もっと津波に関する知識の普及と、危険を伝える仕組みができていれば全然違っていただろうと思ってしまうのです。
とうとう被害が10万人を超えてしまいました。
地元の行政の対応や電気の普及といった問題に手を出すことは難しくても、津波被害を経験している日本としてできることって何かなと考えると、技術と知識の提供なのではないかと思います。
関西で研究をやっている人から聞いた話です。
阪神大震災が起こる前、関西地区では地震の危険性についてあまり認識されていなかったそうです。
しかしその人は「関西だって地震の危険があるのだから、情報を普及しなくてはならない」と思い、地元の新聞に、地震の危険性についてしばらく連載で記事を書いたのだそうです。
しかし大震災が起こってしまい、その後に地元の人が「関西には地震がないと思っていた」と言っていたのを聞いて、自分がやっていたのは何だったのだろう、と落ち込んだそうです。
そういう話を聞くと、本当に何をやったらいいのだろうと考えさせられます。