
海蔵寺は、福聚山と号す臨済宗の禅寺で、大徳寺派に属す古刹です。
創建は正慶年間(1330年)ごろ大暁禅師を開山として創建されたとされていますが、南北朝戦乱によって廃れていたのを、開創約百年の後、竺裔玄中和尚を中興開山として再興したものとされています。
湯川山の山ふところにひっそりと建っています。寺宝の秘仏、馬頭観音像は話には聞いていましたが、まだ拝んだことはありませんでした。
以前は50年に1度しか開帳されていませんでした。昭和38年に県の文化財に指定されてからは、1年に1日だけ、今日、2月18日に御開帳がおこなわれています。
用を済ませた午後、好天に恵まれたので、車を走らせました。
近くの高倉には、室町時代の後期1500年ごろ、岡城主、麻生彈正弘繁によって創建された竜昌寺もあります。こちらは曹洞宗の寺で、黒田二十五騎の一人井上周防が再興に力を尽くし、隠居後は毎日この寺で黒田如水の肖像画と長政の位牌に礼拝していたといわれ、大祭には参道には露店が並び、臨時バスが運行されるほどの隆盛です。母の実家の菩提寺でもありよくお参りします。
3キロくらいしか離れていない海蔵寺のほうは、お堂といったほうがいいくらいの小さなお寺になってしまっていました。麻生氏が大友氏に背いたため。天文15年(1546年)大友宗麟は瓜生左近太夫貞延に岡城を攻めさせました。麻生弘繁の子、隆守は岡城を守りきれず、ここ内浦の海蔵寺に逃れ、妻子を殺した後、家臣ともども自害しました。
目当てのご本尊、馬頭観音像は、胎内に嘉吉元年、(室町時代・1441年)に、三条猪熊仏所・祐尊が造ったと書かれているそうです。
高さ62センチほどの檜の寄木造りで、馬頭を頭上に戴き、炎髪を逆立てた正面の顔は、三つの目を見開いて、やや開いた口は歯牙をむき出していて、側面の顔も憤怒相です。六臂のうち、一手は掌を合わせ馬口印をむすんでいます。二手は、ひじを曲げて上に立て、右手に斧、左手に宝棒を持ち、三手は、下に垂らして左手には数珠を握り、右手は開いて掌を前に向けています。右ひざを立てて座し、少し合せた足裏と足先が衣の裾から見えています。
秘仏として厨子の奥にいますだけ、560年の歳月を経たとは思えない瑞々しいお姿です。天衣の漆地に金泥で描いた蓮華唐草文様もかすかに見られます。仏前の狛犬にも彩色の跡が見えます。
境内の椿の艶やかさが歴史の悲話を語るかのようで、午後3時、人影ももう他にはなく、境内に出ていた地元の人の店も1軒だけで、檀家の人と思しい人たちが、テントの片付け作業中でした。
<

画像は海蔵寺と築地です。










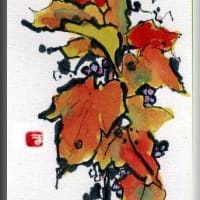





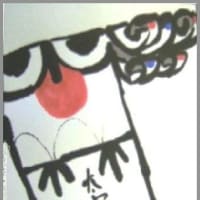

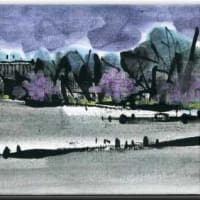
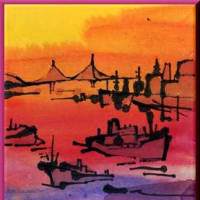
約500年。
①内乱が100年②鎖国が250年③海外戦争100年でようやく眼が覚めて④復興・成長・平和の時代50年、もこの国は目下、お先真っ暗状態。
馬頭観音様はどんな気持ちで眺めてこられたのでしょうか?
我々を罵倒し続けてはりましたか。
何?テレビも新聞もないので分からないって。そんなら大型の液晶テレビでも寄贈しましょう。
お知恵ください。
飲んだくれの大臣を国会議員に選んだボンクラ国民をなんとかしてくださいよ。
ところで、お寺は建築と言わずに、
何故、建立(コンリュウ)と言うんでしょうか?大臣さんが読み間違いする恐れ大なり。
本ブログでは創建と記され読み間違いの恐れなし、さすが我々サポーターを配慮されて・・。
寒さのぶり返し、粕汁でもしますか。
築地の趣に往時も偲ばれ、このスクリーンは窓がいろいろに変わるので面白く、しばらく遊んでしまいました。「栄かえる」も御利益を期待します。
昨日も今日も、つづけざまに絵を描いて近くばかり見つめていました。成田山から遙か見渡せて気持ちがいいですね。ありがとうございました。
香HILLさんお嘆きの通りで、日本丸の舵取りもどう漂うつもりなのかと、自分の身に降りかかる災厄ともども不安になります。
建立は漱石の「行人」ではコンリツと振ってあったと記憶します。おやこんな読みがあると思って憶えています。今は確かめる余裕がありませんが。仏語は読みがややこしいですね。行法もギョウボウですから。中身は同じでしょうに。
今朝パソコンを開いて、お返ししていなかったのに気付きました。遅くなってごめんなさい。
1週間ほどブログはお休みにします。
築地や生垣を撮る私を怪訝そうに眺める人もいました。
大きな海原の眺めは気持ちが晴れますね。
蛙さんの冬眠明けの春の絵を楽しみにしています。
取り込んでいますので、1週間ほどお休みにします。