 九州国立博物館が開館した折、開館記念特別展で、人垣ができていた一つが、この志賀島で、発見された金印の展示でした。
九州国立博物館が開館した折、開館記念特別展で、人垣ができていた一つが、この志賀島で、発見された金印の展示でした。 その折には、戦後、中国雲南省での発掘調査で、1世紀ごろの古墳から出土した金印も並べて展示されていましたが、「漢委奴国王」の金印とそっくりの姿形で、寸法も同じものでした。
(金印の寸法 方形で、タテヨコ2,3㎝、(後漢初の1寸)印台の高さ平均0,887㎝。108,729g。つまみには蛇の彫り物)
二千年の眠りから覚めたこの金印が、かつての綿津見三神を祭る志賀海神社に替わって、今では志賀島を歴史上有名にしています。
金印発見に纏わる話は面白いので、知っていることを少し記します。
掘り出したのは志賀島の百姓、甚兵衛さんということになっていますが、彼は土地の所有者で、実際は仙和尚が書き残しているように、秀治と喜平という小作人と思われます。(志賀島資料館)
天明4年。田の溝の流れが悪いので手入れをしていて、大きな石にぶつかったので、二人がかりで掘り起こしたところ、その石が屋根になっていて、三方が石で囲ってあり、真ん中に光るものがあったのだそうです。
何分にも当時のこと、「こまかのに重たかばい」ということで、持ちまわられる騒ぎとなり、黒田藩の藩校、甘棠館館長、亀井南冥が、後漢書に記載されている金印と気付くわけです。
南冥先生がいなかったら、いまや国宝となった金印も、地金として鋳潰されて武具の飾りにでもなっていたかもしれません。
ただし、これにはおまけがあって、南冥先生は、自分に譲ってくれといって、徐々に釣り上げ、百両まで出すとせり上げたため騒ぎが大きくなり、黒田藩に噂が聞こえ、甚兵衛さんに褒美をやって藩に納まったという経緯があります。
この光武帝に朝貢した奴国のボスとはどのような人だったか想像はつぎつぎの夢を齎します。統一王朝もない弥生中期、海山を渡り越えて行ったのはこの地の海人、安曇族をを束ねた人でしょうか。
博多は大陸文化に直結した文化圏だったことだけは確かです。
金印公園のすぐ前に横たわる能古島には防人達の数々の望郷の歌が残されています。霞む中に也良崎の灯台も見えていました。穏やかな春の波が悠久の時を変わることなく寄せています。











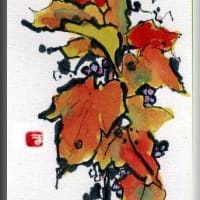





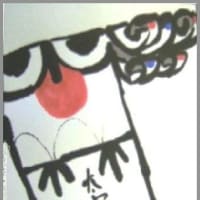

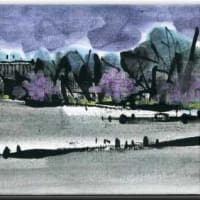
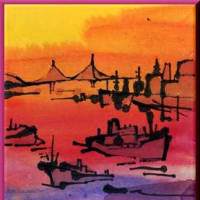
解らずに撮したこれは
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0a/64/8b43f7cc0e98ddc76f10ecc5eb36685b.jpg
どのあたりでしょうか。
十一面観音が縁の下に隠されていたこともありました、「こまかのに重たかばい」と金印は発見されて。見る眼がなければ、その運命は解りませんね。
面白いお話をありがとうございました。
トサミズキの花の付き方も たのしいです。
万葉集には、志賀島に関わる歌が知っているだけでも23首もあり、小さな島に万葉歌碑が10基もあります。
トサミズキは盛りが過ぎてしまいましたが、咲き初めのころ萼近くにちょっと紅をさした姿も面白いです。