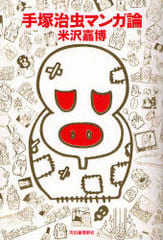
米沢嘉博 「手塚治虫マンガ論」 河出書房新社 2007.07.30.
昭和20年代後半から30年代にかけて、手塚治虫はマンガの絵の魅力で多くのマニアを掴んだ。機能、意味を記号化した絵にもかかわらず、手塚の絵は魅力的だった。少女が、少年が、アンドロギユメスが、半獣半人が、そして怪物達が、快と不快の感覚をその形・線の中に現わしながら、読者達を非論理的な部分で捉えた。それを、手塚のエロチシズムとグロテスクと呼ぼう。
手塚治虫の描く女は色っぽくないと、かつて大人達は語った。その中性的な線は、何を措いても無機的であると言った評論家もいる。手塚自身も、自分の描く女性が人形、ビニール人形的であることを認めている。「やけっぱちのマリア」のマリアがダッチワイフビニール人形という設定だったのは、こうした言われ方に対する手塚の一つの答えだったのかもしれない。
だが、初期「ロストワールド」でケン一とあやめは上半身裸、「魔法屋敷」のヒドラは、ブラとパンティだけのあられもないコスチュームだった。「ジャングル魔境」のコブラは乳首さえ見せていた。そうして、子供達は、そこに一種の興奮を感じたはずだ。
あからさまだったロマンスの匂いは、やがてミッチィ、アトムといったアンドロギユヌスの肉体と、異生物と少年の友情へ形を変えていく。手塚治虫にとって、こうした少年や少女のエロチシズムは不可欠のものだった。
後期になって描かれた「こじき姫ルンペネラ」のえぐさ、「プライム・ローズ」のロリコン趣味を言う必要もなく、手塚治虫はいわゆるロリコンマンガのルーツでもあった。
加えてグロテスクがある。手塚は、常に形の変わるものが大好きだった。このメタモルフォセスは、手塚の一つのテーマでもあり続け、様々なマンガの中に現われている。「メタモルフォーゼシリーズ」「バンパイヤ」「ブルンガ1世」……。
手塚治虫が時にリアルな気味悪さを味わわせたのは、病気や肉体の変呪を描く時だった。「ブラック・ジャック」はさながら衛生博覧会的な様相を見せる作品でもある。
虚構の中にしか住みえない、この快と不快がギリギリ日常に溶け出てくる様に向けて、手塚の想像力は解放される。SF、ホラー、ミステリー、ファンタジーを好んで描いた手塚は、自らの想像力のベクトルを、それとはなく知っていたのだろう。
エロチシズムとグロテスクとは、近代科学合理主義が、哲学が、宗教が、つまりは知性がついに乗り越えることのできない、制御不可能の事柄であり、知によって世界を律し描き出そうとする手塚にとつての、一つの敵でもあり、そうして捉えがたき自分自身でもあったのかもしれない。
昭和20年代後半から30年代にかけて、手塚治虫はマンガの絵の魅力で多くのマニアを掴んだ。機能、意味を記号化した絵にもかかわらず、手塚の絵は魅力的だった。少女が、少年が、アンドロギユメスが、半獣半人が、そして怪物達が、快と不快の感覚をその形・線の中に現わしながら、読者達を非論理的な部分で捉えた。それを、手塚のエロチシズムとグロテスクと呼ぼう。
手塚治虫の描く女は色っぽくないと、かつて大人達は語った。その中性的な線は、何を措いても無機的であると言った評論家もいる。手塚自身も、自分の描く女性が人形、ビニール人形的であることを認めている。「やけっぱちのマリア」のマリアがダッチワイフビニール人形という設定だったのは、こうした言われ方に対する手塚の一つの答えだったのかもしれない。
だが、初期「ロストワールド」でケン一とあやめは上半身裸、「魔法屋敷」のヒドラは、ブラとパンティだけのあられもないコスチュームだった。「ジャングル魔境」のコブラは乳首さえ見せていた。そうして、子供達は、そこに一種の興奮を感じたはずだ。
あからさまだったロマンスの匂いは、やがてミッチィ、アトムといったアンドロギユヌスの肉体と、異生物と少年の友情へ形を変えていく。手塚治虫にとって、こうした少年や少女のエロチシズムは不可欠のものだった。
後期になって描かれた「こじき姫ルンペネラ」のえぐさ、「プライム・ローズ」のロリコン趣味を言う必要もなく、手塚治虫はいわゆるロリコンマンガのルーツでもあった。
加えてグロテスクがある。手塚は、常に形の変わるものが大好きだった。このメタモルフォセスは、手塚の一つのテーマでもあり続け、様々なマンガの中に現われている。「メタモルフォーゼシリーズ」「バンパイヤ」「ブルンガ1世」……。
手塚治虫が時にリアルな気味悪さを味わわせたのは、病気や肉体の変呪を描く時だった。「ブラック・ジャック」はさながら衛生博覧会的な様相を見せる作品でもある。
虚構の中にしか住みえない、この快と不快がギリギリ日常に溶け出てくる様に向けて、手塚の想像力は解放される。SF、ホラー、ミステリー、ファンタジーを好んで描いた手塚は、自らの想像力のベクトルを、それとはなく知っていたのだろう。
エロチシズムとグロテスクとは、近代科学合理主義が、哲学が、宗教が、つまりは知性がついに乗り越えることのできない、制御不可能の事柄であり、知によって世界を律し描き出そうとする手塚にとつての、一つの敵でもあり、そうして捉えがたき自分自身でもあったのかもしれない。



















