アニメーターの金田伊功氏が、7月21日に死去されました。
詳細については不明ですが、直接の死因は心筋梗塞だそうです。
すでにネットの各所で報じられてますが、こちらでは写真入りのアニドウのHPを
ご紹介しておきます。
(追記:「金田伊功を送る会」の開催情報が、同HPの特設ページに掲載されました。)
詳細な業績についてはWikipediaなどを参照していただくとして、アニメといえば
監督かキャラデザイナーばかりが注目されがちな状況の中、一作画マンとして
これだけ大きな名声と影響を遺した人は少ないと思います。
享年58歳とのこと。まだまだ活躍できる年齢だったと思うと、残念でなりません。
最近では美術手帖2008年9月号「スタジオジブリのレイアウト術」の表紙が
金田氏によるレイアウト図で飾られていたのが思い出されます。

クレジットには明記されてませんが、たぶん金田氏の仕事で間違いないと思います。
「ひねもすのたりの日々」や「究極映像研究所」でも、そのように指摘されてましたし。
昨年に東京都現代美術館で開催された「スタジオジブリ レイアウト展」では
金田氏の描くレイアウト図をいくつか生で見られましたが、特に「ナウシカ」の
アスベルがガンシップによる襲撃を行う場面が強く印象に残りました。
力強い構図に加え、殺気すら感じられるアスベルの眼の描写がとにかく凄かった。
奇しくもこのレイアウト展、7月25日からサントリーミュージアム[天保山]で
大阪展がスタートするところでした。
ワイエスといい金田氏といい、なぜこうも計ったように逝ってしまうのか・・・。
関西地方の方はぜひ天保山まで足を運んで、金田氏の遺業をご覧ください。
金田さん、多くの名作を世に出してくださり、ありがとうございました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
詳細については不明ですが、直接の死因は心筋梗塞だそうです。
すでにネットの各所で報じられてますが、こちらでは写真入りのアニドウのHPを
ご紹介しておきます。
(追記:「金田伊功を送る会」の開催情報が、同HPの特設ページに掲載されました。)
詳細な業績についてはWikipediaなどを参照していただくとして、アニメといえば
監督かキャラデザイナーばかりが注目されがちな状況の中、一作画マンとして
これだけ大きな名声と影響を遺した人は少ないと思います。
享年58歳とのこと。まだまだ活躍できる年齢だったと思うと、残念でなりません。
最近では美術手帖2008年9月号「スタジオジブリのレイアウト術」の表紙が
金田氏によるレイアウト図で飾られていたのが思い出されます。

クレジットには明記されてませんが、たぶん金田氏の仕事で間違いないと思います。
「ひねもすのたりの日々」や「究極映像研究所」でも、そのように指摘されてましたし。
昨年に東京都現代美術館で開催された「スタジオジブリ レイアウト展」では
金田氏の描くレイアウト図をいくつか生で見られましたが、特に「ナウシカ」の
アスベルがガンシップによる襲撃を行う場面が強く印象に残りました。
力強い構図に加え、殺気すら感じられるアスベルの眼の描写がとにかく凄かった。
奇しくもこのレイアウト展、7月25日からサントリーミュージアム[天保山]で
大阪展がスタートするところでした。
ワイエスといい金田氏といい、なぜこうも計ったように逝ってしまうのか・・・。
関西地方の方はぜひ天保山まで足を運んで、金田氏の遺業をご覧ください。
金田さん、多くの名作を世に出してくださり、ありがとうございました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。










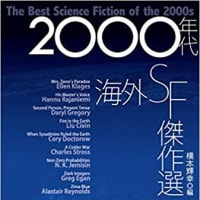


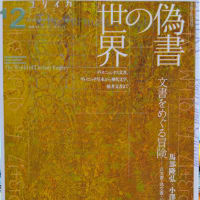










金田先生、亡くなったんですか・・・。
最近ではあまり作品を目にする機会もなくなってしまいましたが、やはり残念です。
デジタル化が進む昨今ではなかなか「金田パース」のようなものは生まれづらのかもしれませんけど、後進の方々には技術や精神を継いでより良い作品を生み出していって欲しいものです。
>金田先生、亡くなったんですか・・・。
>最近ではあまり作品を目にする機会もなくなってしまいましたが、やはり残念です。
金田さんもスクエニに移ってからは、はっきり言って
飼い殺しにされてるようにも見えました。
本来なら会社のバックアップで、もっといろいろな表現に
挑めたのではないか、と思うのですが・・・。
まあ内幕については部外者の知るところではありませんが、
少なくともあれだけの技術と評価を持つ人物にふさわしい
活躍の場を与えられなかったことは、エンターテインメント企業として
非常に罪作りなことだったと思います。
>デジタル化が進む昨今ではなかなか「金田パース」のようなものは
>生まれづらいのかもしれませんけど、後進の方々には技術や精神を継いで
>より良い作品を生み出していって欲しいものです。
まったくもって、姫鷲さんのおっしゃるとおり。
それとデジタル化については、私も危機感を感じているところです。
技術面がどれだけ進んでも、やはりアニメは画が命だし
画に命を吹きためには、やはり作画マンの腕と頭と魂が
モノを言うと思います。
様々な技術が増えてきた今こそ、これからアニメ業界を目指す
若い世代に、金田氏の仕事から多くを学んで欲しいものです。
そのためにも、ここで金田氏の業績についての分析と再評価が、
改めて行われて欲しいと思ってます。
リンクいただき、ありがとうございます。
>>デジタル化が進む昨今ではなかなか「金田パース」のようなものは
>>生まれづらいのかもしれませんけど、後進の方々には技術や精神を継いで
>>より良い作品を生み出していって欲しいものです。
スクエアエニックスでの金田氏の仕事を見ると(実はゲームしないので全部You○○○○経由)、2DのOPアニメとかは別にして、3D-CGで金田パースが再現されているものはないように思います。
たぶんこれは現存のCGソフトの問題なのでしょうね。スクエアで金田氏がソフト製作者と協業をアプローチされていたかどうか、わかりませんが、本来ソフト制作の段階で金田氏のノウハウ/(and or)感覚をうつしとるような作業があったら、もっと展開は違っていたのかも。(フリーウェアのCGソフト:DOGAというのが金田風映像を作れるようなものになっていました(最新はどうなってるか不勉強))。
>>それとデジタル化については、私も危機感を感じているところです。
>>技術面がどれだけ進んでも、やはりアニメは画が命だし
>>画に命を吹きためには、やはり作画マンの腕と頭と魂が
>>モノを言うと思います。
青の零号さんのおっしゃるとおり、最後は人間の感覚勝負と思います(人造意識みたいなものが作成されるまではと、とりあえず留保付きで(^^;))。
ただある程度のところまでは本来上に述べたアプローチがあれば、CGでも金田アニメートは可能だったのではないか、と思います。
例えば金田氏の快感原則にのっとったタイミングとパースで動く超絶リアルなCG映像、といったもの(坂口監督『ファイナルファンタジー』はそういうものになっていると思って観に行ったのですが、、、)。
CGは所詮ツールなのでそれを活かすことができないのなら、ツールを人の感覚に合わせて改良するアプローチをとれば、そうしたことも可能だったのではないかと思います。
極端ですが、壁画では金田アニメートは不可。鉛筆と白い紙とセルという人の感覚をうつしとれるツールテクノロジーがあったので『ザンボット3』は実現した。
要は今のCGはある意味、まだ壁画のレベルなのかも。
>>ここで金田氏の業績についての分析と再評価が、改めて行われて欲しいと思ってます。
その分析と天才的なCGソフトクリエータ(ハッカー)がいれば、金田3D-CGは御本人が亡くなった後でも可能ではないか、これがエンジニア癖の職業病で染まった僕の脳が考えていることです。なんちゃって(^^;)。
>(人造意識みたいなものが作成されるまではと、とりあえず留保付きで(^^;))。
金田さんの作画については、BPさんの記事でも取り上げられていた氷川氏のWeb評論集が
すばらしい内容でしたね。
それに触発されて追加記事を書きましたので、よろしければそちらもご覧ください。
人造意識については「意識」の定義自体が微妙につき、私も留保させていただきます。
でも金田氏の仕事を人造意識で達成するなら、その意識は間違いなく人間と同等か
それ以上のイマジネーションを有しているのでしょうね。
コイツに名前をつけるなら、やはり「エモーション・エンジン」になるのでしょうか。
・・・あ、この名称はすでにSONYのTMでした(^^;。
むしろ脳内映像のダウンロード技術と、それを視覚的に変換する感覚シンセサイザーを
開発するほうが、テクノロジーとしてはより早く実現できるかもしれません。
でもそうなると、アニメというメディア自体がなくなっちゃうかも。
究極的には『宇宙消失』のmodとかアンサンブルとかまで行ったら
ものすごい世界が体験できますね(^^;。
>ただある程度のところまでは本来上に述べたアプローチがあれば、CGでも金田アニメートは
>可能だったのではないか、と思います。
>CGは所詮ツールなのでそれを活かすことができないのなら、ツールを人の感覚に合わせて
>改良するアプローチをとれば、そうしたことも可能だったのではないかと思います。
2Dと3Dの表現の違いと、そこを映像的にどう消化していくかという部分については
今後大いに検討されるべき問題でしょうね。
いま注目されている3DCGの映像についても、こういった研究から示唆されるものは
かなり多いと思います。
>その分析と天才的なCGソフトクリエータ(ハッカー)がいれば、金田3D-CGは
>御本人が亡くなった後でも可能ではないか
その場合、いわば金田氏の電子的クローンというところになりますか。
ただし、あくまで手法や様式に限定されてしまうようにも思いますが・・・。
でも議論としてはすごくおもしろいネタではありますね。
こういう話、できれば金田氏の新作発表とかの機会に
やりたかったですけどねぇ。
かえすがえすも、それが残念でなりません。