「メディア芸術祭 アニメ部門受賞者シンポジウム」の内容ですが、すでに『時かけ』の
公式ブログなどでも既報のとおり、主査の富野 由悠季氏による発言が話題の中心に
なっているようです。
詳細についてはそれらの記事を読んでいただくとして、ここではシンポジウム内で
特に物議を醸したと思われる部分について、私なりの感想を書かせていただきます。
会場では長々としゃべってましたが、富野氏の『時をかける少女』に対する不満を
本人の発言を用いて要約するならば
「アニメで風俗映画を作っているのはもったいない」
という言葉に尽きると思います。(かなりあちこち端折ってますが)
富野氏は登場人物の「つきあいたい」という言葉の使い方を切り口にして、その裏に
性的な肉体関係を示唆する意図が透けて見えると指摘し、こういう言葉のやりとりで
成立する人間関係を肯定的に描写した『時かけ』の作風は「高校生の風俗映画」にしか
見えないという感想を述べていました。
まあそういう意見にもうなずける点はありますよ。言葉遣いの軽さは事実だし。
しかし細田監督もご自分で言ってたように、『時をかける少女』を見て欲しい世代が
主人公たちと同年代の少年少女だとすれば、彼らの「風俗」が書けてない作品なんか
アニメファンでもない限り、見に行くわけがないんですよね。
まあここでの「風俗」という言葉は「性風俗」という意味ではなく、対象世代についての
生活習慣や行動の傾向を指すのですが、そこはやはり年頃の青少年の話ですから
異性への意識が全然描かれてないほうが不自然というもの。
むしろ本作ではヒロインの真琴がそれを「自覚」し、その気持ちと真摯に向き合うまでを
丹念に追っていく過程が、大きな見どころになってるわけです。
そこが抜けちゃったら、それこそ青春映画にもなりゃしません。
そもそもアニメであれ実写であれ、生身の人間を描写するにあたって「セクシュアリティ」を
全く抜きにして描ける物語なんて、実は存在しないんじゃないかな。
両性具有や無性の存在にしても、他の男女の存在する世界の中に置かれる限り、なんらかの
性的な色合いを帯びざるを得ないわけですし。
この問題を確実に回避するためには、描く対象を性的に未分化な世代にするか、あるいは
ロボットを主人公にするしかなくなっちゃうわけです。
だからアニメって子供かロボットものに偏るんだ、と断言するのは極端すぎるのですが、
「つきあいたい=肉体関係」という発想の飛躍だって、まあ似たり寄ったりだと思います。
一般的な高校生を日常からムリヤリ引き離す意図を持って、戦争させたりロボットに乗せたり
異世界に送り込んだりしちゃう物語の設定が、一般的な観客層にどこまで通用するのか?と
考えるとき、それって細田監督の指摘した「アニメの壁」の一例ではないかとも思うのです。
自分はそういう作品を見て育ってきたし、もちろんそれなりに得るものもあったと思いますが
もうそれだけじゃアニメは先細りかもという危機感は出てきても良いと思うし、それに対して
製作者の側がなんらかのリアクションを起こそうとする動きもまた、評価に値すると思います。
オトナ目線で下の世代へ「押し付けがましく」説教をする作風もやはり、「アニメの壁」に
なり得るようにも思います。
それでもいいというアニメファンを相手にしてるうちは結構ですが、それに甘んじていたら
これからのアニメってどこまで行っても自家中毒の作品しか生まないんじゃないのかな。
若い世代に摺り寄れない新作ばかりで、そのうちアニメファンの年齢構成も高齢化の一途を
たどって行ったとしたら、極端な話、このジャンルに未来はないかもしれない。
だからこそ、「アニメでも普遍的な物語がちゃんと描けるんだよ」というところを見せた
『時をかける少女』の作風について、私は肯定的に受け止めたいと思います。
まあそこまでで止まってしまったら、確かに作品としてはもうひと押し足りないということにも
なってしまいますが、この『時をかける少女』という作品には、その表面に見える意匠としての
「平凡な女子高生の日常」の外側に隠れて、もっと大きな「時代の気配」とでも言うべきものが
しっかりと織り込まれているようにも感じるのです。
いってみれば、9.11以降の社会情勢を伺わせる「日常の中の不安感」を巧みに捉えて、それを
女子高生の皮膚感覚のレベルへとうまく置き換えたという感じでしょうか。
それを示唆するのが「白梅ニ椿菊図」と、それにまつわる千昭と真琴の会話なんじゃないかな、
というのが私の考えですが、そこからどういう結論に至ったかは、あえて説明しません。
しても納得できる人とできない人がいるからです。(お、富野発言のパクリ。)
ラストにもう一度タイトル表示が出てくる点についても、このあたりの解釈の仕方によっては
意味合いが変わってくるようにも思いますので、DVDなどで鑑賞する際にはちょっとだけでも
そのあたりを意識してみてもらえれば、と思います。
まあ細かいところを挙げればキリがないので、私なりの総括と感想はこのくらい。
あえて付け加えるとすれば、原作小説や先行する映像化作品と連携について、富野氏が
ほとんど興味を持っていなかったことが、少し残念でした。
細田監督がせっかくその話を出したのにも関わらず、ほとんどスルーでしたからね。
監督自身による芳山和子の位置づけなどの説明は、もっと細かく聞きたかった部分です。
細田監督いわく「原価は回収したけれど、自分の感覚では利益が出たとは思ってない」そうで、
DVDの売れ行きにそこらへんがかかっているそうです。
もちろん細田監督の次回作についても、このDVDの売れ行きが大きく影響するとのこと。
ここはひとつ御大の挑発に興味を持った方にも、ぜひDVDで実際に見て欲しいと思います。
ところでよくよく考えると、細田監督は昨年の「メディア芸術祭アニメ部門」の審査委員として
富野主査と一緒に仕事をしているのでした。
富野氏と樋口氏の仲の良さをうらやんでいた細田氏ですが、あれってもしかして演出(笑)?
公式ブログなどでも既報のとおり、主査の富野 由悠季氏による発言が話題の中心に
なっているようです。
詳細についてはそれらの記事を読んでいただくとして、ここではシンポジウム内で
特に物議を醸したと思われる部分について、私なりの感想を書かせていただきます。
会場では長々としゃべってましたが、富野氏の『時をかける少女』に対する不満を
本人の発言を用いて要約するならば
「アニメで風俗映画を作っているのはもったいない」
という言葉に尽きると思います。(かなりあちこち端折ってますが)
富野氏は登場人物の「つきあいたい」という言葉の使い方を切り口にして、その裏に
性的な肉体関係を示唆する意図が透けて見えると指摘し、こういう言葉のやりとりで
成立する人間関係を肯定的に描写した『時かけ』の作風は「高校生の風俗映画」にしか
見えないという感想を述べていました。
まあそういう意見にもうなずける点はありますよ。言葉遣いの軽さは事実だし。
しかし細田監督もご自分で言ってたように、『時をかける少女』を見て欲しい世代が
主人公たちと同年代の少年少女だとすれば、彼らの「風俗」が書けてない作品なんか
アニメファンでもない限り、見に行くわけがないんですよね。
まあここでの「風俗」という言葉は「性風俗」という意味ではなく、対象世代についての
生活習慣や行動の傾向を指すのですが、そこはやはり年頃の青少年の話ですから
異性への意識が全然描かれてないほうが不自然というもの。
むしろ本作ではヒロインの真琴がそれを「自覚」し、その気持ちと真摯に向き合うまでを
丹念に追っていく過程が、大きな見どころになってるわけです。
そこが抜けちゃったら、それこそ青春映画にもなりゃしません。
そもそもアニメであれ実写であれ、生身の人間を描写するにあたって「セクシュアリティ」を
全く抜きにして描ける物語なんて、実は存在しないんじゃないかな。
両性具有や無性の存在にしても、他の男女の存在する世界の中に置かれる限り、なんらかの
性的な色合いを帯びざるを得ないわけですし。
この問題を確実に回避するためには、描く対象を性的に未分化な世代にするか、あるいは
ロボットを主人公にするしかなくなっちゃうわけです。
だからアニメって子供かロボットものに偏るんだ、と断言するのは極端すぎるのですが、
「つきあいたい=肉体関係」という発想の飛躍だって、まあ似たり寄ったりだと思います。
一般的な高校生を日常からムリヤリ引き離す意図を持って、戦争させたりロボットに乗せたり
異世界に送り込んだりしちゃう物語の設定が、一般的な観客層にどこまで通用するのか?と
考えるとき、それって細田監督の指摘した「アニメの壁」の一例ではないかとも思うのです。
自分はそういう作品を見て育ってきたし、もちろんそれなりに得るものもあったと思いますが
もうそれだけじゃアニメは先細りかもという危機感は出てきても良いと思うし、それに対して
製作者の側がなんらかのリアクションを起こそうとする動きもまた、評価に値すると思います。
オトナ目線で下の世代へ「押し付けがましく」説教をする作風もやはり、「アニメの壁」に
なり得るようにも思います。
それでもいいというアニメファンを相手にしてるうちは結構ですが、それに甘んじていたら
これからのアニメってどこまで行っても自家中毒の作品しか生まないんじゃないのかな。
若い世代に摺り寄れない新作ばかりで、そのうちアニメファンの年齢構成も高齢化の一途を
たどって行ったとしたら、極端な話、このジャンルに未来はないかもしれない。
だからこそ、「アニメでも普遍的な物語がちゃんと描けるんだよ」というところを見せた
『時をかける少女』の作風について、私は肯定的に受け止めたいと思います。
まあそこまでで止まってしまったら、確かに作品としてはもうひと押し足りないということにも
なってしまいますが、この『時をかける少女』という作品には、その表面に見える意匠としての
「平凡な女子高生の日常」の外側に隠れて、もっと大きな「時代の気配」とでも言うべきものが
しっかりと織り込まれているようにも感じるのです。
いってみれば、9.11以降の社会情勢を伺わせる「日常の中の不安感」を巧みに捉えて、それを
女子高生の皮膚感覚のレベルへとうまく置き換えたという感じでしょうか。
それを示唆するのが「白梅ニ椿菊図」と、それにまつわる千昭と真琴の会話なんじゃないかな、
というのが私の考えですが、そこからどういう結論に至ったかは、あえて説明しません。
しても納得できる人とできない人がいるからです。(お、富野発言のパクリ。)
ラストにもう一度タイトル表示が出てくる点についても、このあたりの解釈の仕方によっては
意味合いが変わってくるようにも思いますので、DVDなどで鑑賞する際にはちょっとだけでも
そのあたりを意識してみてもらえれば、と思います。
まあ細かいところを挙げればキリがないので、私なりの総括と感想はこのくらい。
あえて付け加えるとすれば、原作小説や先行する映像化作品と連携について、富野氏が
ほとんど興味を持っていなかったことが、少し残念でした。
細田監督がせっかくその話を出したのにも関わらず、ほとんどスルーでしたからね。
監督自身による芳山和子の位置づけなどの説明は、もっと細かく聞きたかった部分です。
細田監督いわく「原価は回収したけれど、自分の感覚では利益が出たとは思ってない」そうで、
DVDの売れ行きにそこらへんがかかっているそうです。
もちろん細田監督の次回作についても、このDVDの売れ行きが大きく影響するとのこと。
ここはひとつ御大の挑発に興味を持った方にも、ぜひDVDで実際に見て欲しいと思います。
ところでよくよく考えると、細田監督は昨年の「メディア芸術祭アニメ部門」の審査委員として
富野主査と一緒に仕事をしているのでした。
富野氏と樋口氏の仲の良さをうらやんでいた細田氏ですが、あれってもしかして演出(笑)?










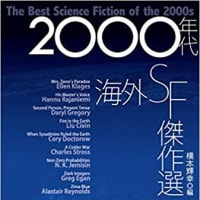


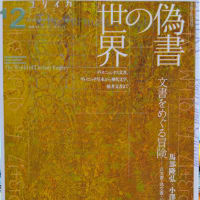









シンポレポのページで多々拝見しました、富野発言。相変わらずで苦笑を禁じえないのですが、他作品を褒める、評価する、というのは特にアニメでは珍しいですね。
これは受け売りですが、富野監督は「映画ではなく舞台劇の人」と理解すれば、発言の違った視点も見えてくると思います。
しかし富野御大の指摘する「時かけ」へ不満は判る気がします。不満への同意はしかねますが、富野監督としては綺麗過ぎる処が引っかかるのだと思います。
そこを良しとするか、不満に感じるかは本当に受けて次第、と見せかけて実は脚本技術のギミックやトリックに感じてしまう制作者としてのジレンマが、先の発言の根底にあるのではないでしょうか。
富野主査の言いたいことはもちろんわかるんですが、
それを鵜呑みにするばっかりもつまらないなぁ、と
へそ曲がりな自分が囁くのですよ。
やっぱり違う意見も出てきてしかるべきだろうし。
まあ今回のシンポジウムの話題を契機に、見る側でも
改めて『時かけ』という作品に向き合い、その中身を
とらえなおしてもらえればいいなと思ってます。
声高なメッセージよりも、つつましく語る形を選んだ
製作陣の意図を、より多くの人に汲み取って欲しいと
強く願ってます。
>富野監督は「映画ではなく舞台劇の人」
これは良くわかります。
セリフ回しひとつをとってみても、富野監督は
「芝居」をつけるのが大好きですからね。
そこが様式美でもあり、胡散臭さでもあるのですが。
>綺麗過ぎる処が引っかかる
むしろ「人物の掘り下げが甘い」ということかも。
でも日常レベルでやたらと素の自分を見せてる人って
むしろいないですからね。まして17歳だし。
ちなみに『春のめざめ』は、同じ年頃の少年が持つ
ドロドロした妄念を、あからさまに描いた作品です。
まさに『時かけ』と好対照な一本と言えるでしょう。
これも最近見てきましたので、そのうちレビュー予定。