『虹色ほたる』について、twitterに寄せられた感想のまとめを読むと、作品についての
賞賛と批判が、かなりくっきり分かれていることがうかがえます。
賞賛については、シンプルな感想から分析的なものまで様々ですが、批判派は数が少ないぶん、
それぞれの主張を強い言葉で表現したり、あるいは仔細に説明しているものが多いですね。
そしておもしろいのが、この批判をひとつひとつ読んでみると、ややぶっきらぼうだったり
肯定派を煽るような文章も見受けられるものの、多くの場合はそれなりに筋が通っていて、
良かれ悪しかれ作品の持つ特徴を、きちんととらえていることです。
これらを参照しながら、自分が『虹色ほたる』をどう見たかを、再度まとめてみようと思います。
これらの批判的な意見をおおまかに分類すると、だいたい次のとおりになります。
1.タイムリープや恋愛要素がご都合主義であり、全般的に論理性や必然性が欠けている。
2.昭和50年代や田舎の素朴さに寄りかかっていて、さらに当時を美化しすぎている。
3.肉親の死や恋愛といった要素に新味がなく、物語そのものが凡庸である。
4.作画が下手な(もしくはうますぎる)ため、観客を無視した極端な表現に走っている。
5.クセのある絵柄にこだわった結果、キャラクターの演技や表現がおろそかになっている。
まずは論理性や必然性について。
これらがすべての物語に不可欠とは思いませんが、本作にそのような部分は確かにあるし、
さらに言っちゃうと、物語自体はとてもありきたりなものだと思います。
口の悪い人なら、たぶん「陳腐」のひとことで片付けられちゃうんじゃないかな。
しかし、そのありきたりなお話を、アニメならではの過剰な作画によって表現したことで、
『虹色ほたる』の場合は「陳腐さ」から逃れているのではないでしょうか。
はっきり言って、このありきたりな物語を、きれいで手堅くまとまった絵で表現されたら、、
いま私が感じているような『虹色ほたる』の魅力は失われてしまうと思います。
そしたらきっと、いま以上に話題にもならなかったかもしれない。(ジブリ作品でもない限りは)
例をあげると、山村という高低差を生かした舞台設定と、それを使った上下の動きに加え、
どこか官能的な身体の躍動を組み合わせることで、子どもならではの疾走感と自由奔放さを
十分に表現した動きは、アニメでなければ、そしてこの作画でなければ、たぶん描くことが
できなかったと思います。
そして、この自由闊達な人体表現を支えるのが、時に写実的、時に情緒的な表現で描かれる、
美術的な背景の存在です。
もしすべてが不定形な線で描かれてしまったら、それはバックやユーリ・ペトロフのように
背景と人物が渾然となった、完全にアート寄りのアニメーションになるでしょう。
しかし『虹色ほたる』では、躍動する子どもの不安定な姿がどれだけ走り回ったとしても、
それを包み込むようにしっかりと支える背景があります。
まるで、彼らを取り巻く大人たちがしっかりと子どもたちを見守っているかのように。
揺るぎのない世界と、その中で絶え間なくうつろう人間によって織り成される光景。
それは見方によっては、最も現実の光景に近いものではないでしょうか。
もしもこれが実写で撮られたなら、それこそ凡庸な作品になったと思います。
そんな作品にある種の非凡さを与えたのが、アニメーションの力であったことについては
やはりきちんと評価されるべきだと思います。
また、twitter上の多くの感想を読むと、さほど時間を置かずに「あの絵に慣れた」という意見が
多数見られることを考えると、絵のクセは観る側が慣れてしまえば問題にならないのが明らか。
ですから、一部の過剰な表現についてはさておき、『虹色ほたる』という作品が終始にわたって
「観客を無視した作画」で構成されていたとするなら、それはやっぱり不当でしょう。
それでも、最後まであの絵がダメだったという人については、最初に予告編か公式サイトを見て、
これは絶対に観ないと決めておくべきだった・・・としか言えません。
嫌いなものは嫌いなままでいいし、いくら努力しても慣れないものはありますからね。
昭和50年代という「失われた時代」に託された原風景の意味は、以前の感想に書きましたが、
この作品が実際よりも田舎を美化している・・・という意見には、そうかもしれないとは思います。
しかし、そもそも主人公は「進んで山に遊びに来た」のであり、誰かに強制されたわけではない。
彼はもともと、(父との想い出も含め)なにがしかの期待を持って、ここに来たわけです。
そしてこの作品は「子ども向けかどうか」とは別に「子どもの目線」で世界を見たものであり、
そのための導入部分として「父とカブトムシを獲りに来た記憶」が配置されているのです。
その意図をわざと見逃すなら、これは映画に対して最初からバリアを張っているに等しい。
また、主人公は地元の子どもにとって「転校生」ではなく「客人」であり、それ自体が一種の
興味の対象ですから、先方から近づいてくることが特に不自然とは言えません。
まして、「村民の親族」という偽装設定があるため、不自然さはさらに減少します。
まあこのへんを「ご都合主義」とするのは否定しないけど、逆に余計なもたつきをなくす上では
うまいことやったなぁ、という感じのほうが強いですね。
さらに、主人公の滞在が一時的なものであること、そして山あいの村の自然とコミュニティが
あと1ヶ月程度で永遠に失われるという時限性が重なり合うことによって、子どもたちの夏は
必然的に切迫した、かけがえのないものになって行きます。
ここで彼らの体験が通常よりも美化されていくのは、むしろ必然のものでしょう。
そして、楽しそうな子どもたちの仕草や表情に見られる細かい演技と、それらにこめられた
高揚感や恥じらい、あるいは葛藤が、時にじわじわ、時にドラマチックに伝わることによって、
観客とキャラクターの距離は縮まっていき、自然に彼や彼女に対する共感を深めていきます。
そのとき、スクリーンに映るのはもう他者ではない、自分の分身としての特別な存在なのです。
もし自分とは別の存在として、登場人物を突き放して見た場合、この感覚は得られないでしょう。
また、ありきたりということは、よく言えば「わかりやすい」ということでもあります。
それはつまり、多くの人の共感を得られる物語だとも言えます。
特に子ども時代の素朴な思い出や肉親の死、さらに恋愛といった素朴な感情に訴えかける内容は、
観客のプライベートな体験と結びついて、広く支持を受けやすい題材なのも確かです。
再度言いますが、物語としてはよく見かけるタイプのお話、ということになるでしょう。
しかし、この「よくある話」を「他ではない表現」で描くことによって、独自の境地に達したのが
『虹色ほたる』という作品であることは、既に説明しました。
ここで、作画と物語の関係について、対象的な2つの例を並べてみます。
1 「見たことのない、個性的でクセのある作画」
2 「みんなが慣れた、キレイにまとまった作画」
3 「見たことのない、個性的でクセのある物語」
4 「みんなが慣れた、キレイにまとまった物語」
たぶん、一番評価が高くなりやすいのは、2と3の組み合わせでしょう。
そして一番多く作られるのが、2と4の組み合わせでしょう。
1と3の組み合わせは、うまくいけば大傑作、あるいはカルト作品になるでしょう。
そして『虹色ほたる』の物語は、間違いなく4です。
だとしたら、他と違う作品にするために選ぶべき選択肢は、ひとつしかありません。
また、いくら凝りに凝ったシナリオでも、物語が初見で「わかりにくい」と思われてしまうと、
観る側の警戒心が強くなってしまいます。
ですから物語そのものはわかりやすく、しかしプロットはやや複雑に(時間線を3本引いている)、
そして演技は密やかに見せることで、それに気づいた人が作中にずるずる引き込まれていくという
非常に手の込んだ作り方をしているのが、『虹色ほたる』の巧みさだと思います。
さて、今回は自分が『虹色ほたる』という作品のどこを評価したか、それだけを書きました。
ですから、あまり良くないと感じたり、あるいは関心のない部分については触れていませんし、
それが何かについても、説明するべきではないと思っています。
なぜなら、それは個性的な作画がやがて気にならなくなるのと同じように、自分にとっては、
この作品の魅力の前では、まったく無視できる程度の不満だからです。
また、そこを直せば・・・という気持ちもある一方で、私以外の人が好きな部分を否定するのも、
なんだか了見が狭い気がしますから、ここでは書かないことにします。
殺伐とした気持ちは、この作品に一番ふさわしくないものですからね。
減点法では測れない『虹色ほたる』の美しさは、観た人が自分でつかむしかありません。
未見の方は、できればソフト化される前に劇場で観ていただき、自ら確かめて欲しいと思います。
賞賛と批判が、かなりくっきり分かれていることがうかがえます。
賞賛については、シンプルな感想から分析的なものまで様々ですが、批判派は数が少ないぶん、
それぞれの主張を強い言葉で表現したり、あるいは仔細に説明しているものが多いですね。
そしておもしろいのが、この批判をひとつひとつ読んでみると、ややぶっきらぼうだったり
肯定派を煽るような文章も見受けられるものの、多くの場合はそれなりに筋が通っていて、
良かれ悪しかれ作品の持つ特徴を、きちんととらえていることです。
これらを参照しながら、自分が『虹色ほたる』をどう見たかを、再度まとめてみようと思います。
これらの批判的な意見をおおまかに分類すると、だいたい次のとおりになります。
1.タイムリープや恋愛要素がご都合主義であり、全般的に論理性や必然性が欠けている。
2.昭和50年代や田舎の素朴さに寄りかかっていて、さらに当時を美化しすぎている。
3.肉親の死や恋愛といった要素に新味がなく、物語そのものが凡庸である。
4.作画が下手な(もしくはうますぎる)ため、観客を無視した極端な表現に走っている。
5.クセのある絵柄にこだわった結果、キャラクターの演技や表現がおろそかになっている。
まずは論理性や必然性について。
これらがすべての物語に不可欠とは思いませんが、本作にそのような部分は確かにあるし、
さらに言っちゃうと、物語自体はとてもありきたりなものだと思います。
口の悪い人なら、たぶん「陳腐」のひとことで片付けられちゃうんじゃないかな。
しかし、そのありきたりなお話を、アニメならではの過剰な作画によって表現したことで、
『虹色ほたる』の場合は「陳腐さ」から逃れているのではないでしょうか。
はっきり言って、このありきたりな物語を、きれいで手堅くまとまった絵で表現されたら、、
いま私が感じているような『虹色ほたる』の魅力は失われてしまうと思います。
そしたらきっと、いま以上に話題にもならなかったかもしれない。(ジブリ作品でもない限りは)
例をあげると、山村という高低差を生かした舞台設定と、それを使った上下の動きに加え、
どこか官能的な身体の躍動を組み合わせることで、子どもならではの疾走感と自由奔放さを
十分に表現した動きは、アニメでなければ、そしてこの作画でなければ、たぶん描くことが
できなかったと思います。
そして、この自由闊達な人体表現を支えるのが、時に写実的、時に情緒的な表現で描かれる、
美術的な背景の存在です。
もしすべてが不定形な線で描かれてしまったら、それはバックやユーリ・ペトロフのように
背景と人物が渾然となった、完全にアート寄りのアニメーションになるでしょう。
しかし『虹色ほたる』では、躍動する子どもの不安定な姿がどれだけ走り回ったとしても、
それを包み込むようにしっかりと支える背景があります。
まるで、彼らを取り巻く大人たちがしっかりと子どもたちを見守っているかのように。
揺るぎのない世界と、その中で絶え間なくうつろう人間によって織り成される光景。
それは見方によっては、最も現実の光景に近いものではないでしょうか。
もしもこれが実写で撮られたなら、それこそ凡庸な作品になったと思います。
そんな作品にある種の非凡さを与えたのが、アニメーションの力であったことについては
やはりきちんと評価されるべきだと思います。
また、twitter上の多くの感想を読むと、さほど時間を置かずに「あの絵に慣れた」という意見が
多数見られることを考えると、絵のクセは観る側が慣れてしまえば問題にならないのが明らか。
ですから、一部の過剰な表現についてはさておき、『虹色ほたる』という作品が終始にわたって
「観客を無視した作画」で構成されていたとするなら、それはやっぱり不当でしょう。
それでも、最後まであの絵がダメだったという人については、最初に予告編か公式サイトを見て、
これは絶対に観ないと決めておくべきだった・・・としか言えません。
嫌いなものは嫌いなままでいいし、いくら努力しても慣れないものはありますからね。
昭和50年代という「失われた時代」に託された原風景の意味は、以前の感想に書きましたが、
この作品が実際よりも田舎を美化している・・・という意見には、そうかもしれないとは思います。
しかし、そもそも主人公は「進んで山に遊びに来た」のであり、誰かに強制されたわけではない。
彼はもともと、(父との想い出も含め)なにがしかの期待を持って、ここに来たわけです。
そしてこの作品は「子ども向けかどうか」とは別に「子どもの目線」で世界を見たものであり、
そのための導入部分として「父とカブトムシを獲りに来た記憶」が配置されているのです。
その意図をわざと見逃すなら、これは映画に対して最初からバリアを張っているに等しい。
また、主人公は地元の子どもにとって「転校生」ではなく「客人」であり、それ自体が一種の
興味の対象ですから、先方から近づいてくることが特に不自然とは言えません。
まして、「村民の親族」という偽装設定があるため、不自然さはさらに減少します。
まあこのへんを「ご都合主義」とするのは否定しないけど、逆に余計なもたつきをなくす上では
うまいことやったなぁ、という感じのほうが強いですね。
さらに、主人公の滞在が一時的なものであること、そして山あいの村の自然とコミュニティが
あと1ヶ月程度で永遠に失われるという時限性が重なり合うことによって、子どもたちの夏は
必然的に切迫した、かけがえのないものになって行きます。
ここで彼らの体験が通常よりも美化されていくのは、むしろ必然のものでしょう。
そして、楽しそうな子どもたちの仕草や表情に見られる細かい演技と、それらにこめられた
高揚感や恥じらい、あるいは葛藤が、時にじわじわ、時にドラマチックに伝わることによって、
観客とキャラクターの距離は縮まっていき、自然に彼や彼女に対する共感を深めていきます。
そのとき、スクリーンに映るのはもう他者ではない、自分の分身としての特別な存在なのです。
もし自分とは別の存在として、登場人物を突き放して見た場合、この感覚は得られないでしょう。
また、ありきたりということは、よく言えば「わかりやすい」ということでもあります。
それはつまり、多くの人の共感を得られる物語だとも言えます。
特に子ども時代の素朴な思い出や肉親の死、さらに恋愛といった素朴な感情に訴えかける内容は、
観客のプライベートな体験と結びついて、広く支持を受けやすい題材なのも確かです。
再度言いますが、物語としてはよく見かけるタイプのお話、ということになるでしょう。
しかし、この「よくある話」を「他ではない表現」で描くことによって、独自の境地に達したのが
『虹色ほたる』という作品であることは、既に説明しました。
ここで、作画と物語の関係について、対象的な2つの例を並べてみます。
1 「見たことのない、個性的でクセのある作画」
2 「みんなが慣れた、キレイにまとまった作画」
3 「見たことのない、個性的でクセのある物語」
4 「みんなが慣れた、キレイにまとまった物語」
たぶん、一番評価が高くなりやすいのは、2と3の組み合わせでしょう。
そして一番多く作られるのが、2と4の組み合わせでしょう。
1と3の組み合わせは、うまくいけば大傑作、あるいはカルト作品になるでしょう。
そして『虹色ほたる』の物語は、間違いなく4です。
だとしたら、他と違う作品にするために選ぶべき選択肢は、ひとつしかありません。
また、いくら凝りに凝ったシナリオでも、物語が初見で「わかりにくい」と思われてしまうと、
観る側の警戒心が強くなってしまいます。
ですから物語そのものはわかりやすく、しかしプロットはやや複雑に(時間線を3本引いている)、
そして演技は密やかに見せることで、それに気づいた人が作中にずるずる引き込まれていくという
非常に手の込んだ作り方をしているのが、『虹色ほたる』の巧みさだと思います。
さて、今回は自分が『虹色ほたる』という作品のどこを評価したか、それだけを書きました。
ですから、あまり良くないと感じたり、あるいは関心のない部分については触れていませんし、
それが何かについても、説明するべきではないと思っています。
なぜなら、それは個性的な作画がやがて気にならなくなるのと同じように、自分にとっては、
この作品の魅力の前では、まったく無視できる程度の不満だからです。
また、そこを直せば・・・という気持ちもある一方で、私以外の人が好きな部分を否定するのも、
なんだか了見が狭い気がしますから、ここでは書かないことにします。
殺伐とした気持ちは、この作品に一番ふさわしくないものですからね。
減点法では測れない『虹色ほたる』の美しさは、観た人が自分でつかむしかありません。
未見の方は、できればソフト化される前に劇場で観ていただき、自ら確かめて欲しいと思います。










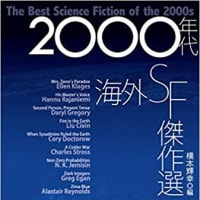


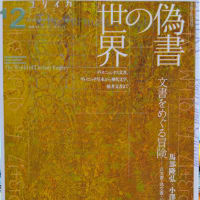













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます