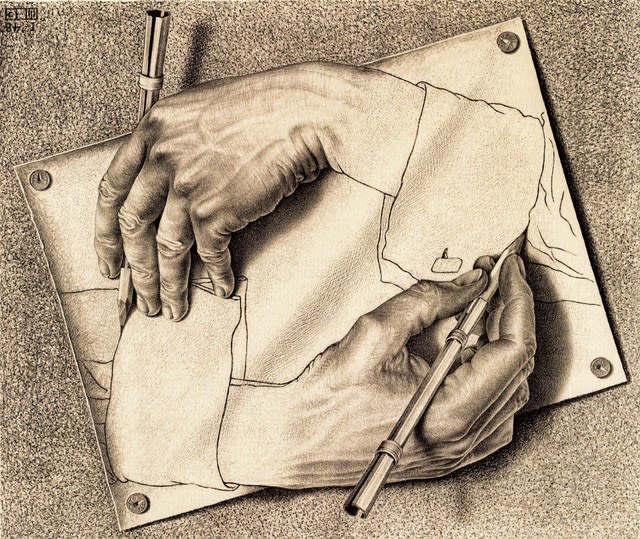年末年始は今年も浜松の実家で過ごした。
壁に掛けてある母の俳句の新作を毎年楽しみにしている。
ベストオブ2018年俳句の2句
鳩の目のまんまる琥珀若葉風
若葉は夏の季語。若葉の間を爽やかな初夏の風が吹く頃、鳩が庭に巣を作った。巣の中にいる愛らしい琥珀色の目をした小鳩を詠んだ歌である。
もう1句
ペダル踏む初登校や風光る
『風光る』は春の季語。冬の弱々しい日光が春になると力を増し、風さえも輝いて見えるようになる。そんな輝く春に初めて高校生になり、自転車で初登校する孫娘(僕から見ると姪)を詠んだ歌。
色紙に書かれた母の句の文字は姪の筆による。