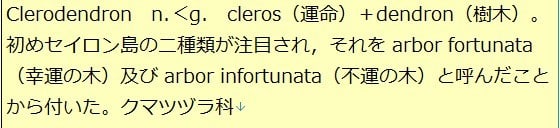ふつうに「ハイビスカス」といってるけど、Hybisucus というのは フヨウ属のことなんですね。
Hibiscus mutabilis ((色が)変化しやすいヒビスクス)というのは フヨウ のことです。
Hibiscus syriacus (シリアのヒビスクス)といったら ムクゲ のことです。
Hibiscus coccineus (緋紅色のヒビスクス)なら、モミジアオイです。

で、私たちがふつうに「ハイビスカス」(和名で
ブッソウゲ)と呼んでいる種類のこの花は
学名では Hibiscus hybridus (交雑種のヒビスクス(フヨウ属))
または Hibiscus rosa-sinensis (
支那のバラのヒビスクス)なんです。
「中国(又はインド)などの熱帯アジアが原産地ではないかと推定されているが、中国やインドで原種の自生種は発見されていない。染色体数も幅が広く、Hibiscus rosa-sinensis は交雑種と推定されている。」(三河の植物観察「ブッソウゲ 扶桑花」)

そんなことより、分かりやすいこの花シベを見てください(^^♪
この下側のオレンジ色(朱色)の外壁をもった円筒から 黄色い葯を立ち上げている器官が雄しべの花糸部分が合着して筒になった「雄しべ筒」です。
上側の赤い毛玉のようなのが雌しべの柱頭で、花柱が下の雄しべ筒の中を貫いて伸びてきて、抜け出た先で柱頭を展開しています。
(めしべとおしべ筒の色が違うので 境目がよくわかります)

柱頭には花粉を受け取りやすいように毛が生えています。

これは 八重のブッソウゲです。
八重の花弁部分は 主としておしべが花弁化するといわれていて、八重咲きスイセンなどでは おしべが無くなっているのがふつうですが、このブッソウゲでは 花シベ構造が残っています。

このブッソウゲはおしべ筒はオレンジ色(朱色)をしていてはっきりわかりますが、その先の雌しべの柱頭部分が見当たりません。
前回やった タチアオイのように 雌雄異熟で 雌しべは後から出てくるのかとも思いましたが、ブッソウゲ(いわゆるハイビスカス)についてはそういう記述は見当たりませんでいた。
(単に 園芸センターで ポキリと折れてしまったのかも?真相は不明です)

ブッソウゲというと、よくこんな風に なが~い花シベがありますね。
花弁は 虫を呼ぶためにあるのが本来なのに、こんなに 花シベが離れていては 役目が果たせないですね?(´v_v`)

雌しべとおしべが組み合わさっているといっても、雌しべの柱頭が必ず上にあります。自家受粉しないためです。
ところが 花シベが長~くなってくると 自重で下を向いていることもあります。
そうなると、
蜜(花弁の付け根)> おしべ > 柱頭
の順に上から並ぶことになるので、これでは チョウが蜜を吸いに おしべ筒に止まると 花粉がその下の柱頭に振りかかることになります。