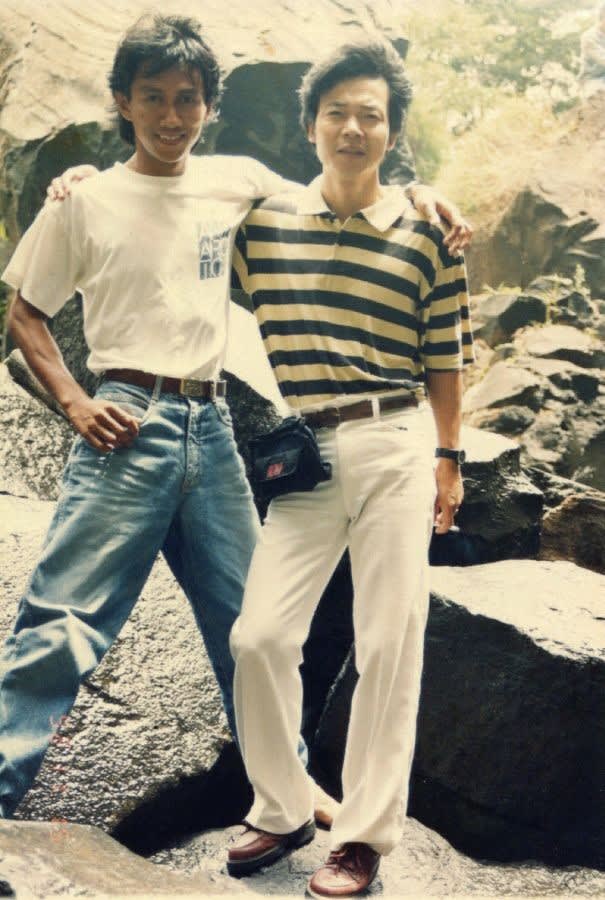<style type="text/css"></style>
<style type="text/css"></style>
| アカザ | APGではヒユ科の中に含まれる。 |
| アガパンサス | ヒガンバナ科 |
| アキノキリンソウ | キク科 |
| アキノノゲシ | キク科タンポポ亜科 |
| アケビ | アケビ科⇒【つる植物】 |
| アゲラタム | キク科 |
| アスパラガス | ⇒【ユリ科ユリズイセン科キジカクシ科】 |
| アセビ | ツツジ科 |
| アップルミント | シソ科ハッカ属 |
| アブチロン | アオイ科 |
| アメリカキンゴジカ | アオイ科キンゴジカ属の帰化植物 |
| アメリカテマリシモツケ | バラ科テマリシモツケ属 |
| アメリカノリノキ | アジサイ科 |
| アメリカフウロ | フウロソウ科フウロソウ属(Geranium) |
| アメリカフヨウ | アオイ科Malvaceaeフヨウ属 Hibiscus |
| アメリカンブルー | ヒルガオ科 |
| アルストロメリア | ユリズイセン科 |
| アレチウリ | ウリ科 |
| アレチハナガサ |
クマツヅラ科クマツヅラ属 (Verbena ヴァーベナ)
|
| アンスリウム | サトイモ科 |
| イシミカワ | タデ科 |
| イソギク | キク科 |
| イタドリ | タデ科ソバカズラ属 Fallopia |
| イチビ | アオイ科イチビ属(アブチロン属)の一年草 |
| イヌサフラン | イヌサフラン科⇒【園芸植物】 |
| イヌタデ | タデ科 Persicaria(イヌタデ属) の一年草 |
| イヌビワ | クワ科イチジク属 |
| イヌホオズキ | ナス科 |
| イヌマキ | 南半球を代表する針葉樹のグループ |
| イノコヅチ | ヒユ科 |
| イボクサ | ツユクサ科 |
| イポメア・ロバータ | ヒルガオ科 Ipomeaイポメア属(サツマイモ属) |
| ウイキョウ(フェンネル) | セリ科 |
| ウィンターコスモス |
キク科キク亜科センダングサ属( Bidens)より別名ビデンス。
|
| ウォーターカンナ | クズウコン科タリア属 ⇒ 園芸植物 |
| ウコン | ショウガ科ウコン属(Curcuma) |
| ウツギ | アジサイ科ウツギ属(Deutzia ドイツィア) |
| エキザカム | リンドウ科 ベニヒメリンドウ属(エキザカム属) |
| エキナセア | キク科 |
| エノキ ムクノキ |
アサ科 |
| エビスグサ | マメ科Senna |
| エビヅル | ブドウ科 |
| エラチオール・ベゴニア | シュウカイドウ科 |
| エリカ | ツツジ科 |
| オオアレチノギク | キク科 |
| オオイヌノフグリ | オオバコ科 |
| オオキンケイギク |
キク科キク亜科ハルシャギク属 Coreopsis の宿根草
|
| オオデマリ | ガマズミ属 |
| オオニシキソウ | トウダイグサ科トウダイグサ属 |
| オオバヤシャブシ | カバノキ科 ⇒【広葉樹】 |
| オオブタクサ | キク科ブタクサ属 |
| オオマツヨイグサ | アカバナ科 |
| オカトラノオ | サクラソウ科オカトラノオ属 |
| オカワカメ | ツルムラサキ科 ⇒【つる植物】 |
| オクラ | アオイ科トロロアオイ属 |
| オミナエシ |
APG植物分類体系ではスイカズラ科に含まれるが、オミナエシ科として分離してもよいとしている。
|
| カエデドコロ | ヤマノイモ科⇒【つる植物】 |
| ガガイモ | キョウチクトウ科 |
| カゲツ(カネノナルキ) | ベンケイソウ科クラッスラ属 |
| カボチャ | ウリ科 |
| カラスザンショウ | ミカン科 |
| カランコエ | ベンケイソウ科 |
| カランコエ | ベンケイソウ科 |
| カロライナジャスミン | ゲルセミウム科ゲルセミウム属の園芸品種 |
| カワラマツバ | アカネ科 |
| カンパニュラ | キキョウ科 |
| キキョウソウ | キキョウ科 |
| キバナセンニチコウ | ヒユ科 |
| キミガヨラン | キジカクシ科 Yuccaユッカ属 |
| キャッツ・テイル | トウダイグサ科 |
| キュウリグサ | ムラサキ科 |
| ギョリュウバイ | フトモモ科 |
| キリアサ | 【イチビを見よ】 |
| キルタンサス | ヒガンバナ科 |
| キンギンボク |
学名: Lonicera morrowii)はスイカズラ科スイカズラ属の落葉低木
|
| キンシバイ |
オトギリソウ科オトギリソウ属の半常緑(半落葉)小低木
|
| ギンバイカ | フトモモ科 |
| クサギ |
シソ科(←クマツヅラ科)Clerodendrumクサギ属
|
| クジャクアスター | キク科 |
| クチナシ | アカネ科 |
| クミスクチン | シソ科オルトシフォン属 |
| クラスペディア・グロボーサ | キク科 |
| クラリンドウ |
シソ科(←クマツヅラ科)クサギ属(Clerodendrum)
|
| クルクマ・メージョー・ジャスミン | ショウガ科クルクマ属 |
| クレオメ | フウチョウボク科 |
| クレマチス | キンポウゲ科センニンソウ属(Clematis) |
| クロッサンドラ | キツネノマゴ科 |
| ゲンペイカズラ | シソ科クサギ属 |
| コエビソウ | キツネノマゴ科 |
| コーヒーノキ | アカネ科 |
| コキア | ヒユ科 |
| ゴボウ | キク科アザミ亜科ゴボウ属 |
| コンロンカ | アカネ科コンロンカ属 |
| サギゴケ |
新分類(APGⅢ)ではゴマノハグサ科
(Scrophulariaceae)からハエドクソウ科に移され、 さらにサギゴケ科として独立 |
| ザクロ | ザクロはバラ科ではなく、ミソハギ科の植物 |
| サマー・クリスマス・ブッシュ | クノニア科 |
| サルビア・ガラニチカ | シソ科 Salviaサルビア(アキギリ)属 |
| サンシュユ | ミズキ科 |
| サンショウ | ミカン |
| サンタンカ | アカネ科 |
| シコンノボタン | (ノボタン科ティボウキナ属(和名シコンノボタン属)の常緑低木) ⇒ 園芸植物 |
| シャクナゲ | ツツジ科 |
| シャシャンボ | ツツジ科 |
| ジャノメエリカ | ツツジ科エリカ属 |
| シャリンバイ | バラ科ナシ亜科シャリンバイ属 |
| ジュズサンゴ | ジュズサンゴ科 |
| ジュズダマ | イネ科 |
| 宿根バーベナ |
クマツヅラ科クマツヅラ属(Verbena バーベナ属)
|
| シラー | キジカクシ科 |
| シラー・ペルビアナ | キジカクシ科 |
| シロシキブ | シソ科ムラサキシキブ属の落葉低木 |
| スイセン | ヒガンバナ科 |
| スイバ | タデ科 |
| スイバ | タデ科 |
| スズメノヤリ | イグサ科 ⇒ 【イネ科・イグサ科】 |
| スベリヒユ | スベリヒユ科 |
| セイタカアワダチソウ | キク科キク亜科アキノキリンソウ属 |
| セイヨウイワナンテン | ツツジ科 |
| セイヨウシャクナゲ | ツツジ科 |
| 西洋シャクナゲ | ツツジ科ツツジ属 (Rhododendron) |
| セイヨウニンジンボク | シソ科 |
| セイヨウバイカウツギ | アジサイ科バイカウツギ属(Philadelphus) |
| セイヨウヒキヨモギ | ハマウツボ科(旧ゴマノハグサ科)ヒサウチソウ属。 ヨーロッパ原産の半寄生植物で、日本では 帰化植物として知られています |
| セイロンライティア | キョウチクトウ科ライティア属 |
| ゼラニウム | フウロソウ科 |
| センニチコウ | ヒユ科 |
| センニンソウ | キンポウゲ科 Clematisセンニンソウ属 |
| ソバ | タデ科 |
| ソラヌム | ナス科Solanum(ナス属) |
| ターメリック | ショウガ科ウコン属(Curcuma) |
| タイツリソウ | ケシ科 |
| タカサブロウ | キク科タカサブロウ属の一年草 |
| ダチュラ | ナス科チョウセンアサガオ属Datura |
| タニウツギ |
スイカズラ科タニウツギ属(Weigela )の落葉低木。
|
| タニワタリノキ | アカネ科 |
| タニワタリノキ | アカネ科 |
| チカラシバ | イネ科 ⇒【イネ科・イグサ科】 |
| チャノキ | ツバキ科 Camellia ツバキ(カメリア)属 |
| チューリップ | ユリ科 |
| チューリップ | ユリ科 |
| チョウセンアサガオ | ナス科 Datura(チョウセンアサガオ属) |
| ツリガネニンジン | キキョウ科 |
| ツリバナ | ニシキギ科 |
| ツルニチニチソウ | キョウチクトウ科 |
| ツルボ | ユリ科ユリズイセン科キジカクシ科 |
| ツルムラサキ | ツルムラサキ科 ⇒【つる植物】 |
| デュランタ・タカラヅカ | クマツヅラ科デュランタ属 |
| トウモロコシ | イネ科 |
| トキワハゼ | ハエドクソウ科の一年草 |
| ドクダミ | ドクダミ科 |
| トケイソウ・クダモノトケイソウ | トケイソウ科 |
| トサミズキ | マンサク科 |
| ドドナエア | オーストラリア原産のムクロジ科の常緑低木 |
| トベラ | トベラ科 |
| トマト | ナス科 |
| トリトマ | ツルボラン科 |
| トレニア(ハナウリクサ) | アゼナ科(←ゴマノハグサ科) |
| ドンベア | アオイ科 |
| ナツメ | クロウメモドキ科ナツメ属 Ziziphus |
| ナワシロイチゴ | バラ科キイチゴ属(Rubus) |
| ニオイバンマツリ | ナス科 |
| ニゲラ | キンポウゲ科クロタネソウ属(Nigella) |
| ニッコウキスゲ | ツルボラン科 |
| ニラ | ヒガンバナ科ネギ属 ⇒【ヒガンバナ科(含ネギ亜科)】 |
| ニワウルシ | ニガキ科の落葉高木 |
| ニワゼキショウ | アヤメ科 |
| ニワナナカマド | バラ科 |
| ヌルデ | ウルシ科 |
| ネギ | ヒガンバナ科 |
| ネジキ | ツツジ科ネジキ属 |
| ネジバナ | ラン科 |
| ノアズキ | マメ科 |
| ノゲシ | キク科タンポポ亜科 |
| バイカウツギ | アジサイ科バイカウツギ属 (Philadelphus) |
| パイナップルリリー | (キジカクシ科ユーコミス属) |
| ハイビスカス● | アオイ科フヨウ属 Hibiscus |
| ハクチョウソウ | アカバナ科 |
| ハグマノキ | ウルシ科 |
| ハコベ | ナデシコ科 |
| ハゴロモジャスミン | モクセイ科 |
| ハゼラン | ハゼラン科(←スベリヒユ科) |
| ハナトラノオ | シソ科 |
| パボニア・インテルメディア | アオイ科 ヤノネボンテンカ属 |
| ハリモミ | 針葉樹 |
| ハルシャギク | キク科キク亜科 ハルシャギク属 Coreopsis |
| パンパスグラス | イネ科 |
| ピーマン |
ナス科(ナス科トウガラシ属の野菜で、パプリカや 唐辛子などと同じ仲間)
|
| ヒゴロモコンロンカ | アカネ科 |
| ヒサカキ | ツバキ科 |
| ヒトツバタゴ | モクセイ科 |
| ヒペリカム | オトギリソウ科オトギリソウ属(Hypericum) |
| ヒマワリ | キク科キク亜科ヒマワリ属 |
| ヒメイワダレソウ | クマツヅラ科 |
| ヒメコリウス | シソ科 |
| ヒメヒイラギ(アマミヒイラギ) | モチノキ科 モチノキ属 Ilex |
| ヒメヒオウギズイセン |
アヤメ科ヒオウギズイセン属(クロコスミア属)の雑種
|
| ヒョウタンボク |
学名: Lonicera morrowii)はスイカズラ科スイカズラ属の落葉低木
|
| ヒヨドリジョウゴ | ナス科 |
| ヒレタゴボウ | アカバナ科チョウジタデ属(Ludwigia) |
| ビロードモウズイカ | ゴマノハグサ科モウズイカ属 |
| ブーゲンビレア | オシロイバナ科 |
| フウセンカズラ | ムクロジ科 |
| フウセントウワタ | キョウチクトウ科(←ガガイモ科) ⇒【キョウチクトウ科】 |
| フウリンホオズキ | ナス科 |
| フサアカシア | マメ科 |
| ブタクサ | キク科ブタクサ属 |
| ブットレア | ゴマノハグサ科フジウツギ属(Buddleja) ⇒【オオバコ・ゴマノハグサ科】 |
| ブルーキャッツアイ | オオバコ(旧ゴマノハグサ)科 ⇒【オオバコ・ゴマノハグサ科】 |
| ブルーベリー | ツツジ科 |
| プレクトランサス | シソ科プレクトランサス属 |
| ヘクソカズラ | アカネ科 |
| ベゴニア | シュウカイドウ科 |
| ベゴニア | シュウカイドウ科 |
| ベニオクラ | アオイ科トロロアオイ属 |
| ペニセタム | イネ科チカラシバ属Pennisetum の宿根草。 |
| ベニヒモノキ | トウダイグサ科 |
| ベロニカ | オオバコ科クワガタソウ属(ベロニカ属)の園芸 |
| ホウキギ | ヒユ科 |
| ホオズキ | ナス科 |
| ボタン | ボタン科ボタン属(Paeonia) |
| ボタンクサギ | シソ科クサギ属 |
| ホトケノザ | シソ科 |
| ホトトギス | ユリ科ホトトギス属の多年草 ⇒【ユリ科ユリズイセン科キジカクシ科】 |
| ボロニア | ミカン科 |
| ホワイト・コンロンカ | アカネ科 |
| マダガスカルジャスミン | キョウチクトウ科 |
| マツバウンラン | オオバコ科マツバウンラン属 |
| マツヨイグサ | アカバナ科マツヨイグサ属 |
| ママコノシリヌグイ | タデ科 |
| マメグンバイナズナ | アブラナ科 |
| マンデビラ | キョウチクトウ科マンデビラ属の園芸品種 |
| ミズカンナ・ウォーターカンナ | クズウコン科タリア属(Thalia) |
| ミズヒキ | タデ科のイヌタデ属(Persicaria) |
| ミゾソバ | タデ科のイヌタデ属(Persicaria) |
| ミッキーマウスノキ | オクナ科オクナ属の低木。観賞用に栽培される |
| ミツマタ | ジンチョウゲ科 |
| ムスカリ | キジカクシ科 |
| ムラサキサギゴケ | サギゴケ科 |
| ムラサキシキブ | シソ科 |
| メドハギ | マメ科 |
| メヒシバ | イネ科 |
| メヤブマオ | イラクサ科カラムシ属の在来種 |
| メランポジウム | キク科 |
| モクゲンジ | ムクロジ科⇒【ムクロジ(←カエデ)科】 |
| ヤイトバナ | アカネ科 |
| ヤナギハナガサ | クマツヅラ科クマツヅラ属(Verbena)の多年草 |
| ヤブガラシ | ブドウ科 |
| ヤブジラミ | セリ科ヤブジラミ属(Torilis) 学名は Torilis japonica |
| ヤブラン | キジカクシ科 Liriopeヤブラン属 ⇒ ユリ科ユリズイセン科キジカクシ科 |
| ヤマブキ | バラ科 |
| ヤマモモ | |
| ユリノキ | モクレン科 |
| ヨウシュチョウセンアサガオ | ナス科Daturaチョウセンアサガオ属 |
| ランタナ | クマツヅラ科の常緑低木 |
| ルドベキア |
キク科キク亜科オオハンゴンソウ属 Rudbeckia
|
| ルピナス | マメ科 |
| ルリタマアザミ | キク科アザミ亜科ヒゴタイ属 Echinops |
| ルリトラノオ | オオバコ科クワガタソウ属(ベロニカ属)の園芸品種 |
| ルリマツリ | (イソマツ科ルリマツリ属) |
| ルリヤナギ | ナス科ナス属 |
| レンギョウ | モクセイ科 |
| ワレモコウ | バラ科バラ亜科 |
| 宿根ロベリア・スペシオサ | キキョウ科 |