■『ヴェルクマイスター・ハーモニー』(ハンガリー、ドイツ、フランス、2000年)
Werckmeister Harmoniak
監督 : タル・ベーラ Tarr Bela
原作 : クロスナホルカイ・ラースロー「抵抗の憂鬱」
2時間25分の上映時間に、たった37カット。「編集し尽くしNGを小刻みに差し替えて作り出すシミュレーション世界が映画だ」という暗黙の常識をさらりと侵犯していく、剥き出しの時間芸術。思わせぶりな素材はぎっしり。平均律を創始した音楽学者アンドレアス・ヴェルクマイスター(Andreas Werckmeister, 1645-1706)への論及、サーカスのクジラの見せ物、暴動、軍の出動など、それなりの素材が互いに繋がりそうな関係なさそうな、ゆるやかな連絡で羅列されてゆく。口述記録する音楽家の顔アップ360度撮影、クジラを積んだ巨大トラクターが夜の街路をゆっくり走る場面、無言で歩くところを延々と追ってゆくだけのシーン、群衆が一方向に歩くシーン、ヘリコプターの旋回シーンなどが、無駄と思われるほどの長回しでこれでもかとばかり提示され続けると、観ているほうはいい加減根負けしてくる、そんな映画だ。
正直のところかなり退屈な映画なのだが(相当気持ちに余裕のあるときでないと全尺を真面目に観賞する気になれないかもしれない)、ポイントポイントに配置されたディテール集中シーンに誘われて、ずるずると魅入ってしまうのが不思議。
ただ、ハンガリーという特殊な風土ならではの「特殊な映画」と見なしてすむかどうか。たしかに、オーストリア・ハンガリー二重帝国の第一次大戦敗戦による国民分断、失地回復を目指してナチス・ドイツの同盟国として最後まで戦った第二次大戦、共産主義国ハンガリー人民共和国下でのハンガリー動乱(1956年)、ソ連軍の介入、冷戦終結とともにハンガリー共和国発足、といった民族の歴史を知った上でないと、この不思議な作品は理解できないかもしれない。とくに、時間の流れ方がハリウッドとは全然違うこと。先進資本主義国のテンポとはまったく異なる「東欧の奥地」を感じさせる(やはり意図的だろうか)。とはいえ、ここで使われた反編集ともいうべき手法は芸術表現の普遍的な一側面を表わしている。色彩の否定、科白とカットの抑制、同じミニマル的BGMの多用、などは、映画に本来できることを極力排除して、最低限の表現資源で最大限の結実を得ようとする、表現の初心というべきものを象徴していた。その一種の<最大化原理>が、この映画の中の意味不明の民衆暴動(病院襲撃)にも共通した「最小限のテーマ」だったのかもしれない。
Werckmeister Harmoniak
監督 : タル・ベーラ Tarr Bela
原作 : クロスナホルカイ・ラースロー「抵抗の憂鬱」
2時間25分の上映時間に、たった37カット。「編集し尽くしNGを小刻みに差し替えて作り出すシミュレーション世界が映画だ」という暗黙の常識をさらりと侵犯していく、剥き出しの時間芸術。思わせぶりな素材はぎっしり。平均律を創始した音楽学者アンドレアス・ヴェルクマイスター(Andreas Werckmeister, 1645-1706)への論及、サーカスのクジラの見せ物、暴動、軍の出動など、それなりの素材が互いに繋がりそうな関係なさそうな、ゆるやかな連絡で羅列されてゆく。口述記録する音楽家の顔アップ360度撮影、クジラを積んだ巨大トラクターが夜の街路をゆっくり走る場面、無言で歩くところを延々と追ってゆくだけのシーン、群衆が一方向に歩くシーン、ヘリコプターの旋回シーンなどが、無駄と思われるほどの長回しでこれでもかとばかり提示され続けると、観ているほうはいい加減根負けしてくる、そんな映画だ。
正直のところかなり退屈な映画なのだが(相当気持ちに余裕のあるときでないと全尺を真面目に観賞する気になれないかもしれない)、ポイントポイントに配置されたディテール集中シーンに誘われて、ずるずると魅入ってしまうのが不思議。
ただ、ハンガリーという特殊な風土ならではの「特殊な映画」と見なしてすむかどうか。たしかに、オーストリア・ハンガリー二重帝国の第一次大戦敗戦による国民分断、失地回復を目指してナチス・ドイツの同盟国として最後まで戦った第二次大戦、共産主義国ハンガリー人民共和国下でのハンガリー動乱(1956年)、ソ連軍の介入、冷戦終結とともにハンガリー共和国発足、といった民族の歴史を知った上でないと、この不思議な作品は理解できないかもしれない。とくに、時間の流れ方がハリウッドとは全然違うこと。先進資本主義国のテンポとはまったく異なる「東欧の奥地」を感じさせる(やはり意図的だろうか)。とはいえ、ここで使われた反編集ともいうべき手法は芸術表現の普遍的な一側面を表わしている。色彩の否定、科白とカットの抑制、同じミニマル的BGMの多用、などは、映画に本来できることを極力排除して、最低限の表現資源で最大限の結実を得ようとする、表現の初心というべきものを象徴していた。その一種の<最大化原理>が、この映画の中の意味不明の民衆暴動(病院襲撃)にも共通した「最小限のテーマ」だったのかもしれない。












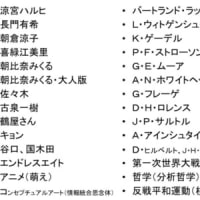
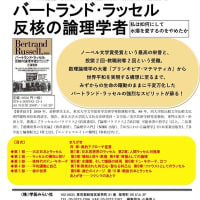
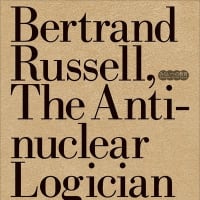
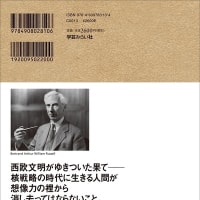
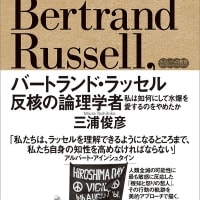
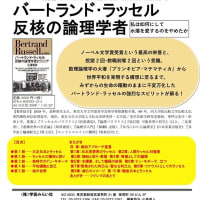

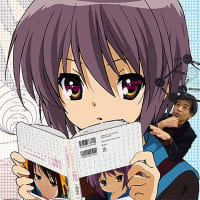
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます