こんにちは‥(^_-)-☆

今日の奈良s降っていた雨もやんで、22℃と少し涼しいですね。
セ、パ両リーグは11日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セの投手は阪神・村上頌樹投手が受賞した。
月間5試合の先発で3勝0敗、防御率0・69。「自分一人だけの力じゃない。野手の方々が守ってくれている。
みなさんに感謝したい」と話した。
月間MVP賞は2023年3、4月度以来、自身2度目。
開幕から12球団トップの7勝を挙げ、防御率1・47と抜群の安定感を誇るエースは「(毎週金曜日の登板で)チームの勝敗に関わってくるっていう自覚を持って投げている。
いい緊張感のなかでずっと投げているのが、こういう結果にもつながっているのかなと思っている」と明かした。
今日は傘の日なんですね・・(^_-)-☆
東京都台東区浅草橋に事務局を置き、洋傘の品質向上や安全性の確立などを追及する日本洋傘振興協議会(JUPA)が1989年(平成元年)に制定。
日付はこの日が暦の上で「梅雨入り」を意味する雑節の一つ「入梅」になることが多いことから。
今年は6月9日 (月)、気象台は中国地方と近畿地方、東海地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。
それぞれ平年より3日遅く、昨年よりは中国地方で11日、近畿地方で8日、東海地方では12日早い梅雨入りです。
今日は梅雨前線がやや北上して、九州南部にかかってきました。
西日本や東海にも梅雨前線の雲がかかり、雨の降り出しているところがあります。
この季節の必需品である傘の販売促進と傘の使い方などモラルの向上が目的。
梅雨の時期に入る日。
または梅雨の季節。梅の実が熟す頃。
太陽の黄経が80度の日。6月10日頃。
雑節の一つ。
梅雨明けのことを出梅という。
「梅雨入り」とは実際に梅雨の期間に入ることを指す気象用語のこと。
中国から梅雨という言葉が伝わる前は、日本の旧暦では5月で「五月雨」と言われていた。
俳句では夏の季語。
令和7年の今年の入梅は6月11日(水曜日)です。
日本洋傘振興協議会(Japan Umbrella Promotion Association:JUPA)は、全国の洋傘製造業者有志により、1963年(昭和38年)3月に設立されてから既に50年を超える歴史のある団体である。
その間、会員企業は洋傘の品質向上と安全性の確立はもとより、常にファッショントレンドの研究や機能性の向上を追求し、より高付加価値製品の開発に努力している。
また、同協議会では、独自にJUPA(ジュパ)基準を設定し、会員の洋傘の品質・信頼・安心の証として、JUPAマークを添付している。
江戸時代後期の1804年(文化元年)、長崎に入港した中国(清)からの唐船の舶載品目の中に「黄どんす傘一本」との記述が見られる。
これ以前にも、安土桃山時代に堺の商人が豊臣秀吉に傘を献上した記録など、洋傘が海外から日本に持ち込まれた形跡はあるが、江戸時代の「黄どんす傘」が洋傘として特定できる最古の記録とされている。
ちなみに、どんす(緞子)とは、室町時代に中国(明)から伝えられたとされる絹の紋織物で、地は繻子(しゅす)織(サテン)で、地と表裏が反対になった繻子織の裏組織で模様を織り出したもの。
光沢があり高級織物の代名詞とされる。
厚地のものは礼装用の帯地、薄地のものは布団や座布団の生地として使われる。
明治時代、洋傘の輸入本数は多くなり、文明開化の波とともに洋傘は一気に市民の手に渡っていった。
1868年(明治元年)に刊行された「武江年表」という書物に、「この年から庶民にも洋傘が普及し始めた」との記述がされている。
入梅とは、季節の移りかわりの目安となる雑節のひとつで、暦の上ではこの日から梅雨の季節に入ります。
昔は、「芒種:二十四節気のひとつで6月6日頃)以降の、最初の壬(みずのえ)の日」または「立春から数えて135日目」などとされていましたが、現在は「太陽の黄経が80度に達した日」で、毎年6月11日頃になります。
今朝の血圧は、145-83、脈拍は80、血糖値は、174でした。
体温は36.9℃でした。
昨日の散歩数は、10236歩でした。
今日も良い日でありますように・・(^_-)-☆










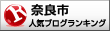











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます