こんばんは‥(^_-)-☆

今日の奈良は朝から、また雨が降ってきました。
その性で、気温も26どと少し涼しい日になりましたね。
私は土用の丑の日にウナギを食べるために二匹のウナギを買いました。
だけど、土用の丑に日がいつか分からないので調べると?・・
2025年は7月19日(土)と7月31日(木)の2日間が、夏の土用の丑の日にあたります。
「土用」とは、日本の暦の中で、季節の変わり目を示す期間のことです。
私たちの暮らしに深く関わる季節は、立春、立夏、立秋、立冬という4つの節目で区切られています。
「土用」とは、これらの立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間を指します。
つまり、土用は年に4回あるのですね。
この考え方のルーツは、古代中国から伝わった「陰陽五行説」にあります。
この説では、自然界のあらゆるものは木・火・土・金・水という5つの要素で成り立っていると考えられています。
春には「木」、夏には「火」、秋には「金」、冬には「水」の気を割り当て、そして各季節の終わりに残った「土」の気を割り当てたのが「土用」なのです。
昔の人々は、この土用の期間を「土の気が盛んになる時期」と考え、土を司る神様である「土公神」が支配する期間としました。
そのため、土を動かす作業、例えば畑仕事や家の増改築、井戸掘りなどは控えるべきとされていました。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあるため、無理をせず、静かに過ごし、次の季節に備える養生の期間という意味合いもあったのですよ。
昔の日本では、日付や方角、時刻などを「十二支」で数える習慣がありました。
十二支とは、皆さまお馴染みの「子・丑・寅・卯…」のことです。
この十二支を1日ごとに割り当てていくと、「丑の日」は12日周期で巡ってくることになります。
「土用」の期間は約18日間あります。
そして「丑の日」は12日ごとに巡ってきますね。
この組み合わせによって、一つの土用期間中に「丑の日」が1回だけの場合と、2回巡ってくる場合があるのです。
もし土用期間中に丑の日が2回ある場合は、最初の丑の日を「一の丑(いちのうし)」、2回目の丑の日を「二の丑(にのうし)」と呼びます。
特に夏の土用は、暑さで体力が消耗しやすいため、栄養価の高いうなぎを食べる習慣と結びつき、他の季節の土用の丑の日よりも広く知られるようになったのですね。
うなぎは冬が旬とされ、夏場は脂が落ちて味が落ちると思われていたためか、あまり売れ行きが良くなかったそうです。
困ったうなぎ屋の主人が、博識でアイデアマンとして有名だった平賀源内に相談を持ちかけました。
そこで源内は、「本日土用丑の日」と書いた貼り紙を店先に掲げることを提案します。
「丑の日に『う』のつくものを食べると夏負けしない」という民間伝承があったことから、これが大当たり。
お店は大繁盛し、他のうなぎ屋もこぞって真似するようになり、やがて夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が定着した、というお話です。
これは一節で本当かどうかは分かりませんが?・・
私はウナギをたまたま二匹飼ったので、19日と31日に一匹づつ食べますね。
今日も良い日でありますように・・(^_-)-☆










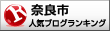











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます