

津和野駅(つわのえき)は、旧・津和野町の中心部に立地しており周辺には観光名所や観光客向け店舗・宿泊施設などが多い観光地の要所にあります。駅前を島根県道13号萩津和野線が通り、駅の東側約200mの場所を津和野川が山口線に並行して流れ、その川向こうを国道9号が並行します。

所在地は島根県鹿足郡津和野町後田です、山口県と誤解されることが多いですが、津和野駅は島根県です。西日本旅客鉄道(JR西日本)山口線の駅です。駅前のロータリーは広く綺麗に整備されています。待合室にはキオスクとそば屋兼弁当屋が営業しています。

「山陰の小京都」と称される観光の町、津和野の玄関口の駅で、蒸気機関車C571が牽引する快速「SLやまぐち号」の終着駅です。津和野町(つわのちょう)は、日本の中国地方、島根県南西部にある町。「山陰の小京都」と呼ばれ、50km西にある山口県萩市とともに、江戸時代の城下町の街並みを非常によく残した町です。

明治維新前には津和野藩亀井氏の城下町であり、山間の小さな盆地に広がる町並みは、「小京都」の代表格として知られているほか、津和野駅はSLやまぐち号の終着駅でもあり、山口市・萩とセットで訪れる観光客が多い。

また、在日米軍基地のある岩国市からも車で訪れることが出来るため、基地職員や米軍兵士などといった外国人観光客も比較的多く見られます。
幕末期以降の廃仏毀釈と、長崎から配流されてきたキリシタンへ、改宗の強要が実施された歴史があります。

2005年9月25日、隣接していた日原町と合併(新設合併)し、新たに津和野町となった。町役場は合併前の日原町役場に置かれることとなった。

毎年7月末に行われる祇園祭の中で、街中を練り歩く鷺舞は津和野の代名詞であり、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

待合室は特に区画されず、そう広くはありません。駅舎の隅に、囲むようなカウンターをもった店舗で「くぼた」という業者がそば屋とSLやまぐち号を包装にデザインの「かしわめし弁当」(730円)を調理しています。うどん・そばのメニューとしては品数は少なく、弁当屋らしく駅弁に力を入れているようです。他にも山菜つわぶき弁当(10月 - 5月限定) かにずし かしわめし弁当 幕の内弁当


島式1面2線のホームを持ち、交換設備を有する地上駅。大型の駅舎で純和風ではないのですが、落ち着いた街並みに馴染み感じの良い駅舎ですは上り線東側にあり、そこから跨線橋がホームの益田寄りに繋がっています。


山口地域鉄道部が管理し、ジェイアール西日本広島メンテックが駅業務を受託する業務委託駅であり、みどりの窓口が営業している。ただし早朝と夜間は無人となります。

構内には蒸気機関車用の転車台や、静態保存されているD51形蒸気機関車があります。また、留置線も何本か設けられています。

津和野駅プラットホーム
ホーム路線方向行先
2■山口線上り山口・新山口方面
3■山口線下り益田・浜田方面

1番線は2番線の駅舎寄りに隣接した線路であるが、乗降設備は設けられておらず、列車の留置などで使われている。SLやまぐち号は一旦この留置線に客車を留置した後に機関車のみ方向転換のために転車台へ向かう。

また、2番線・3番線とも片方向の入線・出発しか対応しておらず、ホームでの列車の折り返しはできない。従って当駅始発・終着の列車は一旦留置線への入換を行う。線路の奥にはターンテーブルもあります。ホームには燈籠が並んでいます。
構内裏手の留置線があり奥の線路はSLの機回しに使用されます。

1922年(大正11年)8月5日 - 国有鉄道山口線が徳佐駅から延伸し、その終着として開業。同時に三田尻機関庫津和野機関分庫を開設し山口線管理所となる。
1923年(大正12年)4月1日 - 山口線が石見益田駅(現・益田駅)まで延伸し、途中駅となる。
1928年(昭和3年) - 三田尻機関庫津和野機関分庫が小郡機関庫津和野支区に変更。

1977年(昭和52年) - 現在の2代目駅舎が竣工。
1984年(昭和59年)1月1日 - 貨物扱い廃止。
1986年(昭和61年) - 小郡機関区津和野支区廃止。

1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により西日本旅客鉄道(JR西日本)が継承。
2003年(平成15年)11月1日 - ジェイアール西日本広島メンテックによる業務委託駅となる。

電報略号ツワ
駅構造地上駅
ホーム1面2線

乗車人員
-統計年度-276人/日(降車客含まず)
-2009年-
開業年月日1922年(大正11年)8月5日
備考業務委託駅
みどりの窓口 有

幻の間欠泉:1997年、温泉掘削のボーリングにより間欠泉の噴出が始まり、諏訪の間欠泉を抜く55mもの噴出高を誇り「日本一の間欠泉」「世界でも2位の間欠泉」ともてはやされた。38度の温泉が炭酸の圧力によって吹き上げるメカニズムでしたが、塩分が含まれており周囲の田畑に塩被害が出たために、風のない昼間に限ってバブルを開放していたが、その後砒素も含まれることが判明し、事業中止が決定、幻の間欠泉となり現在は跡地は公園となっています。











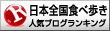


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます