
国鉄キハ04形気動車は、かつて日本国有鉄道(国鉄)に在籍した、一般形機械式ディーゼル動車である。

本形式は1932年(昭和7年)に鉄道省が設計し、1933年(昭和8年)に竣工したキハ36900形(キハ36900 - 36935)を第一陣とする一連の16 m級機械式気動車シリーズを、太平洋戦争後の機関換装によりディーゼル動車化し、形式称号を変更したものである。

設計全般は鉄道省によるものだが、その構造・機構面での基本となったのは、これに先立って日本車輌製造(日車)本店が開発した、日本初の18 m級ガソリンカーである江若鉄道C4形(1931年製造)などの私鉄向け大型気動車であり、その影響は、4枚窓構成の前面窓、型鋼と薄板を多用して軽量化された車体、菱枠構造の軸バネ式台車、それに駆動メカニズムなどに、顕著に現れている。これらは日本車輌製造が1920年代末期から試行錯誤を繰り返した末に実用領域に到達したものであった。

しかし、鉄道省36900形には日本車輌式のシステムやノウハウ、あるいは設計がほとんどそのまま導入されているにも関わらず、鉄道省・国鉄側の設計担当者はこれについて一切言及していない。そればかりか、日本車輌製造が特許や実用新案を保有していた設計や機構について、鉄道省がその使用料を支払った形跡は発見されていない。
気動車の分野に限らず、鉄道省および後身の日本国有鉄道の技術陣には、日本国内での圧倒的な最大手ユーザーという強い立場もあって一種の官尊民卑意識が強く、民間メーカーの独自開発技術をそのまま導入した場合でさえ、そのことに言及しないか「共同開発」という表現で実態を曖昧にする事例が少なくなかった。当時の設計担当者・北畠顕正は、キハ36900形開発から60年余りを経た最晩年にインタビューを受けたが、日本車輌製造からの技術導入・援用についてはまったく言及せず、その全てを鉄道省で開発したかのように証言している。
1936年(昭和11年)までに138両が新造されたキハ41000形、および試作ディーゼル機関搭載車であるキハ41500形(初代)2両の計140両は、木炭ガス発生炉を搭載して代燃車として運行された一部を除き、戦時中の燃料統制で一時使用を停止されていたが、戦後になって一部が天然ガス動車化の上で復活した後、燃料事情の好転を受けて1950年(昭和25年)以降、機関を各種新型ディーゼルエンジンへ換装しディーゼル動車として再生された。
その結果これらは使用燃料や搭載機関の相違から、一旦キハ41200形・キハ41300形・キハ41400形・キハ41500形(2代目)の4形式に細分された。

キハ41000グループは、16m級の車体が地方私鉄には手頃な大きさだったことや、戦時中の休車が復活せずに廃車された際の譲渡例は多く、中には複数の鉄道会社を渡り歩いた車両もある。











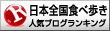


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます